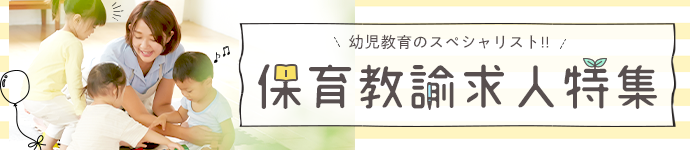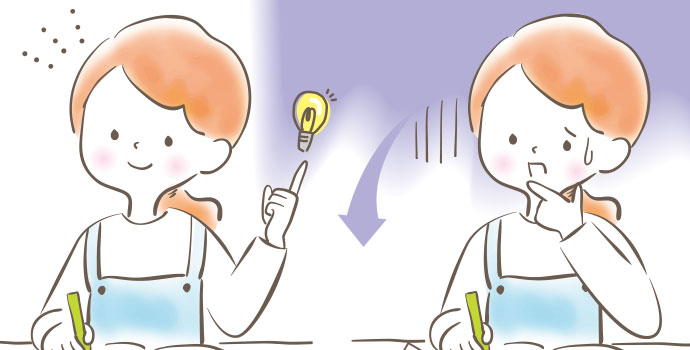保育教諭とは?保育士との違い・仕事内容・必要資格・将来性も!

保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!
X(旧Twitter)をフォローはこちら!
現在、幼保一体化が進められ、育児サービスの多様化や課題に対応しています。幼保一体化が進む中で、幼保連携型認定こども園(以下、認定こども園)の数が急増中です。そのため、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持った保育教諭が注目を集め、保育教諭の求人も増えています。
2025年3月までの特例措置期間には、どちらかの資格・免許しか持っていない人でも、比較的簡単にもう一方の資格取得が可能です。
当記事では、「保育教諭の仕事内容・給料相場」「保育教諭として働くために必要な資格」「保育教諭として働くメリット・デメリット」などについて紹介します。保育教諭の仕事に興味がある人や、保育教諭を目指している人は、ぜひ当記事を参考にしてください。
保育教諭とは?
保育教諭とは、認定こども園で勤務し、保育士資格と幼稚園教諭免許状の両方を持っている職員のことです。幼保連携型認定こども園は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、「保育士資格」と「幼稚園教諭免許状」の両方の免許・資格を有することを原則としています。
学校教育と保育の側面の両方から子どもに関わる認定こども園への円滑な移行を進めるために、保育教諭を充足させることが急務となっています。
保育士・幼稚園教諭との違い
下記は、保育教諭・保育士・幼稚園教諭が対応する子どもの年齢と仕事内容をまとめた表です。
| 資格・免許 | 対象年齢 | 内容 |
|---|---|---|
| 保育教諭 | 0歳~5歳 | 保育士・幼稚園教諭の両側面の援助 |
| 保育士 | 0歳~5歳 | 食事などの日常生活の補助・生活習慣を身につける援助 |
| 幼稚園教諭 | 3歳~5歳 | 知識や運動、芸術を通して情操教育が主体 |
低年齢の保育園児の多くは、毎日の食事・排せつ・着替えなどを自力で行うことができません。そのため、2歳未満の乳児クラスでは子どもたちの日常生活をサポートする保育業務が重視されます。3歳児以上の幼児クラスを受け持つ保育士の仕事は、基本的な生活習慣や社会性を身につけるための援助が中心です。
幼稚園では入園時点で身の回りのことをある程度自力でできる子どもが多く、幼稚園教諭の仕事は生活補助よりも教育や行事の計画・運営などに重点が置かれています。保育教諭は保育士と幼稚園教諭の中間的存在であり、より幅広いスキルを求められます。
仕事内容
保育教諭の仕事では、子どもが生活習慣を身につけるための保育を行う他、運動や芸術を通しての教育も行うため、保育士と幼稚園教諭のどちらのスキルも必要です。
認定こども園では、どの認定の子どもを受け持つかによって保育教諭の仕事内容が変わります。例えば、1号認定の子どもは幼稚園同様の対応で、3号認定の子どもは保育園同様の対応となります。
| 1号認定 | 保育が不要な3歳~5歳児 |
|---|---|
| 2号認定 | 保育が不要な3歳~5歳児 |
| 3号認定 | 保育が不要な0歳~2歳児 |
(出典:内閣府「よくわかる「子ども・子育て支援新制度」」/https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/sukusuku.html)
2号認定クラスの場合、1号認定の子どもの保育時間が終わる14時ごろまでは1号認定クラスと一緒に活動することもあります。1号認定クラスの子どもたちが降園した後は、保育園の幼児クラスとほぼ同じ対応となるでしょう。
認定こども園は、地域の子育て支援施設としても注目されています。地域の子育て世帯に向けた子育て相談や園庭解放などを行う施設もあるため、関連する業務も保育教諭の重要な仕事です。
保育教諭になるには?必要な資格や特例制度も
保育教諭として働くためには、基本的に保育士資格と幼稚園教諭免許の2つが必要です。しかし現在、保育士資格と幼稚園教諭免許のどちらか一方を取得していれば、保育教諭として働くことが可能です。
以下では、保育教諭として働くために必要な資格の取得条件・取得方法・無資格からの目指し方を説明します。
経過措置と特例制度
円滑に認定こども園への移行を進めるために、より多くの保育教諭が必要となったことから、2015年からの5年間は保育士資格か幼稚園教諭免許のどちらかを持っていれば、保育教諭として勤務できる経過措置が取られました。
2020年時点で、未だ保育教諭の数が十分ではない状況を受けて経過措置がさらに5年間延長され、2025年3月まで適用されることとなりました。
(出典:内閣府「新制度施行後5年の経過措置に係る事項の対応について」
/https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_41/pdf/s6-2.pdf)
そのため、保育教諭として長く勤務することを考えている人で、どちらか一方の資格・免許しか持っていない場合は、この期間中にもう一方の資格・免許を取得する必要があります。
次項より、どちらか一方の資格・免許を少ない単位数で比較的簡単に取得できる特例制度について説明します。
保育士資格のみを持っている場合
保育士資格を持っている場合は、保育士として3年間かつ4,320時間以上の実務経験がある人が特例制度の対象者となります。認定こども園や保育園などでの実務経験が必要となるため、保育士資格を持っていても実務経験がない人は対象にはなりません。4,320時間以上の実務経験は、1日6時間を5日間以上勤務すると、3年で満たすことができます。
幼稚園教諭免許を取得するためには、指定の施設で次の5科目(8単位)を修得する必要があります。
| ①教職の意義及び教員の役割、教員の職務内容(2単位) ②教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(2単位) ③教育課程の意義及び編成の方法(1単位) ④保育内容の指導法、教育の方法及び技術(2単位) ⑤幼児理解の理論及び方法(1単位) |
(出典:厚生労働省「特例制度の概要」
/https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/dl/tokurei2.pdf)
上記の5科目を修得後、8単位を受講した施設がある都道府県の教育委員会に申請します。大学などの指定施設で特例措置に特化した講習や通信講座を開設していることもあるため、問い合わせてみましょう。
幼稚園教諭免許のみを持っている場合
幼稚園教諭の免許を持っている場合は、幼稚園で3年間かつ4,320時間以上の実務経験がある人が特例制度の対象者です。
幼稚園教諭の免許を持っている人は、指定施設で以下の4教科(8単位)を修得すると、保育士試験の全科目が免除となります。保育士試験の申し込みをして全科免除の手続きを行ったのち、保育士資格を取得する流れです。
| ①福祉と養護(2単位) ②相談支援(2単位) ③保健と食と栄養(2単位) ④乳児保育(2単位) |
(出典:厚生労働省「特例制度の概要」
/https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/dl/tokurei2.pdf)
無資格から保育教諭を目指す場合
保育士資格も幼稚園教諭免許も持っていない場合は、両方の資格・免許を取得できる大学や専門学校などの養成施設で所定の単位を修了します。
幼稚園教諭免許は、四年制大学などで取得できる一種免許と短大・専門学校で取得できる二種免許に大きく分かれます。実際の仕事内容は一種と二種であまり差がないものの、高収入や管理職候補を目指す場合は一種がおすすめです。この他、大学院修士課程修了程度で取得できる専修免許もあります。
まとまった時間を確保しにくい場合や両方の資格を取得できる養成施設が近隣にない場合は、まずどちらか一方の資格を取得してからもう一方の資格を取得することも可能です。
保育教諭の給料相場
内閣府が発表した資料によると、平均勤続年数8〜10年の常勤保育教諭の給料は、賞与含めおよそ28万〜29万円です。公立と私立の施設での年収の差はほとんどありません。ただし、認定こども園によっては給料が異なるため、応募の際には求人情報をよく確認しましょう。
下記の表は、保育教諭・保育士・幼稚園教諭の給与について比較したものです。保育教諭の求人を探す際は、参考にしてください。
| 資格・免許 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|
| 保育教諭 | 29万円(10年) | 28万円(8年) |
| 保育士 | 30万円(11年) | 30万円(11年) |
| 幼稚園教諭 | 38万円(11年) | 29万円(8年) |
※「( )」は平均勤続年数です
(出典:内閣府「令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査集計結果〈速報値〉」/https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/data/pdf/chousa/kekka.pdf)
保育教諭の求人状況
マイナビ保育士における保育教諭求人の主な特徴は、次の通りです。
・必要とされる経験やスキル
| 基本的に0〜5歳が保育対象となりますが、「0〜2歳児」「3〜5歳児」のように保育対象年齢を絞った求人もあります。保育士資格か幼稚園教諭免許のどちらか一方のみを持っている場合は、保育対象年齢を絞った求人のほうが挑戦しやすいでしょう。また、保育士資格か幼稚園教諭免許どちらか一方の資格・免許のみを応募条件とする求人も少なくありません。 英会話・楽器演奏・スポーツなどの個性的な活動を行う園も多く、保育とは直接関係のないスキルが思いがけず役立つこともあります。 |
・福利厚生の特徴
| 残業時間の少なさをアピールしている園が多く、子育てや資格取得のための勉強と仕事を両立しやすい環境が整っていると言えます。新しい仕事と1人暮らし用の新居を同時に探したい場合は、借り上げ社宅つき求人もおすすめです。多くの求人で産休・育休制度が整備されているため、すでに子どもがいる場合はもちろん今後出産を希望する場合も安心して応募できるでしょう。 |
・休日の特徴
| 平日以外の働き方については園によって差があり、「日曜祝日休み」「行事がある場合を除き土日祝日休み」「月に1〜2回土曜出勤あり」などさまざまです。収入額や家族のライフスタイルなども考慮しつつ、無理なく働ける求人を選ぶとよいでしょう。 |
上記は一例ですが、認定こども園の求人は比較的多いため、幅広い選択肢から応募先を決めることができるでしょう。
保育教諭として働く3つのメリット
保育教諭として働くことで得られる主なメリットは、次の通りです。
・幅広い分野でスキルアップができる
| 認定こども園には幼稚園や保育園と比べて幅広い年齢の子どもが在園し、また子どもの家庭環境や保護者の価値観もさまざまです。そのため子どもの保育・教育や保護者対応などに関するスキルを伸ばしやすく、保育・教育者として柔軟な価値観を持つチャンスも増えるでしょう。 |
・転職に有利となる
| 認定こども園は今後ますます増えると予想されるため、保育教諭として経験を積むことで転職の選択肢が増えると期待できます。認定こども園だけでなく幼稚園・保育園や民間のキッズスクールなどに転職する場合も、保育教諭としての経験はおおいに役立つでしょう。 |
・認定こども園に移行しても働き続けられる
| すでに認定こども園への移行準備を進めている、あるいは移行を検討している幼稚園や保育園は少なくありません。もし勤務先の園が将来認定こども園へ移行しても、保育教諭であれば比較的スムーズに新しい体制になじめるでしょう。また幅広い知識やスキルを持っていることで他のメンバーから頼られる機会が増え、昇進やステップアップの機会にも恵まれやすくなると考えられます。 |
少子化の進行に伴い、今後子どもの数は減っていくと予想されますが、多様な保育サービスに対する需要は高まっています。より柔軟な保育サービスを提供しつつ認定こども園を支える保育教諭は、今後の保育業界にとって欠かせない存在となるでしょう。
保育教諭として働く3つのデメリット・注意点
保育教諭の仕事には、次のようなデメリットもあります。
・職員間で意見が衝突するケースがある
| ひとくちに保育教諭といっても価値観は十人十色であり、保育方針や業務の進め方などについて職員同士で意見が衝突することもあります。幼稚園教諭出身の職員と保育士出身の職員が混在する園では、特にその傾向が強いと言えるでしょう。 |
・預かる子どもによって降園時間が異なる
| 基本的に、1号認定クラスと2・3号認定クラスでは降園時間が異なります。また、預かり保育や延長保育の利用頻度が高い子どもは日によって降園時間が変動することもしばしばです。そのため、保育教諭は子どもたち1人ひとりのスケジュール管理やお迎えに来る保護者への対応で忙しくなることも少なくありません。 |
・覚えること・業務が増える
| 認定こども園は幼稚園や保育園と比べて業務の幅が広く、仕事量や覚えるべき内容も多くなります。例えば幼稚園教諭出身なら乳児保育に、保育士出身なら行事の多さなどに戸惑うこともあるでしょう。また保護者の働き方や子育てに関する価値観も多様化しており、保護者同士のトラブルへの対応を求められることも少なくありません。 |
保育教諭ならではの苦労があるものの、考え方次第でメリットと捉えることもできます。困難を乗り越えつつさまざまな経験を積むことでスキルアップを図り、将来に役立てられるでしょう。
保育教諭の将来性
2021年4月における全国の認定こども園の数は8,500か所を超えており、前年より約70か所増加しています。
(出典:内閣府「認定こども園に関する状況について(令和3年4月1日現在)」
/https://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/pdf/kodomoen_jokyo.pdf)
国は認定こども園の新規開設や既存の幼稚園・保育園から認定こども園への移行を後押ししており、今後も認定こども園の数は増える見込みです。
また、2020年4月時点で全自治体の77%が「待機児童はいない」と発表しています。
(参照:厚生労働省「保育を取り巻く状況について」
/https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000784219.pdf)
しかし、待機児童として扱われていないものの希望する認可保育園に入れなかった「隠れ待機児童」が完全にいなくなったわけではありません。認定こども園は、より多様な保育サービスを提供しつつ、隠れ待機児童を解消するための受け皿としても期待されています。
認定こども園の数を増やしつつ保育サービスの質を維持するためには、十分な数の保育教諭が必要です。そのため今後は都市部だけでなく地方でも保育教諭の求人数が増え、また保育教諭の待遇も改善されると考えられます。
まとめ
今回は、保育教諭の仕事内容や、働くために必要な資格、さらに保育教諭として働くメリット・デメリットについて詳しく解説しました。保育教諭の仕事内容は、保育士や幼稚園教諭の業務とは大きく異なります。保育教諭は、保育と教育の両面から子どものサポートができる魅力的な職業です。
認定こども園の増加に伴い、今後も保育教諭の需要が増えていくと考えられます。保育士と幼稚園教諭のどちらか一方の資格・免許を取得できる特例制度も、2025年3月まで延長されています。
保育業界では保育教諭を支援する取り組みも行われているため、ぜひ保育教諭として働くことを視野に入れてみてはいかがでしょうか。