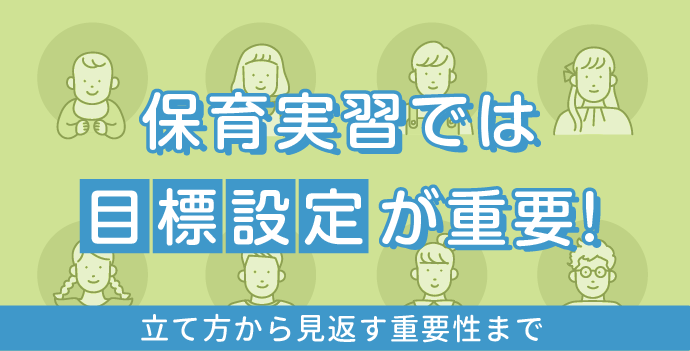
保育実習は、座学によって習得した知識を生きたノウハウに変えるための重要な機会といえます。しかし、初めての保育実習を控え、何かと不安を感じることは当然です。保育実習直前に、「目標の立て方が分からない」といったことで悩み、不安を感じる学生もいるでしょう。
そこで今回は、保育実習の目標の立て方・コツを解説します。目標の参考例も紹介するため、保育実習の準備を進めるときのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
保育実習後の就職活動に不安がある方、必見!
目次
保育実習の目的は一律で定められている

保育士資格を取得するためには、保育士試験の受験もしくは保育士養成施設の卒業を経なければなりません。保育実習は保育士養成課程における必修科目の1つに位置付けられ、学校で学んだ知識を実践的なノウハウに変えるための重要な機会です。
保育実習の目的は、厚生労働省によって、下記のように規定されています。
保育実習は、その習得した教科全体の知識、技能を基礎とし、これらを総合的に実践する応用能力を養うため、児童に対する理解を通じて保育の理論と実践の関係について習熟させることを目的とする。
(引用:一般社団法人 全国保育士養成協議会「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」/ http://www.hoyokyo.or.jp/http:/www.hoyokyo.or.jp/nursing_hyk/reference/30-2s1.pdf)
厚生労働省によって規定されている「目的」は、保育実習の最終的なゴールです。最終的なゴールを実現するための手段として目標を設定し、達成できたかどうかを振り返ります。
自分で目標を設定することが重要な理由
保育実習の目標は、自分で設定する必要があります。自分で目標を設定するためには、保育に関する基礎知識や実践力を自己評価し、把握する手順を踏まなければなりません。そして、自分自身の「できる項目」「できない項目」を把握し、「できない項目」を「できる項目」に変えるための必要要素を目標に落とし込みます。
目標を自分で設定するからこそ、現在の知識やスキルを自己評価する必要性が生じ、振り返りの機会を得ることが可能です。「できないこと」を明確に把握することは、保育実習に対するモチベーションを高め、実りの多い経験を得ることに貢献します。
保育実習は、保育士として働き始めた後の実務に直結する重要な学びの機会です。明確な目標を持って保育実習に臨み、できる限り多くの知識や経験を養いましょう。
保育実習後の就職活動に不安がある方、必見!
【担当年齢別】保育実習の目標の立て方・参考例
保育実習の目標は、抽象的な内容を避け、具体的に決める必要があります。できるだけ明確な目標にすることで、実習の振り返りがしやすくなります。
ここでは、目標の立て方のポイントを年齢別に解説します。目標を立てるにあたって、厚生労働省が提示している「保育所保育指針」が参考になります。実習内容に合わせて保育の目的やねらいをよく理解し、目標設定の参考にしてください。
(出典:厚生労働省「保育所保育指針」/ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000160000.pdf )
0歳児
0歳児クラスでは、体調の把握や健康管理が最も重要です。それぞれの発達状況に合わせた保育と安全の確保を優先した目標を立てましょう。
| 【保育実習の目標の例文:0歳児】 |
|---|
|
1~2歳児
1〜2歳児クラスでは、歩く、走るなどの運動機能の成長やトイレなどの自立支援が中心です。子どものできることを増やす関わり方やその支援方法について記載してください。
| 【保育実習の目標の例文:1〜2歳児】 |
|---|
|
3~4歳児
3〜4歳児クラスは、集団生活の人との関わりの中でさまざまな感情表現や心の成長をする時期です。子ども同士の関わりや遊びの中で、課題解決や心の成長を支援できる目標を立てましょう。
| 【保育実習の目標の例文:3〜4歳児】 |
|---|
|
5~6歳児
5〜6歳児クラスでは、就学前準備として文字の読み書きが始まり、人間関係の構築も必要になります。集団遊びなど子ども同士の活動を通して、探究心や学習する力を育むために、どのような関わり方をするか目標を立てましょう。
| 【保育実習の目標の例文:5〜6歳児】 |
|---|
|
保育実習後の就職活動に不安がある方、必見!
【目的別】保育実習の目標の立て方・参考例

保育実習の期間は有限であるため、習得を目指す知識や経験のすべてを網羅できるとは限りません。そこで、保育実習の参加にあたり、優先的に習得を目指す知識や経験をベースに目標を設定する方法も一案です。
| 優先的に習得を目指す知識の例 | 保育所における保育士の役割 |
|---|---|
| 目標の設定例 |
|
優先的に習得を目指す知識は、自分の現状を踏まえて「重要な課題である」と感じる内容をベースに検討するとよいでしょう。授業で学習した知識を保育の現場で再確認し、生きたものに変えることを目指して、目標に落とし込んでください。
保育士の仕事に着目した立て方
保育現場での仕事は、子どもの食事から着替え、睡眠、排泄など多岐にわたります。基本的な生活習慣を身につけさせることに加え、子どもの安全や衛生面を確保しなければなりません。
保育目標を理解したうえで実習計画を立て、子どもに対する指導方法や関わり方など、具体的な仕事内容や保育知識を覚えることを目標にしましょう。
| 【仕事に着目した目標の立て方の例文】 |
|---|
|
保護者との関わりに着目した立て方
保育士の仕事は子どもとの関わりだけではなく、保護者対応もしなければなりません。子どもの安全を確保することはもちろん、保護者とのコミュニケーションや連絡帳のやりとりを通して信頼関係を構築することが求められます。
保護者との関わり方に関して、具体的にどのような配慮をするのかを目標にしましょう。
| 【保護者との関わり方に着目した目標の立て方の例文】 |
|---|
|
保育実習後の就職活動に不安がある方、必見!
【日程別】保育実習の目標の立て方・参考例
保育実習の期間については、厚生労働省によって40日間と決められています。長い実習期間の中で、期間を分けて取り組むことで目標が明確化されます。
ここからは、保育実習期間を序盤、中盤、終盤の3つに分け、それぞれの目標の立て方とポイントを解説します。
序盤
実習前半は、職場に慣れることや保育内容の流れを覚えることで精一杯です。仕事内容の理解と指導担当保育士の指示を守ることを中心に目標を立てましょう。
| 【保育実習:序盤】目標の例文 |
|---|
|
中盤
保育実習中盤では、具体的な保育方法や子どもたちとの関わり方を学ぶ目標を立てましょう。保育の場面ごとに内容を細かく分けて考えることで、目標を立てやすくなります。
| 【保育実習:中盤】目標の例文 |
|---|
|
終盤
仕事に慣れてくる実習終盤では、子どもの成長を支援する環境設定の方法や、保護者との関わり方について目標を立てます。また、保育士同士の連携や情報共有の方法についても記載しましょう。
| 【保育実習:終盤】目標の例文 |
|---|
|
実習後には目標を見返してみよう
保育士の養成課程では、保育の計画から観察・記録・自己評価までをワンセットと考えて、「保育実習」とみなします。保育実習の終了後は日誌を見返して、保育実習中の態度や取り組み姿勢、習得スキルの振り返りを行ってください。
(参照:一般社団法人 全国保育士養成協議会「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」/ http://www.hoyokyo.or.jp/http:/www.hoyokyo.or.jp/nursing_hyk/reference/30-2s1.pdf )
下記のような方法によって客観的な意見を聞くことも、振り返りの有効な手段といえます。
- 保育所の指導担当保育士と最終日に面談し、フィードバックを受ける
- 学校の保育実習事後指導を受けて、指導担当者の意見を聞く
- 学校の友人とともに反省会を開き、保育実習の成果や反省点を共有する
保育施設は、それぞれ固有の特徴を持ち、さまざまな方法による保育を実践しています。友人と情報共有することで新たな気付きが生じ、知識の幅を広げることも可能です。
なお、保育実習の振り返りでは、「目標を達成できた」「未達成に終わった」という結果に固執する必要はありません。自分自身の取り組み状況から新たな課題や問題点を発見し、次回の保育実習や就職後の実務に活かすことが大切です。
目標設定と自己評価、振り返りを繰り返すことが、優秀な保育士として活躍するための近道といえます。保育実習の段階で一連の流れを経験し、保育現場の即戦力として歓迎される人材を目指しましょう。
まとめ
保育実習において、適切な目標設定・振り返りのスキルを身に付けることは、優秀な保育士として活躍するための必須要素に該当します。
自分の設定目標を達成できた場合には、大きな自信を得ることが可能です。未達成に終わった場合でも、新たな課題や問題点などを得ることができるため、目標を設定すること自体がメリットを伴う行為といえます。
保育士を目指す人は、目標設定の重要性を理解したうえで、保育実習の当日を迎えてください。








