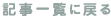
第63回
遊び惚けて120分!?
井上 さく子
主に幼児クラスの子どもたちの遊びを毎日まいにち観察し、記録を取りながら見えてきた裏づけがありました。
しかしこの記録を見事に塗りかえる遊びに遭遇して
驚くやら、嬉しいやらの物語です。
それは、大田区保育園の4歳児クラス。
ここでは、遊び惚けて120分!?
一瞬驚愕しました。
子どもたちは室内遊びの前に
朝一番の園庭遊びで心も身体も存分に全開にして、満喫してから部屋に戻っていました。
そこで、カプラの世界で構成遊びをしている様子を
じっくりと観察させてもらいました。(公開保育研修)
保育室の空間を広げた環境で、
カプラと乗り物
カプラと動物
カプラとミニチュア人形
大きく分けると3つのグループに分かれて、
5〜6人の子どもたちが関わって遊んでいました。
ほとんど、大人は関わらず子どもたちの傍に寄り添っていました。
もちろん、子どもたちに呼ばれてその場を離れたり、戻ったりすることはあっても、大半が仲間の中で遊びを展開していました。
こんな風に子どもたちが主体的に遊んでいるときにこそ、
大人は観察力を研ぎ澄ましてほしいと願います。
なんとなく観ていないと信じています。
場面的に捉えていないと信じたいです。
仲間同士の関係性を丁寧に観る目を確かなものにしてほしいと願いながら、客観的に観察していました。
そこでは、子どもたちのつぶやき、声だけしか耳に入ってきません。
そのつぶやきに耳を澄ますとことばのやり取りだけで、
何を相談しているのか?
どんなイメージを共有しようとしているのか?
共有できたのか?
イメージの世界を
どこからどんなふうに広げようとしているのか?
広げたのか?
一人ひとりの育ちはいかに?
さまざまな角度から観察をして、記録に残し、明日の保育につないでいく機会に。
意識化を図っていく機会に。
大人と子どもの関係性を観ながら、心の中でつぶやく私がそこにいました。
それぞれのグループで繰り広げられている遊びでは
周りに翻弄されることなく、どこのグループの子どもたちも夢中になっていました。
もちろん、カプラ以外の世界でも、机上の遊びで制作に取り組んでいる様子も見て取れました。
実は教えてもらわなかったら気づかない
支援を必要とする仲間の存在。
その遊びの世界に溶け込んでいたので、それほど気にかけずにいました。と言うよりも気づかずにいました。
でも、カプラの世界にこそ入っていませんでしたが、その子どもたちの遊びもちゃんと保証されていたのです。
全体的な風景を捉え、目の前の子どもたちが展開していく物語を綴りながら、
個の育ち=仲間の育ち
「遊び力」をそこに観た思いがしました。
どこまで続くこのカプラの世界!?と思えるほど
延々と続く4歳児クラスの遊び。
皆さまの保育園、子ども園、幼稚園ではいかがでしょうか?
これ程までに、持続可能な保育を心がけているでしょうか?
仲間同士で相談しながら、遊びに没頭している子どもたち。
ケンカも見られず、棒立ちしている子どもも誰一人としていませんでした。
むしろ、遊びに忙しいオーラが流れています。
仲間と共に刺激し合いながら、共育ちしている物語とは?まさしく
今、目の当たりにしているこの風景のことを指していると思いませんか?
こんなふうに
保育室の隅の方から観察しているときのエピソードです。
一人のお嬢さまが水道の方へ移動するときのことでした。
どいてください!とも言わず
通れない!とも言わず
邪魔です!とも言わず
場の空気を読んで
さて?
ここをどうやって通ろうかな?
何気なく、さり気なく、出入りする様子から、心持ち穏やかな、自己肯定感が豊かなお嬢さまと感じ取ることができました。
ひと言
「気がつかなくてごめんなさいね!」と添えると
ニコッと笑って仲間の遊びの世界に溶け込んでいったのです。
何気ないお嬢さまの振る舞いに、日頃の保育園での暮らしを垣間見ることができました。
子どもたちが全部日常の暮らしを教えてくれるとは?
こういうエピソードだと思いませんか?
子どもと相談する保育や対話的保育を丁寧に積み重ねていく先々に、一人ひとりの子どもの育ちがこんなふうに確実に育まれていくと信じています。
毎日子どもたちと暮らしているとそれがあたりまえに映りがちだと思いますが、私にはとてもシンプルで嬉しい育ちに映りました。
久し振りに
遊び惚ける子どもたちの遊びの世界に触れて、
感じて幸せな心持ちになりました。
-------------------------------------------------------------------
~さく子ゼミの参加者募集~
『21世紀型保育とは?~目の前の子どもから学ぶ視点をすえていこう 』
公立保育園の園長を長年経験され、現在も保育環境アドバイザーとして
全国の保育現場の環境改善に奔走する井上さく子先生が、
実践的な事例を元にWEBを通して参加者の『保育に関する悩みや迷い』
に答えます。
※お友達紹介キャンペーンも行っております!※
■開催日時 2021年12月20日(月)18時45分~21時00分
■会場 WEB配信となります。
■詳細・お申込み
https://hoiku.mynavi.jp/
-------------------------------------------------------------------

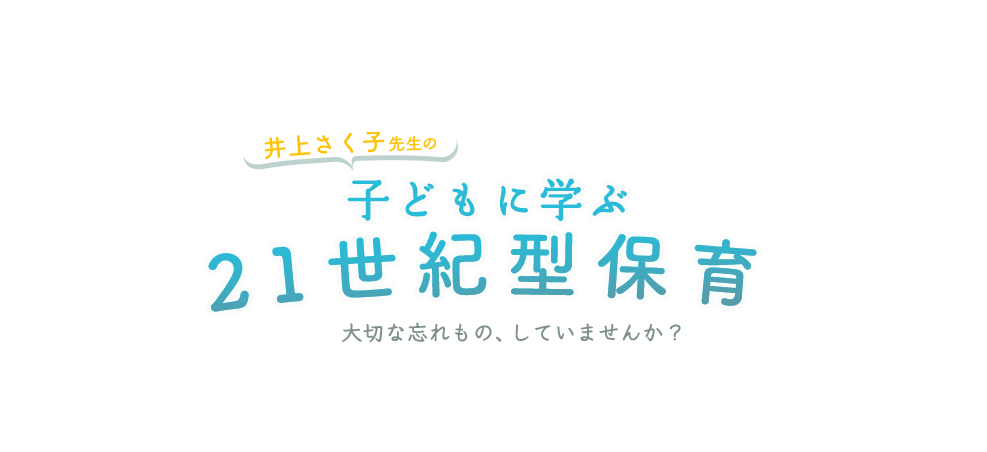





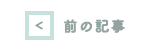

コメント(3)
「遊び惚ける」素敵な言葉ですね。
自分で選んで、決めて、考えるから遊び惚けるんですね。
我が家の近くのとっても小さな公園に孫とよく行きます。孫は、大きなスコップを地面に滑らせ集まった砂を運び、真ん中に集めてを何十回も繰り返して山を作ります。スコップの角度や集め方、砂の盛り方などを工夫し、1時間くらい経つと
滑り台の高い所から作品の山を眺めブランコにのって帰宅になります。
心ゆくまで遊び惚る、子ども時代をそんな風に過ごしてほしいと思っています。
懐かしい風景を思い出します。やりたいことを目をキラキラさせてやり遂げるという体験をした子どもたちは、どう大きくなっていっているのかと、思うだけでもワクワクします。
いつも不満ばかりで、何かあると人のせいにしていた4歳のM君のことを思い出しました。
さく子先生のアドバイスに助けられながら進めた保育の中で、M君は気の合う友だちを見つけ、楽しい遊びを二人で考えました。
丸太に板を置いてシーソー。バランスとタイミングが必要な遊びでしたが、M君は、顎を負傷。
前なら相手のせいにしていただろうなという出来事でしたが、「ぼくが避けられなかったからだよ」とお母様にも伝えていました。
お母様にはお詫びをしながらも、互いに心の成長に喜んだ、というエピソードでした。
今まで、自分に自信が持てなかった子も、考えた遊びをやり遂げることで、顔つきから変わっていく姿を感じることができました。
子どもと共に、自分たちの保育にも自信が持てました。
保育も人事異動などで変わってしまうこともありますが、あの頃皆んなでまいた種は花を咲かせ、また、種はあちこちに飛んでいってくれていると信じています。
遊びこむ姿には沢山の育ちが溢れています。見立て遊びがどんどん膨らんでいったり、ままごと遊びが広がっていったり、例えブロックでもその子のイメージが形になっていく真剣なまなざしは見ている私も楽しくなります。これからというときに「はい、片づけてください‼」と容赦ない声。噓でしょう?この子もう少しで完成なのに‼もう少し見通しが欲しい!このブツ切れの保育。悲しい。子ども達の消化不良がなぜわからないのだろう。でも、もっと悲しい場面は子ども達がこの生活にすっかり慣れている光景。あっという間に片づけてしまうのです。なんだか悲しい‼中に最後までやり遂げたい子が一人二人、保育者の言葉を押し切り、完成目指していると「まだ片づけない人は誰?」とたたみこまれます。保育者の段取りで進められる保育。これを変えたい‼21世紀の保育に変えたい‼