【対談後編|保育の楽しさってなんだろう?】子どもたちの背中を「大丈夫だよ」と押せる大人であるために

汐見稔幸先生と井上さく子先生のインターネットライブ配信による対談後編です。
【対談前編|保育の楽しさってなんだろう?】コロナ禍に見えてきた「保育の楽しさ」をまだご覧になっていない方は、まずはそちらをご覧ください。
マイナビが事前に実施した「コロナ禍における保育と育児の現状」に関するアンケートでは、保育士や園長先生など経営層の方々だけでなく、保護者の皆様からも多く回答をいただきました。保護者の方たちは、子どもと過ごす時間が長くなったことによる「親子の関係性」や「家族の在り方」への関心が高いようです。その声を受けて、汐見先生と井上先生が語った、育児のみならず保育にも必要な「共感・共苦」とは―――。
構成/株式会社京田クリエーション 文/宇佐見明日香 写真/筒井聖子
子ども扱いしないことが自己肯定感を育てる
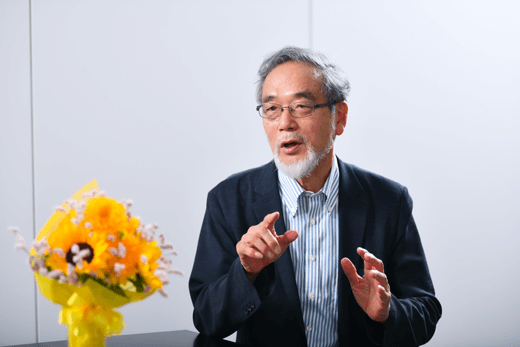
汐見:現役時代にさく子先生が徹底しておられたことの中で、なるほどと感心したのが、子どもに語り掛けるときは丁寧語でしゃべるというものです。言葉ばかりではなく、たとえ赤ちゃんであろうと子ども扱いする態度は厳に戒めておられた。
園長をしている僕の妻も同じです。「たとえ相手が0歳であっても、職員の都合で席を立つときは、子どもに黙って行かないでね」と職員に話しているのだそうです。子どもの顔を見て「先生、トイレに行っていい?」と聞く。それに対して子どもが「いいよ」という言葉こそなくても、そういう素振りを受け取ってから席を立つようにと。
そういうことを繰り返していると、子どもは人として大事にされているのだとわかります。常に尊重され、自分の意見が求められていて、その意見はしっかり受け止めてもらえるのだとわかります。いわゆる自己肯定感が育つんですよね。そういった環境で育った子は成長も早い。
言葉は二の次、一番大事なのは「共感・共苦」

井上:泣くことでしか不安を表現できない乳児期も、大人の都合で「泣かないの」などと意味のないことは言わずに、「泣きたいよね、泣いていいんだよ」と心から共感し、「泣き終わったら、お話聞くね」という言葉を添える。泣き疲れてやって来た子どもを、声を掛けるより先にぎゅっと抱きしめる。それを払いのけた子どもに対して、「あ、もう大丈夫なんだな」と認めて開放してあげる。
汐見:保育者は子どもの気持ちを深く理解して、その気持ちを代弁できるような存在でなければいけません。共感は英語でシンパシー(sympathy)とも、エンパシー(empathy)とも言いますが、保育者にとって必要なのは、シンクロする・模倣するという意味のシンパシーではなく、その子の立場になって考えるという意味のエンパシーなのではないでしょうか。
井上:そんな風に受け止めてもらっていたんですね。ありがとうございます。「共感」はもとより「共苦」は私の引き出しに入れておきたい、貴重なお言葉です。子どもたちはいつも平和で明るく楽しい暮らしを生きているのではありません。今こそ共苦というのはすごく大事な視点だと思います。出口のわからないコロナ禍で、多くの大人が病んでいる。子育てに疲れている。自粛期間中、子どもに手をあげてしまった、虐待してしまったという相談が、私の元にも数多く寄せられました。
対談の前半でも申し上げましたが、大人たちが困難に置かれ、悲鳴を上げているとしたら、その2倍も3倍も、子どもたちの方が混乱し、不安を抱えています。子どもに共苦するという感覚を忘れてはいけませんね。
我が子の意外な個性と成長をおもしろがろう

井上:つい昨日の出来事なんですけど、かかりつけの美容院にお邪魔したら、いつもカットを担当してくださる男性が、自粛期間中に子どもたちと断捨離をしたと話してくれました。年長のお姉ちゃんに要るものと要らないものを決めさせたら、発達に見合わないものをどんどん処分していくんですって。でも、お姉ちゃんが捨てたそばから、1歳の弟さんが「要る」と言ってゴミ箱から拾い上げ、エンドレスで断捨離が続いたと(笑)。でも「大変だったけど、すごく楽しかった」っておっしゃったんです。それってすごいと思いません?
しかも、それまで片付けができなかったお姉ちゃんが、自分の要るものだけを手元に残したら、その日から片づけられるようになったと。
今、この状況で不安でない人なんていません。でも、それぞれの悩みについては、自分の足元から整備していくほかないんですよね。自分はどうしたいのかを一つずつ問うこと。そして、子どもにも同じように「やりなさい」ではなく「あなたはどうしたいの?」と問うこと。昨日聞いて感動した、ほやほやのエピソードです。
汐見:自分で使いたいもの、大事なものだけが手元に残ったら、自分で片づけるんですよね。子どもたちに必要な物的環境をつくる第一歩として、要る・要らないを子ども主体で決めてもらうという試みは園でやってみてもいいかもしれない。
大人が勝手に与えたもので遊びなさい、大人の考えたことに従いなさいとやるから、子どもの行動がぞんざいになるんです。今の話を聞いて、もうひとつすごいなと思ったのが、断捨離をして上の子が捨てたものを下の子が拾う、それをおもしろがる保護者の感覚です。とても素晴らしい。
井上:その美容師さんは「なんでもかんでもコロナのせいにすればいいってもんじゃない」とも言っておられました。私もそう思います。コロナ以前から埋もれていたことが、コロナ禍においてバンっと表出しただけであって、コロナのせい、誰かのせい、ではないんですよね。表出した問題を、どう受け止めていくのかが問われているんです。
汐見:子どもにはこういうことができるようになって欲しいとか、こういうことはしつけておかなければということを優先してしまいがちですけど、この子はこんなことが好きなんだとか、それが必ずしも親好みではないことや、まったくの予想外であることをおもしろがれる親がいい親だと私は思います。
井上:私もそう思います。
汐見:石橋を叩いて引き返す子もいれば、叩くこともなく突っ走っていく子もいる。大事なのはその子のやり方を否定することでも、大人の考えを押し付けてしつけることでもなく、この子はそういう子なんだと認めることです。
この子はこういうときにすごくやる気を出す子なんだとか、この子はずっと観察していて、そろそろ大丈夫だと思ったときにやりだす子なんだとか。その子らしいやり方を見つけて、大事にしてやるのが育児だし、それを見つけることが子育ての楽しさなのではないでしょうか。コロナを機に、そういったことを話し合えるといいですね。
コロナという岐路に立つ私たち
※対談のあとは、インターネットライブ配信に参加してくださった方からの質問に先生たちが答えてくださいました。
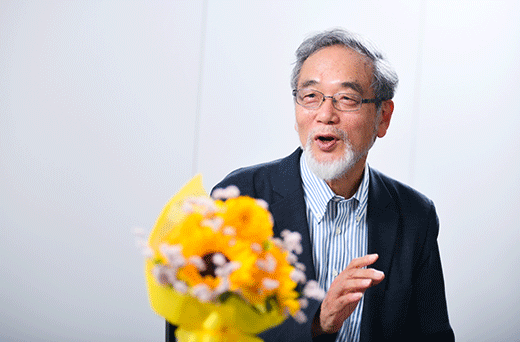
参加者:コロナ禍において制限される生活の中で、子どもたちのためにも、これだけは守らなければならないと思うことはありますか?
汐見:いついかなる状況においても、子どもたちの成長は待ったなしなので、プールがダメなら代わりにどうするのか。最大限の警戒はしつつも、密にならないやり方で、子どもたちのやりたいことが存分にできる保育を模索していくべきだと思います。
また、もし園児や職員がコロナにかかってしまったら、どこに連絡すべきなのか。万が一のとき、とっさに動けるようシミュレーションしておくことが重要です。これからも必要な警戒はしながらも、委縮しすぎることのないよう備えていけたらいいですね。
参加者:今後ますます予測不可能な社会を生き抜いていく子どもたちに、どのような力がつくように保育していくべきでしょうか?
汐見:コロナのような未曾有の危機に直面した際に、どんな知恵を絞ってどう行動すれば、自らの問題を解決に近づけることができるか。もうずいぶん前から表出している危機、たとえば地球環境問題しかり、食糧危機問題しかり、それらの問題はもう行きつくところまで来ているという認識を子どもたちと共有し、国連で世界各国のリーダーによって定められたSDGs(持続可能な開発目標)を日々の暮らしの中で実践する。そういった次世代の担うべき役割や姿勢を忘れないための保育をしていくべきだと思います。今日はもう時間がなくて詳しいお話ができないのですが、「SDGsと保育」という本を近いうちに出しますね(笑)
井上:誰もが未知の体験をしていて、この先どんな風に変化していくのかも見通せない。だからこそ、大人一人ひとりが「今できること」をやっていって、子どもたちにしてやれることは何なのかを具体的に模索していけたらと思います。そして「大丈夫だよ」と、子どもの背中を押せる大人でありたいし、皆様にもそうあってほしいと心から願っています。
汐見:人類の危機は英語でCrisis(クライシス)。クライシスは分かれ道という意味なんです。今まで歩んできた道をそのまま行くのか、新しい道を進むのか。コロナを機に分かれ道に立たされた私たちは重要な選択を迫られています。保育や育児にかかわるすべての大人の知恵比べでもあるのではないでしょうか。
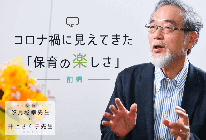
汐見先生と井上先生の対談を聞いて、誰もが「コロナと言う状況に、嘆いてばかりはいられない」と思ったのではないでしょうか。汐見先生のおっしゃったように「いついかなる状況においても子どもの成長は待ったなし」です。コロナという分かれ道を前に、最善の道を選び、進んでいきたいものです。
【対談前編|保育の楽しさってなんだろう?】コロナ禍に見えてきた「保育の楽しさ」はこちら!
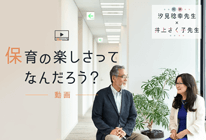
こちらの対談の様子を動画でも配信中です。
いままでにないボリュームで、ここでしか見れない見ごたえある内容になっておりますのでこちらもぜひご覧ください!
【動画】保育の楽しさってなんだろう?
お話を聞いた人

汐見稔幸(しおみ・としゆき)
大阪府生まれ。東京大学名誉教授。
東京大学大学院教授、同教育学付属中等教育学校校長を経て、白梅学園大学・同短期大学学長を2018年3月まで歴任。専門は教育人間学、保育学、育児学。
子どもの教育に幅広くかかわる教育者であり、NHK教育テレビをはじめとする子育て番組などのコメンテーターとしても人気。

井上さく子(いのうえ・さくこ)
岩手県遠野市生まれ。保育環境アドバイザー。
元東京都目黒区立ひもんや保育園の園長職を最後に38年間の保育士生活を終える。新渡戸文化短期大学非常勤講師を経て、保育環境アドバイザーとして研修会講師、講演活動、執筆活動を通じて子どもの世界を広く人々に伝える活動にまい進。
『だいじょうぶ~さく子の保育語録集』、『赤ちゃんの微笑みに誘われて~さく子の乳児保育』と著作多数。
また「遠野あとむ」のペンネームで詩作、朗読、イラストレーターとしても活動中。








