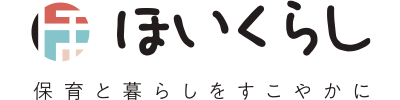「ほめて育てる」には大きな弱点がある!?心理学博士・榎本博明さんに聞く、子どもをダメにしないほめ方・叱り方

近年、「子どもはほめて育てよう」という意識が定着し、子どもを叱らない保護者が増えたといわれます。確かに、「叱る」のはとてもエネルギーがいる行為です。また、一時的であっても、叱ったあとは子どもとの間に気まずい空気が流れます。それを考えれば、「叱らずに子育てできるなら、それにこしたことはない」と思う人が多いのもうなずけますよね。
しかし、ほめてばかりの子育てが広まった結果、まっとうな助言であっても「攻撃された」と感じて傷つく若者や、困難に遭遇すると途端に心が折れてがんばれない若者が増えていると、心理学博士の榎本博明さんは指摘します。そうならないために、保護者そして保育者は、子どもたちをどのようにほめ、どのように叱ればよいのでしょうか。
\お話をうかがった方/
榎本博明さん
心理学博士、MP人間科学研究所代表。東京大学教育心理学科卒業。東芝に入社後、東京都立大学大学院へ。川村短期大学講師、カリフォルニア大学客員教授、大阪大学大学院助教授などを経て、MP人間科学研究所を設立。心理学をベースに、執筆、企業研修・教育講演など幅広く活躍する。『ほめると子どもはダメになる』(新潮社)、『伸びる子どもは○○がすごい』(日本経済新聞出版)『自己肯定感という呪縛』(青春出版社)、『勉強ができる子は何が違うのか』(筑摩書房)など著書多数。

「ほめる子育て」では、ホンモノの自己肯定感につながらない!

――「子どもはほめて育てよう」という風潮はいつごろから、どのような理由ではじまったのでしょうか。
榎本:1990年代に、欧米の教育論の表面だけをまねて生まれた風潮です。子どもに限らず、他者に厳しいことをいって鍛えあげるのは、とてもエネルギーがいる行為ですよね。おまけに、厳しいことをいえば気まずい雰囲気になったり、相手に嫌われたりする可能性もある。そうした事態はできるだけ避けたいと思うのが人情です。だからこそ、「子どもはほめて育てよう」「叱らなくてもいい」というメッセージは、多くの人にとって魅力的だったのでしょう。「やさしいお母さん」「理解のあるお父さん」だと思われたい保護者に支持され、急速に広がりました。
――「欧米の教育論の表面だけをまねた」とのことですが、欧米と日本の「ほめて育てる」にはどういった違いがあるのでしょう。
榎本:私自身、アメリカで子育てをした経験があるのですが、アメリカやヨーロッパには、「子どもをほめるときはしっかりほめる」という感覚が根づいています。「愛しているよ」「大好きだよ」といった言葉がけも積極的にします。
けれどそれは、普段の対応が非常に厳しいからなんです。欧米では、親や教師は絶対であり、子どもはそれに従うのが社会のルール。子どもは小さいうちから親とは別の寝室で寝て、学校の成績が悪ければ容赦なく留年や退学になります。会社だってそう。アメとムチでいえば、子どもを取り巻く社会環境がムチなんです。だから親は、適切なタイミングで「ほめる」というアメを差し出し、子どものやる気を引き出したり、親子間の信頼関係を築いたりする。日本ではそうした文化的背景を省みずに、アメの部分だけを取り入れてしまったわけです。
欧米に比べると、日本はもともとが子どもにやさしい社会です。子どもと一緒に寝るのは当たり前だし、泣けばすぐにあやします。学校は出席日数が足りなくても、それぞれの学年に見合う学力が育ってなくても、なんとか進級させようとします。
つまり、子どもを取り巻く環境がアメの日本では、親や大人があまりほめずに叱ることでアメとムチのバランスがとれていたのです。しかし、叱らない子育て、ほめる子育てが普及した結果、子どもはアメだけをもらって育つようになってしまいました。
――叱られず、ほめられて育った子どもにはどんな特徴がありますか。
榎本:叱られた経験がないと、他人からのアドバイスや注意をきちんと受け止められなくなります。正しいやり方を指示されただけなのに、「攻撃された」「自分を否定された」と感じて傷ついて、心が折れてしまうのです。なかには、開き直って自分を正当化する子もいます。
「ほめられる」というのは、他人にポジティブな気分にさせてもらっているということです。そして、他人にポジティブな気分にさせてもらうのに慣れてしまうと、ネガティブな状況に耐えられなくなります。その結果、傷つきやすくて、忍耐力がなくて、がんばれなくなる。それが、叱られずにほめられて育った子どもたちの大きな特徴といえるでしょう。
ちなみに、「心が折れる」という表現も、ほめる子育てが広がって以降に出てきたものです。そのせいなのか、頑張れない自分を正当化するような場面で使われがちですよね。
――ほめて育てると「自己肯定感が高まる」といわれますが、その点についてはどう見ていますか?
榎本:自己肯定感というのは、2000年代のはじめころから使われるようになった言葉です。一般には、ありのままの自分を認めて大切に思う感覚を指しており、以前は「自尊感情」といわれていました。
もしかすると、「自己肯定感は他者に肯定されることで育つもの」と思っている人がいるかもしれませんが、ホンモノの自己肯定感は、他者からの称賛を必要としません。「成長できた」「本当にがんばった」という本人の実感こそが自己肯定感につながるのです。また、自己肯定感と向上心は密接に関わっています。ホンモノの自己肯定感には、ありのままの自分を受け入れるだけでなく、「成長して欠点を克服する」という動機づけ、つまりは向上心も含まれているからです。
ところがいまは、「がんばらなくてもいい」「無理しなくてもいい」という風潮が強まっています。そのうえ、大人は子どもをこぞってほめようとします。そのせいで子どもたちは、ほめられていい気持ちにしてもらうのが当たり前になり、結果的に「これでいいんだ」「いまのままでいいんだ」と思ってしまう。それって、ホンモノの自己肯定感でしょうか。自己肯定感ではなく、自己満足にすぎませんよね。
そうしたニセモノの自己肯定感は、望むような結果が出なかったり、ほめられなくなったりすると途端に失われてしまい、「でもがんばってみよう」「次はできるかもしれない」という思考や行動につながりません。ホンモノの自己肯定感を身につけなければ、ネガティブな状況や苦しい状況、逆境にとても弱い人間になってしまうのです。
――当の子どもたちは、ほめられて育ったことをどう感じているのでしょう。なかには、デメリットだと考えている子どももいるのではないでしょうか。
榎本:以前、「自分たちは叱られてこなかった世代だけど、ほめるだけの子育てはおかしいと思っている」という中学生に対するコメントを依頼されたことがあります。
大学生のなかにも、周囲の友人の言動を見て「叱られることに耐性がない自分たちはこのままで大丈夫だろうか」と心配する子や、「ほめればいいと思っている自分の母親を見ていると悲しい気持ちになる」「以前は親がほめるばかりの友だちが羨ましかったけど、そういう子はすぐに心が折れるから、今は親に心を鍛えてもらってよかったと思ってる」などと話す学生がいました。
少ない事例ではありますが、違和感を抱いている子どもは一定数いるようですね。
「プロセス」と「姿勢」をほめれば、「チャレンジ精神」や「やる気」が育つ

――とはいえ、子どもをまったくほめないというのも、現実的に難しいと思います。子どもをダメにしないほめ方というのはあるのでしょうか。
榎本:よく誤解されるのですが、私は「子どもをほめるな」と主張しているわけではありません。ほめられれば誰だってうれしいですし、適切にほめてあげればホンモノの自己肯定感を育むこともできます。
では、どんなふうにほめればよいのか。まずは、なんでもかんでもほめるのをやめましょう。大したことをしていないのにほめると、子どもは「なんだ、この程度でいいんだ」と思ってしまい、安易な姿勢が身についてしまいます。あるいは、「これくらいでほめられるなんて、自分はあまり能力がないのかも」と感じてしまう可能性もあります。
そして、勉強でもスポーツでも日ごろの行いでも、ほめるときは「結果」や「能力」ではなく「プロセス」や「姿勢」をほめてあげてください。
たとえば、子どもがテストでいい点数をとったとしましょう。このとき、「100点なんてすごいね」「こんなにいい点数がとれたのは、あなたの頭がいい証拠ね」というふうに「結果」や「能力」をほめるのはおすすめしません。子どもはその「結果」や「能力」を守ろうとしてしまい、より難しい課題に挑戦するような冒険をしなくなるからです。
反対に、「がんばっていてえらいね」「こんなにいい点数がとれたのは、一生懸命努力したからだね」という具合に「プロセス」や「姿勢」をほめると、難しい課題や局面にもチャレンジしてみようという意欲が育まれます。これは、心理学の実験でも証明されているので、ぜひ知っておいてください。
国際化が進むいまだからこそ、国民性に合った叱り方を見直すべき

――ほめるだけの子育てにはデメリットがあると理解できても、いざ叱るとなると戸惑う人もいるかもしれません。上手に叱るコツはありますか?
榎本:近年、社会はめまぐるしく変わっています。変化のスピードは今後さらに上がるでしょう。そんな予想困難な社会を生きていく子どもたちに必要なのは、ホンモノの自己肯定感であり、難しい課題や局面にぶつかってもチャレンジしてみようと思える強い心です。「生きる力」といったほうがわかりやすいでしょうか。
生きる力は、ほめているだけではけっして育まれません。大人はそのことを肝に銘じ、「子どもの将来を見据えた教育をするんだ」という心がまえを、まず持ってほしいと思います。子どもを本当に大切に思っての行動なら、それは必ず子どもにも伝わります。叱られて一時的に傷ついても、乗り越えられるはずです。
ただし、むやみやたらに叱ればいいといっているわけではありません。私が子どものころは、親から「人に見られてみっともないまねはしちゃいけないよ」「そんなことをしていると、ほかの人に笑われるよ」といわれたものですが、そうした言葉は日本人に合った上手な叱り方といえるのではないでしょうか。
最近は欧米志向の高まりから、「人の目を気にする日本人はダメだ」なんていわれていますが、人の目を意識することは、自分を客観視することや、他者を尊重することにつながります。そういう意味でさきほどの言葉は、協調性や謙虚さを大切にする日本らしい叱り方だと思うのです。
――国民性に合った叱り方というのは、面白い視点ですね。ほかにも、似たような言葉はありますか?
榎本:「いい子だからやめようね」という叱り方も、人の目を意識する日本の国民性に合っていますよね。まわりの期待に応えたい、いい子だと思われたいという気持ちは多かれ少なかれ誰もが持っているものですが、それを「いい子だから」という言葉で刺激してあげるわけです。
すると子どもは、「いい子でいるためにはどうしたらいいのだろう」と考え、自分で自分の言動をコントロールできるようになる。国際化が進むいまだからこそ、ひたすら欧米のまねをするのではなく、日本人の特性を生かした叱り方、ひいては教育を実践していくことも重要ではないでしょうか。
ほめるときはほめ、叱るときは叱り、ダメなことはダメだというのが大人の役目

――保育の現場では、「子どもを叱ると保護者からクレームがくる」という悩みが聞かれます。こうした状況に保育者はどのように対応したらよいのでしょうか。
榎本:多くの保育者が同様の悩みを抱えているようですね。ある保育者から、「子どものためを思って叱ったつもりなのに、『親の私も叱ったことがないのに、なんで先生がうちの子を叱るんですか』と怒鳴られた」という話を聞きました。「子どものためだと思っても叱ってあげられない。鍛えてあげられない」という声も聞きます。
若い保護者のなかには、自分自身が叱られずに育ってきたせいで、叱られた経験も叱った経験もない人が多いのかもしれません。けれど、本当に子どもの将来を思うなら、保護者の意識を少しずつでも変えていく必要があるでしょう。
とはいえ、保育者が保護者に直接「ほめて育てるばかりではダメですよ」といったら角が立ちます。ですから、保護者との会合や保護者へのおたよりなどを通じて、ほめるだけの子育ての弊害について解説した記事や本を紹介してみてはどうでしょう。専門家を招いて講演をしてもらうのも、ひとつの方法だと思います。
幼児教育は、子どもの人生に大きな影響を与えます。いずれは社会の荒波に漕ぎ出す子どもたちのために、ほめるときはほめる、叱るべきときは叱る、ダメなことはダメだというのが、私たち大人の役目です。子どもたちの「生きる力」をしっかり育てて、それぞれの未来へと送り出しましょう。
取材・文/小川裕子