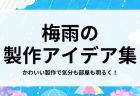保育士の自己評価はなぜ必要?自己評価の流れやポイント、記入例を紹介

文: アリサ(保育士ライター)
保育士の仕事に欠かせないのが自己評価です。自己評価で日々の保育を定期的に振り返ることで、子どもに対する気付きを得たり、理解を深めたりすることができます。
しかし、自己評価の流れや、どのように書けばいいのか分からないと悩む保育士もいるのではないでしょうか。
この記事では、保育士の自己評価とはなにか、自己評価の流れ、大切にしたいポイント、自己評価の3つの観点、記入例を紹介します。
保育士の自己評価とは?

保育士の自己評価は、自分の保育を振り返り、良い点や課題を見つけて、今後に活かすために行われます。
自己評価というと、良し悪しを判断するためのものとして捉えられがちですが、保育士の自己評価は、保育の良し悪しや出来・不出来を表すものではありません。
日々の保育の意味を考え、子どもについての理解をより深めることで、よりよい保育を目指すことが目的です。
厚生労働省の「保育所保育指針」において、保育士の自己評価とその公表が努力義務として位置付けられているため、自己評価による振り返りを実施している園も多いでしょう。
保育士の自己評価の流れ
基本的な自己評価は以下の流れで行います。
- 日々の保育の記録などに基づき、子どもの内面や成長の理解を踏まえ、保育を振り返る
- 保育目標に対して、改善点や充実させたい点を見出す
- 今後の保育で目指す方向性と具体的な取り組み、方法を検討する
- 自己評価の結果を指導計画などに反映させ、実践する
1~4の流れを定期的に繰り返し、子どもの姿と保育について振り返ることでよりよい保育を目指します。
※上記の例は一例です。上記以外に自己評価のフォーマットが園ごとに決められている場合もあります。
自己評価を作成するときのポイント

保育士が自己評価をするにあたり、大切にしたいポイントを見ていきましょう。
子どもの視点で保育を振り返る
保育士の自己評価では、保育士である大人から見た問題点だけに目を向けるのではなく、実際の子どもの姿を通して、子どもの視点から自分の保育を振り返ることが大切です。
具体的には、以下のような視点が考えられます。
- 子どもがどんなことに興味があり、どう感じているのか
- 遊びをさらに発展させるためにはどのようにすればいいのか
一人ひとりの個性や成長しつつある力などから多面的に考えてみるとよいでしょう。
周囲の保育士の視点も取り入れてみる
保育士が自己評価を通じて子どもや保育についての理解を深めるうえで、自分の思いを他の保育士に伝えたり、周囲の保育士と意見を交換したりすることがとても重要です。
保育士同士で対話を活発に行うことで、園全体で子どもや保育について考える雰囲気が生まれます。また、それぞれの保育士の持ち味や専門性、経験などを活かした、より良い保育の実現に向けたアイデアが出やすくなります。
自己評価における3つの観点

厚生労働省の「保育所における自己評価ガイドライン」で参考として示されている以下の3つの観点があります。
- 保育の基本的理念と実践に係る観点
- 家庭及び地域社会との連携や子育て支援に係る観点
- 保育の実施運営・体制全般に係る観点
園によって自己評価の項目が定められていることもありますが、これらの観点をベースに自己評価を考えてみましょう。以下で、3つの観点について具体例を説明します。
1.保育の基本的理念と実践に係る観点
1つ目は、子どもに関する観点です。主な評価項目は以下のようなものが挙げられます。
- 子どもの最善の利益を考慮したか
- 子どもの一人ひとりの成長や個性、他者との関係を理解したか
- 保育のねらいや内容が子どもたちの発達や実態に即したものであったか
- 保育の環境構成(人・物・場)が適切に用意されていたか
- 保育士の子どもへの関わりは適切であったか
- 成長の見通しを持ち、計画を立てることができたか
常に子どもの立場に立って保育を展開できたか、子どもの今をしっかりと見据えていたかを評価します。
2.家庭及び地域社会との連携や子育て支援に係る観点
2つ目は、保護者や地域との連携に関する観点です。主な評価項目は以下のようなものが挙げられます。
- 家庭環境を理解し、保護者との相互理解はできていたか
- 地域の保護者に対し、相談や助言、園庭開放などといった子育て支援を行ったか
- 地域の人や近隣の園、小学校との連携はできたか
保育を行う上で、周囲と連携を取ったり必要な支援を行ったりすることができていたかを評価します。
3.保育の実施運営・体制全般に係る観点
3つ目は、園の運営や同僚との関係性に関する観点です。主な評価項目は以下のようなものが挙げられます。
- 園の保育方針を理解していたか
- 法令の遵守や個人情報の取り扱いなど社会的責任を遂行していたか
- 子どもの健康及び安全の管理を行ったか
- 職員間で協力し合いながら主体的に学び合い、保育を実践できたか
園の保育方針を正しく理解し、職員間で連携を取りながら安全に保育を進めることは基本です。社会人としての常識を持ち、園の一員として適切な行動ができたか、周囲との関係性を築くことができたかを評価します。
【経験年数別】自己評価の記入例

保育士は経験年数によって、スキルや職場での立場に差が出やすいものです。自己評価を記入する際には、自分の経験年数に合わせた目標を立てるとよいでしょう。
ここでは、経験年数別の状況と目標例を解説してから、自己評価の記入例を紹介します。
【経験年数】1年目~3年目の保育士
経験年数が1年目~3年目の保育士は、園の保育方針を正しく理解し、基本的な業務や社会人としての振る舞いを覚える時期です。様々な研修を通して保育のスキルを磨く時期でもあります。
先輩保育士に指導してもらうことも多いため、疑問点は積極的に聞き、解消しておくことが大切です。
また、高すぎる目標だと、現実との差を感じてモチベーションを保てない可能性があります。自分にとって無理のない目標設定を行い、小さい目標でも達成していくことで自信にも繋がるでしょう。
目標例
1年目~3年目の保育士の目標例は以下の通りです。
- 毎日子どもと笑顔で接する。
- 分からないことをそのままにせず、先輩保育士に質問して解決する。
- 先輩保育士や保護者などに対し、報告、連絡、相談を欠かさないようにする。
自己評価例
目標に対する、自己評価の例は以下の通りです。
- 毎日子どもたちと笑顔で接することで、子どもたちにも笑顔が増え、安心して園生活を送る様子が増えた。
- 分からないことはすぐに質問し、その日のうちに解決するようにした。しかし、すぐに何でも聞くのではなく自分なりに考えることも大切にしていきたい。
- 小さなことでも報告、連絡、相談するようにしたことで、先輩保育士や保護者との信頼関係を築くことに繋がった。
【経験年数】4年目~7年目の保育士
保育士の4年目~7年目は、基本的な業務にも慣れ、さらなるスキルアップをする時期です。園によっては責任のある業務を任され、後輩への指導も増える頃で、徐々に園内で中心の存在になっていくでしょう。
目標例
4年目~7年目の保育士の目標例は以下の通りです。
- 子どもの個性を尊重するクラス運営を行う。
- 月に2回はクラスだよりを発行したり、登降園時に見れるよう保育中の写真を掲示したりし、保護者に園生活の様子や保育のねらいを伝えていく。
- 進んで新人保育士の指導に関わり、相談を受ける。
自己評価例
目標例に対する、自己評価の例は以下の通りです。
- 一人ひとりの子どもの興味や関心に寄り添い、子どもの素敵な部分は言葉にして認めていくことで、子ども同士でお互いの良さに気付きあう姿があった。
- 月に2回はクラスだよりを発行することで、現在の活動や子どもたちの日々の成長をこまめに保護者に伝えられた。クラスだよりに写真を入れることも検討したい。
- 新人保育士に対し、自分の経験を話したり参考になりそうなアイデアがあれば提供したりした。
【経験年数】8年目以上の保育士
経験年数が8年目頃になると、ベテラン保育士という立ち位置になるでしょう。日々の保育はもちろん、園の運営に対しても関わる機会が出てくる場合もあります。また、地域の方や関係施設との連携も積極的に行う立場にもなります。
目標例
8年目以上の保育士の目標例は以下の通りです。
- 「保護者支援」や「障がい児保育」に関する研修に参加し、スキルアップをする。
- 園長や副園長、主任保育士などと連携し、園の現状や課題について話し合う。
- 各クラス担任と連携をとりながら、支援が必要な家庭への援助、助言を行う。
自己評価例
目標に対する自己評価の例は以下の通りです。
- 目標としていた研修に参加し、知識を深めることができた。今後、園内でも共有していきたい。
- クラス担任と連携を取り、園全体の把握に努めた。意見をとりまとめ、園長や副園長、主任保育士とも連携を取ることができた。
- 支援が必要な家庭には登降園時にこまめに話をしたり、必要なときには助言したりし、信頼関係を築くことができた。
自己評価を行い、子どもにとってよりよい保育を目指そう

保育士が自己評価を行うことで、子どもへの理解が深まり、保育の質向上へと繋がります。また、自分の保育の良さに気付いたり、課題が明確化したりするため、保育士としての資質や専門性の向上も期待できます。
保育士は経験年数によってスキルや課題が異なります。自己評価を行う際は、経験年数や園内での立場を考慮し目標を立てるとよいでしょう。
保育士の自己評価は、個人の良し悪しや出来・不出来を判断するものではありません。多角的な観点から子どもの姿を見つめ、子どもの立場に立って考えることが大切です。感じたことや考えたことを今後に活かして、よりよい保育を目指しましょう。
保育園で0歳児から5歳児までの担任や障がい児加配、縦割り保育を約10年間経験。家庭の事情で退職後、今までの知識を活かした活動がしたいとの思いからライターに。現在は2歳と5歳の子どもの育児に奮闘しながら、保育士さんや子育て中の方に向けて記事執筆を行っている。絵本とお花が大好き。
保有資格:保育士・幼稚園教諭一種免許
【関連記事】
保育士に目標設定が重要な理由|わかりやすい目標の例文・ポイント
フリー保育士の目標設定はどう立てる?ポイントや例文を紹介
参考サイト: