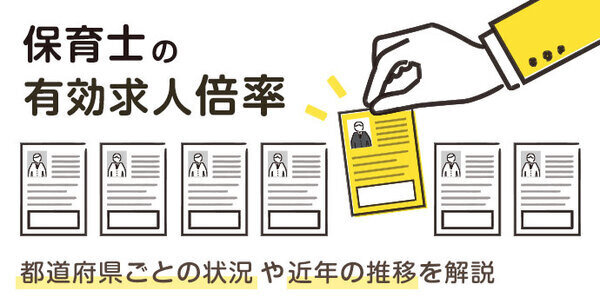
保育士として就職・転職を目指す方にとって、実際の求人状況は重大な関心事です。希望のエリアで保育士の求人がどれくらい存在するのか、保育士の求人が多いエリアはどこなのか、といったことを知らなければ、スムーズな就活は行えません。
保育士の求人状況を客観的に捉えるための指標として欠かせないものが、「有効求人倍率」です。この記事では、保育士の有効求人倍率について、都道府県ごとの状況や近年の推移について解説します。
目次
保育士の有効求人倍率とは
有効求人倍率とは、「仕事を求めている求職者数」に対する「企業が求めている求人数」の割合を指します。簡単に言えば、仕事を探している方に対して、どの程度の働き先があるのかを示す指標です。
経済指標として重要な数字のひとつで、景気の影響を大きく受けるため、雇用情勢を調べるために必ず参照される指標となっています。
有効求人倍率は、以下の式で求めることができます。
(企業からの求人数)÷(求職者数)=有効求人倍率
有効求人倍率について、いくつかの参考例を紹介します。
【100人分の求人数に対して、50人の求職者が存在する】
100人÷50人=有効求人倍率:2.0倍
【100人分の求人数に対して、100人の求職者が存在する】
100人÷100人=有効求人倍率:1.0倍
【100人分の求人数に対して、200人の求職者が存在する】
100人÷200人=有効求人倍率:0.5倍
有効求人倍率が1.0倍より高い場合は、応募者よりも求人数が上回っている「売り手市場」です。一方、有効求人倍率が1.0より低い場合は、すべての求職者が職を得ることができない「買い手市場」となります。
保育士の有効求人倍率

保育士の有効求人倍率は、厚生労働省の資料によると令和2年4月時点で2.45倍であり、ひとりの保育士に対して2件以上の求人があることとなります。
同時期における全職種平均の有効求人倍率は1.32倍となっており、他の職種と比較しても保育士の有効求人倍率は、非常に高い数値です。
(出典:厚生労働省「保育士の有効求人倍率の推移(全国)」 https://www.mhlw.go.jp/content/000636780.pdf)
このような保育士不足の状況を踏まえて、国や自治体による保育士確保を積極的に進める活動が活発化しています。
都道府県ごとの有効求人倍率
全国平均で見た保育士の有効求人倍率は2.45倍(令和2年4月時点)ですが、実際には都道府県ごとに大きな差があります。同じく令和2年4月時点のデータで見た有効求人倍率の上位5県と下位5県は次の通りです。
| 上位5県 | 下位5県 | ||
|---|---|---|---|
| 広島 | 4.37 | 山口 | 0.99 |
| 大阪 | 3.66 | 高知 | 1.07 |
| 宮城 | 3.55 | 島根 | 1.24 |
| 東京 | 3.41 | 青森 | 1.25 |
| 滋賀 | 3.37 | 長崎 | 1.27 |
(出典:厚生労働省「保育士の有効求人倍率の推移(全国)」/ https://www.mhlw.go.jp/content/000636780.pdf)
基本的に大都市とその近郊が高い数値を記録している傾向がありますが、福岡(1.83倍)では平均値を下回っています。また、鳥取(2.74倍)や静岡(2.78倍)といった地方部でも、平均値を大きく上回っている地域があります。
そのため、単純に大都市と地方で有効求人倍率の差を説明することはできません。地域ごとの特性(行政による支援政策の違いなど)によって、各エリアの有効求人倍率の差が生まれていると推測できます。
近年の有効求人倍率の推移
ここでは、近年における保育士の有効求人倍率の推移を紹介します。以下の表は、厚生労働省の資料を参考に、平成26年から平成30年までの11月時点での有効求人倍率を抜粋したものです。
| 平成26年 | 1.67 |
|---|---|
| 平成27年 | 2.09 |
| 平成28年 | 2.34 |
| 平成29年 | 2.37 |
| 平成30年 | 3.20 |
(出典:厚生労働省「「保育士確保集中取組キャンペーン」について」/ https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Hoikuka/0000110430.pdf)
(出典:厚生労働省「「保育士確保集中取組キャンペーン」を実施します」/ https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Hoikuka/0000148854.pdf)
(出典:厚生労働省「「保育士確保集中取組キャンペーン」を実施します」/ https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/jinzaikakuho_torikumi.files/kakuho.pdf)
平成26年以降、年を追うごとに保育士の有効求人倍率は高まってきていることがわかります。平成29年から平成30年にかけては、約35%もの増加率です。
このように、保育園が求める人数に対して、保育士が不足している傾向は年々強まってきていることが有効求人倍率の推移から読み取れます。
保育士の有効求人倍率が高い理由
近年における保育士の有効求人倍率は2倍を超える数値を記録しており、全職種の倍近い数字となっています。
なぜ、保育士の有効求人倍率は他の職種に比べて、非常に高くなっているのでしょうか。ここでは、保育士の有効求人倍率が著しく高い理由について、解説します。
保育需要の高まり
保育士の有効求人倍率が高まっている主な理由は、保育園に子どもを預けたいというニーズが増えてきていることが挙げられます。
かつては、小さな子どもを抱える家庭では専業主婦が一般的でしたが、近年は共働きの家庭が増えています。また、以前は二世帯住宅が多かったですが、近年は核家族化により子どもの面倒を夫婦だけで見なければなりません。
このような社会環境の変化により、長時間子どもの面倒を見てくれる保育園への需要が高まり、保育園に通いたくても通えない待機児童の問題が発生しています。保育需要の高まりにともなう、待機児童問題は都市部ほど深刻です。
保育サービスの不足を解決するために、多くの自治体では保育園の定員増や新規施設の設立を推進しており、結果的に保育士のニーズが高まっています。
保育士のなり手不足
保育士の有効求人倍率が高い理由としては、保育士のなり手が不足していることも挙げられます。保育士のなり手が不足している原因としては、以下のものがあります。
・保育士を養成する学校を卒業したにもかかわらず、保育士として働かない方が多くいること
・保育士として働く人の多くが、5年未満の早期に離職してしまうこと
「潜在保育士」と呼ばれる、保育士の資格を持ちながらも保育士の業務を行わない方が多くいます。潜在保育士を生み出してしまう原因としては、以下のものがあります。
・幼い子どもを預かるという責任の重さや、業務量の多さに見合わない給与水準
・現場での保育士の不足によって生じる、長時間労働・休日の取りづらさ
つまり、労働条件・環境の問題により、仕事として保育士を選択する方が少ないことによって、有効求人倍率が高くなっています。ただし、近年は保育士を集めるために、労働条件の改善に力を入れる自治体が増加しており、給与水準や休暇の取りやすさは改善傾向にあります。
保育士不足に対する行政の対策
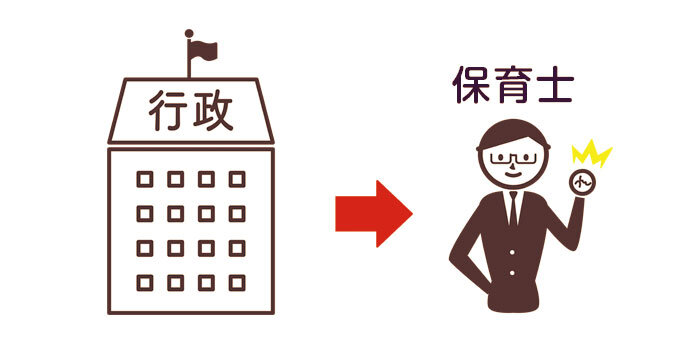
保育士の人手不足は全国的に見られ、多くの自治体は人材不足を解消するための対策に取り組んでいます。多くの自治体で導入されている保育士不足への対策としては、以下のものがあります。
・上乗せ手当の支給
対象となる自治体で働く保育士に対して、勤続年数などに応じた手当を職場からの給与とは別に支給する制度です。勤続年数が増えるほど金額が増えていく仕組みとなっている場合が多く、保育の仕事への定着を促進します。
・家賃補助制度
保育士が不足している地域の自治体が、他の地域から転居して勤務する保育士を呼び込むために実施している施策です。
都市部では月額80,000円程度を上限に設定されていることが多いですが、地域によって金額は異なります。転居して数年間は、家賃についてほぼ自己負担なしで生活できる自治体も少なくありません。
・就職一時金・定着支援金
毎月支払われる給与のような手当ではなく、ボーナスのような形でまとまった金額の一時金を支給する自治体も存在します。保育士として就職が決定した方に支払われる就職一時金や、勤続年数に応じた定着支援金の形で支払われることが多い傾向です。
就職一時金は、就職・転職にともなう出費を支援し、スムーズな入職をサポートします。定着支援金は、保育士として継続して働く方を経済的に支援する制度です。
現在、保育士として就職や転職を考えている方は、有効求人倍率の高低だけではなく、このような支援制度の充実度も参考にしましょう。
まとめ
保育士の有効求人倍率は、他の業種と比較して非常に高い水準にあります。都道府県ごとに比較すると、東京や大阪など大都市部で有効求人倍率の高いことがわかります。ただし、地方部でも全国平均より高いエリアが存在するため、保育士の不足は全国的な問題です。
保育士不足の原因としては、保育需要の高まりと保育士のなり手不足があります。多くの自治体では、保育士の不足を解消するため、積極的に支援制度の導入を進めています。
保育の仕事に関心を持つ方は、有効求人倍率の高い現在の状況を活かして、自分の理想を実現できる職場を探してみてはいかがでしょうか。









