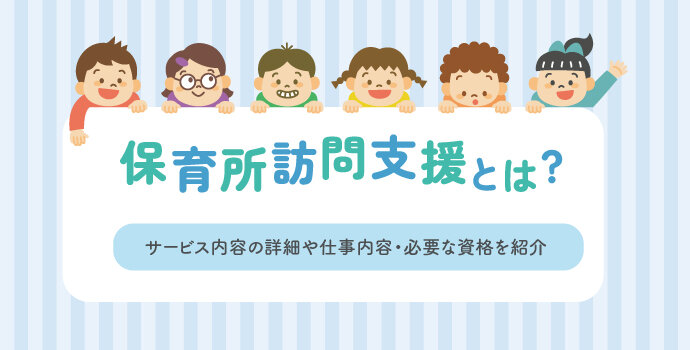
学童保育や放課後等デイサービスなど子どもを支援するサービスは多くあり、その中でも障害を持つ子どもに対して専門的な支援を提供するサービスが「保育所等訪問支援」です。障害を持つ子どもが集団生活で起こる困り事を、専門知識を持った支援員が実際に施設へ訪問し、問題の原因を分析し快適に過ごせるよう支援します。
当記事では、保育所等訪問支援の目的やサービス内容の詳細などを詳しく解説します。保育所等訪問支援の支援員として活躍したいという保育士の方も、ぜひご一読ください。
目次
保育所等訪問支援とは?目的を解説
保育所等訪問支援とは、障害のある子どもが保育所や学校などで集団生活を送るために、専門的な支援を提供するサービスです。2012年の児童福祉法改正で創設され、「児童福祉法」に基づく第2種社会福祉事業として位置づけられています。
主な目的は、障害のある子どもが安心して快適に過ごせる環境を整え、健やかな成長と発達を支援することです。保育所等訪問支援は、保護者からの依頼に基づいて行われます。訪問先と保護者の間を取り持つことで保護者の不安を軽減し、子どもの成長をともに喜び合える関係の構築を目指す支援です。
(出典:厚生労働省「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」/ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000166361.pdf)
(出典:厚生労働省「保育所等訪問支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」/ https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001157666.pdf)
保育所等訪問支援が必要とされる理由
保育所等訪問支援は、障害のある子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を実現するために創設されました。障害のある子どもが地域社会でともに暮らすには、保育所や学校などの集団生活に適応する支援が必要です。集団生活の場では、家庭では見えにくい発達の課題が顕在化するケースが多く、早期発見と適切な支援が求められます。
また、通所型の発達支援事業所で習得したスキルを集団生活で生かすには、保育所などでの支援が欠かせません。さらに、通所支援から集団生活への移行後のフォローアップが不足している現状を改善するためにも、訪問支援が重要です。専門知識を持つ支援員が介入することで、子どもだけでなく保育士・教職員の方々にも適切な対応方法を伝えられます。
(出典:厚生労働省「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」/ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000166361.pdf)
保育所等訪問支援のサービス内容の詳細
厚生労働省の「令和4年社会福祉施設等調査の概況」によると、保育所等訪問支援事業の施設数は令和4年時点で2,281か所にのぼります。前年の1,930か所から、18.2%の増加を記録しました。これは、保育所等訪問支援が多くの方に求められているサービスであることを示す数字です。以下では、保育所等訪問支援のサービス内容を項目ごとに解説します。
(出典:厚生労働省「令和4年社会福祉施設等調査の概況」/ https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/22/dl/kekka-kihonhyou02.pdf)
申請者と対象者
保育所等訪問支援の申請者は、支援を希望する児童の保護者の方です。支援を利用するには、保護者が自治体に給付費支給申請を行う必要があります。施設側からの申請はできないため、保護者と施設が連携して支援の必要性を判断しなければなりません。
対象となる子どもは、主に保育所や幼稚園、学校などの施設に通っていて、集団生活における専門的支援が必要な障害児です。ただし、医学的診断や障害者手帳の有無は問われません。また、申請する時点である程度集団に適応できている子どもや、現在通所支援を利用していない子どもも、必要とあらば対象です。
(出典:厚生労働省「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」/ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000166361.pdf)
(出典:厚生労働省「保育所等訪問支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」/ https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001157666.pdf)
訪問支援の場所
保育所等訪問支援のサービスは厚生労働省令で定められた場所であり、以下のような子どもの集団生活の場で提供されます。
| 園・教育機関など | ・保育所・保育園 ・幼稚園 ・認定こども園 ・小学校 ・特別支援学校 |
|---|---|
| 市町村が認める施設 | 放課後児童クラブ(学童) ・放課後等デイサービス ・中学校 ・高等学校 |
| 入所施設 | 乳児院 ・児童養護施設 ・児童心理治療施設 ・児童自立支援施設 |
保育所等訪問支援は、保育所以外にも多岐にわたる施設で支援が行われるのが特徴です。上記以外にも、市町村が認める施設であれば対象となります。
(出典:厚生労働省「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」/ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000166361.pdf)
(出典:厚生労働省「保育所等訪問支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」/ https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001157666.pdf)
人員配置
保育所等訪問支援をサービス提供するセンターや事業所は、以下の人員配置の基準を満たさなければなりません。
- 訪問支援員
- 児童発達支援管理責任者(1人以上)
- 管理者
訪問支援員は、児童指導員・保育士・作業療法士・理学療法士・言語聴覚士・心理担当職員など、障害児支援に関する知識や経験が豊富な専門職が担当します。
訪問支援員は基本的に単独で支援を行うため、専門知識と経験が必須です。ただし、必要に応じて複数人で支援を行う場合もあります。また、特定の要件を満たす場合は「訪問支援員特別加算」の適用対象です。
(出典:厚生労働省「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」/ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000166361.pdf)
(出典:厚生労働省「保育所等訪問支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」/ https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001157666.pdf)
支援内容
保育所等訪問支援では、子どもへの「直接支援」とスタッフへの「間接支援」を行います。直接支援では、集団活動に加わりながら個別の発達支援を行い、障害のある子どもの適応をサポートします。支援する際は子どもの特性に合わせつつ、日常の生活や活動を妨げないよう配慮しなければなりません。
一方、間接支援では、保育士や教師に対して子どもの特性や適切な関わり方についてアドバイスを行い、環境の整備の補助や活動の工夫を提案します。また、保護者への丁寧な報告を通じて子どもの成長や支援の効果を共有し、不安を軽減するのも大切です。
(出典:厚生労働省「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」/ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000166361.pdf)
支援の頻度と時間・期間
保育所等訪問支援は、標準的には2週間に1回程度の頻度です。ただし、緊急性やニーズに応じて頻度は調整されます。1回の訪問で子どもへの直接支援とスタッフへの間接支援を合わせて、2時間から半日程度の支援時間が一般的です。
支援の継続期間は特に規定されていませんが、半年から1年ごとにモニタリングの結果に基づいた見直しが行われます。子どもや訪問先の状況や環境に応じて、訪問頻度や予定期間の調整を行い、目標が達成されたと判断されれば支援終了が決定します。
(出典:厚生労働省「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」/ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000166361.pdf)
保育所等訪問支援の仕事内容
保育所等訪問支援の仕事内容は、以下の通りです。
| 直接支援 | 子どもの集団生活の中に入り、子どもの特性や困難を観察します。指示が通りにくい子どもには、近くで見守りや声かけを行う、鉛筆の持ち方に困っている子どもには、太めの鉛筆を使わせるなどです。 |
|---|---|
| 間接支援 | 保育士の方や教師に対して子どもの特性や関わり方についてアドバイスします。発表会や運動会への参加方法の検討や、集中しやすい環境設定の提案などです。 |
| 環境整備 | 障害のある子どもが集団生活を送る際の環境整備も重要な業務です。障害に対する適切な理解を得られるよう、環境を整えることで子どもの困難を減らし、安心して生活できるようにします。 |
| 保護者への報告 | 保護者に対して、訪問支援の内容や子どもの様子、周囲の関わり方などを丁寧に報告します。保護者の不安を軽減し、支援の効果を共有することが重要です。 |
(出典:厚生労働省「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」/ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000166361.pdf)
以下は、訪問支援員の1日のスケジュールの例です。
【業務の流れ】
| 8:15 | 出勤 |
|---|---|
| 9:00 | 保育所へ訪問 |
| 10:30 | 学校へ訪問 |
| 12:00 | 休憩 |
| 14:00 | 保育所や学校との連絡調整 |
| 15:00 | 保護者との連絡調整 |
| 16:00 | 記録・報告・書類作成 |
| 17:15 | 退社 |
保育所等訪問支援の仕事は多岐にわたり、子どもが安心して集団生活を送るためのサポートを包括的に行います。
保育所等訪問支援で働くのに必要な資格
保育所等訪問支援で働くために取得が必要な、「訪問支援員」という特定の資格や認定制度は存在しません。ただし、訪問支援員は、子どもの特性に合わせた支援を行うため、相当の経験と専門的な知識が必要です。厚生労働省の指針で定められている、保育所等訪問支援の業務に就くための要件には、以下の資格が該当します。
- 児童指導員
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 心理担当職員 など
-
指定保育所等訪問支援の提供に当たる従業者の要件については、障害児支援に関する知識及び相当の経験を有する児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士又は心理担当職員等であって、集団生活への適応のため専門的な支援の技術を有する者とする。
(引用:厚生労働省「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」/ https://www.mhlw.go.jp/content/000789572.pdf 引用日2024/05/13)
各職種の専門性に応じて、対象児童や訪問先を割り振られるのが一般的です。なお、10年以上の障害児支援経験があるか、以下の要件を満たすと「訪問支援員特別加算」が適用されます。
-
・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・保育士の資格を有している
・児童指導員・児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者・心理指導担当職員のいずれかの職で、障害児支援に関する5年以上の経験がある
(出典:厚生労働省「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」/ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000166361.pdf)
まとめ
保育所等訪問支援とは、保育所や幼稚園、学校などの施設に通い、集団生活における専門的な支援が必要な障害児を対象に行われる支援サービスのことです。障害のある子どもが安心かつ快適に過ごせる環境を整え、健やかな成長と発達を支援します。子どもへの直接的な支援だけでなく、子どもに関わる保育士や教師の方々にもアドバイスをし、保護者に支援内容を共有するなど多方面で支援が行われるのが特徴です。
保育所等訪問支援で働くには、子どもの特性に合わせた支援を行うのに、相当の経験と専門知識が必要とされています。保育士も必要資格の中に含まれているため、専門性を高めたい方やキャリアアップをしたい方は、目指すのもよいでしょう。
※当記事は2024年6月時点の情報をもとに作成しています









