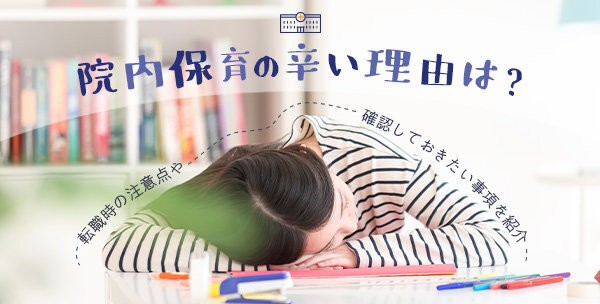
院内保育とは、病院で働くスタッフの子どもを預かる保育事業のことで、院内保育のために病院の敷地や隣接した区域に設置された施設を院内保育所と呼びます。
院内保育は、医療従事者の労働環境を改善する手段として重要な役割を担っています。しかし、院内保育所で働いている方のなかには、体力的な負担が大きかったり、生活のリズムが崩れがちになったりして、「仕事がつらい」と感じている方が少なくありません。いったい、なぜでしょうか。
当記事では、「なぜ院内保育の仕事をつらいと感じるのか」について詳しく解説します。また、院内保育所から他の職場に転職する際のポイントや注意点についても紹介するので、院内保育につらさを感じている方や、転職を考えている保育士の方はぜひご覧ください。
目次

院内保育がつらい理由は?

前述したように、院内保育所は病院に勤める医療従事者の子どもを預かる施設です。
院内保育所では一般的な保育園と同様、子どもたちの遊びや生活をサポートしますが、職員の勤務シフトにあわせる必要があるため、24時間365日体制で保育を行う点に特徴があります。また、利用者が病院職員だけとなるため、少人数の異年齢保育を行っているところがほとんどです。
少人数保育で子ども1人ひとりとじっくり向き合える点や、すぐそばに医療従事者がいる点を考えると、「院内保育所は働きやすそうな職場」だと感じる方も多いでしょう。しかし、実際に院内保育所で働いている保育士のなかには、「仕事がつらい」「きつい」と感じている方もいるようです。
ここでは、院内保育がつらいと感じる理由について、具体的に解説します。
体力がないと続かない
院内保育所の利用者は、病院に勤務する医師や看護師、コメディカル職などの病院職員です。職員が勤務するときに子どもを預けるため、保育士の勤務日は利用者によって左右されます。
職員のシフト次第では夜勤をすることもめずらしくはなく、急な手術などで預かり時間が延長されるケースもあるでしょう。
夜勤中は仮眠が取れるものの、随時子どもの様子を確認しなければならないため、ゆっくり休むことはできません。また、夜勤の場合は夕方から朝にかけて働くことになるため、一般の保育園と比べて生活のリズムが崩れやすくなります。そうしたことから疲れが取れにくくなり、「体力的につらい」という声が多くなります。
子どもとの信頼関係が築きにくい
院内保育では保護者の勤務時間によって、利用時間が変わります。そのため、子どもの登降園時間も一定ではなく、保育士が対応する子どもの顔ぶれは日によって変わります。
病院ではシフト制で働く職員が多いため仕方のないことではありますが、毎日同じ子どもと関われないために、お互いの信頼関係が築きにくいことも事実です。
そして、それが理由で「院内保育はつらい」と感じる方も少なくありません。
自分のやりたい保育ができない
院内保育では、子どもの年齢がばらばらなことが多いため、各年齢に合った保育計画を立てにくく、その日に預かっている子どもにあわせて臨機応変に保育を行うことになります。
また、異年齢保育の場合、異なる年齢の子どもが同じ空間にいることから、すべての子どもが安全に遊べるように配慮する必要があります。年齢によってできることとできないことも異なるため、保育士にとってはスキルを発揮しきれなかったり、負担を感じたりする場面も多いでしょう。
そうしたことから、「院内保育は自分には向かない」と思ってしまう方もいます。
保育士としてのキャリアが築きにくい
院内保育所は、登園する子どもの顔ぶれが毎日違います。加えて、少人数の異年齢保育であることから、年齢別のクラスで集団保育をする(=担任を持つ)こともありません。
こうしたことから、院内保育所は一般的な保育園と比較して特殊な環境にあると言えます。保育士として積める経験にも違いがあるため、院内保育所から他の施設に転職しようとした場合、「院内保育所でのキャリアを評価するかどうか」の判断は応募先によって違ってくるでしょう。
そのため、「院内保育所では保育士としてのキャリアを築きにくい」と考える方もいるようです。
休みが取得しにくい
保育士の人数が多い職場であれば、休みたいときに休みを取ることが可能かもしれませんが、院内保育所は小規模な施設がほとんど。保育士の在籍数もさほど多くありません。また、先に紹介したように、院内保育所は24時間365日体制で保育を行います。
そうしたなかで、バランスよく保育士を配置しようとすると、全員の希望通りに休日を割り振れない場面も出てくるでしょう。
もちろん、就業規則で定められた日数は休めますが、休みたいときに休めるとは限らないのが実情です。そうした状況がきつくて、院内保育所を辞める人もいます。
契約社員の場合は将来が不安
院内保育所を開設している病院数はそれほど多くなく、運営を外部の運営会社に委託しているケースがほとんどです。そのため、保育士のなかには契約社員やパート・アルバイトとして働いている方も少なくありません。
院内保育は一般的に小規模で、他の保育園のように常にたくさんの子どもがいるわけではないので、契約社員やパート・アルバイトとして働く場合は、「契約を更新してもらえるだろうか」と不安を感じてしまうケースもあるでしょう。

転職するときの方法とポイント

院内保育をつらいと感じたときは、転職を検討するのも1つの方法です。上で紹介した「院内保育がつらい理由」は、すべての院内保育所に当てはまるものではないため、別の院内保育所に転職することで、状況が変わる可能性もあるでしょう。
院内保育所から他の施設への転職を成功させるためには、応募先の特徴や勤務形態、福利厚生、休暇の取得状況などを事前に確認しておくことが重要です。
転職先探しがスムーズになるように、「なぜ転職したいか」「どのような職場を希望するのか」についても、きちんと洗い出しておくとよいでしょう。
ここからは、院内保育所から転職する方法を2つ紹介します。
院内保育所
厚生労働省およびこども家庭庁のデータから、病院数と院内保育所数を調査したところ、令和3年における病院数は8,205施設、院内保育所数は2,906施設でした。
この数値を過去のデータと比べてみると、病院数、院内保育所数ともに減少傾向にあります。また、院内保育所の数は全国の病院数の約35%にすぎません。そのため、院内保育所からの求人数はけっして多くないのが現状です。
| 病院数 | 院内保育所数 | |
|---|---|---|
| 平成26年 | 8,493 | 3,523 |
| 平成29年 | 8,412 | 3,685 |
| 令和3年 | 8,205 | 2,906 |
(出典:厚生労働省「院内保育等の推進について」https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000529084.pdf#search='%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81+%E7%97%85%E9%99%A2%E5%86%85%E4%BF%9D%E8%82%B2')
(出典:こども家庭庁「令和3年度 認可外保育施設の現況取りまとめ」https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/9e449dd6-28c2-4066-af0e-8b203ea43ca6/e0cee34d/20230401_policies_hoiku_ninkagai_tsuuchi_genkyou_07.pdf)
なお、マイナビコメディカルの求人情報を調べたところ、院内保育の求人は大都市圏に集中している傾向にありました。
他の院内保育所に転職する場合は、そうした状況を踏まえつつ、以下のポイントを押さえることが大切です。
◆勤務体制や就業形態
シフト制の職場が多いので、「シフトごとの勤務時間」「勤務時間の延長の有無・最大延長時間」「夜勤の有無」「休日出勤の有無」といった条件は、必ず確認しましょう。
また、雇用形態や、契約年数についても確認しておいてください。
◆事前の施設見学
求人に応募する前に、施設見学を行って施設の大きさや子どもや保育士の数、職場の雰囲気、子どもと接している保育士の様子、子どもの表情などを確認するとよいでしょう。それによって、転職後のミスマッチが防げます。その際、シフトの組み方や残業の有無など、疑問点について質問しておくのもおすすめです。
◆運営会社について
運営を外部の会社に委託している院内保育所の場合、保育士は運営会社に雇用されることになります。そのため、他の施設への異動があるかどうかについても、事前にしっかりと確認しておきましょう。
施設によっては、配置基準ギリギリの保育士数で運営されているケースもあります。求人情報や面接で条件を確認し、希望に合った場所かどうかを見極めた上で、転職先を選びましょう。
一般の保育所や託児所などの別施設に転職する場合
保育士の資格を持っていると、一般の保育所や託児所など、幅広い施設に転職できます。
院内保育所から他の施設に転職する場合、さまざまな施設から自分に合った転職先を選ぶことになるため、職場ごとの特徴やメリット・デメリットについて、きちんと把握しておくことが重要です。
ここでは、転職先としておすすめの「学童施設」「託児所」の特徴と、転職する際のポイントについて紹介します。
〇学童保育
学童保育は、放課後や学期間休業中などに小学生を預かり、遊びや学習、日常生活を支援する仕事です。求人サイトでは「学童クラブ」「学童保育所」と呼ばれることもあります。
学童保育では、保護者が迎えにくるまで間、子どもの安全を確保しつつ遊び場や学習の場を提供します。子どもと深く関わりたい方には、ぴったりの仕事と言えるでしょう。
学童保育の運営形態には、自治体が設置・運営する「公設公営」、自治体が設置して民間法人が運営する「公設民営」、民間法人が設置・運営する「民設民営」の3種類があります。
運営形態によって特徴が異なるので、希望する施設を見つけた際は、どの運営形態なのかも確認しておきましょう。
〇託児所
託児所とは、子どもを長期的・一時的に預かる施設のことで、一般的には認可外保育施設を指します。託児所の形態はさまざまで、企業型保育所やベビーホテル、商業施設の預かり施設なども託児所となります。
なお、厳密には院内保育所も託児所に含まれますが、ここでは「院内保育所以外の託児所」について紹介していきます。
託児所で働くにあたって特別なスキルや資格は必要ありませんが、保育士資格を採用の条件にしている職場も多いことから、資格を持っていれば転職の際に有利に働くでしょう。また、託児所では基本的に少人数の子どもを預かるため、子ども1人ひとりに目が行き届きやすいのが特徴です。そのため、子どもとしっかり向き合い、個性を重視した保育を行いたい方には、おすすめの職場と言えます。
ただし、託児所を利用する子どもは、年齢や顔ぶれが一定ではありません。初めて利用する子どもにもすぐに慣れてもらえるよう配慮するなど、託児所で働くにあたっては柔軟な対応力が求められます。
上記の他にも、保育園や福祉施設、一般企業など、保育士が活躍できる職場は多くあります。自分の希望やライフスタイルに合った転職先を見つけるためにも、求人情報、公式ホームページ、職場見学などで職場の特徴や待遇をしっかり調べた上で、転職活動を進めましょう。

まとめ
今回は、院内保育がつらいと感じる理由と、転職する際のポイントについて紹介しました。
保育の仕事をしていると、残業や報酬、人手不足など、働き方に関する悩みは尽きません。しかし、近年は国が中心となって保育士の労働環境や処遇に対する見直しが進められています。
そのため、現在の職場に勤務し続けるのがつらいと感じた場合は、別の施設への転職を検討するのもよい方法です。
転職先の特徴や待遇といった詳細情報をしっかりと調査した上で、自分の希望、ライフスタイルに適した職場を見つけてください。










