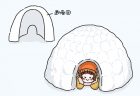幼い子どもが使う「赤ちゃん言葉」。「ねんね」「あんよ」などの独特の表現や、「ぎゅうにゅう→にゅうにゅ」「ひこうき→こうき」といった言い間違えは、とてもかわいらしいものですよね。
そんな赤ちゃん言葉について、「大人も一緒に赤ちゃん言葉を使ったほうがいい?」「赤ちゃん言葉で話しても、正しい言葉はちゃんと身につくの?」と疑問に思っていませんか?
この記事では、よく使われる赤ちゃん言葉の例を一覧で紹介するとともに、赤ちゃん言葉を使った上手なコミュニケーションのポイントを解説します。子どもとのやり取りを楽しみながら言葉の成長を促すコツを、ぜひ押さえてください。
赤ちゃん言葉とは?

赤ちゃん言葉とは、意味のある言葉を覚え始めた幼い子どもが使う、幼児期特有の言葉のこと。幼児語とも呼ばれます。
赤ちゃん言葉の種類
発音が間違っていたり1文字足りなかったりと不完全で未熟な赤ちゃん言葉は、いくつかの種類に分けられます。代表的なものと例は次の通りです。
- 擬音語・擬態語:わんわん(犬)
- 本来の言葉とは別の言い回し:あんよ(足)
- 音の変化・追加・省略:だいおん(ライオン)、おめめ(目)、こうき(飛行機)
赤ちゃん言葉を使い始めるまでの発達段階
子どもの言葉は、泣くことだけで要求を伝える時期から、意味のある言葉を使うようになるまでのあいだ、いくつかの段階を経て発達します。
まず、生後2~3か月頃の子どもは、機嫌のよいときなどに「あー」「う-」といった柔らかい声を発します。母音中心の声で、意味はありません。この声のことを「クーイング」といいます。
生後4~5か月頃になると、「ばぶばぶ」「んまんま」など、母音と子音を組み合わせた「喃語(なんご)」という声を出すようになります。クーイングと同様、喃語にも意味はありません。喃語は、生後9~10か月頃にかけて、音の強弱や高低のついたものへと変わっていきます。
そして、生後10か月頃には、「まま」「ぱぱ」など意味のある言葉を言うように。ここから赤ちゃん言葉の時期に入り、だんだんと言葉が増えていきます。
赤ちゃん言葉の一覧をテーマ別に紹介

では、具体的な赤ちゃん言葉を紹介しましょう。子どもと生活するなかで話題になりやすい言葉を集めてみました。
人を表す赤ちゃん言葉
小さな子どもは身近な人たちのことを、赤ちゃん言葉で次のように表現します。
- まま(母親)
- ぱぱ(父親)
- ばあば(祖母)
- じいじ(祖父)
- ねえね(姉)
- にいに(兄)
- ともらち(友だち)
体や行動を表す赤ちゃん言葉
靴を履いたり、手を洗ったり。子どもとの会話のなかでは、行動や体の一部についてもよく話題になりますね。赤ちゃん言葉ではこう表現します。
- おてて(手)
- あんよ(足、歩く)
- おめめ(目)
- くっく(靴)
- たっち(立つ)
- ちっち、ちー、しっし、しー(おしっこ)
- じゃー(流す)
- ごっつん(ぶつける)
- ねんね(寝る)
- ちん(鼻をかむ)
- ないない(片付ける、捨てる)
- ぽい(捨てる)
- まんま(ご飯)
- ちゅるちゅる(麺類)
- おたら(皿)
身のまわりの物事を表す赤ちゃん言葉
走っている車を見たり、散歩中に犬に会ったりすると、子どもはとても興味を示すもの。そんなときの赤ちゃん言葉はこちらです。
- ぶーぶー、ぶっぶー(車)
- こうき(飛行機)
- わんわん(犬)
- ねと、にゃんにゃん(猫)
- おちゃかな(魚)
- おんも(外)
あいさつや会話をするときの赤ちゃん言葉
小さな子どもとの会話のなかでは、以下のような赤ちゃん言葉がよく使われます。
- あんと(ありがとう)
- だいじだいじ(大事)
- きれいきれい(きれい)
- おいちい(おいしい)
- あっ!(見つけた!)
- よう(おはよう)
- みー(おやすみ)
赤ちゃん言葉でのコミュニケーションのコツ

小さな子どもが赤ちゃん言葉で話す様子を見ると、ほほえましく思う反面、「早くたくさんしゃべれるようになってほしい!」「間違った言葉を使っているけどいいのかな?」などと感じることもありますよね。
赤ちゃん言葉にまつわるよくある疑問にお答えしながら、言葉の発達を促すためのコミュニケーションのポイントを説明しましょう。
子どもの赤ちゃん言葉には、どう反応すべき?
子どもは「ぶっぶ!」「まんま!」と一語だけ言うことも少なくないもの。会話が成り立たないと感じるかもしれませんが、子どもとのコミュニケーションは一語からでも始められます。
子どもが何かを言ったときは、その言葉を大人も繰り返して言い、子どもが言ったことを認めてあげましょう。たとえば、子どもが車を見て「ぶっぶ!」と言ったら、「そうだね、ぶっぶだね」と返してあげるのです。
大人が反応すると、子どものなかで「言えて楽しいな」「聞いてくれてうれしい」「もっと話したいな」という気持ちが育ちます。そうした気持ちが、言葉の発達につながっていくでしょう。
子どもが言った一語を繰り返すだけでなく、関連する言葉を加えながら返事をしてあげることも、子どもが新たな言葉を獲得するのに効果的です。
たとえば、子どもが「ぶっぶ!」と言ったときは「そうだね、ぶっぶ、びゅーんと走っているね。速いね!」などと、状況を語ってみましょう。すると、速く走る様子を「びゅーん」と表現するのだということを、子どもは自然と習得していきます。
大人も赤ちゃん言葉を使っていいの?
子どもの赤ちゃん言葉に対し、大人は赤ちゃん言葉で返すべきなのか、正しい言葉で返すべきなのかと疑問に思う方もいるでしょう。「大人が赤ちゃん言葉を言ったら、子どもはそれを正しい言葉として覚えてしまうのでは?」と心配にもなりますよね。
この点については、大人も赤ちゃん言葉を使って問題ありません。むしろ、大人の言葉だけで話すのではなく、赤ちゃん言葉をどんどん使って子どもとの会話を楽しみましょう。そのほうが、子どもは早く多くの言葉を習得することができます。
このことを明らかにしたアメリカの大学の研究によれば、親から赤ちゃん言葉で話しかけられている子どものほうが、1歳の時点ですでに喃語が多く出ており、2歳になると平均で433語もの言葉を獲得していました。赤ちゃん言葉ではなく大人の言葉で話しかけられた子どもが獲得していた言葉は、平均で169語だったそう。
赤ちゃん言葉は、子どもにとって覚えやすく、親しみやすくて楽しい言葉です。子どもがどんどん言葉を覚えたくなるように、積極的に赤ちゃん言葉で話しかけてみてください。
使わないほうがいい赤ちゃん言葉はある?
大人も赤ちゃん言葉を使っていいとはいえ、使う際には注意すべき点もあります。2つ紹介しましょう。
1つ目は、子どもがまだ発音できない言葉をそのまままねるのは、避けたほうがよいということです。
小さな子どもは、口の中の構造が未発達。そのため、「さ行」や「ざ行」がうまく言えないケースがよく見られます。たとえば「おしり」が「おちり」に、「おいしい」が「おいちい」になってしまうなどです。
舌や上顎などが発達して子音をすべて正しく発音できるようになる目安は、6歳頃。「さ行」や「ざ行」はさらに時間がかかることもあります。子どもが発音できないからといって、大人がいつまでも「~でちゅね」などと言うのではなく、正しい発音で返すようにしましょう。なお、自然と言えるようになるまでは、無理に言い直しをさせる必要はありません。
2つ目は、「ぶーぶ-」など擬音語・擬態語による幼児語の使い方です。たとえば、幼児語の「ぶーぶー」は、本来の言葉である「車」とは違う言葉になっていますよね。このようなケースでは、「ぶーぶーだね。車だね」のように正しい言葉を添えるといいでしょう。子どもは「ぶーぶー」と「車」を結びつけて覚えることができます。
ただし、擬音語や擬態語が悪いというわけではありません。「じゃぶじゃぶ」「びりびり」などのオノマトペは、物事の様子を音のイメージで言い表したもの。子どもが目の前の状況や言葉の意味を理解するうえで、大変役に立ちます。加えてオノマトペは、赤ちゃん言葉の時期が終わってからでもよく使う言葉です。子どもがイメージ豊かに言葉を増やしていけるよう、正しい言葉を添えながら積極的に使ってあげましょう。
赤ちゃん言葉を上手に使って子どもとたくさん話そう
赤ちゃん言葉を話す時期は、言葉を話し始めたばかりの子どもが言葉を習得していくうえで、とても大切な時期です。
大人も赤ちゃん言葉を上手に使い、コミュニケーションを楽しみながら子どもの言葉の発達を促してあげましょう。