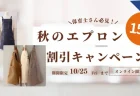待機児童とは?待機児童問題のいまと原因・対策

文: アリサ(保育士ライター)
保育の受け皿が不足することで起きている待機児童問題。様々な取り組みにより待機児童数は減少傾向にありますが、いまだに課題も多く残っています。
本記事では、待機児童の定義、待機児童問題の現状や原因、対策について解説します。
待機児童とは?

「待機児童」のほか、「保留児童(隠れ待機児童)」という言葉もあります。ここでは、それぞれの定義や違いを解説します。
待機児童の定義
待機児童とは、保育園や幼稚園などの施設に入りたくても、定員などの問題で入園することができず、順番待ちをしている子どもを指します。
厚生労働省による待機児童の定義は下記の通りです。
待機児童とは、保育園等の利用申込者数から、
保育所等利用待機児童数調査における除外4類型について②(厚生労働省)
① 保育園等を実際に利用している者の数
② 育児休業中の者などいわゆる「除外4類型」に該当する人数
を除いた数としている。
除外4類型に該当する条件は以下の通りです。
- 特定の保育施設のみ希望している者
- 育児休業中の者
- 地方単独事業を利用している者
- 求職活動を休止している者
除外4類型を見ると、職場から近いといった理由で、実質的に特定の保育施設しか選べない家庭や、希望した保育園に入れなかったため別の自治体の支援(地方単独事業)を利用している家庭の子どもは、待機児童には含まれていないことがわかります。
待機児童と保留児童(隠れ待機児童)の違い
待機児童が「施設側の理由によって入所できず、入所を待っている子ども」を指す一方で、保留児童(隠れ待機児童)は、保育施設に入園できない子どものうち、「特定の施設を希望している」「希望の保育施設に入れず、別の保育サービスを利用してる」といったケースを指します。
「待機児童数は減少傾向にある」と言われてはいますが、保留児童を含めると、その数はまだまだ多いといえるでしょう。
待機児童問題のいま

待機児童問題とは、保育所の利用を希望する子どもが入所できず、順番待ちが発生する問題です。ここでは、待機児童問題の現状についてお伝えします。
待機児童の推移
こども家庭庁の保育所等関連状況取りまとめ(2023年4月1日)によると、2023年の待機児童数は2,680人で、前年より264人減少しています。ピーク時の2017年の26,081人から6年連続で減少しています。

待機児童数が100人以上の自治体はなく、待機児童を抱える自治体は全国で231市区町村です。
待機児童数が減少している背景として、以下の理由が考えられます。
- 保育の受け皿の増加
- 少子化による子どもの数の減少
とはいえ、待機児童問題が完全に解消されたわけではありません。地域差や保留児童問題、保育士の確保や保育の質の向上といった課題が残されているのが現状です。
また、少子化の影響により入所申請数は減少傾向にあるものの、一般的な育児休業が終わる時期と重なる1歳児クラスに申し込みが集中する園も多くなっています。
自治体ごとの特徴
全国的に見ると、待機児童数は地域差が大きいのが実情です。
東京や大阪などの大都市圏では、共働き世帯の増加や人口集中により、保育施設の需要が供給を上回り、待機児童が多く発生している傾向にあります。特に交通の便が良い地域では競争が激しくなりますが、自治体が保育施設の増設に注力したくても土地の確保や保育士不足などの課題に直面しているのが現状です。
そこで、自治体によっては、民間企業との協力を進め、施設増設のための土地や資金を提供するなど、独自の解決策を実施しているケースもあります。
一方、地方では子どもの数が少なく、待機児童が発生しにくい自治体も存在しています。
地域ごとの特性に加えて、自治体ごとの保育サービスの柔軟性によっても、待機児童問題の深刻度が変わる場合があります。一部の自治体では、夜間保育、病児保育、一時保育、ファミリーサポートセンターなど、働く親が利用しやすいように柔軟な保育サービスを拡充しています。こうしたサービスの導入が進んでいる地域では、待機児童の数が減少する傾向があります。
今後の見込み

少子化が進むにつれ、保育ニーズも自然に減少し、待機児童問題が緩和される地域もあるかもしれません。しかし、都市部や保育需要の高い地域では、依然として保育施設が不足する可能性があります。
というのも、2024年10月には、社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の適用対象が、パート・アルバイトなどの短時間労働者に対しても広がるためです。社会保険に加入するということは、扶養から外れることを意味します。そのため、保護者のうち、これまで「フルタイムで働きたかったが、扶養内で働くために短時間しか働けなかった」といった人にとっては、今後、就業時間の制限がなくなる可能性もあり、労働時間を延長する保護者も出てくると考えられます。これにより、保育のニーズが増加する可能性があります。
この変化の影響を受けるのは保育士も同じですので、パートタイムの保育士が就業時間を伸ばすことにより、待機児童問題の改善に繋がる可能性もありますが、待機児童数の動向については引き続き注視していく必要があるでしょう。
政府も、待機児童問題への取り組みに注力していますが、問題の解決には、保育施設の量と質のバランス、保育士の確保、地域ごとの課題に対処する柔軟な政策が鍵となっていくでしょう。
待機児童問題の原因

待機児童問題につながる環境要因には何があるのでしょうか?
保育士不足
慢性的な保育士不足は、待機児童問題に大きく影響していると考えられます。
保育士は、子どもの安全確保や保護者対応といった面でプレッシャーを感じやすい仕事です。残業が多く、身体的な負担が大きいにも関わらず、給料が低いと感じる方も少なくありません。そのため、保育施設を増やしたとしても、保育士が集まりにくいという問題があります。
また、今ある保育施設も配置基準を満たす保育士が集まらず、定員に満たない子どもしか預かれない園もあるでしょう。
2020年の厚生労働省の調査によると、潜在保育士の数は約102万人にも及びます。潜在保育士とは「保育士の資格を持っていても、保育士として働いていない人」を指します。このような潜在保育士が「働きたい」と思えるような、職場環境の整備が望まれています。
共働き世帯と核家族の増加
経済的な理由やキャリア継続の必要性から、共働きは多くの家庭にとって一般的な選択肢のひとつとなっています。共働き世帯が年々増えるにつれて、保育施設の需要も高まり、保育施設の定員が不足しやすくなっていると考えられます。
また、核家族化が進み、祖父母などからの育児支援が受けにくくなっていることも、待機児童問題の要因のひとつです。核家族では、家族からの育児支援が受けづらく、保育施設に頼らざるを得ない状況が増えます。そのため、保育のニーズが増加しますが、受け皿の不足により待機児童問題につながっていると考えられます。
待機児童問題の対策

待機児童問題を解消するために、国や自治体、保育施設は対策を進めています。現在行われている対策についてみていきましょう。
政府による対策
待機児童問題の対策として、政府は様々な取り組みを行っています。例えば、幼稚園の空きスペースを活用した預かり保育を推進するために、施設改修にかかる補助制度を新設したり、既存施設の定員を増やすための支援も行われています。また、従業員がベビーシッターを利用しやすくするために、企業が負担するベビーシッター費用を補助する制度を拡充しています。
保育士不足への対応としては、保育資格を持たない「保育補助者」の活躍を促進するために、勤務時間30時間以下の要件を撤廃し、保育士のサポートにあたる人員の確保に努めています。併せて、待機児童が存在する自治体では、保育施設の各クラスにおける「常勤保育士1名必須」の条件を緩和し、「2名の短時間保育士で可」とする改定を行いました。
また、今後、保育所等に通っていない満3歳未満の子どもに対して、保育施設を時間単位で利用できる「こども誰でも通園制度(2026年4月給付化予定)」が創設されることにも注目すべきでしょう。これにより、専業主婦(専業主夫)も含めて柔軟に通園させられる仕組みを整備していく予定です。
自治体による対策
自治体も保育の受け皿の確保や整備を進めています。
例えば、港区では保育施設の空いている部屋を利用し、希望者の多い1歳児の定員数を60人分拡大したほか、保護者と保育施設の入園マッチングを行う保育コンシェルジュを設置しました。保護者のニーズを適切に理解し、対策が行われた結果、待機児童ゼロを達成しています。
保育園による対策
保育園としては、保育士の業務負担を減らすために、業務効率化に取り組むことが対策のひとつになります。
保育士の退職理由には、人間関係や仕事量の多さ、労働時間の長さなどが挙げられています。保育士の仕事は体力的にも精神的にも負担が大きく、ライフステージの変化によって働くことを断念する保育士も少なくありません。
事務作業におけるITツールの導入や労務管理のシステム化などによって、休憩時間の確保や残業時間の削減につながり、働きやすい環境を実現できるでしょう。
また、様々な雇用形態を用意することで、ライフステージの変化があっても離職せずに、働き続けてもらいやすくなります。
保育士自身ができること
待機児童が発生する原因のひとつに、慢性的な保育士不足があります。
保育士を長く続けていくためには、自身の保育観と合う園で、心身共に健康に働けるバランスを確保すること大切です。自分や家族のライフステージに合わせて、勤務時間や雇用形態を柔軟に選べる施設に転職するのも良いでしょう。
現在は保育士として働いていない場合は、無理のない範囲で職場復帰を考えることで、待機児童問題の解消に大きく貢献します。その際、特別支援教育や絵本、運動などに関する資格取得や研修の受講などのスキルアップをすることで、対応できる仕事の幅が広がり、様々なニーズに応えられる保育士として現場で重宝されるでしょう。
まとめ

待機児童とは、保育園や幼稚園などに入りたくても定員の問題で入れず、順番待ちをしている子どもを指します。
待機児童問題は近年改善されつつあるものの、地域差が大きく、特に都市部では多くの子どもが希望する施設で保育を受けられていません。
共働き家庭や仕事復帰を希望する親にとっては大きな壁となる待機児童問題。この問題を改善するためには、保護者のニーズを適切に把握し、保育の受け皿を確保しなければなりません。
保育園としては、保育士の業務負担を減らすための取り組みとして、事務作業におけるITツールの導入や、シフト管理や労務管理のシステム化などに取り組む必要があるでしょう。また、保育士自身が、自身のキャリアを改めて見つめ直し、長く働き続けられる園に転職を考えることも、待機児童問題の解消に大きく寄与するでしょう。
保育園で0歳児から5歳児までの担任や障がい児加配、縦割り保育を約10年間経験。家庭の事情で退職後、今までの知識を活かした活動がしたいとの思いからライターに。現在は2歳と5歳の子どもの育児に奮闘しながら、保育士さんや子育て中の方に向けて記事執筆を行っている。絵本とお花が大好き。
保有資格:保育士・幼稚園教諭一種免許
参考サイト:
保育所等関連状況取りまとめ(令和5年4月1日)及び「新子育て安心プラン」集計結果|こども家庭庁
令和5年4月の待機児童数調査のポイント|こども家庭庁
保育所等利用待機児童の定義|厚生労働省
共働き等世帯数の年次推移|厚生労働省
各市区町村の「新子育て安心プラン実施計画」(令和5年度)|こども家庭庁
待機児童問題とは?現状と課題・政府による対策について簡単解説|政治ドットコム
保育士の現状と主な取り組み|厚生労働省
東京都保育士実態調査結果の概要|東京都