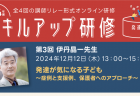世界の保育園事情を知りたい!日本の配置基準や給与、労働時間とはどう違う?

近年は、海外の教育メソッドを導入したり、外国にルーツを持つ子どもを受け入れたりする保育園も増えています。そうした状況から、「海外の保育園ってどんな感じなのかな?」と気になっている保育士さんも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、海外の保育制度に詳しい池本美香さんに、海外と日本の保育施設の違いを教えていただきました。保育園に対する認識から保育士の配置基準、給与、労働時間、親との関わり方など、幅広くお話をうかがっています。
\お話をうかがった方/
池本美香さん
日本総合研究所 調査部 上席主任研究員
日本女子大学文学部英文学科を卒業後、三井銀総合研究所などを経て2001年より日本総合研究所所属。研究・専門分野は子ども・女性政策で、少子化・教育問題や海外の保育制度に詳しい。著書に『失われる子育ての時間』、『子どもの放課後を考える』(編著)、『親が参画する保育をつくる』(編著)、『保育の質を考える』(共著)など。千葉大学客員教授。博士(学術)千葉大学。
海外の保育施設は、「働く親のため」のものではない?

――日本と海外の保育施設を比べた場合、どのような違いがあるのでしょうか。
池本:最も大きいのは、保育施設の位置づけではないでしょうか。日本における保育園は、「働く親のための施設」という側面が強く、親に代わって子どもを保育する「児童福祉施設」という位置づけになっています。一方、幼稚園は、小学校に入る前の3~5歳の子どもを対象とした「教育機関」です。
根拠となる法律や管轄する省庁にも違いがあり、保育園は根拠法令が児童福祉法で、管轄はこども家庭庁。幼稚園は学校教育法に基づいており、管轄は文部科学省となっています。
このように日本では幼稚園と保育園とで制度や担当省庁が異なりますが、海外では幼稚園と保育園の制度や担当省庁の一本化を図る「幼保一元化」が主流となっています。そして、保育施設を「幼児教育のための施設」に位置づける国が多いんです。
――どのような経緯で保育施設イコール「幼児教育のための施設」という位置づけになったのでしょうか。
池本:海外でもかつては、教育を主目的とした幼稚園のような施設と、福祉を主目的とした保育園のような施設に分かれている国が少なくありませんでした。しかし、1980年代あたりから、状況が変わってきたのです。
例えばニュージーランドでは、1980年代後半に大規模な教育改革があり、教育省が保育園を含めた保育施設、保育制度を一元的に所管するようになりました。その後スウェーデンでは1996年から、イギリスでは1998年から、同じく学校教育を担当する省庁が保育施設を所管するようになりました。
このほかノルウェーは2006年、オーストラリアは2007年、デンマークは2011年に、保育施設を教育施設とする改革を実施しています。
――海外でそのような改革が進められた理由を教えてください。
池本:1つは、子どもの権利が重視されるようになったことが挙げられます。1989年に国連総会で「子どもの権利条約」が採択されたことで、すべての子どもが質の高い教育を受けられる環境が求められるようになりました。親が働いている子どもが通う保育施設においても、幼稚園と同じように質の高い教育を受けられるように、制度改正が進められたのです。
女性の社会進出も理由の1つです。結婚・出産後も働く女性が増えれば、保育施設のニーズは高まります。しかし、保育施設がどれだけ増えても、子どもを安心して預けられなければ、仕事を辞める判断をする人が出てくるでしょう。幼児教育の重要性が認識されるようになればなるほど、その傾向は強まるはずです。
実際、改革前のニュージーランドでは、保育施設の数は増えても質が伴わず、仕事を辞めざるを得ない女性が多かったと聞いています。けれど、労働人口が減少すれば国の経済に悪影響をおよぼしかねません。そこで政府は予算を投入し、保育施設の量的拡大とあわせて、質の向上も図ったわけです。
海外では、保育の質を担保するために専門家による評価機関を設置している

――日本では近年、不適切保育を報じるニュースを見聞きすることが増えました。保育施設の質を担保するために、海外ではどのような取り組みがされているのでしょうか。
池本:まず、専門家による評価機関を設置している国が見られます。監査は定期的に行われ、評価については、よい点も改善すべき点もインターネットなどで公開されるんです。その結果を見て親は子どもを預ける保育施設を選んでいますし、保育士も働き先を決める際の参考にしています。
保育に携わる人の性犯罪歴などをチェックする制度も、多くの国が導入しています。
――日本では2024年に「日本版DBS(※)」の創設を含む「こども性暴力防止法」が成立しましたが、海外では以前から同様の制度があったわけですね。
池本:そうです。DBSはイギリスの制度で、子どもと関わる仕事をはじめたい人は、DBSと呼ばれる公的機関が発行する「無犯罪証明書」を事業者に提出しなければなりません。「日本版DBS」は、そうしたイギリスの制度を参考にしています。
DBSのような制度がこれまで日本になかったのは、子どもと関わる仕事に就く人の性犯罪が海外に比べて少なかった、あるいは明るみに出にくかったという背景があるのかもしれません。ただ、子どもの性犯罪被害を防ぐには、子どもと接するのに不適切な人を排除する仕組みが必要です。だからこそ「日本版DBS」は、子どもの権利を守るために欠かせない措置だと考えています。
※子どもに接する仕事に就く人について、性犯罪歴の確認を義務づける制度のこと。
日本の保育士は見る子どもの数が多く、給与は低め、労働時間も長い!?
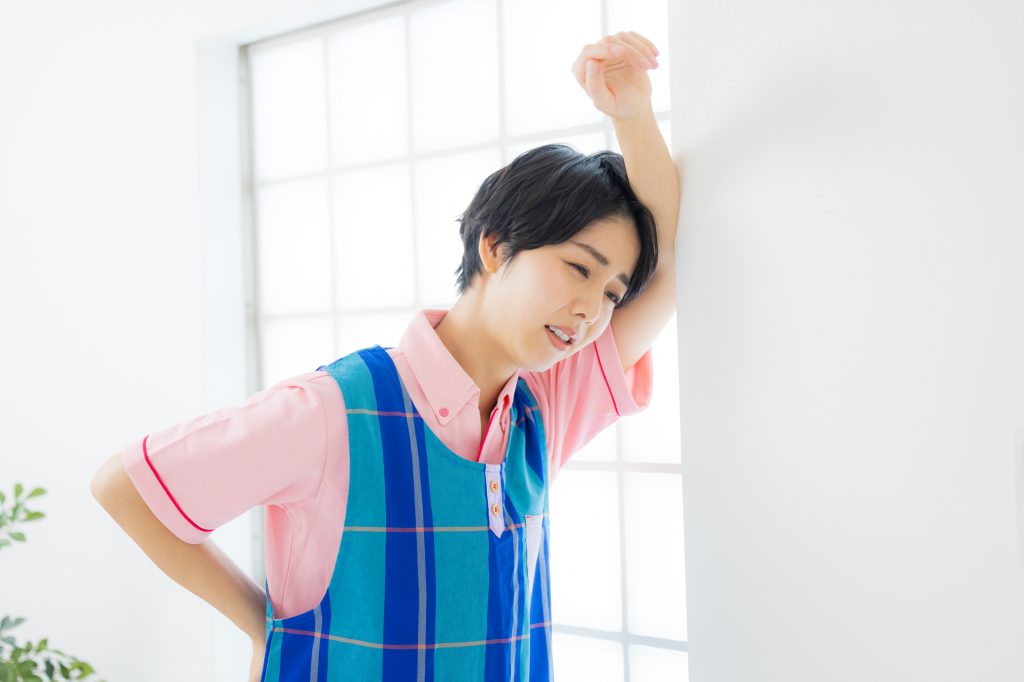
――続いて、保育士の働き方についてうかがいます。海外と日本では、保育士の働き方はどのように違うのでしょう。
池本:保育士の配置基準が大きく異なります。日本では長らく、保育士1人が受け持つ4・5歳児の数が30人でした。しかし、保育の質を向上させるために配置基準が見直され、2024年度から25人に変更となっています。この見直しは、実に76年ぶりのことでした。
それでも、保育士1人あたりが受け持つ子どもの数は、海外に比べると多いと言わざるを得ません。ちなみに、OECD(経済協力開発機構)の報告によれば、3歳以上の保育施設における保育士1人あたりの子どもの数の上限は、OECD平均で18人でした。
さらに欧州では、保育士1人あたりが受け持つ子どもの数を10人くらいに減らそうという動きも出ています。
――配置基準にここまで差があるとは思いませんでした。
池本:「子どもの権利条約」は、子どもには自分の意見を表明する権利があり、大人はそれに耳を傾けて、その子の発達に応じて十分に考慮しなくてはならないとしています。
以前視察したスウェーデンの保育施設では、保育士が0歳児に、「今日は何の歌を歌いたい?」と聞いていました。0歳児ですから、大人が理解できる言葉で回答できるわけではありません。けれど、保育士は普段のちょっとしたやりとりのなかでも「あなたには意見を言う権利があり、あなたには意見を聞いてもらう権利がある」ということを伝え、子どもの意思表示を尊重していたのです。
こうした取り組みを、1人で25人もの子どもを見ている日本で実現できるかと言えば、おそらく難しいでしょう。けれど、担当する子どもの数が少なくなれば、子どもの意見に耳を傾ける余裕ができるはずです。そうすれば、一人ひとりにさらにきめ細かいケアができるようになりますし、親との密なコミュニケーションをとれるようにもなるでしょう。保育士の心身の負担も確実に減ると思います。
――給与も、海外と日本ではかなり違うのでしょうか。
池本:近年、日本では保育士の給与水準がたびたび話題になっていますが、OECDの2018年の調査によれば、給与に満足している日本の保育士の割合は22.6%で、参加9か国中で2番目に低い数値でした。
また、小学校の先生と保育士の給与格差が大きいのも日本の特徴で、OECDの資料では、「小学校の先生と保育士の給与格差がもっとも大きい国」だと紹介されていました。
――なぜ、そうした差が生まれるとお考えですか?
池本:保育士イコール福祉職というイメージが強いことが一因でしょう。でも、例えば6歳の子を担当する小学校の先生と、5歳の子を担当する保育士とで、給与に大きな差があるのはおかしいと感じます。
先ほど名前を挙げたような海外の国では、保育を教育制度の一環と位置づけたことで、保育士も小学校の先生と同じ「子どもの教育を担う職業」と扱われるようになりました。それによって、給与格差も改善されてきています。日本も海外にならい、保育士の処遇改善に取り組むべきではないでしょうか。
――労働時間についても違いがあれば教えてください。
池本:OECDの2018年の調査では、常勤している保育士の1週間あたりの仕事時間は参加国中でもっとも長い50.4時間でした。
ではなぜ、日本の保育士の労働時間が長いかと言えば、保育園の開所時間が長いからです。すでにお話したように、日本における保育園は「働く親のための施設」です。親の労働時間が長くなれば、それにあわせて保育園の開所時間も長くなり、結果として保育士の労働時間も長くなるという状況になっています。
一方、海外の多くの国では「子どもを保育施設に長時間預けることは、子どもにとって望ましくない」という認識が共有されています。そのため、夕方以降もオープンしている保育施設が意外に少ないのです。特にオーストラリアでは、18時以降も開所している保育施設は子どもにふさわしくないとの考えから、国が認可していないと聞きました。
このように、保育士の労働時間は保護者の労働時間と密接に関わっているため、保育士の労働時間を短縮するには、社会全体の働き方改革が必要だと言えます。
親が率先して保育園に参画するのが海外流

――海外の保育制度を研究するなかで、特に印象に残っていることがあれば教えてください。
池本:保育園と親の関わり方の違いです。私自身、子どもを保育園に預けて働いていましたが、日本では、自分の子どもが通っている保育園であっても、親がアポなしで園内を見学するのは難しいですよね。園内の安全確保のため、親が保育園の敷地内に長くとどまるのをよしとしない保育園も少なくありません。
でも、海外の保育施設は、親にどんどん参画してもらおうというスタンスなのです。そこには、親という外部の目を入れることで施設が閉鎖的になるのを防ぎ、不適切保育のリスクを下げようとする狙いと、親の孤立を防ぎ、親同士が支えあう関係性を築くことが、子どもの環境改善につながるという考え方があります。
そのため、親の見学を歓迎している保育施設が珍しくありませんし、親も保育の質の確保・向上のために積極的に意見を伝えています。なかには、親がお茶をしながら話せるスペースを備えた保育施設もありますよ。
――親にとってはよい制度のように思えますが、いざ実施するとなると、保育園側の負担が大きいかもしれません。
池本:クレーマーのような親もいないとは限りませんから、保育園の負担が増える面はあるでしょう。でも、メリットはあるはずです。
例えば、海外で保育施設を見学した際、自分の得意分野を生かして、時間のある親が施設の一角でおしゃべりをしながら教材などを制作している光景が見られました。そんなふうにサポートしてもらえたら、保育園にとって大きなメリットになるのではないでしょうか。
「こども基本法」が施行され、日本の保育園はどう変わる?

――2023年4月に、子どもの権利条約の精神にのっとることを明記した「こども基本法」が施行されました。日本の保育園は今後、どのように変わっていくのでしょうか。考えをお聞かせください。
池本:「こども基本法」は、すべての子どもに意見を表明する機会を確保すると定めています。先ほども述べたように海外の保育施設では、たとえ0歳児であっても意見を聞こうとする風土があります。日本でもすでに取り組まれている施設があると思いますが、今後は、園児一人ひとりの意見を聞き、それをふまえた保育を提供することが一層求められるようになるでしょう。
また、「こども基本法」には、すべての子どもが教育を受ける権利を実現するとあります。近年、インクルーシブ教育が少しずつ進んでいますが、それでも、発達に特性があったりすると希望する保育園に入れないケースがある。それが実状です。
財源や人手の不足といった課題はありますが、「こども基本法」の理念を実現するためにも、インクルーシブ教育を実践できる環境づくりを積極的に進めてほしいと思います。
――ありがとうございました。最後に、「ほいくらし」の読者に向けてメッセージをお願いします。
池本:日本の保育士さんは本当に大変だと思います。それは重々承知しているのですが、だからこそ、保育士さんたちが声を上げていくことが大切だと思うのです。
フランスでは、保育士の資格が「子どもの保育をする資格」であると同時に、「保育制度をよりよくするための資格」だという意識があると聞きました。だからこそ、保育士は自分たちの大変さを積極的にアピールしており、それが制度見直しのきっかけになることもあります。またニュージーランドでは、保育士の労働組合と学校教員の組合を統合して、発言力を強くしていく戦略がとられています。
保育園の課題をいちばんわかっているのは、ほかでもない保育士さんです。そして、当事者が声を上げなければ、制度はなかなか変わりません。保育士さん自身のためにも、保育園で過ごす子どものためにも、これから保育士になろうとする人たちのためにも、不具合があれば声を上げていくことが重要ではないでしょうか。
私自身は保育士ではありませんが、これからも国内外の保育事情を調べてそれを公表することで、保育制度をよりよくするためのお手伝いができればと思っています。
取材・文/小川裕子