自立心とは?子どもの自立心を育てる保育のポイントを紹介

「自分の保育の仕方は、子どもの自立心の育ちにつながっているだろうか……」と気になっていませんか?
この記事では、自立心とは何か、子どもの自立心を育むために保育士ができることは何かについて解説します。子どもたちの自立心をすくすくと育てていけるよう、ぜひ参考にしてみてください。
自立心とは?

自立心とは、「自分でやってみようとする心」のことです。
自立心は、文部科学省が示す「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の10項目のうちのひとつでもあります。
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の10項目は「10の姿」とも呼ばれるもので、下記項目が含まれます。
- 健康な心と体
- 自立心
- 協同性
- 道徳性・規範意識の芽生え
- 社会生活との関わり
- 思考力の芽生え
- 自然との関わり・生命尊重
- 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚
- 言葉による伝え合い
- 豊かな感性と表現
そのうち自立心については、こう説明されています。
身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で、しなければならないことを自覚し、自分の力で行うために考えたり、工夫したりしながら、諦めずにやり遂げることで達成感を味わい、自信をもって行動するようになる。
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」文部科学省
保育所保育指針では、保育所は10の姿を子どもの卒園までに育むこととしています。保育所は、自立心を含んだ人生の基盤を育てる重要な役割を担っているのです。
自立心が芽生えるのは、食事や衣類の着脱を自分でやるようになる1~3歳頃からです。保育所生活を終える6歳までには、生活習慣を構築したりさまざまな遊びに取り組んだりする経験を通し、見通しをもって自分で行動できるようになっていきます。
子どもの自立心を育てるべき理由
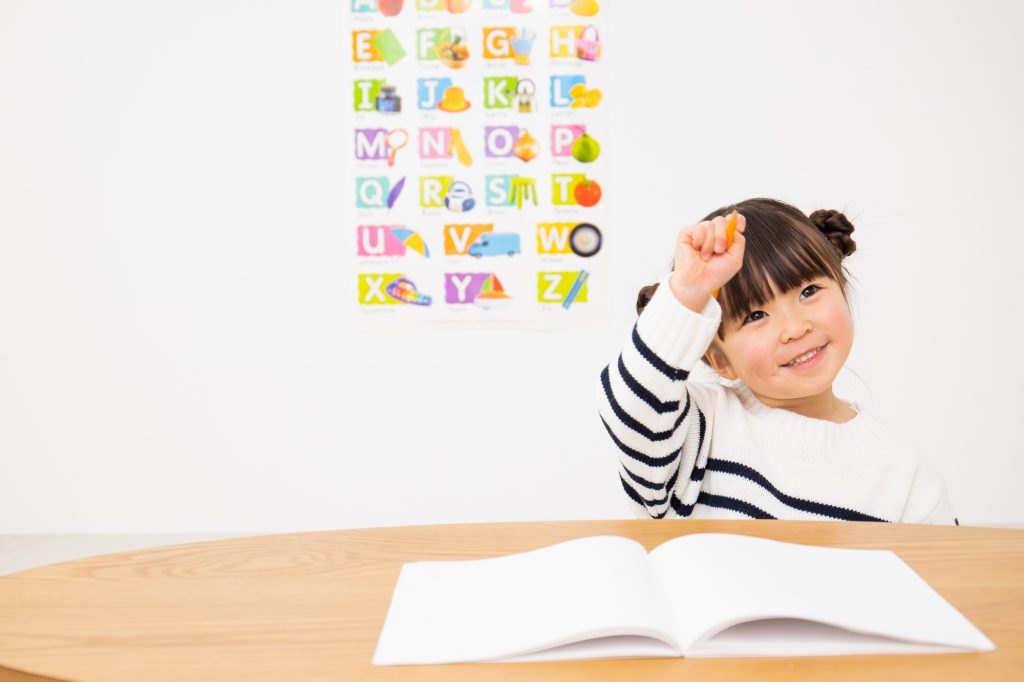
先ほど紹介した自立心の説明をふまえると、自立心のある子どもは以下のことができるといえます。
- しなければならないことを自覚できる
(例)外から帰ったら「手を洗わなくちゃ」と気づける - 自分の力で行うために考えることができる
(例)片付けをするとき「まずブロックをしまって、次に絵本を棚に戻して……」などと見通しをもって考えられる - 自分の力で行うための工夫ができる
(例)上着をハンガーに掛けられないとき、テーブルに置いてハンガーを差し込むという工夫ができる - 自分の力で、物事を諦めずにやり遂げられる
(例)空き箱でタワーをつくるとき、途中で崩れても諦めず、慎重に最後まで箱を積み上げる
このように、自立心を育めば、子どもはうまくいかないことがあっても自ら考えて工夫し、困難を乗り越えられるようになります。まさにこれこそが、子どもの自立心を育てるべき理由です。
また、自立心は人と関わる場面でも重要です。自立心がある子どもは、問題解決のための行動を自らとれるので、友だちとトラブルになった場合は相手と話し合って解決策を考えられます。自力で解決できない場合は、自分から大人に助けを求めることもできるでしょう。こうした力は、小学校入学後の生活にも不可欠ですよね。
逆に自立心を育てなければ、いま何をすべきなのか自分で判断できず、物事を自分で行う方法を考えることも、そのための工夫もできず、諦めやすく挑戦心のない子どもになるおそれがあります。
自立心を育てるには?子どもと関わるときのポイント

自立心を育むために保育士は子どもにどう関わるべきなのか、大切なポイントを3つ紹介します。
自分で考えさせる
自立心を育てるには、子どもに自分自身で考えさせることが大切です。とはいえ、ただ「自分で考えて」といえばいいのではありません。質問を投げかけ、自分で考えるきっかけを作ってあげましょう。
「何をしなくちゃいけないかな?」「いつやればいいと思う?」「どうすれば上手にできるかな?」「どれからやる?」など、何をどのようにやるのかを尋ねながら行動へと導いていきます。
ただし、子どもは大人のように素早く考えられないため、子どもがゆっくりと考えるのを待ってあげることが大切です。
最後までやり遂げさせる
子どもに自分で考えさせたあとは、それを最後までやり遂げさせましょう。
少し難しいことでも、どうすればうまくいくかを自分なりに考えたうえで達成すると、子どもは満足感や達成感を得ます。その充実した感情からは自信が生まれ、「もっとやりたい」という意欲や、「次は自分だけでやってみよう」という自立心へとつながっていくのです。
必ずしもひとりきりで達成させる必要はありません。大人の助けを借りたり、友だちと一緒にやったりしながらでもいいので、やり遂げる経験をさせましょう。
甘えを受け止める
自立心を育むには、子どもの甘えを大人が受け止めることも大切です。「自分を守ってくれる存在がいる」「いつでも大人が見ていてくれる」と思えることが、安心して行動できるベースになります。その結果、スムーズな自立につながっていくのです。
普段なら自分でできることを「やって!」と言ってきたときは、少しだけ手を貸したり、一緒にやったり、「見ていてあげるからやってごらん」とじっくり見守ったりしましょう。子どもの甘えたい気持ちに寄り添った対応を心がけてください。
自立心の育ちを妨げてしまう行為とは

子どもとどのように関わると自立心が育ちにくくなるのかについても、ぜひ押さえておきましょう。
手伝いや口出しをしすぎる
大人が手伝いすぎたりダメ出しばかりしたりすると、自分で考え最後までやり遂げる機会を子どもから奪ってしまいます。
たとえば、子どもがおもちゃを片付けようとしているとき「それはこっちの箱でしょ」と代わりに片付けたり、着替えを選んだ子どもに「その服じゃおかしいよ」と言ってすぐさま否定したりすることは避けましょう。
また「早くやりなさい」「自分でやって!」などと命令ばかりするのもよくありません。子どもは自分で考える余地を与えられず、自立しづらくなります。
突き放す
甘えを許さないような突き放した態度をとると、子どもは不安になり自分で行動できなくなります。
「これやって」と頼ってきた子どもを「いつもやってるんだから自分でできるよね」「それぐらい自分でやって」と突っぱねると、子どもの要求はますます強くなるかもしれません。
また、子どもを奮い立たせるつもりで「もっとできるでしょ!」などと言うことも、場合によっては逆効果。子どもが疲れているようなら、「よくやったね。今日はこれで終わりにしよう」と頑張りを認めましょう。元気になったら子どもはまた安心して次の行動を起こせるはずです。
ほかの子と比べる
たとえ競争心に火をつける意図があったとしても、「〇〇ちゃんはできたのに、まだできないの?」「〇〇くんよりずいぶん遅かったね」など、ほかの子どもと比べる発言は控えましょう。
子どもは自信を失い、どうせ自分でやってもうまくいかないという思考をしがちになります。自分でやってみようと思えなくなり、自立心が育ちにくくなるのです。
比べていいのは、過去と現在です。「1か月前よりも早くできた」というように成長したところを認めてあげれば、子どもにとって自信になります。
自立心を育む保育の仕方

自立心の育ちを促す保育の例を、具体的に紹介しましょう。
当番活動を導入する
給食や掃除といったルーティンの活動に加え、お手紙当番、生き物当番といった当番活動を導入すると、子どもの自立心の育ちを促すことができます。
自分のやるべきこと・やるべきタイミングを自覚しながら、見通しをもって行動する力を養えます。また、役割を認識し責任をもって行動することによっても、自立心が育まれていくでしょう。
保育士は、「〇〇ちゃんは何をするお当番だったかな?」「〇〇当番さんはいつやってくれるかな?給食のときかな?帰りの会の前かな?」など、子どもが自分で考えながら行動できるような声かけをするといいですね。
コツのいる遊びを取り入れる
コマ回しなど、少しコツがいる遊びを活動のなかに取り入れてみましょう。うまくいく方法を自分で考えて試行錯誤したり、できるようになるまで諦めずに挑戦したりするいい機会となります。
保育士は、うまくいかない子どもに「こう持つとやりやすいよ」などと説明して、少しだけ援助してあげましょう。練習を重ねてできるようになった子には「何回もやったら成功できたね!」と頑張りを認めます。
友だちや保育士に自ら助けを求めて方法を教わり、できるようになっていくという過程も味わえるでしょう。自信が深まり、別の機会でも自分でやってみようと思えるようになるはずです。
イベントを企画させる
ピクニックや園の祭りといったイベントを子どもに企画させることも、自立心を育むのに効果的です。何をしたら楽しいか、用意するものは何かなど、子どもたち自身で考えてもらうのです。
子ども同士で相談するなかでは、意見が割れて決まらなかったり、話し合いが停滞したりすることもあります。そんなときは「アイデアが2つ出ているね。どうすればどちらもできるかな?」「やりたいことがいっぱいありすぎるみたいだね。どれか2つに絞って考えてみようか」などと声をかけ、話し合いをうまく誘導してあげてください。
意見の相違を乗り越えながら自分たちで物事を決めて実行していくプロセスによって、子どもの自立心が自然と育まれていくでしょう。
自立心の育ちをじっくりと見守ろう
子どもの自立心を育むうえで大切なことや、具体的な保育の仕方について解説しました。重要なのは、子どもが自分自身で考え、試行錯誤し、やり遂げる経験です。何でも大人のペースで進めるのではなく、子どもが自分でやってみようとする姿をじっくりと見守ってあげましょう。





