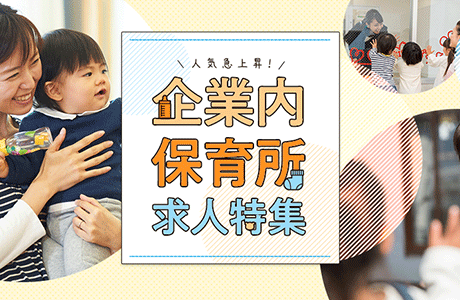保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!
X(旧Twitter)をフォローはこちら!
年中行事の意味を子どもに正しく教えることは、日本の文化に対する興味・関心を育て、季節感を学ばせることにつながります。そのため、保育士や保護者は「夏至って何?」と子どもから質問されたときに適切に回答できるよう、確かな知識を身につけることが大切です。
この記事では、夏至の意味や由来、子どもに対する説明方法を解説します。子どもと一緒に夏至を楽しむためのアイデアも紹介するため、保育園での活動や家での過ごし方を考える際のヒントとしてぜひ活用してください。
夏至とは?夏至の意味・由来を解説!
夏至とは、一年の中で太陽がもっとも北に来て、昼の時間が長くなる期間のことです。「夏」に「至る」という名前が示すように、夏至を過ぎると「本格的な夏が来る」と考えられています。ただし、夏至の日程は毎年6月21日〜7月7日頃の梅雨シーズンにあたるため、日照時間が一年の中でもっとも長くなることは非常に稀です。実際の日照時間は、冬と同じ程度である年も多くあります。
また、カレンダー上では夏至の期間の最初の日付に「夏至」と書かれます。一般的に「夏至」という場合にはカレンダーの日付を指すことも多く、夏至を期間として捉える方法・特定の日付を指す方法のいずれも間違いには該当しません。
1. 夏至の由来
夏至は、古代中国で作られた暦「二十四節気」の10番目にあたります。二十四節気とは、太陽の黄道(こうどう)の動きを基準に一年を二十四等分して、それぞれに名前を付けた暦です。二十四節気では、太陽の視黄経が90度にあたる日付を「夏至」・180度にあたる日付を「冬至」と考えます。視黄経が0度にあたる日付は「春分」で、270度にあたる日付は「秋分」です。
二十四節気では、夏至・冬至・春分・秋分を合わせて「二至二分」と呼び、二十四の区切りを定める際の基準として考えます。夏至・冬至・春分・秋分のさらに中間が、立春・立夏・立秋・立冬です。
日本では平安時代から二十四節気が取り入れられ、暮らしに深く根付いてきました。二十四節気は、農作業を行う際の目安として使われることが多くあります。たとえば、「田植えは夏至の後に始めて半夏生(夏至から数えて11日目)の前に終わらせる」といった要領です。夏至をはじめとする二十四節気は日本人の生活に定着している考え方であるため、農業とは無関係の人でも、季節の節目を象徴する言葉として使われています。
子どもに伝えたい!夏至にまつわる風習・慣習
江戸時代の日本では、人口の8割〜9割が農業によって生計を立てていたといわれています。そのため、農業と深い関わりを持つ夏至は、日本人にとって大切な節目の一つでした。現代の日本にも、一部の地域では、夏至にまつわる風習・慣習が残っています。
ここからは、夏至に関連する2つの風習・習慣を紹介します。
1. 夏至祭が行われる
日本の一部の地域では夏至に合わせたイベントとして、夏至祭を開催します。日本における夏至祭の中では、以下の2つが有名です。
・三重県二見浦の夏至祭
日の出スポットとして知られる二見興玉神社では、夏至を「太陽のパワーが強まる日」と考えて、夫婦岩の間から上る朝日の中、禊(みそぎ)を行うイベントが開催されます。
・北海道当別町の夏至祭
当別町の夏至祭は、スウェーデン流の夏至祭にならい、夏の到来を祝福するイベントです。フォークダンスやグリーンコンサート、ミッドサマーウェディングなどの催し物が開催され、見る人を楽しめます。
日本以外の世界各国においても、夏至を祝うイベントは開催されます。世界の夏至祭の中では、以下のイベントが有名です。
・デンマークの夏至祭
公園などにたかれた焚き火の中で歌ったり踊ったりしつつ、夏至の白夜を楽しみます。
・ノルウェーの夏至祭
ノルウェー南部・ヴォス周辺の村では、子どもたちによる模擬結婚式が開催されます。
・イングランドの夏至祭
イングランドの古代遺跡「ストーンヘンジ」において、太陽礼賛の儀式が開催されます。
デンマークやノルウェーなど、ヨーロッパの一部の国では冬の期間が長いため、夏の到来を意味する夏至は喜ばしい日とされています。そのため、夏至を祝うイベントを数多く開催し、地域の人々が夏の到来を祝福することが慣例です。
2. 夏至ならではの行事食を食べる
夏至には全国的に知られる行事食が少ないものの、一部の地域には特別な食べ物を食べる習慣があります。たとえば、以下の風習は、夏至ならではの行事食の一例です。
・タコ(関西)
関西地方では夏至から半夏生の時期にかけて、「タコの足の吸盤のように稲がしっかり根付くように」という想いを込め、タコ飯が食べられています。
・水無月(京都)
水無月は、ういろうの上に小豆を乗せて、三角形にカットした和菓子です。京都では6月30日に水無月を食べて、残りの半年の無病息災を願います。
・小麦餅・半夏生餅(関東・奈良)
関東地方の一部や奈良には、小麦ともち米を半分ずつ混ぜてつき、きなこをまぶした餅を夏至に食べる風習があります。
そのほか、福井県大野市では越前の焼き鯖・香川県さぬき市では讃岐うどんを田植えが終わる時期に食べて重労働を労う風習があったといわれます。いずれも、地域ごとの名産品を食べることで体力回復に努めるねらいから始まった風習です。
【保育士・保護者向け】子どもと一緒に夏至を楽しむアイデア
子どもたちに夏至の由来を伝える際には分かりやすい言葉を使用し、噛み砕いて話すことが大切です。二十四節気の説明は省略し、「夏の始まりの日」「太陽の出ている時間が長い日」と伝えるとよいでしょう。
夏至の意味を説明した上でイベントを楽しむことは、子どもに季節感を学ばせる効果的な方法です。以下では、子どもと一緒に夏至を楽しむアイデアの具体例を紹介します。
1. キャンドルナイトを楽しむ
世界各地では、部屋の照明を消してロウソクの明かりで過ごすキャンドルナイトが夏至の日に合わせて開催されます。子どもと一緒に手作りロウソクを製作し、キャンドルナイトを楽しみましょう。
【手作りロウソクの材料】
- 鍋
- 割り箸
- 紙コップ
- ロウソク
- 空き缶
- クレヨン
- カッター
【作り方】
ロウソクを2cm〜3cmに折り、空き缶に入れる(ロウソクの芯はとっておく)
空き缶を鍋に入れて湯煎で溶かし、紙コップに流し込む
好きな色のクレヨンを削り、ろうに混ぜる
ロウソクの芯を割り箸で挟み、紙コップの上に置く
ろうが固まるまで冷やし、紙コップから外す
カッターでクレヨンを削る作業・ろうを流し込む作業は、必要に応じて保護者や保育士がサポートします。安全管理を徹底するために、完成したロウソクは家に持ち帰り、大人と一緒に火をつけるように指導しましょう。
2. 夏至の時期に咲く花を鑑賞する
夏至の時期には、アジサイやアヤメ、花ショウブが咲きます。子どもと一緒に季節の花を鑑賞し、自然を大切にする心を養いましょう。子どもは、花と触れ合う機会を得ることで植物との関わり方を学び、生命あるものに対する優しさを身に付けます。身近な場所にアジサイ園やアヤメ園があれば、子どもと一緒に出掛けることもおすすめです。
3. 手作りのうちわを作る
夏至の時期には、近所で夏祭りが開催されることもあります。そこで、夏至のイベントとして、夏祭りに持参するうちわを手作りしましょう。
【手作りうちわの材料】
- うちわ本体
- デコレーション素材(折り紙やリボン、絵の具など)
【作り方】
100円ショップなどで購入できる無地のうちわを配布する
子どもの好きな道具を使用し、デコレーションさせる
より本格的に手作りを楽しみたいときは、うちわの骨のみを配布し、半円形に切り取った画用紙を貼り付けるところから始めてもよいでしょう。デコレーション素材は多くの種類を用意して、子どもの好きなデザインを実現できるようにサポートしてください。
まとめ
夏至とは、一年の中でもっとも昼の時間が長い期間や日付を意味します。日本各地には豊作を願って特別なものを食べたりイベントを開催したりする風習があり、子どもと一緒に季節の移ろいを楽しむことが可能です。
マイナビ保育士の運営する情報サイト「ほいくらし」では、季節のイベントを題材とした催し物のアイデアを多数紹介しています。子どもの喜ぶ保育を実践したい人は、ほいくらしをぜひ参考にしてください。
お得な情報や最新コラムなどをいち早くお届け!ほいくらし公式LINE 保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!ほいくらし公式X(旧Twitter)