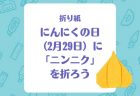うるう年とは?次はいつ?計算方法・子どもに説明する際のポイントを解説

保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!
X(旧Twitter)をフォローはこちら!
2024年はうるう年です。基本的に4年に1度訪れるため、同じく4年に1度のオリンピックは、うるう年に開催されると認識している人も少なくありません。
また、オリンピックとの関係以外にも、4年に1度訪れる理由や2月29日が誕生日の人が年を取るタイミングなど、うるう年には子どもが疑問に思うポイントも多数存在します。
当記事では、うるう年の意味・由来などの知識から、子どもと一緒にうるう年を楽しむアイデアまでを紹介します。ぜひ、保育園や家庭で役立ててください。
うるう年とは?うるう年の意味・由来を解説!
1.うるう年とは?
うるう年とは、2月29日が追加され、1年が366日ある年です。漢字で「閏年」と書きます。平年の年間日数365日に1日を加え、実際の季節と暦とのずれを修正することが、うるう年を設けている理由です。なお、2月29日は「うるう日」とも呼ばれます。
平年の年間日数365日は、地球が太陽の周りを1周する公転周期にあたります。そして、地球の公転周期に基づいて作られた暦が「太陽暦」です。
しかし、地球の公転周期は正確には365日ではなく365.24219日です。小数点以下を時間に換算すると、公転周期と暦には毎年6時間のずれが生じます。1日は24時間であるため、4年に1度うるう日を設けると、ずれを修正することができるという計算です。
太陽暦は「グレゴリオ暦」とも呼ばれます。1582年、ローマ教皇のグレゴリウス13世が制定したことにちなんだ名称です。当時すでに、古代ローマ皇帝ユリウスが定めたユリウス暦がありましたが、季節と暦のずれが生じるために新たな暦を作ったとされています。
一方、日本では古くから、月の満ち欠けと太陽の動きの両方を基準とした太陰太陽暦が採用されていました。しかし、明治5年12月2日の翌日を明治6年1月1日と定め、太陽暦の年号として1873年が始まりました。現在、太陰太陽暦は旧暦と呼ばれています。
2. うるう年の見分け方
うるう年は、原則的に西暦年数が4で割り切れる年とされており、4年に1度訪れますが、例外的に8年に1度となるケースもあります。
●西暦年数が4で割り切れてもうるう年にならないケース
うるう年を設けないと暦にずれが生じるものの、うるう年を設けることで生じるずれも存在します。そのため、グレゴリオ暦においてうるう年は400年間で97回と定められており、400年に1度、とすることがあります。
その条件は下記のとおりです。
1)西暦年数が100で割り切れる年
2)(1)のうち西暦年数が400で割り切れる年はうるう年とする
以上をふまえ、うるう年の見分け方を簡単にまとめると下表のようになります。
| 条件 | 例 | |
|---|---|---|
| うるう年 | ・西暦年数が4で割り切れる ・西暦年数が100で割り切れる年を除く(ただし、400で割り切れる年はうるう年とする) | 1964年・1996年・2008年・2020年・2024年・2028年 2000年・2400年・2800年 |
| うるう年ではない | 西暦年数が100で割り切れる年のうち400で割り切れる年を除く | 2100年・2200年・2300年 |
4年に1度訪れるものといえば、うるう年のほかにもオリンピックがあります。
第1回オリンピックはギリシャのアテネで開催されました。開催年はうるう年の1896年ですが、オリンピックとうるう年が重なったことは、あくまでも偶然です。しかし、第1回以降、オリンピックは4年に1度開催され、うるう年と重なるようになりました。
1994年の冬季オリンピックからは、夏季オリンピックとの開催年を2年の間隔を置くようになったため、うるう年と重なる大会は夏季オリンピックのみです。
ただし、例外もあります。パリ大会が開催された1900年は「100で割り切れるが400で割り切れない」ため、うるう年ではありませんでした。パリ大会は数百年に1度のまれなケースであったといえます。そのため、通常は「夏季オリンピックはうるう年に開催される」と考えて問題ないでしょう。
3. うるう秒とは?
うるう秒とは、数年間で生じる秒のずれを修正するために差し引きされる1秒のことです。
1日の長さは地球の自転を基準としています。しかし、地球が太陽の周囲を365日で公転していないように、1日あたり24時間ちょうどとなるように自転しているわけではありません。自転速度は一定でなく、速くなったり遅くなったりするためにずれが生じます。
一方、地球の自転とは関係なく、より正確に秒を測定する手段として原子時計が存在します。原子時計は、自転の回転速度によって生じる秒のずれを修正する基準となっており、自転による時間と原子時計のずれの許容範囲は、プラスマイナス0.9秒です。両者のずれが1秒以上になる前に、うるう秒によって1秒を足し引きして修正します。
うるう秒はうるう年とは異なり、定期的には生じません。必要に応じ、世界時間の12月31日または6月30日の最終秒でずれを修正します。日本では世界時間との時差があるため、1月1日または7月1日の午前8時59分の最終秒で修正されます。
うるう秒による修正は1972年に初めて採用されて以来、27回行われました。一番最近は2017年1月1日です。
(出典:日本標準時グループ「うるう秒実施日一覧」)
うるう年(2月29日)が誕生日の人はいつ年を取る?
人々は毎年誕生日を迎え、1歳ずつ年を取ります。しかし、うるう年の2月29日に生まれた人には、暦の上で誕生日が4年に1度しか訪れません。とはいえ、実際にはうるう日に生まれた人も毎年、年を取ります。
日本では明治35年12月22日、年齢の計算方法を定めた「年齢計算ニ関スル法律」が施行されました。同法律によると、各年齢は誕生日から起算し、次に迎える誕生日の前日に満了となります。
例えば、2021年2月29日に生まれた赤ちゃんが満1歳となるタイミングは、2022年2月28日の24時です。つまり、うるう年の人は誕生日に切り替わる直前に年を取ります。なお、3月1日生まれの人の場合、2月28日の24時または2月29日の24時に年を取ります。
うるう年を子どもに説明する際のポイント
地球の自転周期や公転周期に起因する、うるう年のしくみは、大人でも正確に理解することが容易ではありません。そこで、子どもに説明する際は、ポイントを押さえてわかりやすくまとめることがおすすめです。
【うるう年を説明するポイント】
・平年の2月は28日までだが、うるう年には2月29日がある
・うるう年は4年に1度ある
・地球は太陽の周りを365日と6時間かけて回るため、「6時間×4年」の24時間分を4年に1度、2月29日に調整する
・うるう年がなければ、「冬の5月」「春の9月」のように季節とカレンダーがずれてしまう
以上のように、うるう年に関する事実とうるう年がある理由を簡潔にまとめると、子どもも理解しやすいでしょう。
【保育士・保護者向け】子どもと一緒にうるう年を楽しむアイデア
うるう年は、毎年決まって訪れる2月28日や3月1日とは異なり、4年に1度しか訪れません。幼い子どもにとって、4年に1度の体験は大人にとって以上に貴重です。うるう年を貴重な機会としてとらえ、思い出に残る過ごし方で楽しむことをおすすめします。
ここでは、子どもと一緒に2月29日を楽しむ3つのアイデアを紹介します。
1. 天体について学ぶ
うるう年は地球の公転周期や自転周期が影響してできた年であるため、地球や太陽を含めた天体について学ぶ良い機会となります。
自宅や保育園に天体望遠鏡があれば、実際に星や月の動きを観察できますが、天体望遠鏡がなくても問題ありません。
例えば、地球や星座、宇宙についての書籍を使用する方法が挙げられます。子ども向けの絵本や図鑑はイラストを豊富に使い、わかりやすい言葉や例え話で解説しているため、興味をひきやすいでしょう。
また、プラネタリウムや天文台、科学センターなどを訪ねることもおすすめです。神話から星座について学んだり、宇宙飛行にまつわる展示物を見たり、さまざまな観点から天文の知識を深めることができます。
2. オリンピックについて学ぶ
偶然の一致とはいえ、オリンピックの開催年は基本的にうるう年です。したがって、うるう年はオリンピックについて学ぶ機会としても適しています。
オリンピックは1896年の第1回ギリシャのアテネ大会以来、世界各国で30回近く開催されてきました。これまでの開催国・都市や参加競技、参加選手など、子どもが興味を持って学べるテーマも豊富です。
東京都やオリンピック関連団体などは、子ども向けのデジタル教材などを数多くインターネット上で提供しています。学んだ成果をクイズ形式で確認するなど、遊びの要素を取り入れると、より楽しく学ぶことができるでしょう。
3. ひな祭りの準備をする
2月29日の3日後は3月3日、ひな祭りの日です。「桃の節句」とも呼ばれ、家庭や保育園などでは女の子の健やかな成長を願う行事が行われます。そこで、3日前の2月29日をひな祭りの準備に充ててはいかがでしょうか。
ひな祭りにはひな人形の飾りつけが欠かせません。7段や15段の飾り棚に内裏雛(だいりびな)や五人囃子(ごにんばやし)などを飾る作業です。ひな人形や供物を、紙コップや折り紙などを素材に子どもと一緒に手作りしても、楽しい思い出となるでしょう。事前に作っておくことによって、作ったひな飾りを当日も含め長く楽しめるというメリットもあります。
準備の過程で、ひな祭りの由来や意味についてわかりやすく説明することが大切です。何を、なぜ祝うかを知れば、ひな祭りに対する親しみや楽しみも増します。
まとめ
うるう年とは、2月29日がある年を指します。地球の公転周期によって発生する実際の季節と暦とのずれを修正するための年です。オリンピックは4年に1度のうるう年に開催されますが、意図してうるう年と重ねたわけではなく、偶然重なりました。また、日本の法律に則ると、誕生日が2月29日の人は前日の28日24時に年を取ります。
以上のような知識を深めながら、うるう年や2月29日を子どもたちと楽しく過ごしましょう。
マイナビ保育士が運営する「ほいくらし」は、保育園での遊びや行事の紹介、仕事情報などが多数掲載された保育士のためのサイトです。うるう年以外にも、気になる行事や記念日があれば、ほいくらしの情報をぜひご活用ください。
お得な情報や最新コラムなどをいち早くお届け!ほいくらし公式LINE 保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!ほいくらし公式X(旧Twitter)