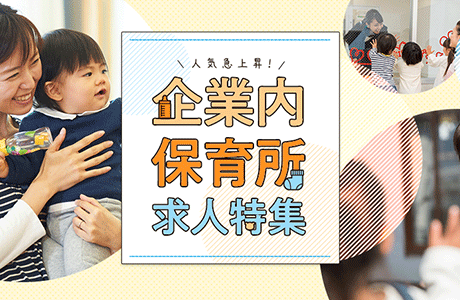<情報PICKUP>「孤育て」という言葉はゾクッとする響きがありますね。こちらは保育者向けのパンフレットですが、確かにその子の違和感を感じとれる第三者って保育士さんかもしれないですよね。子どもが生き生きと園生活を送るためにも、保護者の置かれている環境に思いを巡らせることも大事。なかなか荷が重いお仕事ですが、春からの新人保育士さん、ぜひお役立てください。(保育ライター ヨシコ)
本件のポイント
子育て家庭の孤立には、ワンオペ育児やつながりの希薄化、経済的な問題など複雑な要因が重なりあい、深刻な児童虐待につながるケースが発生するなど社会全体の問題
本学短期大学部こども教育学科の教員5名が、孤立した子育て家庭の「孤育て」をテーマに2年間にわたる共同研究を展開し、研究成果としてパンフレットを発行
パンフレットは保育者としての社会人生活を始める新任職員を読者に想定し、日頃の園・所での仕事をふりかえってもらうヒント集になることをめざして作成
本件の概要
2024年3月1日(金)、龍谷大学 社会的孤立回復支援研究センター(①)「子育て家庭ユニット」は、2022~2023年度の2年間にわたる子育て家庭の社会的孤立に関する共同研究の成果として、『「孤育て」のトリセツ~がんばるワタシの応援パンフ~』を発行しました。本パンフレットのデータは、「孤育て」を見守る多くの方々とも共有し、活用していただけることを目的として、WEBでも公開しています。
このパンフレットは、保育者としての社会人生活を始める新任職員を読者に想定しながら、「孤育て」という難問と隣りあわせの可能性を考慮し、日頃の園・所(幼稚園・認定こども園・保育園・所の総称)での仕事をふりかえってもらうヒント集になることをめざして作成したものです。内容は、児童虐待と保育者の役割や気付きのポイント、保護者との関わり方、相談窓口など多岐にわたります。また、保育者である“ワタシ”自身の健やかな心身あっての仕事でもあるため、セルフケアのヒントやローリングストック(②)・レシピなども盛り込み、新人職員が気軽にパラパラと眺めて、一つでも参考になるようイラストや写真を多用しているのも特長です。
研究代表者の短期大学部(③)中根 真教授をはじめ、同ユニットメンバー全員が短期大学部こども教育学科において保育者(保育士・幼稚園教諭)養成に従事していることから、今回の研究成果は直接的には在学生や卒業生、保育実習園・施設、教育実習園に対して、さらに間接的には4年制学部の教職志望学生に対して、それぞれ還元する見込みです。なお、本学短期大学部こども教育学科2年生には3月14日(木)の卒業式当日に配布するほか、1年生には2024年度の授業時に配布を予定しています。
発行概要
タイトル:『「孤育て」のトリセツ~がんばるワタシの応援パンフ~』
著者:中根 真(代表、本学短期大学部教授 | 專門:社会福祉学)
赤澤 正人(本学短期大学部准教授 | 專門:社会心理学、保育の心理学)
堺 恵(本学短期大学部准教授 | 專門:社会福祉学)
野口 聡子(本学短期大学部教授 | 專門:食品機能学、調理学)
広川 義哲(本学短期大学部准教授 | 專門:教育哲学)
発行:龍谷大学 社会的孤立回復支援研究センター「子育て家庭ユニット」
※パンフレットデータ(PDF)の掲載先:https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-14388.html
ページ紹介(※一部抜粋)



■本パンフレットおよび研究内容に関する問い合わせ
龍谷大学短期大学部こども教育学科・教授 中根 真
E-mail: makoton@human.ryukoku.ac.jp