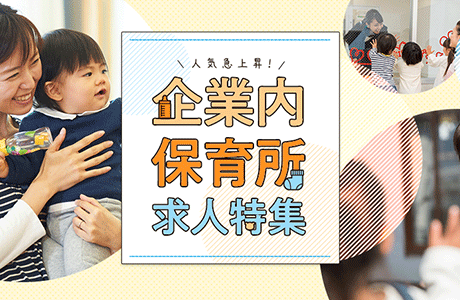みなさんは、「保育園留学®(株式会社キッチハイクの商標です)」という言葉を聞いたことがありますか。初めて耳にする方は、「保育園児が留学?」と驚いてしまうかもしれませんね。保育園留学®とは、都市部に暮らす家族が1〜3週間地方で暮らしながら、子どもを地元の保育園であずかってもらうプログラムのこと。テレワークの普及などが追い風になって、参加枠を待つ親子が2500組以上いるという、大人気の取り組みなんです。今回は、保育園留学®を運営する株式会社キッチハイク広報担当の福田将人さんに、こうした取り組みが子どもたちや地域にもたらす効果についてお話をうかがいました。
◆ 保育園留学®HP
\お話を伺った方/
福田将人さん 株式会社キッチハイク
都市部の子どもたちに、感受性や運動能力を育むための環境を提供したい
──まずは、保育園留学®の概要からお聞かせください。
福田:簡単に言うと、全国にある拠点に家族単位で1〜3週間滞在し、子どもが地域の保育園やこども園に通うプログラムです。2023年5月の時点で拠点は15か所あり、雄大な北の大地でのびのびと遊べる北海道厚沢部(あっさぶ)町や、日本一の米どころで食育にも力を入れている新潟県南魚沼市。そして、美しい海のすぐそばで暮らせる熊本県天草市など、日本中の魅力ある地域で保育園留学®を展開しています。
ウミガメが産卵にくるほどの美しい海が、身近に感じられる天草市の拠点。
──観光旅行やワーケーションとは、どのような点に違いがあるのでしょう?
福田:保育園留学®は、「豊かな自然環境のなかで、子どもたちの感性を育みたい」という、子どもファーストの視点から生まれた取り組みです。つまり、子どもを主役にしたプログラムであり、子どもの活動を一番に考えて滞在を設計している点が、観光旅行やワーケーションとの違いですね。
──アイデアが生まれてから、事業化に至るまでの流れを教えてください。
福田:キッチハイク代表である山本が、地域の食文化を紹介するイベントで厚沢部町と交流したことがきっかけになっています。山本はもともと幼児教育に興味があり、娘さんが通う保育園に園庭がないことや、コンクリートの道で散歩をしていることに対して、「感性や運動能力を育むために、自然と触れ合える環境を提供できないだろうか?」と、もどかしい思いを抱いていたんです。
そうしたなか、ふと「おいしいメークインが育つ厚沢部町では、いったいどんな子育てをしているのだろう?」ということが気になりインターネットで調べてみると、森に囲まれた丘の上に佇む認定こども園「はぜる」のすばらしい環境と、子どもたちのはじけるような笑顔が目に飛び込んできた。それを見た瞬間に、「ここに娘を通わせたい!」という思いが湧き上がってきたそうです。
保育園留学®の最初の拠点となった、北海道・厚沢部町の認定こども園「はぜる」。
そこから、「自治体の一時預かり制度と保護者のリモートワークを組み合わせれば、新しい保育のスタイルが実現できるのではないか?」と発想し、現在の保育園留学®につながっています。
恵まれた環境のなか、野菜の収穫を楽しむ認定こども園「はぜる」の子どもたち。
アイデアが生まれてから事業化までは、非常にスピーディーでしたね。厚沢部町に事業を提案し、山本一家が夏と冬の年2回、厚沢部町で生活しながら保育園留学®のプランをブラッシュアップ。4か月ほどの準備期間を経て、2021年11月に正式サービスとしてスタートさせました。
「また来るね!」「また来てね!」と涙ながらにさよならする子どもたち
──保育園留学®に参加した子どもたちの様子はいかがですか?
福田:最初は恥ずかしがって隠れているような子もいますが、事前に面談を行っている保育者が上手に誘導してくれるので、すぐに現地のお友だちと話せるようになります。そこからは、お友だちに自然のなかでの遊び方を教えてもらったり、秘密基地で一緒に過ごしたり……。そういえば、「カマキリを見たことがない」と言った子のために、園児と保育者が総出で探しまわるようなシーンもありました。
お客様扱いをせず、園の日常に招き入れるという姿勢が功を奏してか、滞在中の子どもたちは、大人が想像する以上にすばらしい反応を示してくれます。保護者の方にも「これまでに見たことのないような笑顔で帰ってきた」とびっくりされることが多いですね。
──迎え入れる側の子どもたちは、新しいお友だちに対してどのような反応を示していますか?
福田:すごくフレンドリーな反応で、「東京ってどこ?」「20階に住んでいるって本当?」など、子どもなりに聞きたいことをどんどん質問しています。そうしたやりとりのおかげなのか、地図に興味をもつ園児が増えたと聞きました。そして留学最後の日がやってくると、「また来るね」「絶対だよ」と涙ながらに別れを惜しんでいます。もしかしたら、生まれて初めて覚える「名残惜しい」という感情かもしれないですね。
──そうした約束が、次につながったら素敵ですね。
福田:実を言うと、留学組の「また来るね」の言葉通り、リピート希望率は95%を超えています。子どもにとっても親にとっても、忘れられない経験になっているのでしょう。
成功のカギは「保育者の力」と「地域のポテンシャル」にあり
──リピート希望率の高さもさることながら、キャンセル待ちの親子が2500組以上いらっしゃるのも驚きです。どういった点が成功のカギだったのでしょうか。
福田:保育園留学®は、受け入れる施設や保育者の理解・協力がないと成り立ちません。そういう意味では、保育者の力があってこそのプログラムと言えるでしょう。新しい子どもたちが、一時保育枠で次々とやってくるのは大変だと思いますが、どの園も「子どもたちのためになるなら!」「ここでの体験が子どもたちの心に残るのはうれしい」と本気で関わってくださいます。子どものやりたいことを一緒にかなえようとする姿勢には、いつも感嘆させられますね。
加えて、それぞれの地域が持つポテンシャルも、支持されている要因だと思います。虫採りや川遊び、星空観察などは、地元の人にはありふれた日常かもしれませんが、都会から留学してくる家族にとっては非日常的な価値ある体験です。そして、「何もない田舎だから」と謙遜されている地域にも、必ず光る魅力があり、子どもたちの感性を育んでくれる。そういう意味では、地域ごとのポテンシャルを掘り起こすのも、私たちの大事な使命だと考えています。
南魚沼市でのひとコマ。あたり一面に田んぼが広がり、さわやかな風が吹き渡る。
熱量の高い「関係人口」を増やし、地域課題を解決していきたい
──保育園留学®は、受け入れる地域にとっても良い影響がありそうですね。
福田:子どもが宝物のような時間を過ごした地域は、その家族にとって第二、第三のふるさととして心に刻まれます。そのため、留学後に旅行先として選んだり、ふるさと納税を行ったりと良縁が続く可能性も高いのではないでしょうか。地域と強い絆でつながる「関係人口※」の増加は、経済的にもメリットがあると考えています。
また、保育園留学®をきっかけに移住の問い合わせも増えていると聞きますし、実際に移住に向けて動き出した家族もいらっしゃいます。今はどの地域も人口減少の課題に直面していますから、少しでもお役に立てればうれしいですね。
※移住した「定住人口」や、観光にきた「交流人口」とは違った形で、地域や地域の人々と関わる人々を指す言葉。
──最後に、今後の展望についてお聞かせください。
福田:今後はさらに全国拡大を目指し、留学先を増やしていく予定です。代表の山本も「保育園留学®が、世のなかに必要な仕組みだという確信は間違っていなかった」と、目標達成に向けて意気込んでいます。加えて、保育園留学®を受け入れている園同士をつなげて、ノウハウを横断的に共有できる「保育園留学®コンソーシアム」の仕組みも構築中です。そうしたさまざまな活動を通じて、保育園留学®が“当たり前の選択肢”となる育児文化を築いていきたいですね。
取材・文/万谷 絵美 編集/イージーゴー