価値観や社会構造の変化、テクノロジーの発展などによって、未来予測が難しくなった現代。そんななか、「予測不可能な時代を生き抜く力」を身につけるためのメソッドとして、STEM(ステム)教育が注目されています。
近ごろは、メディアでも「STEM」という言葉をよく目にするようになりましたが、みなさんはこの言葉にどういったイメージを持っていますか? なかには「プログラミング教材を使って理系に強い子を育てる教育」といった、難しそうなイメージを抱いている方もいるのではないでしょうか。
しかし、STEM教育を実践するのに理系の専門知識や特別な教材は必須ではなく、日常的な遊びを通じてSTEM的な学びを深めることも可能なのだそう。そこで今回は、幼児や小学生への科学教育を研究する中村大輝さんに、STEM教育の基本的な知識や保育の現場で実践できる遊び方について、お話をうかがいました。
\お話をうかがった方/
中村大輝さん
宮崎大学教育学部講師
1992年、東京都生まれ。東京都の公立小学校教員を経て、広島大学大学院で学んだあと、2023年度より現職。2022年広島大学大学院教育学研究科博士課程後期修了。専門は科学教育、理科教育、教育心理学。特に科学的探究を通した思考力の育成、現代的な教育測定法の開発などの研究に取り組んでいる。国立教育政策研究所PISA2025年調査の問題検討委員などを務める。2024年9月、初の単著となる『生成AIで進化する理科教育 ─導入から実践までの完全ガイド─』を上梓。
統合的な学びで、子どもの自発性・創造性・協働性・問題解決能力を養う

──まず、STEM教育とは何なのか、基本的なところから教えてください。
中村:STEMとは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Mathematics(数学)を総称する言葉です。これら4つの学問領域に力を入れることはもちろん、それぞれを関連づけながら学ぶことで、これからの時代に必要とされる自発性や創造性、協働性、問題解決力といった能力が育成できると期待されています。
ちなみに、STEMにArts(芸術・リベラルアーツ)を加えてSTEAM(スティーム)教育と呼ばれることもあります。
──数学や理科に強い、理系人材を育成するための教育というイメージがありましたが、必ずしもそういうわけではないのですね。
中村:STEM教育の強化を先導したのは、オバマ政権下のアメリカです。当時は「近い将来、科学技術を担う人材が不足する」といわれていたのですが、科学技術力の低下は国力の低下を意味します。そのため、オバマ政権は科学技術を担う人材を育成するキャンペーンを実施し、STEM教育の重要性を強調。そこから、STEMという言葉が一躍脚光を浴びるようになったのです。
そういう意味では、理系人材を育成するための教育ではありますが、STEM教育の意義はそれだけではありません。これからの時代はあらゆる職業において、他分野と連携しながらイノベーションを起こす必要があるといわれており、複数の分野の知識を関連づけて学んだり、異なる分野の人たちと協働できる能力が求められています。さきほど申し上げたとおり、STEM教育ではそうした資質・能力の育成が期待できるため、現在、アメリカのみならず世界各国でSTEM教育が推進されているのです。
日本の「STEM教育」は発展途上!?今後は教育現場への導入が加速する可能性も

──その流れから、日本でもSTEM教育が注目されるようになったのですね。
中村:そうです。ただ、日本の場合は学習指導要領によって、初等教育や中等教育における教育課程の基準が定められているので、諸外国のようにSTEM教育を教科として導入できなかった経緯があります。そのため、スーパーサイエンスハイスクールのような限られた学校や学校外の学びの場所で、STEM教育が展開されてきたというのが実状です。
──今後、学習指導要領が改定され、日本の小学校や中学校にもSTEM教育的な教科が導入される可能性はあるのでしょうか?
中村:次の学習指導要領の改訂は2027年といわれていますが、そのときにSTEM教育の扱いがどうなるのかは、まだわかりません。とはいえ、文部科学省もSTEM教育の重要性は認識していて、現行の学習指導要領でも「STEM」という言葉こそ使っていないものの、「教科横断」「教科間の連携」といった言葉で統合的な学びを推奨しています。
たとえば小学校の場合だと、理科の授業のなかに身につけた科学的知識を活用しておもちゃづくりをする、「ものづくり」という時間が設定されています。試行錯誤をしながらプロダクトを完成させる過程は、技術分野の学びにつながりますから、教科の横断・連携だといえますよね。理科の授業で実験データを処理する際には算数の知識も必要になり、ここにも教科横断の学びがあります。
また、近年は「GIGAスクール構想」の名のもとに、子どもたちが1人1台タブレット端末を持ち、情報技術を活用しながら学習を進めています。そうした取り組みも、情報・技術と各教科の連携と考えて良いでしょう。今後も、統合的な学びが強化されていく可能性は十分にあると思います。
遊びを通じたSTEM教育の実践では、大人の「声かけ」が大事

──最近は、幼児向けのSTEM教育系スクールも増えてきているようです。未就学児のうちからSTEM的な学びに触れることに、意味はあるとお考えですか?
中村:もちろんあると思います。近年の幼児教育においては、子どもが主体的に環境と関わりながら、遊びを通じてさまざまな学びを深めることが重視されています。STEM教育というと、子どもがロボットや工学的な装置と関わる姿を連想する方が多いのですが、日常的な遊びのなかにもSTEMの要素がたくさん詰まっているんですよ。
代表的な例を挙げると、保育園で子どもたちに人気の「色水遊び」がそうです。「色水遊び」は食紅や絵の具、植物などで水に色をつける遊びですが、花を使って植物性の色素を抽出する行為には、科学の要素が含まれています。花の量や水の量によって色を調整することには計量──すなわち数学の要素が入っていますし、自分好みの色をつくるために色を混ぜて試行錯誤する行為には、技術や工学の要素が入っています。
さらに、自分がつくった色で絵を描けば、芸術の要素が入ってくる。そうすると、STEMどころかSTEAMの要素がすべてそろうことになりますよね。このように、必ずしもICTの機器を使わなくても、統合的にSTEMを学ぶことは可能なんです。
──確かにおっしゃるとおりです。色水遊びのほかにも、STEMの学びを深められる遊びやレクリエーションがあれば教えてください。
中村:すぐに思いつくのは砂場遊びです。日本の保育園や幼稚園、公園にはかなり高い確率で砂場が設置されていますよね。実はこれ、世界的には珍しい日本特有の現象なんです。なぜ砂場が多いかというと、かつて日本の幼児教育の礎を築いた方たちが「砂場は幼児教育に良い」と提言し、公園への砂場の設置が推奨されるようになったのだそうです。

それはさておき、砂場はSTEM的にも非常に面白い遊びの場です。砂場では、子どもたちが穴を掘ったり、立体的な造形物をつくったりしますが、立体的な造形物をつくるのに必要な空間認識能力は数学と深く関係しています。また、砂の粒の大きさや水分の量によって加工の仕方を調整するには科学的な思考が必要です。
完成したら造形物をつぶして、すぐに新しいものをつくるという試行錯誤のしやすさも砂場遊びならではですし、友だちと一緒に造形物を完成させれば協働性も養われます。
──つまり、保育園や幼稚園では、子どもたちが日常的にSTEM的な学びを経験してるということですか?
中村:そうともいえますが、色水や砂場はあくまでも「教材」だとお考えください。STEM教育としての学びを深められるかどうかは、遊んでいる子どもに対して周囲の大人がどんな声かけをするかで大きく変わってきます。
たとえば色水遊びをしている子どもに対しては、「こっちの水よりあっちの水のほうが色が濃いね」と声をかけて、比較の視点を与えてあげる。同じように、砂場で泥団子をつくっている子には、「こっちのお団子よりあっちのお団子のほうが硬いね」などといってあげるのが良いでしょう。教材を与えっぱなしにするのではなく、保育者や保護者が「気づき」を促すような声かけをすることで、子どもの学びはさらに深まっていくはずです。
STEM教育の本質は、「遊び」を通じてさまざまな学びを深めること

──お話をうかがっていると、すぐにでも子どもたちの遊びにSTEM的な要素を取り入れられる気がしてきました。ところで、STEM教育の実践をしている保育園は、日本にもあるのでしょうか?
中村:日本でも実践例が増えており、有名なところでは、お茶の水女子大学附属のこども園による「就学前STEAM教育実践を目指すお茶大こども園ラボ」があります。参考までに、同ラボの事例から「フライトラボ」をご紹介しておきましょう。
この遊びでは、穴のあいた机の下に大型の扇風機を置き、机の上には穴と同じ直径の透明な筒を設置します。扇風機のスイッチを入れると、筒のなかでは下から上に向かって強い風が吹きますから、筒のなかにものを入れると上に向かって飛ばされますよね。
最初、子どもたちは筒に入れたものが飛ばされることをシンプルに楽しみますが、教育者が多種多様なアイテムを用意しておくことで、上に飛ぶものと飛ばないものがあることに気づきます。布は勢いよく飛んでいったけど、小さなボールは飛ばなかったという具合ですね。そして、「それはなぜだろう」「ボールを飛ばす方法はないのか」とみんなで試行錯誤しているうちに、ボールを飛ばす方法を見つけます。
どうやったかというと、ボールを布で包み、布が飛ばされる勢いを利用してボールも一緒に飛ばしたのです。子どもが夢中になる遊びのなかにSTEMの要素を取り入れ、試行錯誤を通じて協働性や問題解決能力を養っていく。すばらしい取り組みだと思います。
※参考:文京区立お茶の水女子大学こども園「就学前STEAM教育実践を目指すお茶大こども園ラボ」
──そうした取り組みが、今後ほかの保育施設に波及していく可能性はあるのでしょうか。
中村:大いにあると思います。お茶の水女子大学附属こども園で行われている研究も、全国に活動を広げたいという思いがあってやっていることでしょう。最近は、乳幼児STEM保育研究会のような学会も立ち上がり、「乳幼児期の子どもたちにいかにSTEM教育を展開していくか」が、各所で研究されています。
──STEM教育はプログラミングに関連づけて語られがちなので、どうしてもハードルが高いイメージがありました。しかし、中村さんのお話を聞いたことで、肩の力が抜けたように感じます。
中村:「STEM教育」と「幼児教育」というキーワードでネット検索すると、「プログラミング教材を通じたSTEM教育」のような情報がたくさんヒットするので、そういうイメージを持たれがちですよね。もちろんプログラミング教材を使うのも悪くないのですが、未就学児にはあまり向いていないかもしれません。低年齢の子どもはパソコンのキーボードも満足に操作できませんから、その意味でのハードルはどうしても高くなってしまうんです。それよりは、身近な遊びを通じて学びを深めていくほうが、日本の幼児教育との親和性が高いと思いますよ。
先ほどお話したような声かけをしながら、ぜひ子どもたちの学びをサポートしてあげてください。
取材・文/岸良ゆか





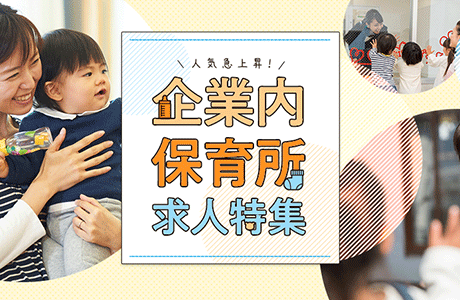

![園のルールを守らない保護者に、意を決して注意喚起!返ってきた予想外の反応とは [ヤメエピ@保育士辞めたいエピソード]](https://hoiku.mynavi.jp/contents/wp-content/uploads/2024/10/header_ep044-140x96.jpg)