英語は早く始めるだけでは意味がない!早期英語教育の研究者が教える、「おうち英語」のポイントとは

グローバル化が進む現在、子どもが小さいうちから、「おうち英語」に取り組む家庭が増えています。「おうち英語」というのは、自宅でパパ、ママがガイド役になって子どもの英語教育に取り組むこと。動画や絵本、知育玩具などを使って生活の中に英語環境を整え、子どもが自然に英語を習得できるようにアプローチしていていきます。「英語学習は幼少期から始めたほうが有利」と言われていることを考えれば、「おうち英語」に注目が集まるのも納得ですよね。
しかし、研究者の中には「単純に早く始めればいいわけではない」という声があることも事実。早稲田大学教授で、早期英語教育や第二言語習得を研究している尾島司郎先生によれば、英語学習には開始年齢だけでなく、「学習に取り組む時間」や「インプットの量」に配慮することも大事なのだそうです。
今回は尾島先生に、早期英語学習の効果や効率よく英語を習得するためのポイントについてお話をうかがいました。保育園で実践できる英語学習についても聞いてみたので、ぜひ最後までご覧ください。
\お話をうかがった方/
尾島司郎先生
早稲田大学 理工学術院 英語教育センター教授。専門は、第二言語習得論、早期英語教育など。横浜国立大学教授などを経て2023年より現職。インターネットを通して、研究の成果や英語教育に関する提言を数多く発信している。
大切なのは、「早期に始める」と同時に「学習時間を多くとること」
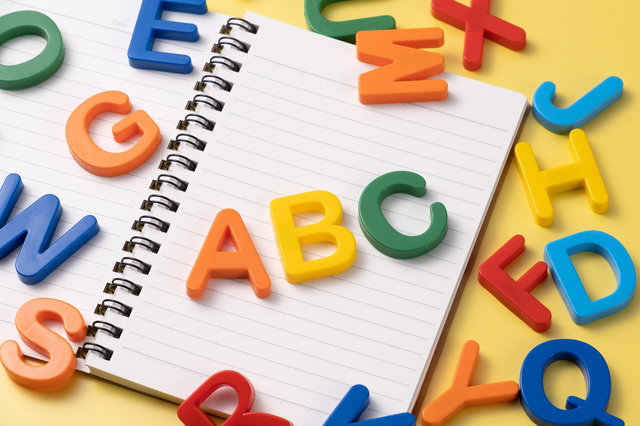
――先生は現在、早期英語学習について研究されているとうかがっています。なぜ、その領域を研究テーマに選んだのでしょう。
尾島:日本人の英語習得のメカニズムに興味を持ったのが、研究を始めたきっかけです。日本人は英語習得に苦労する傾向が強いので、「どうしたらうまく習得できるのか」を調べてみたかったんです。そして、調査・研究を進める中で注目したのが、英語学習の開始時期と習熟度の関係、つまり「人生のどのタイミングで英語学習を開始すれば、どのぐらいの英語習熟度に到達するか」ということです。ただし、調べ始めると、開始タイミングとともに、かける時間が大事だと気づきました。
研究では、「おうち英語」を継続している小学生にスピーキングの課題をこなしてもらい、その成果を調べたり、脳波計を使って日本語と英語を聞いたときの脳活動の違いを調べたりしています。
――近年は「おうち英語」が注目されていますが、小さいうちから英語を学ぶことにメリットはあるのでしょうか。
尾島:もちろんあります。絶対的なメリットは、時間がたくさん使えるという点ですね。英語習得のプロセスでは、多くの学習時間を確保する必要があるので、未就学の子どもには大きなアドバンテージがあると言えます。
ただ、ここで注意しないといけないのは、「時間をかけること」と「早く始めること」は、似ているようで違うという点です。
早く始めることの効果は、中高生や大人が同じくらいの学習時間をとった場合と比較しないとわかりません。また、さまざまな研究によって、早い時期から英語学習を始めても、学習時間が短いとあまり効果がないことがわかっています。極端な話ですが、0歳から始めて週に1回1時間の英語学習をしている子どもと、10歳から始めて毎日3時間やっている子どもだと、後者のほうが断然早く伸びます。また、普段の学習時間が仮に同じだったとしても、幼児よりも中高生の方が、最初は伸びが速いです。
――始める年齢が遅くても、学習時間が長ければ力がつきやすいのですね。
尾島:ただし、ここにも注意点があります。中高生や大人であっても、学習に多くの時間をかければ英語力は伸びます。けれど、途中から伸びにくくなってしまうんです。
年間500時間を英語学習にかけた中高生と幼児がいたとしましょう。その時点では中高生のほうが伸びますが、学習時間の合計が5,000時間、1万時間と増えてくると、幼児の頃から学習を始めていた人の英語力のほうが、逆転して伸びていきます。
こうした逆転が起こるのは、子どものころに数千時間の英語学習を達成したケースだと考えられます。例えば、乳児期に開始して、年間500時間以上を10年続けて、小学生のうちに5,000時間を越えたようなケースです。
理由はいろいろと考えられますが、一般的には中学から本格的に始めた学習者には、「化石化」という現象が起こるからだと言われています。化石化というのは、化石が長期間固まっていることになぞらえた言葉で、言語能力がある一定の段階から伸びなくなったり、間違って覚えた英語が癖になったりする状態を指します。
化石化の主な要因として挙げられるのは、音が聞き取れていないことや、音の違いがわからないことです。例えば、音が小さい前置詞の「at」や「in」は、正確に聞き取るのが難しいとされていますが、そうした音が聞きとれないと、文法的に正しい情報がインプットされませんよね。しかし、幼児は発音や音を聞き分ける能力が高いので、そうした音もインプットされやすい。そのため、学習時間が長くなるにつれて正しいインプットの量が中高生を上回り、結果的に逆転現象が起こるのです。
また、母語の影響も大きいと言えます。中高生はすでに日本語の能力が身についており、脳が日本語用にチューニングされています。一方、幼児の場合は、どの言語にも完全にチューニングされ切っていない状態なので、英語など他の言語の習得に母語があまり干渉しないのです。
――時間の大事さはよくわかりました。「おうち英語」で多くの時間を確保するには、親の側も相当頑張らないといけませんね。
尾島:英語をネイティブのように自在に操れるまでには、幼少期のうちに数千時間の接触が必要なことがわかっています。その点では、親の頑張りも必要ですね。
日本の場合、小学校から大学まで授業で英語に触れたとしても、時間的には1,500時間にも達しません。子どものうちに数千時間、英語に接触するのは容易ではないでしょう。
英語教材は、視覚情報を伴ったものを選ぶのがおすすめ

――学習時間と同様、インプットの量も多ければ多いほどいいのでしょうか?
尾島:幼児は、中高生のように文法を教科書で学んだり、先生の説明を聞いて理解したりすることができません。ですから、英語を習得するにあたっては、まず音声をインプットし、自分の頭の中で英文法を生み出していくことになります。
こう説明すると、難しい作業に思えるかもしれませんが、幼児のうちは日本語に対しても同じ作業をしており、子どもにとっては自然なことです。
ただ、教科書を見て文字からインプットするのと違って、音声は一瞬で頭の中を通り過ぎてしまいます。そこから文の構造や文法のパターンを抽出するには、まず英語の音声を頭に定着させ、音声記憶を大量に作っていかなければなりません。そのためには、ひたすら音声を聞かせることが重要になるでしょう。
――大量の英語のインプットをしていくと、母語である日本語の習得に影響が出たりはしませんか?
尾島:2か国語が話せるバイリンガルの子どもが、2言語を扱うことで母語の発達に遅れが出るかどうかを調べた研究はたくさんあります。そして、そうした研究では、使う言語のどちらかが遅れているように見えても、年齢を重ねるうちに追いつくことがわかっています。
とはいえ、読み書きを含めた総合的な言語力を、すべてネイティブのレベルまで持っていくのは、バイリンガル環境にいても簡単ではありません。そのために、バイリンガルの子どもは日常会話が問題なくできても読み書きができない、という状態になりやすいんです。
もし、「おうち英語」に取り組む際に母語への影響が心配なら、「親との会話は日本語にする」と決めておくのがよいでしょう。学校での会話や親との会話は日本語を使い、そのほかの時間は教材や動画で英語を学ぶ。そのやり方で、十分効果が期待できると思います。
――具体的には、どのような形でインプットすればいいのでしょう。例えば、英語を流しっぱなしにするという学習法は効果的ですか?
尾島:インプットの方法を考えるときは、ビジュアルが伴っている場合と、音声だけの場合とを分けて考えたほうがいいでしょう。
DVDやインターネットの動画など、ビジュアルが伴っている場合、子どもは話の流れとキャラクターの動きなどから英語の意味を推測できます。ビジュアルによって状況や前後の文脈が示されていれば、初めて聞く表現でも「この言葉は、“にんじん”かな」「これは“うさぎ”かな」と対応させて覚えることができるんです。
一方、音声だけの場合はそれができないので、効果が限定的になります。例えば、日本人の大人がスワヒリ語のCDを聞き続けても意味がわかるようにならないのと同じです。音に慣れたり、「この単語の次はこの単語がくることが多いな」と予測できたりすることはあるでしょうが、音だけでは意味の理解が深まりませんよね。
――確かに、音声だけで「何を話しているか」を理解するのは難しそうです。
尾島:それを踏まえるなら、単なる音源の聞き流しよりも、ビジュアルが伴っているほうが効果的です。親御さん、あるいは保育士さんが英語の絵本を読み聞かせたり、その絵本を読みながら関連する英語の音声を流したりするのもよいでしょう。
といっても、外国の絵本をそのまま読み聞かせるのはおすすめしません。ネイティブ向けの絵本は文学作品として作られているので、意外と難しい表現が多いんです。ですから、読み聞かせるなら、ノンネイティブの子どもに向けた英語学習教材がいいでしょう。そうした教材の絵本ならCDなども付属しているので、音声を流しながら絵を確認することができます。
――日本人である親や保育士が英語の絵本を読み聞かせる場合、ネイティブの発音とはかけ離れているかもしれません。それでも意味はありますか?
尾島:意味はありますが、音声のインプットが日本人の発音だけだと、子どもは「日本人の話す英語」を身につけます。それが心配なら、動画やDVDなどを利用して、それを上回る量のネイティブな発音をインプットするように心がけてください。1日15分、親が英語の絵本の読み聞かせをしている家庭の場合なら、その数倍から10倍程度の時間、ネイティブの英語を聞けば、日本人英語よりもネイティブの英語が記憶に残るでしょう。
――英語があまり得意ではないという方が、教材を選ぶ際の判断基準についても教えてください。
尾島:大量のインプットができることと、ビジュアルと音声が連動していること。この2点が満たされている子ども向け教材であることが、まず大事です。最近は、インターネットで多くの動画を見られますが、子どもの英語レベルに合った動画を探す手間を考えると、DVDが付属している子ども向け英語教材のセットのほうが便利だと思います。
ネイティブかそれに近い発音の教材で、子どもの興味が続きそうなものを選んであげてください。
英語学習には、大量のインプットで情報量を増やすことが不可欠

――アウトプットについては、どのように進めればよいでしょう。
尾島:基本的には、大量のインプットがあって、そのインプットが頭の中に定着してこないとアウトプットにつながりません。ですから幼児の場合は、最初はインプットだけで大丈夫です。
アウトプット、つまり「発話」というのは、自分が持っているものを外に出す作業なので、少ししか英語の知識がない場合、話せる量は限られます。逆に、たくさんの英語を聞いて、「こういう場合はこういうふうに言うんだ」ということが頭の中に定着してくれば、子どもは勝手に話し始めます。なので、まずは大量のインプットで英語の情報量を増やすことを心がけてください。
話し始めたら、短い時間でもいいので話せる機会を作るのがおすすめです。今は子ども向けのオンライン英会話も多いので、子どもに合った先生を見つけてみるのもいいでしょう。
――ちなみに、インプットは0歳児からでもできますか?
尾島:実を言うと、0歳と1、2歳で習得の差が出るかどうかは、はっきりとわかっていません。0歳の子どもは母語である日本語でも理解できる単語が少なく、自分から発話できる内容はさらに限られていますよね。それを考えると、外国語の学習効率がいいとは言えないでしょう。
実際のところ、母語の習得が加速するのは1歳半くらいからなので、0歳から「おうち英語」を始めるアドバンテージが確実にあるかは、私にもわかりません。
――保育園で英語教育の取り組みを行うとしたら、何が効果的でしょうか?
尾島:大人数に見せられる大判の絵本を使って、絵本の読み聞かせをするのがいいと思います。慣れてきたら、英語のDVDを見せる、英語の音楽を流して手遊びやダンスをする、といった活動をしてもいいかもしれません。
ただ、保育園は高い教育効果を追求する場ではないので、「英語学習のための時間を確保しなければいけない」などと考える必要はありません。余裕があればやってみる、くらいの感覚でいいと思います。保育士さんの中にも、英語が得意な方とそうでない方がいるので、無理なくやるのがいちばんです。
――尾島先生がご存知の範囲で構いません。保育園の英語の取り組みで、興味深い事例はありますか?
尾島:私の知人に、英語の発音指導に特化したサービスを行っている人物がいるのですが、現在自治体とタッグを組む形で、保育士さんに英語の発音を指導しています。そして、正しい発音を身につけた保育士さんは、園の子どもたちに対して、簡単な会話や英単語のインプットを行っているそうです。
小さな取り組みではありますが、早いうちから英語に触れるという意味では、興味深い事例です。しかし、先ほどもお話したように、英語学習は保育園が無理してやることではありません。あまり頑張りすぎず、保育士さん自身も楽しめる範囲で取り入れてもらえればいいかなと思います。
――ありがとうございました。最後に、今回の記事を読んで「おうち英語」に興味を持った方たちにメッセージをお願いします。
尾島:おうち英語を続けられるかは、親御さんの精神状態にすごく左右されます。なかには「SNSで英語を話せる子どもの動画を見て、おうち英語を始めてみたけれどあまり効果が出ない」と悩む方もいますが、子どもの言語習得には個人差があって当たり前。みんながみんなできるわけではないので、キラキラした成功体験投稿に引っ張られて、「自分がダメなのか」「子どもに才能がないのか」などと悩まないでください。「おうち英語」を始める場合は、「できたらラッキー」くらいの気持ちで取り組むのがよいでしょう。
保育士のみなさんが英語の読み聞かせなどに取り組む場合も、余裕のある範囲で楽しみながら行ってもらえたら幸いです。
取材・文/木下喜子





