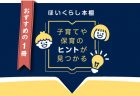第7回 目の前の対応に追われていませんか? コロナ禍であらためて考える「園での食育」
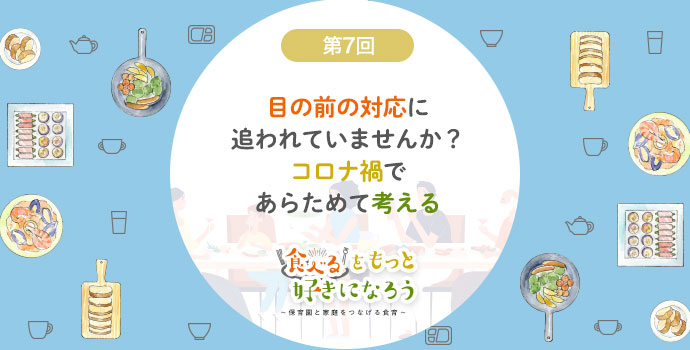
誰もが予期しなかったパンデミックから既に1年以上が経過し、保育所における子どもたちの食環境は以前と大きく変わりました。
この変化は子どもたちの将来にどのような影響を及ぼすのか、不安な人も多いでしょう。栄養士・笠井奈津子さんは、「子どもたちの食の体験が変化していることに気がつくことが大切」と語ります。
新年度がはじまり、これまでとはちがう「日常」ではありながらも通常運転になってきた今、保育所における食育についてあらためて考えてみましょう。
文/栄養士 笠井奈津子 写真/櫻井健司
感染予防対策をする一方で食育の機会は減った

降園時、給食のサンプル展示の前で、その日の給食について子どもたちが楽しそうに保護者に話している姿をよく見かけます。
それは我が子も同様で、「これ、美味しかった!」と興奮気味に話してくれることもあれば、わたしが先生に「やっぱりお魚が苦手ですよね……」と報告をうけている隣で気まずそうにしていることも。
1日のほとんどを保育所で過ごす子どもたちにとって、保育所での「食」が大きな役割を担っていることはいうまでもありません。
パンデミック以降、パーテーションを使用するようになったり、少ない人数でテーブルを囲んだり、横並びで座って食事をしたり。子どもたちが慣れない環境であっても給食やお弁当の時間を楽しめるのは、先生のサポートがあってこそ。
毎日子どもたちを見守り、食事の様子を教えてくれる先生にはいつも感謝しています。
ただ、感染予防対策を実施することで、食育の機会は確実に減っているはずです。
コロナ禍で行動が制限されたのは大人も子どもも同じでしょう。しかし、子どもたちの機会損失の影響は計り知れません。本来であれば体験できていたことを体験できないまま、「知らない」ことが積み重なってしまうからです。
祖父母、親戚、近所の友だちらとの食事の機会は失われますし、地域によって異なる食材や料理・文化などを知る機会も減るでしょう。
そうした家庭以外での「食の体験」を広げることができなくなることを思うと、保育所における食育の役割はこれまで以上に意味を持つと考えられます。だからこそ、「今はできないよね。難しいよね」で終わらせてはいけません。
緊急事態宣言も頻繁に発令されるなか、ただただ目の前の対応に追われていると、食育における本来の目的を忘れてしまいがちです。だからこそ基本に立ち返り、「なぜ食育が大切なのか」をあらためて考える必要があります。
季節の行事も一巡し、各園での感染予防策も確立されてきた現在、「保育所における食育に関する指針」(厚生労働省)を読み返しながら食育について考えてみてほしいのです。
食育は「学習」ではなく「保育の一環」

食育の目標の一文には、次のように書かれています。
現在を最もよく生き、かつ、生涯にわたって健康で質の高い生活を送る基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことが保育所における食育の目標である。
※厚生労働省「楽しく食べる子どもに~保育所における食育に関する指針~」より
ここで具体的に示されるものには、「食と健康」のみならず、「食と文化」「食と人間関係」「いのちの育ちと食」「料理と食」など広範囲に及びます。
食育がその時々の「学習」ではなく「保育の一貫」であると考えると、新型コロナウイルスの感染を防ぐ食事環境を整えるだけでは十分とはいえません。
ぜひやってほしいのは食育計画を見ながら、「コロナ前とコロナ禍の変化」を整理すること。
改めて比較することで、子どもたちが置かれている状況をより把握できるのではないでしょうか。
とくに「料理と食」に関しては、コロナ禍での対応は非常に難しいと感じます。かつてのように、盛りつけや配膳を手伝う、料理の授業をする、調理員とコミュニケーションを取る、生産者と会う——前ならあたりまえにできていたことが簡単ではなくなっているからです。
とはいえ、接触を避けてもつながりはつくれます。それに、子どもたちはいつもとちがうことを楽しめる「天才」ですよね。料理というプロセスを「体験できること」「見ること」「知ること」は、子どもたちの食欲にもダイレクトに反映されるものです。
だからこそわたしたち大人が「こんなご時世だからできなくても仕方ないか」から一歩進んで、「このタイミングではなにができるかな? もっと工夫してできることはあるかな?」という前向きな気持ちでいることが大切なのだと思います。
また、食育という言葉にはどこか「学び」の要素を感じさせるものがありますが、基本的な食育の環境整備には、体調や発達への気づき、なかには虐待への気づきといったことも求められます。
食育が保育の一貫である以上、あくまでも子どもたちの日常生活に根ざしたものであることも忘れないようにしたいものです。
家庭でなく、保育所だからこそできる食育がある

食育は各家庭でも取り組むべきものですが、わたしは保育所だからこそできることがあると見ています。
たとえば、子どもが「食べたくない」と言ったときを考えてみましょう。家庭ならば、1対1でのやりとりになりがちですが、保育所なら、保育士さんだけではなく、友だちとのやり取りも生まれます。
友だちがおいしそうに食べている様子を見て、あまり好きではない食べ物に興味を持つ子もいるでしょうし、負けん気が強い子は「自分だけ食べられないのが恥ずかしい!」と頑張って食べることがあるかもしれません。
そして、大人がいくら「おいしいから、ひと口食べてみよう」と言っても効果がなかったのに、友だちが言ったひとことなら素直に聞き入れることだってあります。
保育士と子ども、調理師と子ども、栄養士と子ども、そして、子どもたち同士というように、豊かな関係性がある食の場はコロナ禍を生きる子どもたちにとって、かけがえのない学びの場であり体験の場です。
できることが限られるこのような状況下では、できる部分を伸ばしていく視点が大切ではないでしょうか。
もしも、「この現状でできることがあるだろうか……?」と難しく感じるときには、食育の目標である「5つの子ども像」をイメージしてみることをおすすめします。
①お腹がすくリズムのもてる子ども
※厚生労働省「楽しく食べる子どもに~保育所における食育に関する指針~」より
②食べたいもの、好きなものが増える子ども
③一緒に食べたい人がいる子ども
④食事づくり、準備にかかわる子ども
⑤食べものを話題にする子ども
目の前にいる子どもたちの姿は、これらの像と重なって見えていますか? もっと重なるためにはなにができそうでしょうか?
対応に追われた1年が過ぎ、新しい年度がはじまりました。感染防止対策ありきの給食・お弁当時間になっていないかをここで一度顧みて、「保育所における食育が持つ意味」を再考してみましょう。
繰り返しになりますが、まずは子どもたちの食の体験が変化していることに気づき、それを洗い出すことです。そうすることで、保育士であるみなさんがこれまでに培ってきた経験や知恵が間違いなく生かされるはずです。