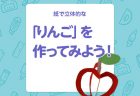第13回 園で子どもが食を楽しむために。保育士さんができる声かけのポイント 栄養士|笠井奈津子
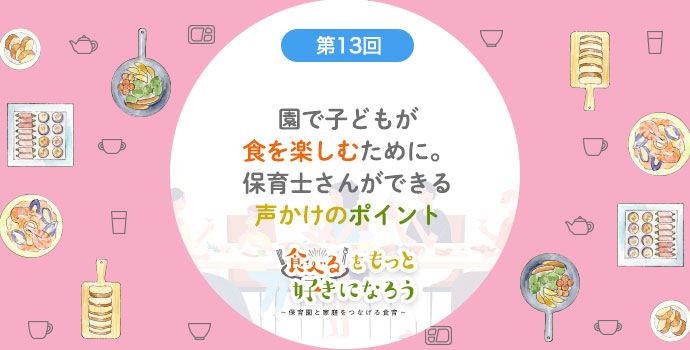
子どもというのは食べ物の好き嫌いが激しいうえに、「バランスよく食べる」という概念をまだ持ち合わせていません。そんなことからも、みんな揃って園の給食を完食してもらうことは一苦労ではないでしょうか。
もちろん相手は子どもですし、食べる量もそれぞれ。強制的に食べさせるわけにもいかず、保育士さんたちも頭を悩ませているはずです。
子どもたちが楽しい気持ちを失うことなく、できるだけ好き嫌いをなくし、食べることに意欲的になってもらうために必要な「声かけ」について考えていきます。
文/栄養士 笠井奈津子 写真/櫻井健司
食べることが「好き」であれば嫌いなものがあっても大丈夫
昨日は「○○ちゃんのこと大好き!」といっていたのに、今日になったら「○○ちゃんなんて大嫌い!」。そんなふうに心変わりするのは、まさに子どもが持つ特徴だと思います。
子どもというのは、好き嫌いがはっきりしていて、その中間がほとんどありません。それは食事に関しても変わらず、好きなメニューなら完食するけれど、嫌いなメニューがあると手つかずに……。そんなことが日常茶飯事ではないでしょうか。
「好きではないけれど栄養があるから食べる」「この料理をつくってくれた人のことを思いながら感謝して食べる」というような考えは、自然と身につくものではありません。それらの意識は、やはり周囲にいる大人たちの働きかけで徐々に身についていくものだと思うのです。
そこでわたしたち大人が意識したいのは、苦手なメニューや食材をすべて好きにならなくてもいいということです。食べることが好きになってさえくれれば成長していく過程で苦手なメニューや食材を好きになる可能性は十分にあります。
でも、食べること自体が好きでなければ、いつか好きになるどころか「お腹が満たされればなんでもいい」という食事に無関心な大人になりかねません。
ですから、「好き」と「嫌い」の差を縮めることが大切です。言い換えれば、「嫌いだけれど、ちょっと食べてみてもいいかな」という気持ちにどれだけなれるかがポイントになるでしょう。
もちろん、まだ食べたことのないメニューや食材への抵抗感が強い子は少なからずいます。そのため、まずは一口チャレンジすることからはじまり、「思ったよりも食べられるな」という成功体験の積み重ねが大事になってきます。
「一人ひとりの子どもに合った」声かけを意識する

そこでポイントになるのが、声かけです。
「嫌いな食べ物にチャレンジできたね! カッコいい!」というダイレクトな伝え方から、「嫌いなら食べなくてもいいけれど、先生は一口チャレンジしたほうが素敵だと思うよ!」といった次につながる声かけも考えられるはずです。
また、あえてほかのクラスの先生にお願いして、「嫌いだったピーマンを頑張って食べんだって!? 凄いね!」と間接的に褒めてもらうこともいいですよね。園で毎日見ているからこそわかる、「一人ひとりの子どもに合った」声かけができると最高です。
また、「できれば完食をしてほしいけれど、なかなか難しい……」というとき、保育士であるみなさんはどう対応していますか? 集団給食には終わりの時間がありますし、一人ひとりにつきっきりで完食を目指すことは現実的ではないでしょう。
先生によって、そういった際の対応もそれぞれだと推測します。「あと一口食べたらいいよ!」「がんばって!」「無理ならもう終わりにしていいよ」……。いろいろと考えられますが、わたしにはそのどれもが正解に感じます。
それこそ、どうしても早く食べることができない子もいますし、嫌いなものが多くて食べきれない子もいます。そういった場合、給食の時間がくるたびに緊張し、最後にひとりで食べていて悲しい気持ちになっているかもしれません。
食べることが楽しめない理由は人それぞれだからこそ、一人ひとりに適した声かけがあるのだと思います。
新型コロナウイルス感染症対策の一貫で給食の時間を短く設定している園もあると聞きます。しかし、「ほら、もう時間だよ!」と急かされるような食事は、子どもも大人も楽しめるゆとりが生まれません。
もともと食べるのが遅い子や少食な子には、配膳の際に少し量を調整するなどして、「必死に食べる」から「楽しんで食べる」への変換を考えましょう。状況に応じて「食事に対する劣等感を増幅させない工夫」が大切です。
食べるのが遅い子どもにもいい部分はある

少し触れましたので、食べるのが遅い子どもについても考えてみます。実は、時間をかけて食べることは、視点を変えればメリットも複数あるのです。「よく噛んでいるから食事に時間がかかる」、「味わって食べているから食事に時間がかかる」という見方ができますし、マナーがいいという見方もできます。
そう考えると、ちょっと手がかかるように感じていた子どもほど、見本になるような食べ方をしている可能性も否定できません。
「おしゃべりをしないで食べようね」と声かけしても遊んでいるような子どもがいたら、「〇〇ちゃんを見てー! お口を閉じてよく噛んで食べているよ。素敵な食べ方だね」なんていってみるのも効果がありそうです。
「子どもがおしゃべりをしないで食べることは無理」「友だちと遊びながら食べないなんて無理」という考えがあると、「(いまの時期は飛沫感染を防ぐためにも)できるだけ給食時間を短く設定する」「給食前で終わる、午前保育にする」といった選択肢も出てくるはずです。
しかしながら、給食をみんなで一緒になって食べる機会というのは、成長していく過程で必要な食べ方やマナーを身につけるまたとないチャンスでもあるのです。そのことも忘れたくありません。
「子どもの食」の大変さを保育士と保護者で共有する

また、コロナ禍が長引くいまは、保護者も家族以外と触れる機会が減り、日頃の食事内容だけでなく、食事の際の子どもへの声かけも固定化されやすくなっているはずです。子どもの食事で悩んでいてもわざわざ別の保護者に相談するほどのことでもないし、忙しい保育士さんに相談するのも気が引けるでしょう。とはいえ、ネットの情報をすべて鵜呑みにするのも怖いはずです。
そこで、保育士さんから保護者へのアドバイスの場として、教室の前の掲示板や給食見本の近くなどに模造紙を1枚貼るなどして、「お食事相談室コーナー」を設けるのはどうでしょうか? 「保護者に自由に質問を記入してもらう」ではハードルが高くなるので、「子どもが食べたくないといったらどうしていますか?」「子どもにご飯がまずいといわれてイライラした。そんなときどうする?」というようにテーマを随時変えていき、保育士さんたちがそれに答えるかたちで回答を書き込むのです。その際の回答は、わかりやすくひとことで十分だと思います。
ここで大切なのは、「ああなるほど。園ではこんなやり方をしているんだ」「いろいろな考え方があるんだな」と保護者に知ってもらうことです。「保育士さんだって、子どもに食べてもらうのは大変なんだ」というその事実を保護者にも理解してもらい、その大変さを共感し合うのです。
そういったコミュニケーションの積み重ねが園と家庭をつないでいき、その先にある、子どもたちの「“食べる”をもっと好きになる」があるのだと思います。
産後、働き方を見直すなかでパラレルキャリアの道を開拓。