第3回 子どもの「食べない」を考える~保育士が実践すべき食育のポイント
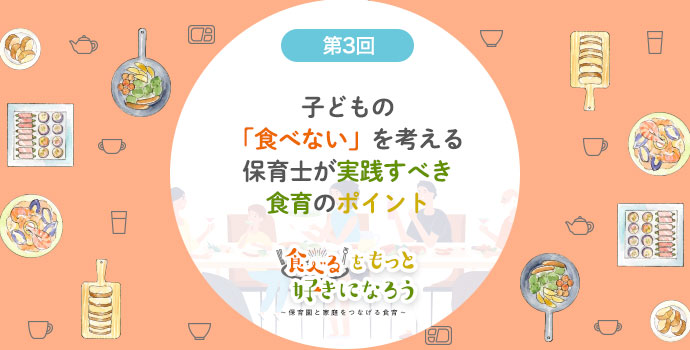
保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!
X(旧Twitter)をフォローはこちら!
文/栄養士 笠井奈津子 写真/櫻井健司

インターネットを開けば簡単に食や栄養の情報収集ができるようになった結果、なにをどれだけ食べればいいのだろうかと選択に悩むことが増えました。多くの情報をあれもこれもと実践するわけにはいきませんし、本当に正しいことをしているのかも不明瞭なまま。
そんな情報過多な時代に必要なのは、「ものごとを俯瞰してみる力」です。これまで園児を持つ親御さんから多くの食事相談を受けてきた栄養士、笠井奈津子さんは「個々の情報に惑わされずに『基本の食事』をおさえることが大事」だと話します。
よくありがちな、栄養素だけで考えてしまう落とし穴

「家では炭水化物ばかり食べているけれど大丈夫でしょうか」
「家では魚を食べないのですが、園では食べていますか?」
「少食なので、栄養がとれているか心配で……」
ミルクや母乳が唯一の栄養源となる乳児期から、離乳食や幼児食へとステージが進むほどに、お母さんたちの悩みは深くなっていくようです。
「大切な子どもの口に入れるものはどんなものがいいのだろう?」「これくらいの量でいいのかな?」食べ物から栄養を摂るということが、考えれば考えるほどに難しくなってしまうのでしょう。
そんなタイミングで、「幼児期に摂るべき栄養素」という話をWebサイトやテレビなどで見聞きすれば、気をつけるべきポイントは明確になるかもしれません。
たとえば、「血液をつくるためには鉄。骨をつくるためにはカルシウムがとても大切ですよ」という情報があれば、「とにかく鉄とカルシウムに気をつけよう」と選択肢が絞り込まれて楽になるでしょう。
しかし、栄養素を含む食品は数多くあります。たとえば次のとおり。
<鉄を多く含む食品の例>
- あさり
- 牛肉の赤身
- レバー
- 卵の黄身
- ほうれん草
- 納豆
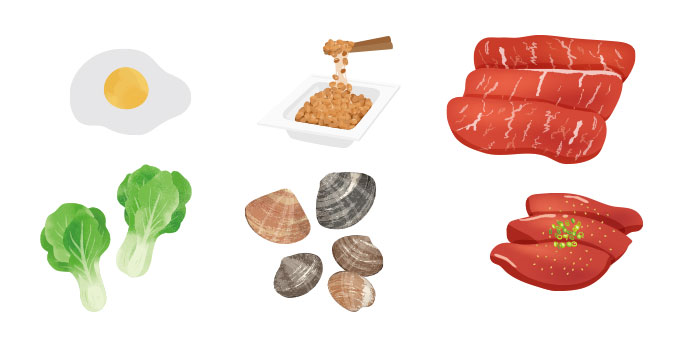
<カルシウムを多く含む食品の例>
- 乳製品
- 煮干し
- ひじき
- 小松菜

このなかで子どもがよろこんで食べそうなものはありますか? 鉄ならば卵や納豆、カルシウムなら乳製品くらいでしょうか。
「摂りたい栄養素に対して、こどもが食べられるものを選ぶ」。一見正しい判断に思いますが、これは、栄養素だけで考えたときの落とし穴なのです。
実際の子育てのなかでは、あれもこれもと考える時間がないという現実がありますよね。そして、食べられるものがまだ限られる子どもを相手に、「とりあえず卵や納豆を食べさせていれば安心かな」「朝はパンだけだけど、牛乳も飲んだから栄養的に大丈夫だよね」「鉄やカルシウムが入っているお菓子はなんだかよさそう!」となると食材が偏ってしまい、それにより摂取する栄養も偏ってしまいます。
特定の栄養素を意識したばかりに、「〇〇ばっかり食」になり、食事全体で見たときにはかえって栄養バランスが悪くなってしまう。せっかく食べているのに、それではあまりにもったいないですよね。
まだ食べムラがある幼児期は、特定の栄養素よりも「主食・主菜・副菜」の栄養バランスを整えることを優先したいところです。
特に、次の3つの基本は必ずおさえておきましょう。
- エネルギー源となる主食
- 体をつくるタンパク質がメインの主菜
- ビタミンやミネラルを補給する野菜がメインの副菜
また、3つの仕切りに分けられている子ども用の食器がよく売られていますが、ここに彩りよく食べ物を配置すれば花丸! そして、ここに入る食材は、できるだけバラエティに富んだものが理想です。
つまり「この栄養素が必要だ」と考えるよりも、園児に食べることを好きになってもらい、まんべんなく食べられるように働きかけていくことが大事なのです。
巷にはたくさん食の情報が溢れていて、なにが正しいのかわからなくなることもあるでしょう。でもやはり、大切なのは「食の基本」。たくさんの食の情報に惑わされそうになったときには、自らを俯瞰して、「バランスよく」という基本に立ち返れば大丈夫です。
「食べない」理由を消すために咀嚼力のチェックを

しかし、バランスを考えてつくられた食事も、子どもに完食してもらってこそ意味を持ちます。そのためにも、咀嚼能力やフォーク、スプーン、お箸といったカトラリーをつかむ力など、子どもの「食べる力」をよく見てあげましょう。
とくに咀嚼力は月齢だけでは判断できないもので、かなり個人差があります。つくった食べ物と食べる力が合っていないと、どんなにバランスがいい食事でも、「食べられない」と子どもに拒否されてしまいます。
園で個別対応をするのはなかなか大変だと思いますが、咀嚼能力に合った固さや大きさにしたり、使いやすいカトラリーにしたりして、食べられない理由を消していきましょう。
また、傍目にはちゃんと食べているように見えても、じつはきちんと食べることができていないといったケースもあります。それがどういうことかというと、飲み込むように食べていて、「よく噛むこと」ができずにいるのです。
これはむしろ、好き嫌いがない子にありがちなので、量をたくさん食べる子であっても「よく噛んでいるか」というポイントは気をつけてチェックしてみてください。噛むことは、せっかく摂った栄養をきちんと消化吸収するためにも必要なことです。
食育は日々の会話から! 子どもにも栄養の話をしてみよう

子どもに積極的に食べてもらうには、「食べる」という行為だけで考えるのではなく、食そのものに興味を持つようにサポートすることも大切です。
たとえば、その日の給食に使う食材のなかから旬のものをひとつだけ見せて、その栄養的特徴を月齢に合ったわかりやすい言葉で紹介していく——。こうしたことに取り組んでいる園も多いですよね。
そこから発展させて、それが主食なのか主菜なのかと、子どもたちにクイズを出すのもいい食育です。少し年齢が上がると、わかりやすい言葉よりも、「ビタミンC」など難しい単語のほうが「知っていてカッコいい!」となる子もいるでしょう。
食育は、月に一度まとまった時間をつくってたくさんのことを伝えるよりも、日々、こまめに伝えるほうが記憶に残りやすく、子どもたちにとっても身近なものになります。
学問として知る前に、大好きな先生の口から自分の体に関係することとして学べたら、子どもたちにとって「栄養」がもっと大切なものになるのではないでしょうか。
食事も栄養も園任せ……。卒園後も困らないために保育士さんができること

ただ、ここまでの話を実践したからといってすべてが解決するわけではありません。まわりにいる大人が日々いろいろと考えていても、幼児期の食欲は気分や体調に大きく左右されがちだからです。
ですから、園と家庭、どちらかに栄養摂取を期待するのではなく、どちらでもきちんと食べられるようにすることが重要です。でも、「園ではお弁当や給食をちゃんと食べているから大丈夫」といって、家でちゃんと食べなくても「ま、仕方ないか」で片づけてしまう親御さんも多いと聞きます。
食事とは、生活の一部——。各家庭、いろいろな事情のなかでやりくりをしているので善悪の判断をすることではありませんし、いつも完璧でいる必要はありません。でも、「いい食習慣を身につける」ことを考えると、各家庭でも積極的に取り組んでもらいたいところですよね。
好き嫌いが多い偏食気味の子を持つ親御さんは、毎食の対応に疲れてどうしてもあきらめモードになりがちです。そのため保育士さんが園で発見した「〇〇くん/○○ちゃんはどうしたらよく食べるのか」を積極的に親御さんに共有してみてください。
その日のお弁当や給食の様子を交えて話しながら、送迎時にひとことさりげなく伝えるといいでしょう。そういった「小さな情報」が、親御さんにとっての「大きなヒント」となるはずです。
また、親御さんから「家ではあまり食べなくて心配」といわれた場合に、「園ではちゃんと食べていますよ」と答えるのは要注意です。安心させたくて言った言葉でも、親御さんが「わたしの料理がおいしくないのかな?」などと自虐的にとらえてしまい、子どもが食べないときのイライラを加速させてしまうこともあるからです。
「おうちではどんなものを食べているんですか?」と聞いてみて、それが菓子パンなどではなく、「主食・主菜・副菜」に該当するものであれば、「バランスよく食べられているから大丈夫ですね」と安心させてあげましょう。
子どもにも親にも食事への苦手意識を持たせないことは、食育への積極性を持ってもらうための大事なステップです。
産後、働き方を見直すなかでパラレルキャリアの道を開拓。








