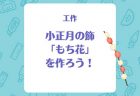手づかみ食べはいつから?進め方やおすすめの調理方法・育児アイテムを紹介

文: 神戸のどか(保育士ライター)
子どもが離乳食を食べることに慣れてくると、自分から食事に手を伸ばそうとする姿がみられるでしょう。子どもの成長のためにも「そろそろ手づかみ食べをさせてあげたほうがよいのだろうか」と考えるかもしれません。
この記事では、「手づかみ食べをいつから始めたらよいの?」「どのような調理法があるの?」とお悩みの保護者に向けて、手づかみ食べを始める時期や、子どもに与えるよい影響、進め方のポイントを紹介します。
おすすめの調理方法や役立つアイテムもまとめていますので、安心して手づかみ食べをスタートさせるための参考にしてください。
手づかみ食べはいつからできる?
手づかみ食べとは、言葉の通り、子どもが手でつかんで食事をすることです。厚生労働省の「授乳・離乳の支援ガイド」によると、手づかみ食べは離乳食後期の9ヶ月頃から始まるとされています。
とはいえ、子どもの成長のペースはそれぞれ異なるため、この時期から始めなくてはならないわけではありません。
手づかみ食べをスタートする目安としては、以下の2点が挙げられます。
- 腰が据わり椅子に座れること
- 自分で食べ物を口に運ぼうとすること
子どもによっては、離乳食中期の7~8ヶ月頃を迎えると、興味をもって食事に手を伸ばそうとする子もいます。また、5~6ヶ月頃から、自分で食べ物を口に持っていこうとする子もいるでしょう。
自分で食べたいという気持ちはとても大切なことです。食べ物をつかむことに興味をもっている子どもには、食べやすいものからスタートしてもよいでしょう。
子どもが手づかみ食べをしない!理由は?

子どもの成長とともに食べ物に興味をもち自然に手づかみで食べるようになりますが、なかなか食事に手を出さない子もいます。
子どもが食事に手を出そうとしない場合、以下のような理由があるのかもしれません。
- 保護者に食べさせてもらうことが好き
- 手で食材に触れる感触が苦手 など
手で食材に触れる感触を嫌がる子どもには、手がべたつかないパンや野菜などがおすすめです。無理に手づかみ食べをさせる必要はありませんが、保護者が手づかみ食べするところを見ることで、子どもが真似をしたり興味をもったりするかもしれません。
また、お水遊びや寒天遊びなどの「感触遊び」を取り入れることで、食材に触れるハードルが下がる可能性もあります。
また、子どもが自分で食べようとする気持ちになるためには、空腹を感じている状態で食事をすることが大切です。生活リズムを整えるために、毎日の食事をなるべく同じタイミングにしたり、食事前にたっぷり遊ばせたりすることにも意識を向けてみましょう。
手づかみ食べが子どもにとってよい理由

手づかみ食べは食べる意欲や脳を育てるため、子どもの成長にとても重要な経験です。手づかみ食べをすることで食べ物への関心が増し、健やかに育つために欠かせない「食べたい」という気持ちをもてるようになります。
食べることに慣れている保護者にとってはシンプルな行動に思えますが、手づかみで食べることには、「食べ物を見る」「確かめる」「手指でつかむ」「口に運ぶ」などさまざまプロセスが含まれます。子どもは脳や目、手指、口などを使いながら、自分で食べられるように練習を積み重ねていくのです。
手づかみ食べを経験することで、目と手、手と口など、別々の機能を一緒に動かすための「協調運動」が向上していきます。また、食べた時に味や香り、音、温度、色などの五感を感じることで感覚機能も育まれます。
手づかみ食べに慣れていない子どもはこぼしてしまったり、口に入れられなかったりしてはじめはうまく食べられません。しかし、繰り返し手づかみ食べをすることで、距離感や力加減を学んでいきます。手先が器用になることで、スプーンやフォークに移行した時にスムーズに使えるようにもなるでしょう。
手づかみ食べは、保護者にとっては「服が汚れる」「後片付けが大変」といったイメージが強く、始めることに不安を感じている方もいるかもしれません。しかし、子どもの心や脳を育てる大切な経験ですので、前向きに取り組めるとよいですね。
手づかみ食べの進め方のポイント3つ

子どもが食事を楽しむためには、周りの保護者の関わり方がとても大切です。ここからは、手づかみ食べをする時に心掛けるとよいポイントを3つ紹介します。
手づかみ食べをしやすい環境を作る
まずは、手づかみ食べができるように、子どもが食事に手を伸ばしやすい環境を整えましょう。テーブルや椅子の高さを確認して、ひじがテーブルにつく高さにします。子どもが、歯ぐきで食材をつぶす時に、力を入れやすいように、足がぶらぶらしないようにすることが大切です。足元が安定していることで舌と顎に力が入り、しっかり噛んだり飲み込んだりできます。
そのため、足裏が椅子の補助板にきちんと乗り、安定した姿勢を保てる状態が望ましいです。椅子に補助板がない場合は、足裏が台にきちんと乗る高さの台をおきましょう。安定した姿勢で食べることは、食事に集中することにもつながります。
できそうなタイミングでスタートする
手づかみ食べで大切なことは「子どもの食べたい気持ち」です。手づかみ食べは子どもにとって大事な経験ですが、毎日手づかみ食べをしなくても心配することはありません。焦らずにできそうなタイミングで手づかみ食べを少しずつ取り入れましょう。
子どもの月齢だけで判断せず、子どものペースや意欲に寄り添ってあげてください。
手づかみ食べを始める生後9ヶ月頃は、まだ保護者が主に食べさせる時期です。食べにくいものは保護者が食べさせてあげて、手づかみ食べをしやすい食材からスタートするとよいでしょう。
遊び食べは時間で区切る
9~11ヶ月は偏食や遊び食べが出てくる時期です。手づかみ食べを始めると、子どもは食材をちぎったりこねたりすることがあります。食材に直接触れることはとても大事なことですが、食事がなかなか進まない時は保護者が食べさせてあげたり、「食事の時間は30分で終わりにする」と決めて時間で区切ったりしましょう。
【月齢別】手づかみ食べにおすすめの調理方法

手づかみ食べにおすすめのメニューは、一口サイズのおにぎりやパン、茹でた野菜などです。食材は子どもがつかみやすく、柔らかく食べやすいものにしましょう。
ここからは、月齢に合わせた離乳食の与え方やおすすめの調理方法を紹介します。
離乳食後期(生後9~11ヶ月頃)
手づかみ食べを始めた頃は、一度に食材を口に入れようとすることがありますので、喉に詰まらせないように子どもの側で見守ることが大事です。また、噛む動きが出てくると、今までよりも食事に時間がかかることもあります。保護者が口を動かして、一緒に噛む動作をしたり、「カミカミしようね」と咀しゃくを促したりしてみましょう。
【与え方】
- 1日3回食
手づかみ食べは、毎回の食事でなくても問題ありません。子どもが意欲をもったタイミングで取り入れてみましょう。
【調理の仕方】
食材は指でつまむとつぶれる硬さにします。目安は、バナナくらいの硬さです。食材が柔らかすぎると、丸のみの原因になるため気を付けましょう。
子どもが一口サイズのサイコロ状で食べることに慣れてきたら、前歯でかじりとって一口量を覚えられるようにスティック状や小判型にしてみてもよいでしょう。成形する時は、片栗粉をくわえることで崩れにくくなります。
【おすすめの食材】
- にんじん、大根、さつまいも、かぼちゃ、ブロッコリーなどの柔らかく煮た野菜
- 食パンの白い部分、蒸しパン
- マカロニ
- 口どけがよい赤ちゃんせんべい など
離乳食完了期(生後12~18ヶ月頃)
離乳食完了期は手づかみ食べがメインとなる時期です。子どもが持ちやすいように食材を大きめにしましょう。手づかみ食べをしたがらない子どもには、パンケーキや食パンなど手がべたつかないメニューがおすすめです。
離乳食完了期は柔らかく薄味にすることで、保護者と同じようなものを食べられるようになる時期です。また、手づかみ食べに慣れてきた子どもで、スプーンやフォークに興味がある場合には持たせてあげましょう。
【与え方】
- 1日3回食
3回の食事で足りない場合は、1日に1∼2回のおやつを準備しましょう。
【調理の仕方】
食材は、歯ぐきでつぶせる肉団子くらいの硬さにします。汁物は食べやすいように少量して出すとよいでしょう。ホットケーキミックスに、好みの食材を入れて焼くと食べやすくなり栄養もとれます。
【おすすめの食材】
離乳食完了期は、ほとんどの野菜や果物が食べられるようになります。魚やお肉も食べやすい大きさにカットして出してみましょう。
手づかみ食べの時期におすすめの育児アイテム3選

大変なイメージがある手づかみ食べですが、育児アイテムを使うことで少し心に余裕ができるでしょう。
ここからは、手づかみ食べの時期におすすめ育児アイテムを3つ紹介します。
食事用マット
手づかみ食べが始まると、こぼすことが増えるため片付けが大変になることが予想されます。こぼしても片付けやすいように、テーブルの上に敷いておく食事用マットを使用するとよいでしょう。シリコン製でできているものは、お皿が滑りにくく気軽に洗えます。
また、手づかみ食べを始めると食事の半分くらいが床に落ちてしまうこともあります。テーブルの下には、新聞紙やレジャーシートを敷いておくと後片付けしやすくなります。手づかみ食べが本格的に始まると子どもの体が汚れてしまうでしょう。現在、お風呂の後に夕食を食べている場合は、お風呂に入るタイミングを食後に変えてもよいかもしれません。
ひっくり返りにくいお皿
手づかみ食べに慣れていない子どもは、お皿をひっくり返してしまうことがよくあります。
お皿の裏に吸盤が付いているものや滑り止めがついているもの、マットとお皿が一体化しているものなどを使うと食べやすくなるでしょう。お皿が動きにくいので、落としたりひっくり返したりする回数を減らせます。
おにぎり型
一口サイズのおにぎりは、手づかみ食べをする時期の定番メニュー。簡単に作れるおにぎり型(おにぎりメーカー)を活用すると便利です。
商品によって丸型や三角のおにぎり型があり、作れる数も1つから複数などさまざまです。混ぜごはんやふりかけなどを入れて、アレンジすることも可能です。100円均一のお店でも販売されているので、手軽に手に入れられるでしょう。
まとめ
手づかみ食べは、「自分で食べたい」という意欲や、脳を育てる大事な経験です。はじめはうまく食べられなかった子どもも、数ヶ月すれば食材を手でつかむことが上手になったり、スプーンやフォークで食べるようになったりします。子どもの成長を楽しみながら、温かく見守ってあげましょう。
子どもが「食事が楽しい」「自分で食べられることが嬉しい」と思えることは、生きていくうえで重要なこと。とはいえ、手づかみ食べを始めたばかりの頃は、離乳食の準備や片付けなどを大変だと感じてしまうでしょう。
この時期は、周りの保護者の心の余裕も大切です。育児アイテムを上手に活用して、無理なく手づかみ食べができる環境を整えましょう。
参考サイト:
- 授乳・離乳の支援ガイド|厚生労働省(P.31)
- <参考3手づかみ食べについて>|厚生労働省
- 離乳食 月齢別 食べる姿勢・食べさせ方のポイント|福知山市
- 子どもの食事|大木町
- 離乳食用食材一覧|筑紫野市
- 離乳完了期の進め方(生後12~18か月頃)|まちだ子育てサイト
保育園で、0歳児から5歳児の子どもたちの保育を5年半担当してきました。
「一人ひとりの個性」や「主体性」を大切にする保育園での勤務経験を活かし、
現在は保育士さんや子育て中のママやパパに向けて記事を執筆しています。
絵本や歌が大好きで、特に絵本の読み聞かせや手遊びが得意です。
保有資格:保育士・幼稚園教諭・認定ベビーシッター