歯と口の健康週間とは?由来や歯磨きの基本、過ごし方を紹介
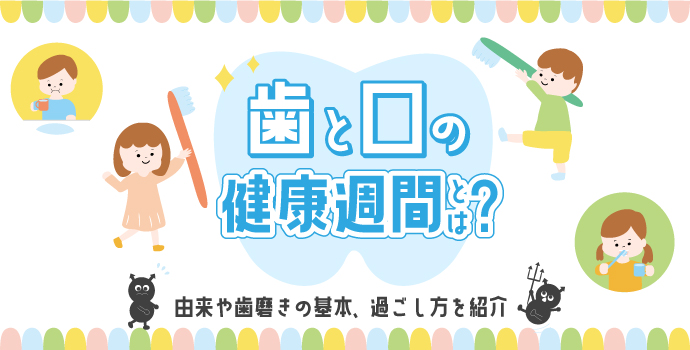
毎年6月4日から6月10日までの1週間は、「歯と口の健康週間」となっています。
歯や口は、体の健康の入り口です。何歳になっても健康な口腔状態を維持するためにも、定期的にセルフケアを行いつつ、歯の寿命を伸ばすことは大切と言えます。
小さな子どもをもつ親や、多くの子どもたちと日々関わる保育士の方は、歯と口の健康週間を機に、歯科疾患の適切な予防方法や歯と口の健康づくりにおける正しい知識を伝え、普及啓発に努めるとよいでしょう。
そこで今回は、歯と口の健康週間の意味から、子どもたちに伝えたい「歯磨きの基本」、さらに歯と口の健康を子どもと一緒に楽しむためのアイデアまで徹底紹介します。
1. 歯と口の健康週間とは?歯と口の健康週間の意味・由来を解説!
歯と口の健康週間とは、厚生労働省・文部科学省・日本学校歯科医会・日本歯科医師会の4つの機関が、毎年実施する啓発活動です。むし歯の「むし(64)」にちなんで、「虫歯予防デー」とされていた6月4日から6月10日までの1週間が、歯と口の健康週間とされています。
歯と口の健康週間では、歯科疾患の適切な予防方法や口腔ケア、さらに歯と口の健康における正しい知識を伝え、各個人が普及啓発に努めながら、国民全体の健康の維持・促進に寄与することが目的となっています。
| この週間は、歯と口の健康に関する正しい知識を国民に対して普及啓発するとともに、歯科疾患の予防に関する適切な習慣の定着を図り、併せてその早期発見及び早期治療等を徹底することにより歯の寿命を延ばし、もって国民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。 |
また、歯と口の健康週間では毎年、歯と口の健康に関する知識をより普及啓発するために「標語」と「ポスター」が作成されることも特徴です。2022年度の標語とポスターは、下記のようになっていました。
■2022年度 歯と口の健康週間啓発チラシ「いただきます 人生100年 歯と共に」
1. 歯と口の健康週間の由来
歯と口の健康週間は、2013年から始まった週間です。しかし、それまでも歯と口の健康に関する週間は制定されており、名称が度々変更されていました。始まりは、歯科衛生思想の普及運動として1928年6月4日に行われた「虫歯予防デー」です。
■歯と口の健康週間の歴史
(1)「虫歯予防デー」/1928年6月4日
(2)「護歯日」/1939年~1941年(毎年6月4日)
(3)「健民ムシ歯予防運動」/1942年6月4日
(4)1943年~1948年までは中止
(5)「口腔衛生週間」/1949年6月4日
(6)「口腔衛生強調運動」/1952年6月4日
(7)「口腔衛生週間」/1956年6月4日
(8)「歯の衛生週間」/1958年~2012年(毎年6月4日)
(9)「歯と口の健康週間」/2013年~
上記の通り、歯の健康や衛生環境に関する週間は、約100年前から存在しています。名称が度々変更されていますが、基本的な目的・実施内容については大きな変わりはありません。また、虫歯予防デーは現在も実施されており、歯と口の健康週間は虫歯予防デーにちなんだ週間となります。
(出典:日本歯科医師会「歯と口の健康週間」/https://www.jda.or.jp/enlightenment/poster)
2. 歯にまつわる記念日
歯にまつわる記念日は、歯と口の健康週間のほかにも意外と多くあります。下記に、歯にまつわる記念日をいくつかピックアップします。
| 4月2日 | 「歯列矯正の日」 |
| 4月4日 | 「歯周病予防デー」 |
| 4月18日 | 「よい歯の日」 |
| 4月29日 | 「歯肉ケアの日」 |
| 7月25日 | 「知覚過敏の日」 |
| 8月8日 | 「歯並びの日」 |
| 10月8日 | 「入れ歯ケアの日」「奥歯の日」 |
| 11月8日 | 「いい歯の日」「いい歯並びの日」 |
歯にまつわる記念日は年中存在しており、年間を通して歯の健康維持がいかに大切なのかが分かるでしょう。
2. 子どもに伝えたい!歯磨きの基本
歯と口の健康週間では、子どもたちに歯磨きの基本を伝えるとよいでしょう。そもそも歯磨きは、歯垢と呼ばれるプラークを落とし、健康な歯を守ることが目的です。
プラークは最近の塊であり、歯と同じような乳白色をしているため見えにくくなっています。磨き残しがあると虫歯や歯周病につながる可能性があるため、プラークを磨き落とすことに注意しながら歯磨きをすることが大切です。
子どものときから口腔機能の健康状態を保つことで、言葉の発音や味覚の発達などにもよい影響を与えるだけでなく、口腔に関連する病気予防にもなり、将来的な医療費の負担も大きく軽減できるでしょう。何歳になっても食事や会話を楽しむためには、毎日の歯磨きが重要と言っても過言ではありません。
そこで次に、子どもたちに伝えたい歯磨きの基本について、順を追って説明します。
1. 正しい磨き方で磨く
歯磨きをするときにまず重要なのが、正しい磨き方で磨くという点です。磨き方が間違っていると、プラークをしっかり除去することができません。
正しい磨き方は、「歯ブラシの毛先を歯の先にあてる」「1か所あたり20回以上磨く」「適度な力加減で磨く」の3つがポイントです。特に重要なのが、力加減と言えるでしょう。ブラッシング圧が強ければ毛先が広がり、もう1つのポイントである「歯ブラシの毛先を歯の先にあてる」という部分も不可能となってしまいます。
プラークは軽い圧でも除去できるため、無意識に圧が強くなってしまわず、かつ細かい動きが可能な鉛筆持ちで歯ブラシを握ることもコツです。
2. 磨き残しの多い部分に注意する
どれだけしっかり歯磨きをしたつもりでも、プラークがまだ残っていたというケースは多々あります。下記は、特に磨き残しが目立つ部分です。
| ・上奥歯の表側 ・上下奥歯の裏側 ・前歯の上 |
上奥歯の表側や上下奥歯の裏側は、大人・子ども問わず磨き残しやすい部分と言えます。「イ」の形となるよう口を横に大きく広げて、歯ブラシの動く範囲を広げることがポイントです。ブラシが届きにくい歯のすき間ケアには、歯間ブラシの使用も推進されています。
また、前歯の上には「上唇小帯」と呼ばれる筋があります。子どもの場合、上唇小帯は歯に近い部分までつながっているため、歯と同時に磨いておくことがおすすめです。しかし、この筋は非常に敏感な部分となるため、歯ブラシを使用せず指で軽く押さえながら磨くとよいでしょう。
3. 自分に合った歯ブラシを選ぶ
歯ブラシは、商品によってヘッドの形状やサイズ、毛の硬さがそれぞれ異なります。サイズは、上前歯と同じくらいの大きさが目安です。しかし、大きすぎると奥歯まで磨くことが難しくなるため、子どものうちは子ども用の小さい歯ブラシを使用しましょう。
また、大人・子ども問わず、歯茎が健康な場合は「ふつう」の硬さの歯ブラシ、歯茎が傷んでしまっている場合は「やわらかい」歯ブラシがおすすめです。
歯ブラシは使用するうちに毛先が傷んだり、コシが失われてしまったりするため、1か月ごとに交換するとよいでしょう。
3. 【保育士・保護者向け】子どもと一緒に歯と口の健康週間を楽しむアイデア
歯と口の健康週間は、歯磨きや歯の大切さを見つめ直すのによい機会です。子どもたちに歯の健康について伝えるためには、ただ口頭で説明するより、歯や口を題材にした絵本やおもちゃなどを取り入れると効果的でしょう。歯や口を題材にした絵本や制作を取り入れることで、子どもたちは楽しみながら積極的に歯について学ぶことが可能です。
ここからは、保育士・保護者の方に向けて、子どもと一緒に歯と口の健康週間を楽しむためのアイデアをいくつか紹介します。
1. 歯を題材にした絵本や紙芝居を読む
最も手軽に取り入れられるアイデアが、歯を題材にした絵本や紙芝居の読み聞かせです。歯磨きや虫歯をテーマにした絵本を読み聞かせることで、子どもたちは物語の登場人物に感情移入し、歯を大切にすることの大切さがより理解できます。
また、読み聞かせそのものには、想像力の発達・言語能力の向上にも役立ちます。
2. 歯に関する制作をして遊ぶ
多くの子どもたちに、一人ひとり積極的に歯の大切さを学んでほしいという場合は、歯に関する制作をさせることもおすすめです。例えば、下記のような制作が挙げられます。
【オリジナル歯磨きコップの材料】
- 紙コップ
- シール
- 色画用紙
- カラーペン
- はさみ
- のり
【作り方】
無地の紙コップにシールや色画用紙、カラーペンなどで好きな模様を作ってもらう
画用紙を歯ブラシの形に丸めて、ヘッドとなる先端部分に画用紙をのりで貼る
先端に貼った画用紙にはさみで切れ込みを入れて、ブラシを完成させる
【ワニの歯磨きセットの材料】
- 牛乳パック
- 画用紙(緑・赤・白)
- はさみ
- のり
【作り方】
牛乳パックを縦(2/3)にカットして、ワニの口となる部分を作る
画用紙を体(緑)・口(赤)・歯(白)にそれぞれ貼りつける
画用紙を歯ブラシの形に丸めて、ヘッドとなる先端部分に画用紙をのりで貼る
先端に貼った画用紙にはさみで切れ込みを入れて、ブラシを完成させる
上記のように、オリジナルの歯ブラシセットを作成するだけでなく、制作した歯ブラシセットを用いた「歯医者さんごっこ」をさせることもポイントです。歯医者さんになりきった子どもたちが、自分で作った動物を患者さんに見立てて歯磨きをするといった方法は、より楽しみながら学ぶことにつながります。
3. クイズを楽しむ
歯と口の健康週間では、子どもたちに対して歯に関するクイズを出すこともおすすめです。クイズ形式にすることで、勝ち負け関係なく楽しく歯について学べるだけでなく、正解して褒められた経験は「嬉しかった思い出」として心に残るでしょう。また、クイズは子どもたちでも簡単に解けるよう、三択問題にすることもポイントです。
【問題1】
子どもの歯は何本ある?
(1)10本
(2)15本
(3)20本
答え:20本
【問題2】
歯磨きはどれくらいのペースでする?
(1)1週間に1回
(2)2日に1回
(3)毎日
答え:毎日
クイズの途中や正解を伝えるときには楽しいBGMを流したり、正解した子には子どもたち全員で大きな拍手を送ったりすることで、子どもたちはよりやる気に満ち溢れるでしょう。
まとめ
毎年6月4日から6月10日までの1週間は、厚生労働省・文部科学省・日本学校歯科医会・日本歯科医師会が実施する「歯と口の健康週間」です。この期間中は、子どもたちに歯磨きの大切さを教えるのに絶好の機会と言えるでしょう。
子どもとともに歯と口の健康週間を楽しむためには、歯を題材にした絵本を読んだり、歯に関する制作を楽しんだり、歯に関するクイズを出したりすることがポイントです。子どもたちがより楽しめる工夫を取り入れながら、歯と口の健康がどれほど大切なのかを伝えましょう。
「ほいくらし」では、保育業界で働く方に向けてお役立ち情報を日々掲載しております。保育士としてより幅広い知識をもちながら、多くの子どもたちと関わりたいと考えている方は、ぜひ子育て・保育の総合情報サイト「ほいくらし」の他記事も参考にしてください。
※当記事は2022年9月時点の情報をもとに作成しています
お得な情報や最新コラムなどをいち早くお届け!ほいくらし公式LINE 保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!ほいくらし公式X(旧Twitter)







