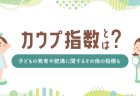シュタイナー教育とは、知的な学習だけではなく、感情や意志に働きかける総合芸術も重視する教育方法の一種です。オーストリア出身のルドルフ・シュタイナーの思想に基づき、子どもの個性を尊重しつつ、個人の能力を最大限に引き出すことを目指します。
この記事では、シュタイナー教育の概要に加え、5つの特徴とメリット・デメリットを詳しく解説します。お子様の教育方針としてシュタイナー教育を検討している方だけでなく、シュタイナー教育を実施する施設に関心を持つ保育士の方も、ぜひご一読ください。
1. シュタイナー教育とは
シュタイナー教育とは、オーストリア出身のルドルフ・シュタイナーの思想に基づいた教育方法の総称です。教育や芸術、医学などの各界に影響を与えたシュタイナーは知的な学習だけではなく、感情や意志に働きかける総合芸術としての教育を重視しました。
シュタイナー教育において、教育という営みは子どもが「自由な自己決定ができる人間になるための補助」と表現されます。子ども達の個性を尊重しながら、個人が持つ能力を最大限に引き出すのが目標です。
1919年には、ドイツで最初のシュタイナー学校が誕生し、現在では世界30か国に1000校以上のシュタイナー教育実践機関があります。日本においても、幼児教育施設や学校法人、スクールなどでシュタイナー教育学が取り入れられています。
シュタイナー教育を実践する機関では、年齢や発達に適したカリキュラムの中で、芸術教育にも重点を置いた取り組みが行われるのが特徴です。頭と手足を使って思い思いに活動しながら、子どもたちが自己の能力を発展させていける「人間形成」を目指しています。
2. シュタイナー教育の特徴
シュタイナー教育は、日本における一般的な教育方針とは異なる点が多くあります。ここでは、シュタイナー教育の特徴5つを解説しているため、保育現場で活用する際の参考にしてください。
1. 7年周期の発達段階
シュタイナー教育では、人間学に基づいて人は7年周期で成長の節目を迎えると考え、0〜21歳までを発達段階に応じて3段階に分けて教育する方法を提唱しています。以下はそれぞれの段階における教育の内容です。
| ・第一(0〜7歳):【身体】意思を育てる時期 7歳までの時期には、遊びやさまざまな動きを通して、健康な身体づくりや創造性を育むことが重視されます。日本の学校では、7歳は小学1年生の時期ですが、シュタイナー教育では幼稚園時代の延長と考えて教育活動を行うのが特徴です。多様な遊びを経験する中で、子ども一人ひとりの興味や関心を尊重し、内面形成や思考形成の土台を固めることを目指します。 ・第二(8〜14歳):【心】感情を育てる時期 シュタイナー教育における8〜14歳は、さまざまな芸術に触れ、表現力や創造力を養う時期です。感情豊かに成長することを重視するため、子ども達に対して思考を強いるべきではないとされています。 ・第三(15〜21歳):【頭】思考を育てる時期 思春期から大人を迎えた直後の15〜21歳は、思考力を養うことを重視して教育が行われる時期です。知識をインプットするだけではなく、論理的な考え方や自ら判断し行動する力の養成を目指し、文化や自然活動などの多様なプログラムが実践されます。 |
2. 縦割りの同一担任制
一般的な保育園や学校では、年齢ごとにクラスが編成されるのに対して、シュタイナー教育では縦割りでクラスが編成されます。シュタイナー教育を取り入れる保育園や幼稚園では、異年齢の子ども達が同じクラスで活動するのがポイントです。
小中学校については、シュタイナー教育の場合は8年間の一貫教育の中で1人の教師が同じクラスを担当するため、生徒にきめ細かな対応ができるのが魅力です。また、生徒は小学1年生から中学3年生まで同じクラスで学びます。
3. 子どものタイプ分け
シュタイナーは、子どもの気質を生まれながらの個性と遺伝の混合であると考え、4つのタイプに分類しました。周囲の大人達は、それぞれの気質の特徴を理解して、子ども達に接する必要があります。
シュタイナー教育によって分類される、気質の4タイプは以下の通りです。
| 胆汁質 |
|---|
| 意志が強く判断力や行動力に長けているが、自身の意志が通らないと感情的になるなど、周りと衝突しやすい傾向も見られる。胆汁質の子どもは、エネルギー量が多いのも特徴で、発散させる機会や尊敬できる大人の存在が重要。簡単な課題ばかりを与えると自信過剰になりやすいため、難易度が高い課題を与えることが望ましい。 |
| 憂鬱質 |
|---|
| 傷つきやすく、非社交的なため、孤独になりやすい。物事をネガティブに捉えがちだが、自己に対する関心が強く、他人の辛い話にも共感できる繊細な感性を持っている。憂鬱質の子どもは、辛い経験をした人物と出会えないことで、孤独に陥りやすい。 |
| 粘液質 |
|---|
| 注目されることを好まず、マイペースで、食べる・寝るなどの欲求に忠実。物事の習得には時間がかかるものの、1度スイッチが入ると、集中力ややる気が持続する。子どもが自ら興味や関心を持って学べる教育環境を整えることが大切。 |
| 多血質 |
|---|
| 明るく元気で周囲の人と良好な関係を築くことが得意だが、多くのことに関心を持つため、1つに集中して取り組むのが苦手。喜怒哀楽に敏感で、気持ちが先走りやすい特徴も。周囲の影響を受けやすいため、大人はゆっくりとした態度で接することが必要。 |
4. 授業の内容
シュタイナー教育ならではの授業として、以下の3つを紹介します。
| ・エポック授業 シュタイナー教育校において、1時間目に行われる110分間授業を指します。全学年が、国語・算数・理科・社会のいずれかの科目を2〜4週間かけ、集中的に学ぶのが特徴です。エポック教育ではレポート提出や担任との受け答えのみで評価され、優劣をつけるテストは実施されません。 ・オイリュトミー 音楽に合わせて身体を動かし、さまざまな表現を行う授業です。クラスの仲間との関わりを通して、責任感や他者との調和などを学びます。 ・フォルメン 画材を用いて幾何学模様を描き、集中力や指先の繊細な動きを養う授業です。 |
5. 禁止事項
一般的な保育園で行われている保育方法でも、シュタイナー教育では禁止されているものがあります。
| テレビやキャラクターを見せない |
|---|
| シュタイナー教育では、テレビを見るという受動的な行為は、子どもに悪影響があると考えられている。 |
| 早期教育をしない |
|---|
| 人格の8割は幼児期に形成されると言われるため、先取り学習などは行わず、子どもの心を育てることを重視する。幼少期には、知的感覚を養わせないのが特徴。 |
| 絵本を読まない |
|---|
ストーリーのみを語り聞かせることで、子どもの想像力がより豊かになると考えられており、物語のみを淡々と語るのが望ましいとされる。 |
3. シュタイナー教育のメリット・デメリット
シュタイナー教育におけるメリットは、下記の3点です。
シュタイナー教育のメリット
・感受性や表現力、想像力豊かな人材に ・子どもの才能が開花しやすい ・判断力や論理的思考力が身につく |
芸術や自然環境などに触れて、自ら学ぶ活動を取り入れるシュタイナー教育では、感受性や表現力豊かな人材に育つことが期待できます。
テストなどで優劣をつけず、子どもの個性を重視しながら伸ばすこともシュタイナー教育の特徴です。発達段階に合わせ、焦らずに人間力を養う環境が整っており、子ども自身が持つ本来の可能性が開花しやすいところも魅力です。また、シュタイナー教育は自ら判断して行動できる力や論理的思考力が養える点で、世界でも高く評価されています。
シュタイナー教育におけるデメリットとしては、次の3点が挙げられます。
シュタイナー教育のデメリット
・シュタイナー教育を取り入れている場所が少ない ・転校が必要になった場合に学習面で不安を抱えやすい ・ルールを負担に感じる場合がある |
日本国内では、シュタイナー教育を採用している施設が少ないのがデメリットです。また、シュタイナー教育のカリキュラムは日本の学校教育と異なるため、転校や卒業後の進路で悩むケースもあるでしょう。
絵本の読み聞かせやテレビの制限など、シュタイナー教育には特有のルールが存在します。子どもや保護者にとっては、生活スタイルの転換を求められることが負担になる場合もあります。
まとめ
シュタイナー教育では、7年ごとの発達段階に応じた教育が実施されていることのほか、縦割りのクラス分け・子どものタイプ分けが行われるなどの特徴があります。また、日本の公立校とは大きく異なるカリキュラムとなっています。
シュタイナー教育には、子どもが発達段階に合わせて本来の能力を開花しやすくなるといったメリットがあります。一方で、採用されている教育機関が少ないことや、子ども自身や家族がルールを負担と感じることはデメリットとなり得ます。
「ほいくらし」では、保育現場に関わる方に向けたさまざまな情報を発信しています。シュタイナー教育以外にも教育に関する情報を掲載しているため、気になる方はぜひ「ほいくらし」をご覧ください。
※当記事は2023年4月時点の情報をもとに作成しています
お得な情報や最新コラムなどをいち早くお届け!ほいくらし公式LINE 保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!ほいくらし公式X(旧Twitter)