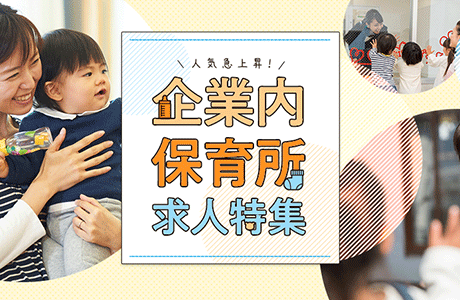保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!
X(旧Twitter)をフォローはこちら!
立春は、暦上で春が始まる日です。立春には神社で立春祭が行われ、酒蔵から「立春朝絞り」という祝い酒が提供されるなど、全国各地でおめでたいイベントが開催されます。しかし、立春の意味について知らない人は多いのではないでしょうか。
今回は、立春の意味・由来について詳しく解説します。また、立春にまつわる風習や、子どもと一緒に立春を楽しむためのアイデアも紹介するため、立春について詳しく知りたい人はぜひ参考にしてください。
立春とは?立春の意味・由来を解説!
立春とは、暦上で春が始まる日であり、「二十四節気」の最初の節気です。二十四節気は、太陽が動く道である黄道を24等分して名称をつけたもので、季節を知るために用いられます。立春は太陽が黄経315度の位置に来た日と定義されており、例年2月4日頃です。
二十四節気において、各季節は6つの節気で構成されており、春は「立春」「雨水」「啓蟄」「春分」「清明」「穀雨」によって成り立っています。立春は春の始まりであるとともに、旧暦において新しい1年が始まる日でもありました。
1. 立春の由来
現在の暦では太陽暦が採用されていますが、6世紀頃から明治時代初期までの日本では太陰太陽暦が用いられていました。太陰太陽暦は、月の運行を基準としつつ一部に太陽の動きを取り入れた暦で、一般的に旧暦として知られています。しかし、太陰太陽暦では季節と月日にズレが生じるため、四季の指標となる二十四節気が編み出されました。
立春の意味が「春が立つ日」であれば、通常は主語+述語の並びで「春立」となるはずです。しかし、「立春」は他動詞+目的語の組み合わせであるため、「春を立てる」という意味となります。
「立春」が「春立」ではない理由は、二十四節気が古代中国によって考案されたことに由来します。古代中国では、季節や星の巡りは王が支配し、王の宣言によって国民に知らされるものでした。このため、王が「春を立てる」という思想に基づき、立春となったといわれています。
なお、実際の季節感と二十四節気の季節にズレが生じている理由も、二十四節気が中国の季節に準じていることが原因です。
2. 節分との違い
二十四節気には節気のほかに、季節の移り変わりの目安となる「雑節」があります。雑節は、日本の生活に基づいて生まれた日本独自の文化です。
節分は「季節を分ける」という意味を持つ雑節で、「立春・立夏・立秋・立冬の前日」を指します。本来、節分は1年に4回ありましたが、大晦日にあたる立春の前日だけが重視され、節分の日として定着しました。
昔は季節の変わり目には病気や災害が起こり、邪気が生じると考えられていたため、節分にはさまざまな邪気払いが行われていました。節分に行う豆まきには、病気や災害を鬼に見立て、邪気を追い払うという意味が込められています。
子どもに伝えたい!立春にまつわる風習・慣習
立春は春の始まりを告げる日であり、昔の人々にとっては1年のスタートでもありました。昔は立春と正月の時期が近いことから「迎春」「早春」「新春」という言葉が生まれ、今でも年賀状などで使われています。
昔の日本では、立春を起算日として八十八夜や入梅などの雑節を決め、生活の目安を立てていました。季節とともに生きる日本人にとって、立春はとても重要な日であったといえます。
ここでは、立春にまつわる風習や慣習を紹介します。
1. 「立春大吉」を玄関に貼る
立春の早朝には、禅寺で「立春大吉」と書かれた厄除けの札が貼り出されます。新年が始まる立春の朝に「立春大吉」の札を貼ることで、1年の無病息災を願いました。
「立春大吉」の文字は左右対称で、縦書きにすると裏から見ても立春大吉と読むことができます。そのため、家に入ってきた鬼が振り返って札を見たときに「この家にはまだ入っていない」と勘違いして家から出ていくとされ、厄除けになると考えられていました。
立春大吉の札はお寺から通販で購入することができます。また、白い紙に自身で「立春大吉」と書いても構いません。立春大吉の札は大人の目線より高い位置に貼り、翌年の立春の日まで貼り出しておきましょう。
2. 若水を飲む
新年の早朝に井戸や湧き水から初めて汲んだ水のことを「若水」といいます。若水は1年の邪気を払うとされ、神棚に供えたあとに雑煮を作ったりお茶を淹れたりしていました。若水を使って淹れたお茶は縁起物として「福茶」と呼ばれます。
平安時代では立春に天皇へ捧げた水のことを若水といいましたが、のちに元旦の行事として庶民の間に広まります。若水を汲みにいくことを「若水取り」や「若水迎え」といい、地域により汲む際の作法が決まっていました。
現代は井戸へ水を汲みにいくことが難しいため、蛇口から出てくる水を若水としても構いません。立春の朝には、清い気持ちで若水をいただきましょう。
3. 豆腐を食べる
古来より「白い豆腐は邪気を払う」とされ、身を清める食べものとして扱われてきました。節分に豆腐を食べると穢れや罪を払い、立春に食べると清めた身体に福を呼び込むことができるといわれています。節分・立春に食べる豆腐のことを「立春大吉豆腐」といいます。立春大吉豆腐を食べる際は、縁起がいいとされる白い豆腐のままいただきましょう。
立春が近づくと、豆腐屋などでは神社で祈祷した大豆を用いて作った立春大吉豆腐が販売されることもあります。ぜひ、縁起のいい立春大吉豆腐を求めて、立春の日に食べてみてください。
【保育士・保護者向け】子どもと一緒に立春を楽しむアイデア
立春の日を楽しみたい場合は、子どもに立春の意味をわかりやすく伝えましょう。下記は、立春について伝える際に押さえておきたいポイントです。
・立春は「春が始まる日」である
・立春の前日が「節分」で、豆まきをして鬼退治をする
・昔の日本では、立春はお正月でもあり、おめでたい日であった
子どもには「まだ寒いけど、これからお花が咲いたり生きものが出てきたりして、だんだん春になるんだよ」と伝え、春の訪れを感じてもらいましょう。ここでは、子どもと立春を楽しむアイデアを紹介します。
1. 子どもと一緒に春を探しに出かける
立春には子どもと一緒に街や公園へ出かけ、五感を使って春の訪れを感じてもらいましょう。立春はまだ寒い時期であるものの、注意深く観察すると季節の変化を感じることができます。下記は、立春の頃に観察できる動植物の一例です。
| 立春頃に咲く花 | フクジュソウ、梅、椿、スイセン |
| 立春頃に見られる鳥 | うぐいす、メジロ、ツグミ、モズ |
| 立春頃に見られる虫 | テントウムシ、カメムシ、シジミチョウ、クマバチ |
散歩中に子どもが何かを発見したら、触ってみたり匂いをかいでみたりと、いろいろな方法で春を感じてみましょう。
2. 春をイメージした作品を作る
春の始まりである立春にちなんで、春をイメージした作品を作ることもおすすめです。作品作りを通し、子どもは室内でも春の訪れを楽しく感じることができます。下記は、春をイメージした作品の一例です。
〇梅の木を咲かせよう
(1)折り紙で梅の花を作る
(2)画用紙に木の枝を描く
(3)画用紙に梅を貼りつけ、満開の梅の木を作る
〇オリジナルテントウムシを作ろう
(1)テントウムシの体となる丸い紙を用意する
(2)丸、ハート、星などに切り抜いた紙やシールを、テントウムシの体に貼りつけて自分だけのテントウムシを作る
完成した作品を壁に飾ると、部屋の中も春らしくなります。散歩中に見つけた春の虫や花を作品として作ることもおすすめです。
まとめ
立春は春が始まる日で、旧暦では1年の始まりでもありました。現在では立春は例年2月4日頃とされ、立春の前日が節分となります。立春には、「立春大吉の札を貼る」「若水を飲む」「立春大吉豆腐を食べる」などの風習があります。
子どもと一緒に立春を楽しみたいときには、春を探しに出かけたり、室内で春をイメージした作品を作ったりすることがおすすめです。
「ほいくらし」では、保育に役立つさまざまな情報をお届けしています。保育士や保護者の人は、ぜひ「ほいくらし」を活用してください。
お得な情報や最新コラムなどをいち早くお届け!ほいくらし公式LINE 保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!ほいくらし公式X(旧Twitter)