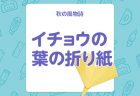夏祭りの意味とは?日本の有名な夏祭りと子どもと過ごすポイント

保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!
X(旧Twitter)をフォローはこちら!
「夏祭り」は、日本の夏を楽しむうえで欠かせない行事のひとつです。古くからの伝統ではあるものの、なぜ夏祭りが行われているのか知っている人は少ないでしょう。夏祭りの意味や由来を知ると、また違った角度から夏祭りを楽しむことができます。
そこで今回は、夏祭りの意味・由来と、日本の有名な夏祭りを紹介します。子どもと一緒に夏祭りを楽しむアイデアも紹介するため、忘れられない夏の思い出を作りましょう。
夏祭りとは?夏祭りの意味・由来を解説!
夏祭りとは、夏の間に行われる祭りのことです。日本では、古くから四季ごとに祭りが行われており、季節によって祭りの意味や目的は異なります。夏祭りの多くは、豊作を妨げる害虫や台風を追い払うことが由来です。夏は疫病が流行しやすい季節だったことから、疫病退散を目的とする夏祭りもあります。
春夏秋冬の中でも、夏は天気の良い日が多く、人が集まりやすい季節です。そのため、全国的に有名となっている大規模な夏祭りも存在します。
子どもに伝えたい!日本の有名な夏祭り
夏祭りは、日本の文化や伝統と密接に関わっています。全国各地で行われている夏祭りの由来を知れば、各地方の歴史にも詳しくなれるでしょう。そのため、子どもに日本の地理や文化を教えたいときは、子どもが親しみやすい夏祭りを題材にする方法がおすすめです。
ここからは、日本の有名な夏祭りの概要や由来、特色を紹介します。
青森ねぶた祭(青森県)
青森ねぶた祭は、青森県青森市で行われる、日本を代表する夏祭りです。本州の最北端にあるにもかかわらず、例年200万人ほどの観光客が全国から訪れます。
【開催日時】
8月2日~7日
【行われること】
歴史上の偉人や歌舞伎を模した山車燈籠(だしとうろう)とともに、人々が青森市の街をまわります。
【由来】
七夕祭りの灯籠流しに由来しているといわれており、厄除けの目的があります。
【知っておきたいポイント】
- 審査員によるねぶた制作の審査・表彰がある
- ねぶたは海外に派遣されることもあり、国外の認知度も高い
- 祭りに登場するねぶたは「ねぶた師」と呼ばれる名人によって作られている
神田祭(東京都)
神田祭は、東京都千代田区にある神田明神で、西暦の奇数年に行われる祭りです。「鳳輦神輿遷座祭(ほうれんみこしせんざさい)」や「氏子町会神輿神霊入れ(うじこちょうかいみこしみたまいれ)」「神幸祭(しんこうさい)」などの行事があります。
【開催日時】
5月9日~15日
【行われること】
だいこく様・えびす様・まさかど様の御御霊(おみたま)を神輿に遷す「鳳輦神輿遷座祭」が祭りの始まりです。メインとなる行事の「神幸祭」では、明神様が乗る「一の宮鳳輦(いちのみやほうれん)」「二の宮神輿(にのみやみこし)」などが街中を巡ります。
【由来】
旧神田祭り(9月15日)の日に徳川家康が天下統一を果たしたことに由来します。
【知っておきたいポイント】
- 「日本三大祭り」「江戸三大祭り」のひとつに数えられている
- 祭りの持つ歴史や華やかさから「天下祭」とも呼ばれている
- インターネットでは生中継も行われる
祇園祭(京都府)
祇園祭は、京都の有名観光地である八坂神社を中心に行われます。平安時代の869年、京洛で蔓延した疫病を封じ込めるために行われた御霊会が起源とされており、世界的にも注目されるほどの歴史と規模を誇る夏祭りです。
【開催日時】
7月1日~31日
【行われること】
山鉾が街中を練り歩く「山鉾巡行」を中心に、多くの出店が立ち並ぶ「宵山」など、1か月にわたる期間の中でさまざまな行事が開催されます。
【由来】
869年に京都で流行した疫病の退散を祈願したことが由来だといわれています。
【知っておきたいポイント】
- 京都の人は祇園祭で夏本番を実感するほど、夏の風物詩となっている
- 「京都三大祭り」「日本三大祭り」「日本三大美祭り」のひとつに数えられている
- 「山鉾行事」は、ユネスコ無形文化遺産に登録されている
徳島市阿波踊り(徳島県)
徳島市阿波踊りは、400年以上も続いている徳島県の文化のひとつであり、世界に誇る伝統芸能でもあります。阿波踊り自体は日本の定番の盆踊りですが、徳島市の阿波踊りは最大級の規模で、お盆の期間に昼も夜も踊り続けることが特徴です。
【開催日時】
8月12日~15日(11日に前夜祭)
【行われること】
昼は「選抜阿波おどり大会」、夜は演舞場で「阿波おどり」が開催されます。
【由来】
定説はないものの、1587年に徳島城が完成したときの踊りが起源という説があります。
【知っておきたいポイント】
- 2021年は「ニューノーマルモデル」として規模を縮小して開催している
- 阿波踊りは高円寺(東京都)や南越谷(埼玉県)などで町おこしとしても実施されている
- 「日本三大盆踊り」のひとつとして数えられている
博多祇園山笠(福岡県)
博多祇園山笠は、正式名称を「櫛田神社祇園例大祭」といい、櫛田神社の奉納神事として700年以上の歴史があります。迫力や熱気から、昔は女性禁制の祭りであり、男性だけで行われていました。
【開催日時】
7月1日~15日
【行われること】
魅力的な装飾を見て楽しむ「飾り山笠(かざりやまがさ)」と、迫力満点の競争を楽しむ「舁き山笠(かきやまがさ)」の2つが、街中をまわります。
【由来】
1241年に博多で疫病が蔓延した際、承天寺の開祖である聖一国師が、水を撒きながら疫病退散を行ったことが起源とされています。
【知っておきたいポイント】
- ユネスコ無形文化遺産に登録されている
- 花笠は10メートル以上におよぶ高さを誇っている
- 山笠にはアニメのキャラクターなど、さまざまな種類の装飾がされる
【保育士・保護者向け】子どもと一緒に夏祭りを楽しむアイデア
保育士や保護者の中には、子どもから「夏祭りがどんな日なのか」を聞かれるケースもあるでしょう。子どもには「夏祭りは暑い夏を元気に乗り越えられるように開くんだよ」と、噛み砕いて説明すると理解してもらえます。
ここからは、子どもと一緒に夏祭りを楽しむアイデアを紹介します。子どもにとって特別な思い出を作りましょう。
夏祭りに関する絵本を読む
夏祭りに関する絵本を読み、由来や内容を学ぶことも楽しみ方のひとつです。夏祭りに関する絵本には、下記が挙げられます。
〇「おまつりおばけ」
可愛らしいおばけが、祭りに向かう途中に人間の泥棒に捕まってしまう話です。お化けが祭りを楽しみにしている姿を見て「祭りに僕・私も行きたい」と、夏祭りに興味を持ってくれるきっかけになるでしょう。
〇「祇園祭」
「祇園祭」は、祇園祭の様子を描いた絵本です。祇園祭の準備から当日までが丁寧に描かれており、裏側も学べる作品となっています。夏祭りの様子は見開きいっぱいで描かれており、その迫力を肌で感じられる作品です。
〇「えんにち」
「えんにち」は、文字がなくイラストだけで楽しむ絵本です。文字が読めない小さな子どもなど、年齢にかかわらず楽しめます。絵本の中では、射的やお面など、屋台が立ち並ぶ縁日の様子が描かれています。自分自身が小さいときの記憶もよみがえり、大人も子どもと一緒に楽しめるでしょう。
地域の夏祭りに一緒に行く
地域の夏祭りに子どもと一緒に足を運び、実際に祭りの様子を見たり演奏を聞いたりすることで、記憶に残る思い出となるでしょう。夏祭りに行く場合は、子どもに浴衣を着せることをおすすめします。日本文化のひとつである浴衣を着用することで、夏祭りの雰囲気をさらに楽しめます。
ただし、夏祭りは多くの人が集まって混雑するため、子どもが迷子にならないよう注意が必要です。特に、夏祭りが夜に行われる場合は周りが見えにくくなるため、必ず子どもと手をつないだまま行動するようにしてください。
保育園で夏祭りイベントを開く
保育園の夏祭りイベントで手軽に夏祭り気分を味わってもらえば、子どもが夏祭りや日本文化に興味を持つきっかけとなります。
金魚すくいや的当て、ヨーヨー釣りなど、夏祭りの屋台は身近なもので再現できます。牛乳パックや画用紙などを使い、幼児や乳児でも楽しめるゲームを作ってみましょう。可能であれば保護者にも参加してもらい、親子で楽しめるようにすると、さらに有意義なイベントとなります。
まとめ
夏祭りとは、夏の間に行われる日本の祭りです。害虫や自然災害から作物を守ったり、疫病を退散させたりする目的で行われます。「青森ねぶた祭り」「神田祭」「祇園祭」「徳島市阿波踊り」「博多祇園山笠」などの夏祭りは、全国的にも有名です。機会があれば、子どもと一緒に行ってみてはいかがでしょうか。夏祭りに関する絵本を読んだり、地域や保育園の夏祭りイベントに参加したりすることも、楽しみ方のひとつです。
「ほいくらし」では、夏祭りの意味・由来以外にも、子どもたちに教えたい情報を発信しています。保育や子育てに役立つ知識も掲載しているため、子どもの成長や関わり方に日頃から悩んでいる人はぜひご覧ください。
お得な情報や最新コラムなどをいち早くお届け!ほいくらし公式LINE 保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!ほいくらし公式X(旧Twitter)