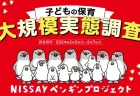保育参観の内容を年齢別に紹介!準備と当日のポイント

文: ちかっぱ(保育士ライター)
保育参観のねらいは、園での子どもの過ごし方や保育士と子どもたちとの関わり方を、子どもたちと一緒の活動を通して、保護者に肌で感じてもらうことです。
保育参観を実施するにあたり、「どのような活動を取り入れたらよいのか」「日頃の子どもたちの様子を保護者に伝えるには何をすればよいか」と悩む保育士もいるのではないでしょうか。
本記事では、保育参観の年齢別のねらいや、活動内容の例、準備と当日のポイントを紹介します。あわせて、保護者への挨拶のスピーチ例や、保護者から「参加できない」と言われたときの対応についても解説しています。指導案作成や、保育参観の活動を考える際にお役立てください。
保育参観のねらいとは

保育参観のねらいは主に以下の3つです。
- 子どもの園での様子を保護者に見てもらう
- 保護者に実際に園を見学してもらい、職員の雰囲気や園舎の環境、方針を感じてもらう
- 親子で楽しむ活動を通じて、保護者に子どもの成長を感じてもらう
上記のねらいを踏まえて、子どもたちの普段の生活の様子がわかるような活動を取り入れるとよいでしょう。保護者にとっても、園の様子を知れる貴重な機会となります。保育参観を通じて「安心して預けられる」という気持ちを持ってもらえることを目指しましょう。
【年齢別】保育参観の内容や遊びのアイデア例

保育参観の内容を考えるうえで大切なのは、子どもたちの成長や発達に合っており、保護者にも楽しんでもらえる活動にすることです。発達に遅れがある子どもにも配慮し、その旨を保護者へ事前に伝えることも必要です。
ここでは、年齢別の保育参観の内容や遊びのアイデアの例を紹介します。
0・1歳児クラスの保育参観
0・1歳児は、ハイハイする子どもや少し歩ける子どもがいたり、手づかみ食べをしたり、目まぐるしく成長が加速します。普段の生活リズムや過ごし方が保護者に伝わり、保護者と一緒に成長を喜べる活動がよいでしょう。
【0・1歳児の遊びのアイデア例】
- 手遊び(グーチョキパー、いとまき、しあわせならてをたたこう など)
- ふれあい遊び(バスごっこ、おふねがぎっちらこ、ぞうきんのうた など)
- 製作(新聞紙遊び、シール貼り、楽器製作 など)
2歳児クラスの保育参観
2歳児は徐々に身の周りのことを行うようになり、目の前のものがどうなっているのか、どんなものでも触って確かめてみたい、試してみたいと好奇心旺盛な時期です。また、自我が芽生えてくるため、自分でできるという自信につながる活動や、親子で行うルールのある遊び、手先を使う遊びを通して、成長が感じられるように進めていくとよいでしょう。
【2歳児の遊びのアイデア例】
- 運動遊び(ボール、かけっこ など)
- ふれあい遊び(バスごっこ、ペンギンさん など)
- 製作(簡単な折り紙、シール遊び など)
- やさいスタンプや絵の具の活動
3歳児(年少)クラスの保育参観
3歳児は言葉が達者になり、自分でできることが増え、簡単なルールも理解して集団行動ができるようになってくる時期です。発達に寄り添いながら、成長を感じられて親子で楽しめる活動を取り入れるとよいでしょう。
【3歳児の遊びのアイデア例】
- ふれあい遊び(ぺんぎんさん、あたまかたひざぽん など)
- ルールのある遊び(いすとりゲーム、しっぽとりゲーム など)
- 季節が感じられる製作(フォトフレーム作り〈母の日や父の日など〉、こいのぼり、ちょうちょ など)
4歳児(年中)クラスの保育参観
4歳児は身の周りのことを自分でできるようになり、友だちとの関わりが増え、話し合って物事を進め、自主性が出てくる時期です。自主的に動く姿や、個がわかる活動を取り入れるとよいでしょう。
【4歳児の遊びのアイデア例】
- 運動遊び(フルーツバスケット、なわとび など)
- リズム遊び(ピアニカや打楽器 など)
- 製作(季節が感じられる製作〈にじみ絵の傘や花、みのむし など〉、身近な人を絵で描く など)
5歳児(年長)クラスの保育参観
5歳児は、社会性やコミュニケーション能力が高まり、保護者や友だちと話し合うことができるようになる時期です。友だちや自分のことを認めたり、協力して動けたりするような様子を見てもらえるとよいでしょう。
【5歳児の遊びのアイデア例】
- リズム遊び(もうじゅう狩り など)
- ダイナミックな遊び(パラバルーン、大きな紙を使ってみんなで作り上げるもの など)
- 製作と遊びが融合したもの(たこ製作、けんだま作り、スライム、こま など)
- 季節感が感じられる製作(絵の具を使った巨大なこいのぼり製作、紙皿での時計作り、紋切りやはじき絵などの花火 など)
保育参観の事前準備・当日のポイント

保育参観では、事前準備や心構えが重要です。想定外のアクシデントやトラブルが起こることもあるので、すぐに対応できるようにしておくと安心でしょう。
事前準備のポイント
保育参観の事前準備に大切なポイントを4つお伝えします。
保育参観のねらいや活動を明確にする
保育参観では、保護者に、子どもたちのどんな姿を見てほしいのか、ねらいや目的を指導案にしっかりと記載しましょう。以下のように、ねらいや目的を明確にしておくことで、保護者に参加してもらう貴重な時間を意義のある時間にできます。
【ねらいと目的の例】
- 親子でふれあいながら、音楽遊びを楽しむ
- 友だちとの話し合いを通じて、自分の気持ちを伝えたり、友だちの意見を受け入れたりできる成長を保護者に見てもらう
備品準備とイメージトレーニングをしておく
準備が足りないと、限られた保育参観の時間が削られてしまう可能性があります。また、保護者は普段子どもと関わっている保育士が「どんな先生なのか」気になるものです。子どもたちだけでなく保育士も注目されているので、準備物に抜けがあると保護者を不安にさせてしまう原因にもなるでしょう。
事前に準備しておくべきものとして、例えば以下のようなものがあります。
- 使用する道具や材料……数も確認しておきましょう。
- 製作の手順書……事前に製作物の作り方を記載した紙を机に貼っておくと、保護者が確認しながら進められます。
- 机やいす……保護者側の人数制限がない場合には、兄弟姉妹や祖父母などが来ることも想定して多めに用意しておきます。
また、当日の流れや想定されるトラブルを一通りイメージし、対処法まで考えておくと安心です。
【想定されるトラブルの例と対処法】
- 「製作活動で子どもたちが思うようにできず、泣き出してしまった」
子どもの気持ちに寄り添い、保護者と一緒に活動できるよう促します。 - 「保護者がいる緊張から、いつも通り活動ができず保護者にべったり」
いつもと違う環境に慣れない子どももいること、無理せず見学していてもよいことを保護者に伝えます。
おたよりに「服装」と「当日の活動」を明記する
保育参観のおたよりは、保護者の仕事や家庭の事情なども考慮し、保育参観の2~3週間前には配布するとよいでしょう。保護者はどんな服装で行けばよいか迷う場合も多いので、わかりやすくおたよりに記載してください。
【おたよりの例】
- 当日はお子さんとホールで体を動かしますので、動きやすい服装でお越しください。かかとのある室内用シューズのご用意もお願いします。
- 当日は絵の具を使用した活動を行いますので、汚れてもよい服装でお越しください。
また、おたよりには当日の活動の流れをわかりやすく書き、保護者懇談会や担任との話し合いが予定されている場合は、その内容も記載しましょう。
保護者から参加できないと言われたら
保護者のなかには、仕事や家庭の事情で参加できない方もいます。参加できないと言われたときは、その旨を受け入れましょう。他の職員が保護者の代わりに園児と一緒に活動する旨を伝えておくと、保護者も安心できます。
当日のポイント

保育参観当日のポイントを3つお伝えします。
保護者への挨拶やコミュニケーションで信頼度アップ
保育士の動きは保護者から常に注目されています。また、保護者への挨拶はコミュニケーションのきっかけとなります。丁寧な言葉遣いや明るい口調は、保育者への信頼にもつながるため、明るく笑顔でハキハキと、ふさわしい対応を心がけましょう。
安全面の配慮を忘れない
製作を行う場合ははさみやテープ台、運動遊びの場合はテーブルの角や使用する玩具が割れていないかなど、安全面の確認を徹底しましょう。
子どもたちにとって安全な環境設定をすることが、充実した保育参観には欠かせません。
保育士の服装や身だしなみに配慮する
保護者に信頼してもらえるよう、保育士の服装や髪形は清潔感があるか、爪は長くないかなどをチェックしましょう。
保護者への挨拶・お礼【スピーチ例文】

当日は、保護者の貴重な時間をいただいていることを忘れずに、感謝のお礼をきちんと伝えましょう。
保護者への挨拶は、ある程度考えておくと当日の緊張が和らぎ、スムーズな流れを作れます。長すぎないように注意し、心のこもったお礼を伝えましょう。
最初の挨拶のスピーチ例
本日はお忙しいところお越しいただきありがとうございます。
改めまして、○○くみの担任をしております○○です。
今日は子どもたちと一緒に楽しい時間をお過ごしください。
よろしくお願いいたします。
では、今日の活動の説明をします。
最後のお礼のスピーチ例
本日は楽しい時間をありがとうございました。
子どもたちの○○な姿を見ていただけたでしょうか。
おうちでもぜひ、遊んでみてくださいね。
本日はお忙しいところ、貴重なお時間をいただきありがとうございました。
お忘れ物がないよう、気をつけてお帰りください。
保育参観は子どもが主役!保護者も楽しめる内容を検討しよう

保育参観は子どもが主役です。子どもたちが楽しく活動できる内容や流れを考えてみましょう。子どもたちと話し合って活動内容を考えるのも楽しいですよ。
保護者も参加する貴重な機会なので、ふれあいが楽しめる内容を取り入れてみてはいかがでしょうか。
幼稚園の子育てサロンで未就学児の活動を担当し、満3歳児~5歳児の担任や、幼稚園事務も経験。
勤務歴10年の経験を活かし、現在はフリーランスライターとして子育て中のママパパや保育士、幼稚園教諭に向けて記事を執筆している。
自分自身も6歳4歳の子育てをしながら、子どもたちと体を動かしたり本を読んだりする時間を大切に、「明るく楽しく笑顔で」をモットーにしている。
保有資格:保育士・幼稚園教諭一種
参考サイト: