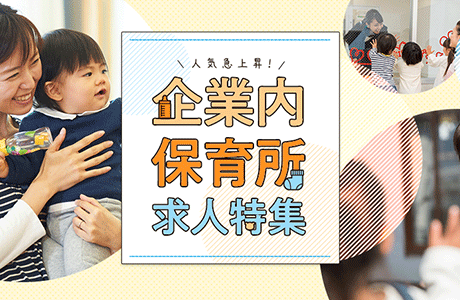独自のトイレトレーニングを実践し、「トイレの神様」と呼ばれている、「八王山学園 あすなろ幼稚園」の田中彩先生。2020年にはその活動が評価され、第22回「がんばれ先生!東京新聞教育賞」も受賞しました。彩先生考案のトイレトレーニングは、特製のシールシートなどを活用して、子どもが「自分でトイレに行きたい」気持ちになるように応援するのがポイントです。今回は同園を訪問し、トイレトレーニングに取り組むときの考え方や、始めるタイミングなどについて話をうかがいました。
\お話をうかがった方/
田中彩先生 八王山学園 あすなろ幼稚園 教頭
1973年1月9日生まれ、日本女子大大学院修士課程修了後、1997年あすなろ幼稚園に入職し、現在に至る。保育の師匠は、幼児教育学者の故森上史朗さん。平成22(2010)年に文部科学大臣優秀教員として表彰され、令和2(2020)年には第22回「がんばれ先生!東京新聞教育賞」を受賞。

子どものトイレトレーニングを応援する、オリジナルのシールシートを制作
——まずは、「八王山学園 あすなろ幼稚園」についてご紹介ください。
田中:当園は、東京都葛飾区の私立幼稚園として1965年に創立しました。子どもたち1人ひとりの気持ちや個性を尊重するとともに、「一生ものの心や力」の形成・育成を目指して、子ども主体の保育を実践し続けています。園児の定員は200名となっており、保育教諭は正規教諭23名、非正規教諭7名の合計30名が在籍しています。
——先生が「トイレトレーニング」を応援するオリジナルシートを作ったきっかけは何だったのでしょうか。
田中:2017年に、当園で「満3歳クラス(年少クラスより1学年下の満3歳を対象としたクラス)」というプレスクールを立ち上げることになったのですが、満3歳ごろはちょうどトイレトレーニング(以下、トイトレ)をする時期。保護者のみなさんが苦戦している様子を見て、親子ともにトイトレを楽しめるツールや指針のようなものがあったらいいなと考えていました。それで、当時プレスクールの担任をしていた先生と一緒に、オリジナルのツールを作ってみたのが、「トイレトレーニング応援シールシート」の始まりです。
シールシートには、子どもたちが好きな動物や乗り物が描かれており、トイレにチャレンジできた子どもには、「がんばったね!」とシールを渡して、シートに貼ってもらう仕組みです。満3歳クラスの家庭に配布していますが、いざ作ってみたら、保護者のみなさんから、「うちの子は車が好きなので車のシートを作ってほしい」「次はうんちにチャレンジするためにうんちのシートを作ってください」とリクエストがたくさん! 乗り物や海の生き物、キラキラ、新幹線、果物など、シートのバリエーションがどんどん増えています(笑)。
——子どものトイトレについて、保護者からどんな質問を受けることが多いですか?
田中:トイトレを進めるにあたって「子どもにどのような言葉をかければよいか」や、「どんなタイミングで言うべきか」といった細かい質問を受けることが多く、みなさん正しい方法や正解を求めているのだなと感じます。子育てに正解がないことはわかってはいても、「自分のやり方に問題はないのだろうか」と不安になるのかもしれませんね。
でも、子どもの数だけトイトレの方法があり、「こうしたら絶対うまくいく」というマニュアルはありません。私がシールシートを作ったのも、うまくやってほしいからではなく、保護者の方にトイトレを含めた子育てをもっと楽しんでほしいという思いがあったからです。

「能動的に待つ」ことが、トイトレに取り組むにあたってのポイント
——トイトレに楽しく取り組むためのポイントがあれば、お聞かせください。
田中:トイトレには、重要なポイントが2つあります。1つ目は、ゴールを「子どもが自分からトイレで用をたそうとする」に設定すること。2つ目は、「能動的に待つこと」です。
まずは、1つ目のポイントからお話ししましょう。トイトレというと、つい「おむつが外れること」をゴールにしがちですが、本当のゴールは「子どもがおしっこやうんちをしたいと思って、自分からトイレに行くこと」のはず。それを忘れないようにしてください。「子どもが自分でやる気になること」をゴールにすれば、親もおむつが外れないことに悩まなくてすむし、子どもへの声がけも気軽にできるようになりますよ。
2つ目のポイントである「能動的に待つこと」については、塾のCMで使われている「やる気スイッチ」という言葉を思い浮かべてみてください。子どもにとって何が「やる気スイッチ」になるのか、正直わかりませんよね。もちろん、「ぼくは今日からトイレでします!」と子どもが言い出すこともありません。でも、わからないからといって何もしないのは違います。
だとしたら、どうすればよいのか。子どもがトイレに興味を持ちそうな仕掛けをいくつも用意することから始めてみてください。たとえば、家族(親やきょうだい)がトイレに誘ってみて、トイレをしている姿を「かっこいいでしょ」とさり気なく見せたり、一緒にトイレに入って「ドアを開けるぞ! パンツを脱ぐぞ〜、さあ便座に座るぞ!」と実況中継をしたりするのも1つの方法です。
音が鳴ったり光ったりするおもちゃをトイレに設置して、子どもがトイレに行く楽しみを作るのもよいでしょう。そういった楽しい仕掛けや、自然とトイレに興味を持つような環境を作り、子どもがトイレで用をたすことに興味を持つのを「待つ」のです。
注意してほしいのは、仕掛けづくりの段階で「トイトレをやる気になってくれ!」という、こちらの下心を前面に押し出さないこと。親に下心があると、子どもはなかなか乗ってきてくれませんよ。
2歳になった初夏が、トイトレチャレンジを始める好機

——子どものトイトレを始めるタイミングについても教えてください。
田中:「歩ける」「ジェスチャーや言葉でコミュニケーションが取れる」など、体や認知能力の準備ができてきたころが、トイトレにチャレンジするタイミングです。おしっこの間隔は2時間空いていなくても大丈夫。トイトレを始めることで、少しずつ間隔も空いてくるでしょう。おすすめの時期は、子どもが2歳になった初夏ごろですね。薄着になって洋服の着脱がしやすいことや洗濯物が乾きやすいこと、汗をかくためおしっこの間隔が空きやすいことなどの理由から、トイトレに取り組みやすいはずです。
ただ、下の子の出産を控えていたり、職場復帰と重なったりして、保護者の方がトイトレに取り組む時間や気持ちに余裕がない場合は、チャレンジを先延ばしにしてもよいでしょう。「今なら楽しくやれそうかな」と前向きな気持ちで取り組めそうなタイミングで、チャレンジしてみてください。子どもが保育園に通っているなら、保育園の先生に手助けをお願いしてみるのもよいと思います。
「理論派」か「感情派」か、子どものタイプを見極めることも大事
——トイトレを進める場合、女の子と男の子で違いはありますか?
田中:トイトレを進めるうえでポイントとなるのは、性別よりも子どもの性格です。子どもには大きく分けて「見通しを持ちたい理論派」と「その場の空気感が大事な感情派」の2つのタイプがいるので、ぜひ覚えておいてください。
たとえば、子どもが「幼稚園に行きたくない」とぐずったとしましょう。そんなとき「理論派」の子には、「今日は、靴を履き替えて、スモックを着て、おやつを食べたらもう帰れるよ」と見通しが立てやすくなる声かけをすると、安心してくれます。一方の「感情派」は、ぐずっているときの気持ちを「そうか、そうか」と聞きながら、「今日は朝ごはんに何を食べたの?」と話を広げ、「じゃ、よ〜いドンしよう!」などとかけ声をかけることで、パッと気持ちが切り替わる場合があります。
トイトレにチャレンジする幼児期には、女の子に「理論派」のタイプが多く、男の子に「感情派」のタイプが多く見られます。全員が必ずどちらかに分類されるわけではないし、両方が共存している子どももいますが、よく観察して「理論派」と「感情派」のどちらが強く表れているかを見極めると、トイトレの作戦を練る参考になると思いますよ。ちなみに、この特徴は成長とともに男女逆になってくるのがおもしろいところです。
停滞期には、子どもの「やりたくないスイッチ」を探してみて!
——最後に、トイトレがうまく進まないときのアドバイスをお願いします。
田中:トイトレが停滞しているときは、何かしらの「やりたくないスイッチ」があるものです。その証拠に、「原因を考えて取り除いてあげたら、驚くほどスムーズに進んだ!」という話をよく聞きます。子どもの「やりたくないスイッチ」を探るのはとても大事な作業ですが、少しだけ心の距離を置いて観察してみると、意外なポイントが見つかったりするので、試してみてください。
たとえば、「カーテンをさわりながらしたい」という子なら、カーテンのそばにおまるを持ってきたり、カーテンと同じような生地を握らせてあげたりすることで、トイトレがスムーズになる可能性があります。保護者の視点だけでは「やりたくないスイッチ」が見つからない場合は、保育園・幼稚園の先生に相談してみるのがおすすめです。
トイトレは、子どもの主体性が育つさまを体感できるチャンスです。また、保護者がどんなにがんばってもうまくいかないこと、思い通りにならないことをわかりやすく実感できるよい機会でもあります。挫折を感じる場面もあるかもしれませんが、子育てのおもしろさを学べるチャンスだと捉えて、楽しく取り組んでみてください。親が楽しみながら子どもの成長を見守る気持ちは、きっと子どもにも伝わるはずですよ!
◆八王山学園 あすなろ幼稚園: http://www.asunaro-kg.ed.jp/
◆現役幼稚園教師『トイレの神様』のトイレトレーニング♫ STEP1:https://youtu.be/UiMHx76QkPs
取材・文/早川奈緒子 編集/イージーゴー