保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!
X(旧Twitter)をフォローはこちら!
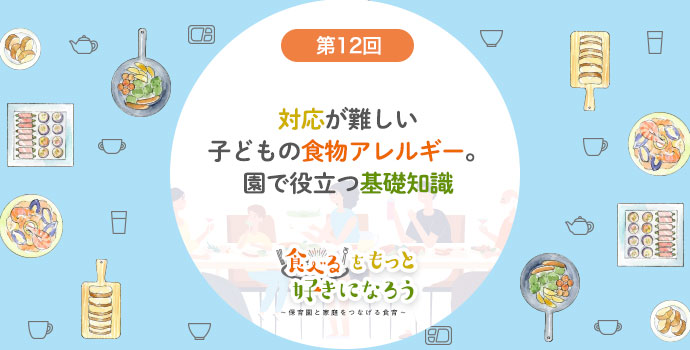
激しいアレルギー症状が出ると命に関わることもあるため、保育の現場では食物アレルギーに対して、慎重にならざるを得ません。
しかし、「問題が起きないようにする」ことに注力し過ぎてしまうと、食物アレルギーを持つ子どもが他の子どもと一緒になって「食べるのを楽しむ」ことができなくなるというジレンマもあるでしょう。
今回は保育士のみなさんに知っておいてほしい、食物アレルギーの基礎知識と注意したいポイントを見ていきます。
文/栄養士 笠井奈津子 写真/櫻井健司
入園したばかりの園児はとくに注意が必要

「食後に子どもが痙攣を起こしたときは、生きた心地がしなかった……」
これは食物アレルギーがある未就学児を持つ友人がわたしに話してくれたことですが、親御さんに限らず、保育士のみなさんもこのような怖い体験をしたことがあるかもしれませんね。
食物アレルギーは、その原因となる食物を摂取してから早くて15分以内、遅くとも2時間以内に症状が出る「即時型」がほとんどです。そのため、入園したばかりの園児や、すでに食物アレルギーがあるとわかっている園児には、食事がはじまってからお昼寝の時間まで注意深く見守る必要があるのではないでしょうか。
アレルギー反応とは、外部からの異物を排除しようとする免疫反応が過剰に出ることで起こるものです。大人にとっての身近なアレルギーといえば「花粉症」かもしれませんが、食物アレルギーは子どもによく見られるものです。特に乳児期に多く見られるため、まわりにいる大人たちは神経質になるはずです。
これについては、親御さんへのヒアリングはもちろんのこと、給食ではじめて食べる食材がないよう入園前に食材のチェックリストを親御さんに渡したり、翌月の献立の内容を親御さんと一緒に確認したりするなど、園それぞれで対応していることと推測します。
ただ、いくら上記のように対策しても、なにかを食べたときにちょっとした蕁麻疹などの皮膚症状が出ることもあるものです。当然、食物アレルギーを疑いますが、調理法によっては食べられる場合もあるので、自己判断(園においては保育者の判断)で除去食を選択するのではなく、その子がかかりつけのクリニックなどで検査してもらうよう親御さんと相談するといいでしょう。
肌のバリア機能が低下することから起こるアレルギーもある
また、肌のバリア機能が低下して、アレルゲン(アレルギー疾患を持っている人の抗体と特異的に反応する抗原のこと。一般には、そのアレルギー症状を引き起こす原因となる物質)が侵入することで食物アレルギーの要因となるケースもあります。その場合には、肌を清潔に保ちしっかりと保湿することが、食物アレルギーの悪化を防ぐ手立てとなります。
保育の現場でやれることとしては、こまめに衣類を交換する、よだれや食後の口まわりの汚れを優しく拭いてあげる、寝具の交換頻度を考えるといったサポートです。保湿に関してはなかなか難しいところですが、清潔に保つことは保育の現場でもできることだと思います。もちろん、「いつどんなときも」というわけにはいかないかもしれませんが、子どものつらさを和らげるために気にかけてあげたいポイントです。
アレルギーのこと、子どもたちにどう説明する?
子どもたちが一斉に食事をする給食の場では、子ども同士の食べ遊びの延長でアレルギーの要因となるものを食べてしまうという思いがけない出来事が起こることもあります。大人たちの理解や配慮だけでなく、子どもたちが食物アレルギーに対して理解を持つこともまた、「安心で安全な食」の大事な要素になります。
そこで気をつけたいのは、「間違って食べると危ないんだよ」ということを伝えようとするあまり、「○○ちゃんは特別だから」「みんなと同じものを食べられないからかわいそう」というネガティブな感情で説明しないことです。子どもによっては、食べられないことよりも、特別視されることが負担になることもあるからです。
また、アレルゲンとなる卵・牛乳・小麦などは、卵ならばマヨネーズに、牛乳ならホワイトソースに、小麦粉ならハンバーグのつなぎにといった具合に、目視できないかたちで含まれていることもやっかいです。「見えない=ない」と考えてしまう子どもは少なくないでしょう。
では、子どもたちにはどのように教えていくといいのでしょうか。例えば、幼児クラスであれば食育の授業とからめて、「卵が隠れている料理はなーに?」などとクイズ形式で教えていくのもおすすめです。アレルギーを持つ友だちにとっての「安心で安全な食」に対して、みんながそれぞれに学びながら協力できるといい関係性、ひいてはいいクラスができあがっていくように思うのです。

おやつの時間に、小麦粉でつくったホットケーキと米粉でつくったホットケーキを食べ比べるというような取り組みもいいですね。食感のちがいを感じたり、甘みのちがいを感じたりすることもできます。なかには、「米粉でつくったほうが美味しいね!」という子がいるかもしれません。
発育の視点から見ても、「これは絶対に食べないとダメ!」というものはなく、調理の手間は少しかかるもののアレルギーを持つ子が安心して食べられる食材に代替することは可能です。「食べられない=かわいそう」ではなく、違う選択肢により安心を手に入れることができるということを、子どもたちと一緒に学んでいきましょう。
園での様子を見て変化に気づき、親御さんに共有する

食物アレルギーが赤ちゃんの頃にもっとも多く見られるのは、消化機能が未熟なことに加え免疫の調整作用も弱いことが影響し、アレルギー反応そのものが起きやすいためです。成長するとともに改善していくこともあるので、折を見て、家庭での様子などをヒアリングすることも大切なことです。
個人差こそありますが、乳児期に多く見られる卵・小麦・牛乳の「3大アレルゲン」では、3歳頃までには5割程度、6才頃までには8〜9割程度の子どもがふつうに食べられるようになるとされています。
一方で子どもが食べ慣れていない食べものにも注意が必要です。卵・小麦・牛乳などのように日常的に食卓に出やすいものなら家庭でも簡単にアレルギーの有無に気づけますが、甲殻類や果物はあまり食卓に出ないという家庭も少なくありません。もしそれらを家で食べていたとしても、アレルギー症状として「鼻水が出る」「ちょっとかゆい」くらいの症状だと、月齢が低い年齢では気づきにくいということもあるでしょう。
親御さんからの報告はないけれど、園での様子を見ていて気になることがあれば、「どの食べ物でどんな症状が出たか、食べてからどれくらいで症状が出たか、どれくらいで症状が消えたか」などの情報を共有するようにしましょう。
「親であるわたしがアレルギー体質だから遺伝したのかもしれない……」「あまりいろいろな料理を食べさせていないからかもしれない……」などと自分を責めてしまう親御さんもなかにはいます。「誰にでも起こり得ること」であるのと同時に、「成長とともに食べられるようになるケースも多い」ということもしっかりと伝えてくださいね。
産後、働き方を見直すなかでパラレルキャリアの道を開拓。








