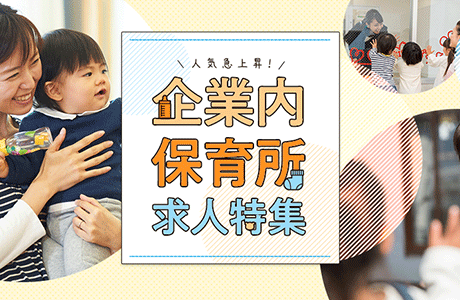ひどい肩こりを何とかしようと、薬を服用したり、マッサージに通ったりしているけれど、結局は肩こりを繰り返してしまう……。みなさんのなかにも、そんな方がいらっしゃるのではないでしょうか?
肩こりや疲れがある状態だと、仕事や家事に集中できませんよね。また、肩こりがあると、猫背や巻き肩(肩が前に丸く出てしまう状態)になってしまうなど、姿勢も悪くなりがちです。痛みやわずらわしさのせいで心が晴れず、表情まで暗くなってしまうかもしれません。
でも、こりが改善されて体が整ったとすればどうでしょう? 心が晴れやかになって、仕事や人間関係も円滑になるはずです。おまけに表情も豊かになり、内面の美しさも増すでしょう。
この記事では、肩こりの根本原因を解説するとともに、ひどい肩こりが3日で楽になる体操と、肩こり知らずの体を手に入れる方法をご紹介します。

生体道場
明清彩® 道主 身体開発専門家
松原 武司(まつばら・たけし)先生
慢性疲労や首こり、肩こり、腰痛、猫背などに悩む人、あるいは、そうした不調を感じつつも「運動はしたくない」という人に向けて、「簡単に体の使い方を覚える方法」を指導している。レッスンは、理論的かつ体が覚えやすいと大好評!
ひどい肩こりが起こる根本原因
肩こりの原因として挙げられるのは、「猫背などで姿勢が悪い」「運動不足による血流の悪化」などです。これをもっとシンプルな言葉で表現するなら、ひどい肩こりは、体を動かすと疲労物質がつくられるからといえるでしょう。
疲労の蓄積がこりを引き起こす
人は生きている以上、疲労(疲労物質)と無縁ではいられません。息を吸うと二酸化炭素が出るように、体を動かせば疲労物質がつくられるからです。同様に脳でも、神経性の疲労物質がつくられます。それらが日々の入浴や睡眠などで代謝されれば問題ないのですが、忙しい現代社会ではうまく休むことができず、どうしても疲労が蓄積されてしまいます。
疲労が体にたまると筋肉はかたく縮み、脳や内臓にも悪影響を与えてしまいます。また、筋肉がかたく縮むと体の動きが悪くなるため、血流や代謝も滞ってしまいます。そして、そうしたなかで日々頑張って生活すると、ますます疲労が蓄積し、体の動きが悪くなるという「疲労の悪循環」に陥ってしまうのです。
疲労の蓄積を止めるには?
では、この疲労の悪循環を断ち切るには、どうすれば良いのでしょうか? それには、「疲労の蓄積を解消すること」と「疲労しないように上手に体を使うこと」の2つが重要です。
疲労の蓄積を解消する
疲労がたまっている体は、筋肉がかたく縮んでしまっている状態です。そのため、正しい姿勢を意識した程度で、肩こりを改善するのは難しいでしょう。また、運動しようとしても疲れているので長続きしませんし、けがもしやすいので、かえって悪化してしまうおそれがあります。
だからこそ、まずはひどい肩こりのもとである疲労を除去しなければいけません。疲労が抜ければ、筋肉は柔らかく伸び伸びとした状態に戻ります。また、脳や内臓の働きも円滑になり、疲労が代謝されやすくなるでしょう。姿勢に気をつけたり、運動を始めたりするのは、それからで良いのです。
疲労しないように上手に体を使う
では、どうすれば疲労がたまらない体がつくれるのでしょうか。多くの方は体を何となく動かして、日常を過ごしていると思います。しかし、そうした体の使い方をしていると、疲労を除去してもすぐにたまってしまい、再び肩こりが発生します。 一方、体の仕組み通り適切に動かせるようになれば、日常生活でそんなに疲れることはありません。つまり、疲労しない体の使い方を覚えることが、肩こり解消にはとても重要なのです。
ひどい肩こりを3日で解消する3つの体操

肩こり解消には、「疲労を除去して、体を上手に動かせるようになること」が大切だとおわかりいただけたところで、ここからは、肩こりを改善するための体操をご紹介します。 さっそく体操のやり方を……。といいたいところですが、その前に肩の仕組みについて、簡単に説明させてください。
肩の仕組みを知って体を上手に動かす
みなさんは、腕はどこから始まっているかご存知ですか? 脇のあたりからだと思っている方が多いかもしれませんが、実をいうと、腕は鎖骨のあたり(胸鎖関節・きょうさかんせつ)から始まっています。

試しに、片手で鎖骨を触りながら、腕を前後上下に動かしてみてください。鎖骨も前後上下に動いているのが分かると思います。このように腕は、鎖骨を基点とした自由度の高いパーツなのです。
そして、「腕は自由に動くパーツである」ということを意識しながら生活すると、体の仕組みの通りに多くの筋肉を使えて、負担が少なく疲れにくい動きができるようになります。
では、実際に体を動かしていきましょう。
ご紹介するのは、疲れを解消する「関節ほぐし」「じっくり伸ばし」「ふわふわゆるめる」の3種類の体操です。この3つを行うことで、疲労を徹底的に除去することができ、体の上手な動かし方も習得できます。
なお、実際に体操をする際は、嫌な痛みがあればストップし、やっていて気持ちがよければ続けるという具合に、体の声に耳を傾けながら行ってください。くれぐれも無理をしないことが大事です。
解放体操「関節ほぐし」で肩だけをほぐす
「関節ほぐし」は、関節や関節まわりの筋肉をほぐす体操です。これを習慣化することで、骨格の仕組み通りに関節を動かせるようになりますよ。
ちなみに、この体操では肩だけをほぐすこともできます。肩こりの方は、腕を後ろに動かす動作が特に苦手な傾向がありますので、焦らずゆっくりほぐしていきましょう。
「関節ほぐし」のやり方

1. 体の前で手のひらを合わせ、手首から肘までをくっつける。
2. 両手の親指のつけ根が離れないように、両手首をねじって手のひらを前方に向ける(これがスタート位置。脇や腕がやや窮屈に感じることでしょう)。

4. 3と同じ要領で、左腕を下から上に向かって大きく3回まわす。
5. 右腕も同じように、上から下、下から上へと3回ずつまわす。

・腕をまわすときに、体がつられないように注意しましょう。
・痛みの少ない範囲で動かし、日々くり返しながら徐々に大きく動かしていきましょう。
<期待できること>
肩や肩甲骨の可動性の向上、肩こりの改善、滑らかな腕の動き
解放体操「じっくり伸ばし」で胸や肩、腕、手指を一気に伸ばす
「じっくり伸ばし」は、疲労により縮んだ筋肉を伸ばし、疲労物質の代謝を促す体操です。体の中心部分である体幹と手足の末端を同時に動かすことで、身体感覚を養うことにもつながります。
個々の筋肉を伸ばすストレッチとは異なり、胸・肩・腕・手を一度に連動させて伸ばせるのも「じっくり伸ばし」の特徴です。肩こりの原因箇所はさまざまですが、網羅的にアプローチすることで、一度に歪みを補正することができるでしょう。
「じっくり伸ばし」のやり方


1. 正座で座る(あぐらや椅子に座って行ってもOK)。
2. 胸を反らしてから、後ろで指を組む。手のひらを背中側から下へ返し、手の甲を上に向けてポーズを取る。このとき、肩甲骨が寄っているのを意識するのがポイント。


3. 10秒ほど息を吐く→素早く息を吸う。これを3回くり返す。
4. 姿勢を戻して一息つく。
5. 胸をすぼめてから、体の前で指を組んで、手のひらを下から前に返してポーズを取る。このとき、肩甲骨が開いているのを意識すること。


6. 3回呼吸しながら、腕を前に伸ばす。
7. 姿勢を戻して一息つく。
8. 胸を反らせるポーズと、胸をすぼめるポーズのうち、やりにくい方をもう一度行う。




明清彩® 道主
身体開発専門家
松原 武司先生
・やりにくい方を多く行うことで、歪みを解消できます。
・目をつぶって行うと、より深い伸びを感じられます。
<期待できること>
首・肩・肩甲骨の柔軟性の向上、首こり・肩こりの改善、巻き肩・肘の故障・ばね指の改善、猫背や反り腰の姿勢改善、喘息や呼吸機能改善、バストアップ、明るい表情、落ち着き、ストレス解消
解放体操「ふわふわゆるめる」で代謝を促進させる
「ふわふわゆるめる」は、疲労によってかたくなった筋肉や神経、血管をゆるめて、代謝を促す体操です。
前項の「じっくり伸ばし」だけでは、体は緊張したままです。この体操でふわ〜っと力を抜いて、体を休息モードに切り替えましょう。特に、緊張しがちで肩に力の入りやすい方は、積極的に体をゆるめることでストレスも解消され、眠りやすくなります。
「ふわふわゆるめる」のやり方


1. 左を下にした状態で横向きに寝て、右腕を上げる。
2. 右手首を円を描くように振りながら、腕や肩をゆっくり5秒ゆらす。
3. 左腕も同様に行う。




明清彩® 道主
身体開発専門家
松原 武司先生
・肩や肘を軽く曲げるとゆらしやすくなります。
・ふわ〜っと力が抜ければOKです。
<期待できること>
肩・肩甲骨・腕・指の疲労除去、手技の能力向上、自律神経の調整、血流・代謝向上、安眠
生涯、ひどい肩こりにならないための方法


3つの体操を数日くり返すだけでも、肩こりはかなり楽になります。しかし、前述したように、生きている以上は疲労が生まれますし、放置すればまた肩こりになってしまいます。「こりが楽になったから、もうOK」では、いつまでたってもこりから解放されません。
重要なのは、体をつくり直して自由に動けるようにしておくことです。体が本来の能力を発揮できるように、すっきりとした状態をつくってしまえば、少々のこりや疲れならすぐにリセットできます。また、生涯にわたって、身軽でクリアな身体感覚を保つことにもつながるでしょう。
とはいえ、そこまで体をつくり直すには、長期間の反復・継続が必要です。なかには「継続が苦手」という方もいると思いますので、そんな方には、体操を日々の生活に組み込んでしまうことをおすすめします。以下では、3つの解放体操を日常のなかで効果的に行うコツをお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
朝の「関節ほぐし」で疲れにくい身体感覚をセット
寝起きのとき、体はかたまっている状態なので、そのまま日常生活をスタートさせると、何となく体を使うことになってしまいます。そこでおすすめしたいのが、朝に「関節ほぐし」をすることです。「関節ほぐし」を行えば、疲れにくい身体感覚がセットされ、1日中快適に動けるようになるでしょう。
また、自律神経が交感神経優位にシフトして、体がすっきりと目覚めるため、1日を元気よくスタートさせることができます。
昼の「じっくり伸ばし」でこまめに疲労除去
日中、「ちょっと疲れたな」と感じたときには「じっくり伸ばし」を行いましょう。疲労が取れるだけでなく、ちょっとした気分転換にもなるはずです。
また、こまめに体操すれば、それだけ筋肉を伸ばす回数が多くなるので、柔軟性も上がり早く効果が出ます。
夜の「じっくり伸ばし」と「ふわふわゆるめる」で1日の疲れをリセット
お風呂上がりで体が温まったときや寝る前に、「じっくり伸ばし」と「ふわふわゆるめる」を行うと、疲労のリセットに効果的です。寝る前の体操で力を抜いておくと、自律神経が副交感神経優位にシフトし、代謝・修復が促されるからです。
どの体操も2分以内でできますが、なかなか継続できない方は、「最初は朝だけ」というように、1つずつ始めるのが良いでしょう。3日続ければ、ひどい肩こりでも十分楽になるはずです。 その後も、引き続き朝の体操を3週間行い、自分のなかで「体操するのが当たり前」になったら、他の時間帯の体操を増やしてみてください。そうやって段階を踏むことで、無理なく習慣化できるでしょう。
まとめ
今回は、ひどい肩こりを改善する方法として、「疲労の蓄積を除去すること」と「疲労しないように上手に体を使うこと」の2つをお伝えしました。ご紹介した3種類の解放体操を少しずつ日常生活に取り入れて、肩こり知らずの体を目指しましょう。
今は肩こりがつらい状況かもしれませんが、だからこそ「体を変えていこう」という気持ちを持つことが大事です。自分を変えていく気持ちがあれば、体は必ずよくなっていきますよ。
自分の体を信じて、毎日コツコツと体操を実践してみてください。この記事が、みなさんの健康のお役に立てば幸いです。
<参考文献>
鶴田 聡.仙骨理論 パート1.たにぐち書店,2003
月刊「秘伝」編集部【編】.天才・伊藤昇と伊藤式胴体トレーニング「胴体力」入門.BABジャパン出版局,2006.
ブランディーヌ・カレ-ジェルマン.新 動きの解剖学.科学新聞社,2009
高岡 英夫.脳と体の疲れを取って健康になる 決定版 ゆる体操.PHP研究所,2015
イラスト:たいらさおり