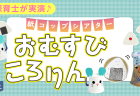書籍紹介『チューくんといっしょ せいかつのおはなし』 子どもの「やりたい気持ち」がぐんぐん育つ魔法の一冊
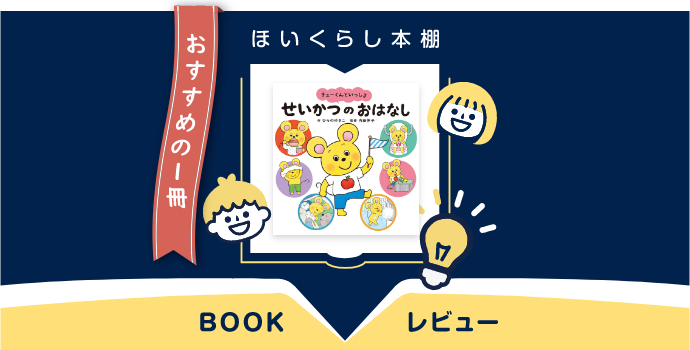
今回ご紹介するのは、小さな子どもが生活の基本を学ぶのにぴったりな一冊『チューくんといっしょ せいかつのおはなし』(ポプラ社)です。「はみがき」「トイレ」「かたづけ」など、全部で8つの生活習慣は、どれも絶対に押さえておきたいものばかり。
監修は、発達心理学、認知心理学の専門家で、お茶の水女子大学名誉教授、学術博士、文化功労者の内田伸子先生。イラストは「おばけのやだもん」シリーズ、「おべんとうばこのぱっくん」(ともに教育画劇)などを手がける、絵本作家として活躍する、ひらのゆきこさんです。
1日の流れに沿って物語が進む生活絵本『チューくんといっしょ せいかつのおはなし』とは?
この絵本の主人公は、かわいらしいねずみの男の子「チューくん」です。おはようからおやすみまで、チューくんの1日の流れに沿って、生活習慣にまつわる短いエピソードと身につけるコツ、保護者に向けた役立つコラムをコンパクトにまとめています。各トピックは次の8つ。「おはよう」から「おやすみ」まで、子どもたちはチューくんの物語に自分を重ね合わせて読み進めることができます。
- おはよう
- きがえ
- トイレ
- はみがき
- てあらい・うがい
- かたづけ
- おふろ
- おやすみ
小さい子どもは、いくら大人が「あれしなさい」「これしなさい」といっても、「どうして身につけなければいけないのか」という理解に結びつけることができません。そのため、毎日同じことを何度も繰り返したり、できない子どもを叱ったり、「教え方か悪いのかな…」と自己嫌悪に陥ってしまったりと、大人の方が疲弊してしまうのです。みなさんも、保護者の方から「生活習慣がなかなか身につかない」という相談を受けることが多いのではないでしょうか。
子どもが生活習慣を身につけるためにまず必要なのは、「いつ・何を・どのようにやるのか」また、「それは何のためか」を、イメージできるようになること。理屈だけを教えるのではなく、自然な共感を持って理解できるよう、導くことが大切です。
引用:『チューくんといっしょ せいかつのおはなし』(作・ひらの ゆきこ 監修・内田 伸子/ポプラ社)
ーー「はじめに」より
「チューくんのパパやママ、妹のチェリちゃん、チューくんのお友だちなどと、かかわりあい、対話し、いっしょにあそびながら、いつのまにか生活習慣が身についていくことを願って、生活絵本をつくりました」
と話すのは、本書を監修したお茶の水女子大学名誉教授の内田 伸子先生。長年にわたり「こどもちゃれんじ」の監修に携わり、発達心理学を専門とする内田 伸子先生ならではの楽しいしかけが満載です。
子どもがまねしたくなるとっておきの工夫とは?
POINT①「あそび」
おはなしの中に、楽しくあそべるアクティビティを取り入れています。朝から元気いっぱいなチューくんの動きをまねした「たいそうやってみよう」、たくさんのパターンの洋服を組み合わせられる「チューくんのきたいふくどれかな?」など、子どもも大人も一緒に楽しめるあそびが満載!
POINT②「オノマトペ」
「シャキーン!」「シュコシュコシュッ!」など、動作を表す言葉やかけごえになる言葉を強調して描いています。実際の生活の中でも、同じ動作をするときに使ってみると楽しいですね。
POINT③「ずかん」
おはなしの中で扱いきれなかった、関連するものや動作を「ずかん」ページで紹介しています。「いろいろなおトイレの仕方があるね」「奥歯を磨くときには口を大きくあけたらいいんだね」など、会話をしながら読み進めると◎。登場するほかの動物たちの個性もしっかりと描かれているので、どんなお子さんでも共感できる内容になっています。
POINT④「ポーズ」
各章の終わりに、チューくんがポーズをしているので、 生活習慣が身についたら、キメポーズで「できたよ!」をアピールをしてもらい、「できたね」と声をかけるなど、実生活に取り入れると楽しいですね。
POINT⑤「おうちの方へ」
「おうちの方へ」コラムでは、科学的な根拠に基づいた内容をわかりやすく、丁寧に説明。子どもとのかかわり方や成長の目安など、ポイントを押さえて理解することができます。保護者の方から相談を受けた際にも、このコラムを参考にアドバイスしてみてもいいですね。
コロナ禍の“いま”知っておきたい情報が満載!
コロナ禍において、これまで以上に子どもたちの衛生意識を高めることが求められています。保育園でも、徹底した衛生習慣を身につけさせるためにさまざまな工夫をしているのではないでしょうか。本書の「てあらい・うがい」の項目では、バイキンの怖さや、手洗い・うがいの大切さが子どもに伝わりやすい表現で描かれています。ぜひ保育園でも活用してみてくださいね。