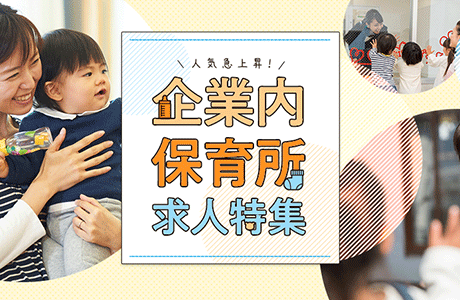パソコンやスマートフォンの普及で字を書く機会が減った現在、書道人口は昭和の時代の4分の1にまで減っているといわれます。しかし、2020年8月に実施された学研教育総合研究所による子どもの習い事調査をみると、習字と書道はTOP10(それぞれ8位、9位)に入っており、いまだに“人気の習い事”のひとつであることも事実です。ここでは、多様化の時代にあってもなお求められ続ける、「書道の魅力」に迫るべく、東京・広尾と横浜で宙 書道院を主宰する、書道家の並河博子先生にお話を伺いました。
文:保育ライター 長野真弓
書道をはじめるのは、早ければ早いほうがいい
——素朴な疑問なのですが、習字(書写)と書道は何が違うのでしょうか?
簡単に説明すると、正しく整った字を書けるように学ぶのが習字(書写)。それを立体的に、自己表現として作品にしていくのが書道です。
——小学校で学ぶのは習字のほうだと思いますが、小さいお子さんでも書道を学ぶことはできますか?
もちろんです。小さいお子さんの場合は、まずはお手本の形をまねして、きれいな字を書くことからはじまります。とはいえ、最初のうちは、お稽古で習った字は上手に書けるのに、教えていない字はうまく書けなかったりするもの。字を覚えて、応用できるようになるには、繰り返しの練習が必要で、それだけ時間もかかります。ですから、書道を習いはじめるのであれば、できるだけ早いほうがいいですね。いまは、就学前に字を覚えることも多いでしょうから、字を学びはじめるタイミングでお習字もはじめると、最初から美しい字の形を認識することができるでしょう。
——先生ご自身は、何歳から習いはじめたのでしょう。いいはじめどきはありますか?
私は6歳からです。性に合っていたようで、休むことなく通い続けて、ふと気がつくと大学生になっていました(笑)。一時、海外で暮らしていたのですが、そのときは「書道を教えることで、他国に日本文化を広める」という貴重な体験もでき、書道をはじめるきっかけをつくってくれた両親にはとても感謝しています。
はじめどきとしては、親が「自分の字には自信がないけれど、子どもにはきれいな字を書いてほしい」と思ったときが、いいかもしれません。小さい子は何かと親を見て、親のまねをして育ちますよね。字だって同じで、子どもは親が書いている字を「正しい」と思います。ですから、親が「自分のまねをしないで、きれいな字を学んでほしい」と感じたときが、いいはじめどきになるのです。
日本では、昔から「書は人なり」といいます。つまり、字はその人をあらわすものであり、字を美しく書くことは教養のひとつともされているのです。そして、字を書くことが減ったいまでも、それは変わっていないように感じます。その証拠に、「きれいな字ですね」は変わらずほめ言葉ですよね。だから、書道教室に通われる方がいまだに少なくないのだと思います。
人としての成長を促すための書道の手ほどきとは?

——子どもの頃から習字あるいは書道を学ぶメリットについては、どうお考えですか?
書道を含め、茶道、武道、華道といった「道」がつくものは、すべて作法を通して、精神性、生き方を学ぶ、日本古来の文化です。美しい字を書けるようになることは、もちろん大きなメリットですが、それ以外にも「集中力がつく」「お作法を学べる」「達成感から自信がつく」「道具を大切にするようになる」「相手を尊重できるようになる」など、生活面や精神面のメリットも少なくありません。私が主宰する教室にも、お稽古をはじめた頃はじっとしていられなかったのに、徐々に集中力がつき、日常生活も落ち着いてきた男の子がいます。もちろんいまも、楽しそうに通ってくれていますよ。
——子どもたちを指導するうえで、気をつけていることはありますか?
私が指針としているのは、「北風と太陽」の話です。厳しく言いきかせるのではなく、自分で気づいて行動できるように、自主性を促すように働きかける——。そのことを常に心がけていますね。
その根底にあるのは、私の大切にしているポリシーである「ぶるな。らしくあれ」です。「先生ぶるな。先生らしくあれ」「母ぶるな。母らしくあれ」といった考え方もその一例で、それが書道の場だけではなく、人としての基盤だと思っているんです。書の世界では、師として多くのお弟子さんを指導していますが、お弟子さんだからといって、人としてのリスペクトを忘れてはいけません。お子さんであれ、大人のお弟子さんであれ、基本的に接するスタンスは同じ。もちろん、私がお弟子さんたちから何かを学ぶ機会もたくさんあります。
加えて、もうひとつ意識していることがあります。「新しい書道のかたち」です。「道」がつく習い事は、上下関係にも厳しいですが、作法や尊敬の念は守りつつも、古い価値観から脱却して、新しいことにも積極的にチャレンジするようにしているんです。そうすることで、多くの人に書道を身近に感じていただけたら、とてもうれしいですね。
——そういえば先生の教室では、年賀状やうちわに墨やカラフルな絵の具を使って、好きな字を書く時間があります。見ていると、みなさん自由にのびのびと書いていて、とても楽しそうですよね。
そうなんです。「新しい書道のかたち」を追求するうえで、何より大切にしているのは「とにかく楽しく書いてほしい」ということ。そのためにも、自由に創作活動を行う時間は、非常に大切なのです。といっても、自由に書いているように見えて、作品制作の基本はしっかり学んでもらっているんですよ。校正や余白の取り方、主役と脇役の配置、コンセプトの伝え方など、書道のさまざまな学びが、あの楽しい時間の中に詰まっているんです。
幼少期にはじめるなら、まずは筆に慣れることから

——保育士さんや親が子どもにお習字を手ほどきする際のコツがありましたら、教えてください。たとえば、「墨を使うと部屋を汚されそう」と心配される方もいらっしゃると思うのですが、そんなときは「水書きタイプ」を利用してもいいのでしょうか?
お習字をはじめるきっかけとして、水書きセットを利用するのはいいと思います。筆に慣れたり、字の形を学んだりする練習にはなりますから。でも、できることなら墨を使って書いてほしいですね。墨を使って、墨や筆の表現力を体感してほしいです。
——まだ字が書けないお子さんでもできることはありますか?
まずは、筆に慣れることからはじめてみてください。そして、クレヨンや色鉛筆などの硬筆とは違う、筆の柔らかいタッチを知り、その感覚を覚えてもらいましょう。筆はいろいろな表現ができて、毛先だけで書けば細い線、強く書けば太い線が書けます。また、墨の量や濃度でにじんだり、かすれたりもします。もちろん、字を書けるようになるまでは、お絵かきと同じ要領で大丈夫。筆で線を自由に書くことが、お習字のいいウォーミングアップになると思いますよ。
——声かけなどの対応についてもお聞かせください。先生の指導を拝見していると、「わぁ、元気よく書けたね!」「この線がすごくいい!」など、まずはいいところを思い切りほめていらっしゃいます。
どんなものを書いたとしても、最初はいい点を見つけてほめてあげる。これがいちばん大切です。とにかく楽しく書いてほしいので、怒らず、大らかに見守ってあげてほしいですね。アドバイスをするならそのあと。ほめてから、アドバイスをすることで、子どもは素直に大人のいうことを受け入れられるようになるんです。
——確かに……。先生の言葉を聞いて書き直し、すぐにまた意気揚々と先生に見てもらいにいく楽しそうな子どもの姿が印象に残っています。では最後に、保護者や保育士の方々にメッセージをお願いします。
昨年からコロナ禍にあって、非常事態が続いていますが、1日24時間という時間は、誰もが平等にもっているもの。子どもたちには、その時間を上手に使って自分を磨き、感性豊かな人になってほしいと願っています。そして、そのひとつの方法が、書道であってくれるとうれしいなと思います。
字を書くことが少なくなった時代だからこそ、美しい字を書くことの価値は高まっているともいえます。人としての成長と、日本の素晴らしい文化体験の両方をかなえるのが、書道の魅力。また、書道での学びは日常生活の場でもきっと生かされます。まずは、気軽に筆を手にとってみてはいかがでしょうか。
[参照]学研教育総合研究所|白書シリーズWeb版|小学生白書|2020年8月調査|
白百合女子大学文学部英文科卒業後、20代は全日空国際線CAとして勤務し、30代は子育てをしながら
中東(イラン、UAE)での生活を経験。40代で書道界に本格復帰する。
現在横浜の自宅、東京広尾にて書道教室を主宰。
宙書道院 https://www.hirokonamikawa.com