【8月のぬりえ①】夏休み
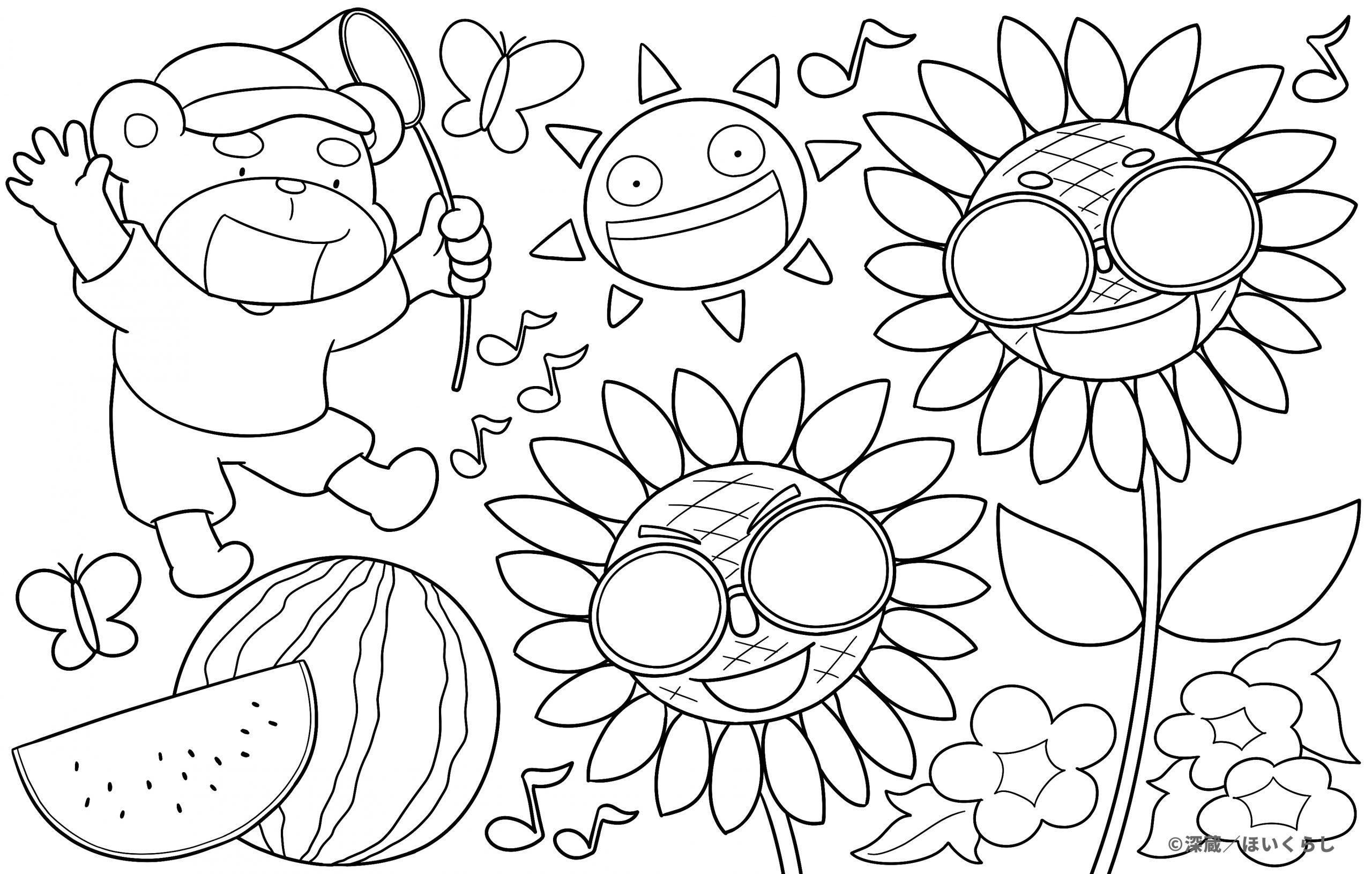
みなさんは「夏休み」と聞いて、何を思い浮かべますか? 海水浴にプール、花火大会、お祭り……。夏にはいろいろな楽しみ方がありますが、「夏の風物詩といえば、やっぱりお盆」という方も多いのではないでしょうか。
でも、あらためて考えてみると「お盆」というのは、不思議な言葉ですよね。一体どうやって生まれて、どんな意味を持っているのでしょう。
お盆の正式名称は「盂蘭盆会」といい、次のような仏教の説話に由来しています。
ある時、お釈迦様の弟子の一人である目連は、神通力で亡き母が地獄に落ちて苦しんでいることを知ります。悲しんだ目連が「どうしたら母親を救えますか」とお釈迦様に相談すると、お釈迦様は「夏の修行を終える7月15日に、すべての修行僧に供物をささげれば母親の供養になる」と伝えました。そして、言葉に従って日蓮が僧侶たちに食べ物や飲み物、寝床などを捧げると、その功徳によって母親は救われ、無事に極楽往生を遂げたのだそうです。
以来、先祖をもてなして供養する盂蘭盆会の行事が生まれ、それが日本古来の先祖を敬うお祭り(=祖霊祭)と結びついて、お盆という風習になったとされています。 なお、お盆はもともと旧暦7月15日前後の行事でしたが、明治時代の改暦後は新暦の8月15日前後に行う地域が多くなり、13日の夕方に先祖の霊を迎えて供養し、15日の夕方または16日に送るのが一般的な習わしとなっています。
[参考]
『12ヶ月のしきたり 知れば納得!暮らしを楽しむ』(新谷尚紀/PHP研究所)
『子どもにつたえたい年中行事・記念日』(萌文書林編集部編/萌文書林)
イラスト/深蔵
ぬりえ素材のダウンロードはこちらから
■7月のぬりえ
【7月のぬりえ①】七夕
【7月のぬりえ②】海の日
【7月のぬりえ】0〜2歳 七夕飾り
【7月のぬりえ】3~4歳 夏の野菜を食べよう
【7月のぬりえ】5~6歳 たのしい夏祭り
■8月のぬりえ
【8月のぬりえ②】盆踊り








