【8月のぬりえ②】盆踊り
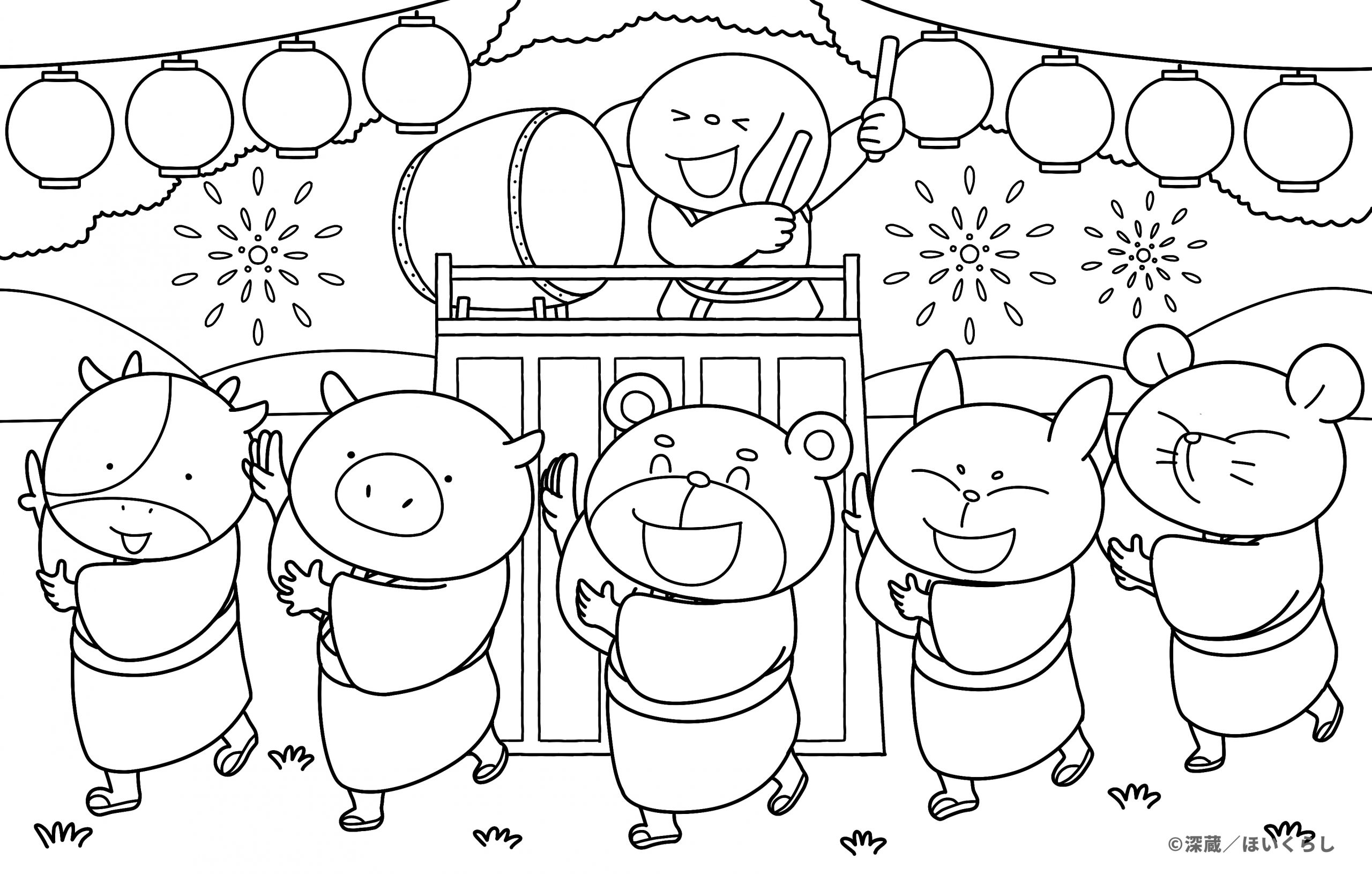
毎年、お盆の頃になると、寺や神社、公園などで盆踊りが開催されます。浴衣姿の踊り子がやぐらを囲んで踊ったり、屋台でわたあめやかき氷を買って食べたり……。その光景は、まさに「日本の夏」といった感じですよね。
ところで、みなさんは盆踊りにどんな意味が込められているかをご存じですか?
実をいうと、盆踊りは単なる踊りではなく、お盆の時期にお迎えした先祖の霊をにぎやかな踊りでなぐさめ、再び送り出すための神聖な行事です。その原型は、鎌倉時代に一遍上人が広めた「念仏踊り」(集団で「南無阿弥陀仏」を唱えながら踊る民俗芸能のこと)で、それがお盆の先祖供養と結びついて、今の姿になったといわれています。
また、盆踊りには「先祖を供養する」だけでなく、「地域の住民が集まって交流を深める」という意味合いもあります。老若男女が一緒になって踊り、会話を楽しむ。あるいは、お盆休みを利用して帰省した旧友と再会する。そんなシーンがあちこちで見られる盆踊りは、地域の絆を深める格好の催しなのです。
現在は、8月15日に盆踊りを行う地域が多いですが、かつて盆踊りが行われていたのは旧暦の7月15日。この日の晩は満月にあたるため、照明がなくても周囲が明るく照らされていたそうです。月明かりの下、浴衣姿で踊りを楽しむなんて、とても素敵だと思いませんか?
[参考]
『12ヶ月のしきたり 知れば納得!暮らしを楽しむ』(新谷尚紀/PHP研究所)
『子どもにつたえたい年中行事・記念日』(萌文書林編集部編/萌文書林)
『文化デジタルライブラリー』
イラスト/深蔵
ぬりえ素材のダウンロードはこちらから
■7月のぬりえ
【7月のぬりえ①】七夕
【7月のぬりえ②】海の日
【7月のぬりえ】0〜2歳 七夕飾り
【7月のぬりえ】3~4歳 夏の野菜を食べよう
【7月のぬりえ】5~6歳 たのしい夏祭り
■8月のぬりえ
【8月のぬりえ①】夏休み








