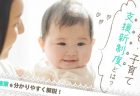子どもの権利条約とは?条文の内容をわかりやすく解説

保育士を目指すために日々学んでいる人の中には、「子どもの権利条約」という言葉を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。子どもにも基本的人権があることを定めた子どもの権利条約は、保育の仕事に携わりたいと考えている場合に知っておきたい項目の1つです。
今回は、子どもの権利条約についてわかりやすく解説します。子どもの権利条約が発効されるまでの流れや、日本国内における批准後の動きについても紹介するため、保育の仕事を目指す人や携わっている人は参考にしてください。
子どもの権利条約とは?
子どもの権利条約とは、子どもが一人の人間として基本的人権を所有し、行使する権利を保障するための条約です。世界中のすべての子どもが健康に生きて存分に学んだうえで自由に活動し、大人や国から守られ援助されながら成長する権利があると定めています。
子どもの権利条約は1989年の国際連合総会において採択され、1990年に国際条約として発効しました。2019年2月の時点で、子どもの権利条約は196の国と地域で締約されています。なお、アメリカ合衆国は1995年に署名したものの、いまだ批准はしていません。日本は1990年に署名し、1994年に批准しました。
(出典:unicef「子どもの権利条約」)
(出典:unicef「教えてユニセフ 子どもと先生の広場」)
1. 子どもの権利条約が定める「4つの権利」
子どもの権利条約は、各条項で規定されている内容ごとに大きく4種類に分類することができます。下記は、各権利の概要とその権利の根拠となる条文をまとめた表です。
| 生きる権利 子どもの命が守られ、健康かつ人間らしい生活を送ることができる権利です。 |
|---|
| <第24条>子どもは、病気やケガの治療に必要な保健サービスを受ける権利と、大人たちの都合や伝統的な儀式などで健康を害されない権利を持ちます。 <第27条>保護者の力のみで心身の健やかな成長が望めない場合は、国から金銭や教育の支援を受ける権利を持ちます。 <第38条>戦争に巻き込まれた子どもの救出・保護のために、国ができることはすべて行う必要があります。また、15歳以下の子どもを入隊させてはなりません。 |
| 育つ権利 子どもが自分たちの持つ才能を伸ばし、心身共に健康に成長できる環境が整備され、保証される権利です。 |
|---|
| <第17条>子どもは、国内外のあらゆるメディアから人生に有益な情報・資料を入手する権利と、有害な影響を及ぼす情報から守られる権利を持ちます。 <第23条>心身の障がいの有無にかかわらず、人としての尊厳が保たれたまま自立して社会生活を送るために必要な、教育・訓練・保健サービスを受ける権利を持ちます。 <第28条>すべての子どもが小学校へ無償で通い、中学校以上の教育を受けたい者には実力に応じた機会を得る権利を持ちます。また、学校の規則は子どもの尊厳を傷つけるものであってはなりません。 |
| 守られる権利 子どもがあらゆる暴力・虐待・搾取から守られ、幸福に生きられる権利です。 |
|---|
| <第19条>保護者の養育下において、子どもが心身への虐待を受けなくて済むように国から守られる権利を持ちます。 <第32条>子どもが労働を強要されて学べなくなることや、心身に有害な仕事を押しつけられることがないよう、国から守られる権利を持ちます。 <第36条>子どもは、利益を得るために子どもの幸せを奪おうとするあらゆる出来事から、国に守られる権利を持ちます。 |
| 参加する権利 子どもの意思が尊重され、他人の権利を侵害しない範囲で自由に発言や活動ができる権利です。 |
|---|
| <第12条>自分に関わる事柄について自己の意見表明権を持ち、年齢や精神の成長に則って対応される権利を持ちます。 <第15条>平和的・道徳的と認められる範囲において、団体活動を行ったり集会を開いたりする権利を持ちます。 <第31条>長期休暇や課外時間などは、子どもの年齢や体力に応じて勉強・遊び・休息を自由に選択でき、文化芸術活動に参加できる権利を持ちます。 |
2. 子どもの権利条約における「4つの原則」
子どもの権利条約では、18歳未満を子どもとして定義しています。子どもの年齢にかかわらず、すべての子どもが平等に大人と同じ人間として扱われ、主体的に生きる権利を持つ存在として定めています。
しかし、大人への成長段階にある子どもは身体的・精神的に未熟であり、経済力が備わっていません。弱い立場の子どもが自立できるまでに十分な配慮や保護が必要なため、子どもの権利条約には子どもならではの権利も盛り込まれています。
下記の「4つの原則」は、子どもの権利条約における根源的な理念です。
●生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
(引用:unicef「子どもの権利条約」)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
●子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。
●子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
●差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
また、子どもの権利条約では、子どもの権利を守る責任は保護者が負うべきであると定めています。国は保護者が子どもの権利を守れる環境や法律を整備し、それでも保護者の力が及ばない場合は子どもの利益を最優先に考えて動かなければなりません。
3. 子どもの権利条約に関する「3つの選択議定書」
子どもの権利条約には、前文と全54条の本文のほかに「3つの選択議定書」が設けられています。3つの選択議定書は、子どもの権利条約を締約した国が個別に批准するか否かを選択できる、独立した議定書です。この3つの選択議定書は、既存の条約を実施するにあたって、条文の内容を補強したり追加したりする目的で作成されました。
| 子どもの売買、子ども買春および子どもポルノに関する子どもの権利に関する条約の選択議定書 | |
|---|---|
| 子どもに対する人身売買・性的搾取の禁止と、違反者の取り締まりや罰則強化を定めています。 | |
| 発効:2002年1月 | 日本の批准:2005年1月 |
| 武力紛争における子どもの関与に関する子どもの権利に関する条約の選択議定書 | |
|---|---|
| 第38条において15歳と定めている子どもの入隊可能年齢を、18歳に引き上げます。 | |
| 発効:2002年2月 | 日本の批准:2004年8月 |
| 通報手続に関する子どもの権利条約選択議定書 | |
|---|---|
| 子どもの権利条約および上記2議定書の締約国が子どもの権利を侵害した場合に行える、子どもの権利委員会に対する通報・調査手続きの制度について定めています。 | |
| 発効:2014年4月 | 日本の批准:- |
子どもの権利条約の内容
子どもの権利条約には、すでに紹介した条文のほかにも次のような内容の条文が記されています。ここでは、子ども権利条約の内容をわかりやすく噛み砕いて説明します。
<第1条>
条約では、18歳未満のすべての人を子どもと見なします。ただし、法律などによって18歳未満でも成人と見なされている人を除きます。
<第2条>
国は、人種、肌の色、性別、言葉、宗教、政治的意見、社会的出身、財産、障害などを理由に子どもや保護者を差別せず、あらゆる方法で子どもの権利を守ります。
<第3条>
国が子どもに関係する措置を実行する際は、子どもの利益を最優先します。子どもをきちんと保護・養護できるようにするため、父母や法定保護者の権利と義務も考慮します。
<第4条>
国は立法・行政をはじめとするあらゆる分野において、子どもの権利の実現に向けて行動します。国が子どもの権利を守ることが難しい場合は、必要に応じて国際協力を得ます。
<第5条>
国は、子どもが自らの権利を行使するときに、父母や法定保護者などが適切に指導する責任・義務・権利を尊重します。
<第6条>
すべての子どもは、生きる権利と成長する権利を持ちます。国は、子どもの生きる権利と成長する権利を最大限守ります。
<第7条>
子どもが誕生したら、すぐに出生届を出します。子どもは生まれたときから名前と国籍を持つ権利、そしてできる限り自分の父母を知り、父母に養育される権利を持ちます。
<第8条>
国は、子どもが国籍・氏名・身元などについてむやみに干渉されないよう守ります。もし子どもが身元などを不法に奪われた場合、国は子どもの身元などをすみやかに回復させるよう努めます。
<第9条>
国は、子どもが父母と引き離されないよう守ります。父母の別居や父母による虐待・放置などがある場合はこの限りではないものの、国は子どもと父母が定期的に会ったり関係を維持したりする権利を尊重します。
<第10条>
父母と異なる国に住んでいる子どもは、定期的に父母と会ったり関係を維持したりする権利を持ちます。国は、子どもと父母が会うことを目的として自由に出入国する権利を尊重します。
<第11条>
国は、子どもがむやみに国外へ連れ去られたり、自国へ戻れない状況になったりしないよう努めます。
<第13条>
子どもは、あらゆる情報や考えをさまざまな方法で知ったり伝えたりする権利を持ちます。ただし、人々の安全・健康・道徳などを守る目的でこの権利に一定の制限をかけることができます。
<第14条>
国は、子どもの思想・良心・宗教の自由に関する権利を守ります。人々の安全・健康・道徳などを守るため、宗教や信念を表現する自由については法律に従って制限をかけることができます。
<第16条>
すべての子どもは私生活・家族関係・住居・通信に対してむやみに干渉されたり、名誉や信用を傷つけられたりするべきではありません。
<第18条>
子どもの養育・発達についてはまず父母が共同で責任者となり、国はこれを守るために最大限努力します。また、国は父母および法定保護者のための子育て支援をします。
<第20条>
家庭環境を奪われた子どもやその家庭環境にとどまるべきでないと判断された子どもは、国から特別な保護や援助を受けることができます。その際、国は子どもの種族・宗教・文化的背景などについて十分配慮します。
<第21条>
国や公的機関が子どもの養子縁組を認める際、子どもの最善の利益について最大限考慮します。その際は父母や親族などの状況と照らし合わせて養子縁組が適切かどうかを確認し、国内養子縁組が難しい場合は国際養子縁組も考慮します。
<第22条>
国は、難民として国外から自国へ逃れてきた子どもに対して適切な保護や援助をします。その際、子どもが父母などに付き添われているかどうかは問いません。
<第25条>
国は子どもの収容施設における子どもへの処遇や施設の状況などを把握するため、施設に対して定期的に審査を行います。
<第26条>
すべての子どもは、社会保険およびその他の社会保障から給付を受けることができます。この給付は、父母や法定保護者の経済状況などに応じて決定されます。
<第29条>
子どもに対する教育指導の目的は、子ども自身の才能や能力を最大限伸ばすこと、人権・自由・環境を尊重すること、自国や他国の文化・言語・価値観を尊重することなどです。
<第30条>
少数民族・原住民ならびに宗教的・文化的な少数者グループに属する子どもは、自らの文化・宗教・言語などを保持する権利を持ちます。
<第33条>
国は、麻薬・覚せい剤・向精神薬などの不正利用や生産・取引から子どもを守るためにあらゆる手を尽くします。
<第34条>
国は、売買春や不法な性的行為の強制などの性的搾取、ならびに性的虐待から子どもを守るためにあらゆる手を尽くします。
<第35条>
国は、あらゆる目的および手段の誘拐・人身売買から子どもを守ります。
<第37条>
子どもに拷問をしたり、死刑・終身刑などの非人道的な刑罰を科したりすることを禁止します。犯罪を行った子どもの身柄を拘束する際は拘束期間をできる限り短くし、子どもの尊厳や年齢を考慮して人道的に扱います。
<第39条>
虐待・拷問などの非人道的な扱いや武力紛争などの被害者となった子どもは、心身の回復や社会復帰のための支援を受けることができます。
<第40条>
犯罪を行った子どもは、他人の人権・自由を尊重できるようになること、将来社会参加して建設的な役割を担えるようになることを目指して扱われる権利を持ちます。
<第41条>
条約が定めるすべての規定は各国の国内法または国際法に含まれるものであり、子どもの権利を実現するための物事に影響を及ぼしません。
(出典:外務省「児童の権利に関する条約」)
子どもの権利条約とユニセフの関係
ユニセフは、子どもの権利条約の実施にまつわる検討や専門的な助言などを行う国際機関です。国連人権委員会において子どもの権利条約の草案づくりに参加し、また国連総会における条約採択や各国政府による条約の批准を目指して広報活動を実施しました。条約が発効した1990年以降、ユニセフは条約が定める子どもの権利を実現すべく発展途上国の支援活動や先進国での広報活動などを行っています。
条約採択から30周年となる2019年には、ユニセフはより多くの人に条約の内容と重要性を知ってもらうためのポスターを作成しました。子どもを含む全世界の人々からのオンライン投票で選ばれたアイコンは、各条文の内容をわかりやすく示しています。また、特定の人種や文化的価値観に偏らないよう、ユニバーサルデザインのアイコンが採用されていることも特徴です。なお、ポスターは啓発目的や非営利目的での使用で、かつ加工しないことを条件として自由にダウンロード・印刷できます。
(出典:unicef「子どもの権利条約」)
子どもの権利条約が発行されるまでの流れ
子どもの権利条約が生まれたきっかけは、世界中の人は同じ権利があり平等な存在であることが示された、1948年の「世界人権宣言」です。この宣言自体は法的効力を持たないものの、以降に国際社会で人権に関するさまざまな条約が発行される先駆けとなりました。
子どもの権利条約は、社会的に弱い立場にある子どもの人権確立を実現するための条約です。
| 1948年 | 「世界人権宣言」すべての人は平等であり、それぞれが同じ権利をもつとした宣言。 |
| 1959年 | 「児童の権利宣言」子どもは子どもとしての権利をそれぞれもつとした宣言。このときから、宣言だけでなく実際に効力のあるものができないかと考えられはじめた。 |
| 1978年 | 「子どもの権利条約」草案をポーランド政府が提出。 |
| 1979年 | 「国際児童年」 「児童の権利宣言」20周年。世界中の人が子どもの権利について考える機会になった。国連人権委員会の中に「子どもの権利条約」の作業部会が設置された。 |
| 1989年 | 「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」 国連総会で満場一致で採択。 |
| 1990年 | 「子どもの権利条約」発効 国際条約として発効 |
(引用:unicef「子どもの権利条約カードブック」)
1990年の条約発効以降も、時代が変化することへの対応やさらなる権利の向上を求めて、選択議定書という形で条約の補強・改善が行われています。
子どもの権利条約採択後の日本国内の動き
1994年に日本で子どもの権利条約が批准されて以降、国内でも子どもの権利を守るための動きや議論が活発化しています。各地域の状況や特性に合わせて独自に考案した条例を制定し、子どもの権利条約の浸透を後押しする自治体は少なくありません。下記は日本で条例を設けている自治体の一例です。
- 東京都豊島区「豊島区子どもの権利に関する条例」
- 青森県青森市「青森市子どもの権利条例」
- 愛知県岩倉市「岩倉市子ども条例」
子どもの権利条約を批准した国は、国連の子どもの権利委員会に対して政府と民間団体から定期的に報告を上げ、審査を受ける義務があります。2017年に提出した報告書に対しては、早急に対応すべき課題として下記の6点が指摘されました。
- 差別の禁止
- 児童の意見の尊重
- 体罰
- 家庭環境を奪われた児童
- 生殖に関する健康および精神的健康
- 少年司法
(出典:外務省「日本の第4回・第5回政府報告に関する総括所見」)
上記事項のうち、いくつかは初回から勧告され続けている指導内容であるため、未来に向けてより一層の努力が必要といえるでしょう。
まとめ
「4つの原則」をもとに定められた「4つの権利」からなる子どもの権利条約は、子どもが持つ基本的人権を保障するための条約です。日本は1994年に批准し自国内の意識が高まっているものの、いまだ十分に条約が遂行されているとはいえず、今後もさらなる向上が求められます。
子どもたちと密接に関わる職業の保育士は、保育に関する情報を常に収集することが求められます。「ほいくらし」は、保育士にとって役立つ情報を発信する情報サイトです。子どもの健やかな成長を助け、充実した日々を送るためにも、ぜひ当サイトを役立ててください。
お得な情報や最新コラムなどをいち早くお届け!ほいくらし公式LINE 保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!ほいくらし公式X(旧Twitter)