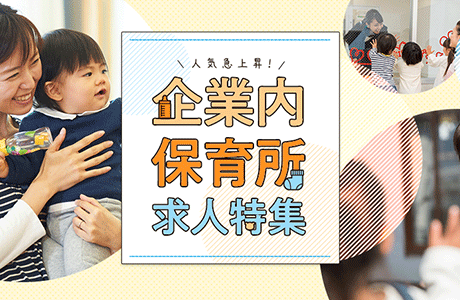保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!
X(旧Twitter)をフォローはこちら!
3歳児健康診査とは、満3歳から満4歳になるまでの子どもを対象に、各自治体で実施される健康診査です。子どもの成長について知るだけでなく、日ごろの心配事や気になることを医師や保健師、管理栄養士などに相談できる機会でもあります。
本記事では、3歳児健康診査の目的・3歳児健康診査の実施場所や当日の持ち物・健康診査の具体的な内容についても紹介します。
小さな子どもを育てる保護者はもちろん、3歳児健康診査について知識を深めたい保育士もぜひ参考にしてください。
3歳児健康診査とは
3歳児健康診査とは、「母子保健法」に基づいて各市区町村が実施する、満3歳を超え満4歳に達しないすべての幼児を対象にした健康診査事業です。3歳児健康診査は、無料で受けることができます。
(出典:厚生労働省「母子保健関連施策」)
3歳児健康診査は、「乳幼児健康診査(1歳6か月児健診・3歳児健診)」の一部であり、以下のような目的があります。
| ・子どもの発育 ・発達状況の確認 ・疾病の早期発見 ・栄養指導 ・家庭との関わりの場を形成 |
3歳は、幼児期の中でも、身体発育・精神発達だけでなく、自我の芽生えや生活主幹の確立などにより「社会性」が急速に発達する時期です。人間形成の基礎となる大切な時期であるため、多角的な健康診査を行い、心身障害の有無や疑いをチェックしています。
以下は、3歳児健康診査における受診率の年次推移をまとめた表です。
| 平成26年度(2014年) | 平成27年度(2015年) | 平成28年度(2016年) | 平成29年度(2017年) | 平成30年度(2018年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受診率 | 94.1% | 94.3% | 95.1% | 95.2% | 95.9% |
(出典:厚生労働省「平成30年度地域保健・健康増進事業報告の概況」)
母子保健法により、「市区町村は健康検査を受けることを勧奨しなければならない」と定められています。そのため、3歳児健康診査の受診率は90%を超える数値で推移しています。
実施場所
3歳児健康診査は、自分の住む地域にある「保健福祉センター」など、指定された場所で実施されます。
主な実施場所は、以下の通りです。
| 3歳児健康診査の主な実施場所 |
|---|
| ・保健福祉センター ・保健所 ・子ども ・子育て支援センター ・公民館 ・集会所 |
3歳児健康診査の案内が各家庭に送付されるため、その案内に記載されている実施場所で健康診査を受けましょう。
また都合が悪く、指定された日程・場所での実施が難しい場合は、案内に記載されている問い合わせ先に相談してください。
持ち物
3歳児健康診査の当日の持ち物は、市区町村からの案内に記載されています。自治体によって違いはありますが、一般的には以下のような持ち物が必要です。
| 3歳児健康診査の主な持ち物 |
|---|
| ・母子健康手帳 ・3歳児健康診査質問票(アンケート、問診票) ・歯ブラシ・子どもの尿(なるべく起床してすぐの尿) ・子どもの健康保険証 |
上記のほかにも、オムツ・おしりふき・ハンカチ・ティッシュなどの衛生用品があると安心です。
また、3歳児健康診査は集団健診が一般的であるため、混雑により待ち時間が長くなることも考えられます。子どもの待ち時間対策のために、おもちゃや絵本なども持参するとよいでしょう。
3歳児健康診査の主な内容
乳幼児に対する健康診査は「母子保健法第12条及び13条」に規定されており、国の定めにより、3歳児健康診査では以下の3つの健康診査を行います。
(2) 健康診査の種類
健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査とする。
(引用:厚生労働省「「乳幼児に対する健康診査の実施について」の一部改正について」)
そのため、3歳児健康診査で行われる健康診査の内容は、自治体にかかわらず基本的に同じです。健康診査終了後は、結果に基づき、保健師・臨床心理士・管理栄養士などに個別相談が行えます。
一般健康診査
一般健康診査は医師や保健師が行い、目的は以下の通りとなっています。
| ・視覚・聴覚 ・運動発達状況の発見 ・自我の確立状況 ・社会適応能力の確認 ・保護者の関わりや保育環境の確認 ・指導 |
一般健康診査は内科健診がメインであり、事前に保護者が記入した質問票や問診票をもとに、以下のような健診を行います。
| 身体測定 | 身長・体重・頭囲・胸囲などを計測し、身体発育曲線に沿って、痩せ・肥満などの状況を確認する |
|---|---|
| 栄養状況の確認 | 食事回数・食事内容・食欲・偏食・おやつの時間・おやつの内容などを確認する |
| 視力検査、聴力検査 | 遠視・近視、斜視などが見られるか、聴覚異常が見られるかなどを確認する |
| 尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血を確認する |
| 運動発達状況の確認 | 階段昇降、両足とびなどの「粗大運動」や、クレヨンで丸を書けるかなどの「微細運動」の確認を行う |
| 精神発達状況の確認 | 言語能力・認知能力・社会性の発達を確認する【例】自分の名前が言えるか、大小・長短・色の区別ができるか、ごっこ遊びなどができるか |
| 生活習慣の確認 | 起床・就寝・食事の時間、排尿や排便のしつけ状況、歯磨きができるかなどを確認する |
| 予防接種 | ワクチンの接種状況を確認し、必要に応じて予防接種を実施する |
| 子育て状況の確認 | 保護者の子育て状況や支援者を確認する |
一般健康診査の際には、子どもの発達状況に関する相談や栄養相談、育児相談なども行えます。
歯科健康診査
歯科健康診査は、歯科医師や歯科衛生士が実施し、以下のような目的があります。
| ・むし歯・歯周病の有無の確認 ・口腔機能の確認と指導 ・歯科相談 |
3歳は、一般的に20本の乳歯が生えそろう年齢であり、食生活・食習慣、歯磨きの習慣が定着する時期です。そのため歯科健康診査では、3歳児の口腔の発育・健康状態を確認します。
歯科健康健診で確認される具体的な項目は、以下の通りです。
- むし歯のリスクとなる生活リズム・生活習慣の確認
- 歯垢付着状況
- 乳歯の萌出状況
- 歯の形態
- 歯数
- むし歯・要観察歯の確認
- 歯列・かみ合わせの確認
- 指しゃぶりなど、口腔習癖の確認
基本的に3歳頃には、咀しゃくなど、食事をとる際の基本的な動きができるようになっています。一方で、発達障害を持つ幼児などは、食事に関する調整機能が未熟なことが少なくなく、食べ物を飲み込む前に次々と口へ食べ物を運んでしまうケースがあります。
口腔機能・摂食機能に関して、普段の生活で気になる部分があれば、歯科健康診査で相談するようにしましょう。
精密健康診査
精密健康診査は、一般健康診査・歯科健康診査で何らかの異常が見つかった場合のみ行われます。3歳児健康診査により発見された疾病・異常に対し、精密検査や早期治療を促すことで、幼児の健康の保持・増進を図ることが目的です。
精密健康診査が必要になるケースは、一般健康診査を受診した幼児の5~7%程度となっており、割合的には多くありません。2018年度は、996,606人が3歳児健康診査を受診し、その内65,477人(約6.5%)が精密健康診査の対象でした。
(出典:厚生労働省「平成30年度地域保健・健康増進事業報告の概況」)
まとめ
3歳児健康診査は、子どもの成長を確認するだけでなく、さまざまな疾病や異常の早期発見、早期治療のためにも重要な事業です。3歳児健康診査は、一般健康診査・歯科健康診査・精密健康診査から構成されており、特に異常がない場合は精密健康診査は行われません。
小さな子どもを育てる保護者だけでなく、子どもの保育に携わる保育士も、ぜひ今回の内容を理解し、保護者から3歳児健康診査について相談されたときなどに役立ててください。
また「ほいくらし」では、ほかにも保育士に関する豆知識・お役立ち情報・最新情報を掲載しています。保育士や保育士を目指している方は、ぜひご参考ください。
お得な情報や最新コラムなどをいち早くお届け!ほいくらし公式LINE 保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!ほいくらし公式X(旧Twitter)