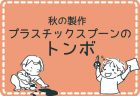やっぱり家の日とは?家を通じた異文化への理解を子どもと深めよう

保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!
X(旧Twitter)をフォローはこちら!
世界中では、年間を通してさまざまな記念日が設定されています。記念日は、すべてを把握することが困難なほど日々新たに制定されており、企業が登録した記念日にはサービスにちなんだイベントが行われることも特徴です。
2010年には、イケア・ジャパンが8月1日を「やっぱり家の日」という記念日に正式制定しました。制定して以降、毎年8月1日にはさまざまなイベントが行われています。
今回は、イケア・ジャパンが制定した記念日「やっぱり家の日」について、意味や由来を説明します。また家にちなんで、子どもに伝えられる家・住環境の雑学や歴史も解説するため、家に関する文化の理解を子どもに教えたいという方もぜひ参考にしてください。
やっぱり家の日とは?やっぱり家の日の意味・由来を解説!
やっぱり家の日とは、全国の家庭に「家の大切さ」を改めて認識する機会として、イケア・ジャパンが2010年に制定した8月1日の記念日です。
やっぱり家の日の制定して以降、イケア・ジャパンでは毎年8月1日に記念として下記のような各種イベント・企画を行っています。
●新商品の発表
●IKEAカタログの発行・無料配布
●レビュー投稿者限定オリジナルギフトのプレゼント
●IKEA Familyメンバー限定の抽選会
●限定ルームセットの特設
●シンポジウムの開催
上記の各種イベントは、10年以上が経った現在でも欠かさず行われています。
1. やっぱり家の日の由来
やっぱり家の日の名前と日付は、「やっぱり家が一番」という家の良さを改めて実感しているかのような言葉が由来です。
ヤ(8)っぱりイ(1)エがいちばん
上記のように、「やっぱり」の「ヤ」を8、「家」の「イ」を1とした語呂合わせから、8月1日という日付に設定されました。
前述の通り、やっぱり家の日は家の大切さや暮らし方を見つめ直すきっかけを得てほしいというイケア・ジャパンの想いから制定されています。新商品を取り入れた商品カタログは毎年配布されており、公式ホームページからはオンライン版も閲覧可能です。ステイホームを楽しむ方法の一つとして、やっぱり家の日について考えてみてはいかがでしょうか。
子どもに伝えたい!家・住環境の雑学・豆知識
家は、人間にとってなくてはならない大切な場所です。さらに、家・住環境は文化や社会のあり方を反映するものでもあります。そのため、家について子どもの頃からきちんと学んでおくことで、社会や異文化への理解も広がるでしょう。
ステイホームが注目されている近年、子育て中のお母さん・お父さんは、やっぱり家の日に子どもと一緒に知識を増やすこともおすすめです。ここからは、子どもたちと一緒に学べる家・住環境の雑学・豆知識を紹介します。家の歴史や異文化を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
1. 家の歴史
子どもにとって家は、当たり前かのようにある場所です。しかし普段自分たちが過ごしている快適な住環境は、たくさんの古人たちの努力によってつくられた環境でもあります。
やっぱり家の日には、当たり前の日常生活はどのようにして構築されたかを知る機会として、子どもと一緒に家・住環境の歴史を学ぶことがおすすめです。下記では、社会についての興味・参加意欲を持たせることのできる「家の歴史」について詳しく解説します。
■【縄文時代】たて穴式住居
紀元前14,000年から3世紀ごろまで1万年続いたと言われる縄文時代では、「たて穴式住居」が主な住居でした。たて穴式住居とは、100cm程度の穴を掘った地面に柱を建て、上部に藁などでつくった屋根を置いた住居です。夏は涼しく冬は暖かいことが特徴ですが、土の上で生活しなければならないことや、湿気がこもりやすいことが欠点でした。
■【弥生時代】高床式住居
紀元前4世紀から3世紀ごろまでの弥生時代では、「高床式住居」が主な住居でした。高床式住居とは、柱や杭を活用し地面から床面を高くしてつくられた住居です。浸水・害虫被害・湿気を防ぐことができ、収穫した穀物の保存にも役立ちました。たて穴式住居よりも快適となりましたが、当時の高床式住居は身分が高いものしか住めませんでした。
■【平安時代】寝殿造り
西暦794年から1185年までの平安時代では、「寝殿造り」が主な住居でした。寝殿造りとは、庇や濡れ縁を巡らせた大きな寝殿を中心に、対の屋や庭園を廊下で結んだ豪華な住居です。上級貴族の住まいとして使われていました。なお、平安時代の庶民の家は地面に穴を掘って固定させた住居が多く、階級による住居の差が大きくなり始めたことも特徴です。
■【室町時代】書院造り
西暦1336年から1573年までの室町時代では、「書院造り」が主な住居でした。書院造りとは、一棟の建物を複数の部屋に区切った武家住宅です。寝殿造りから発展したとされており、床の間や障子も取り入れられた書院造りは、現代の和室の原型とも言われています。
■【現代】近代化住宅
現代では、「近代化住宅」が主流となりました。第二次世界大戦直前の明治時代から昭和時代にかけては木造住宅が増加し、戦後からは高層住宅も登場し始めます。平成時代からはより快適性に優れた省エネ住宅も登場し、令和時代となるとインターネットを活用して家中のあらゆる操作ができるIoT住宅も徐々に増加傾向です。今後の近代化住宅は、より快適な住まい空間へと進化を続けるでしょう。
2. 世界の家
やっぱり家の日には、日本の家の歴史だけでなく、世界の家の文化について学ぶこともおすすめです。世界中に存在する家について学ぶことで、国際理解教育にもつながるでしょう。また、異文化への理解を深めることで、子どもの視野を広げることも可能です。
下記に、世界の家でも特に特徴が多いイタリア・ノルウェー・トルコ・モンゴル・カンボジア・カナダの家について紹介します。
■【イタリア】トゥルッロ
トゥルッロは、南イタリアのプーリア州に存在する伝統的な住居です。石灰石を積み重ねてつくられた長方形・円筒形の家の上部に、円錐型の屋根が置かれています。トゥルッロはアルベロベッロの町に1500軒がずらりと並んでおり、「アルベロベッロのトゥルッリ」として世界遺産にも登録されています。
■【ノルウェー】草屋根の家
草屋根の家は、夏の暑さ・冬の寒さが厳しいノルウェーに存在する、名前の通り草の屋根が特徴的な住居です。ノルウェーの森林資源を有効に活用し、丸太を積み重ねた建物の屋根に白樺や土を乗せ、その上に芝を植えてつくられます。植物の蒸散効果で夏は屋内が涼しく、冬は木材が断熱材となり屋内の寒さを抑えることが可能です。
■【トルコ】洞窟の家
洞窟の家は、トルコのカッパドキアに存在する、不思議な形をした岩の中につくられた住居です。大きな岩の中にある部屋はそれぞれが独立しており、日当たりの有無により適切な目的の部屋が決められています。その芸術的な景観から、カッパドキアは世界遺産登録もされており、洞窟ホテルに泊まる観光客も多くいます。
■【モンゴル】ゲル
ゲルは、モンゴルに存在する移動式住居です。モンゴルで一般的に販売されている材料を使用し、家畜とともに住む遊牧民自身が組み立て・解体を行います。気温の高い日には、ゲルについている円形の天窓「トーノ」を開けて温度を調節し、寒い日は建物の外側にフェルトやじゅうたんを巻くなどして、各調節をすることも特徴です。
■【カンボジア】高床式住居
日本では弥生時代に主流となっていた高床式住居は、現在のカンボジアの伝統的な住居となっています。カンボジアは、家畜を飼う家庭も多く床下を家畜スペースにするため・洪水被害を防ぐために高床式住居が主流となったと言えるでしょう。現代のカンボジアの高床式住居は、日本の弥生時代に用いられていたものと大きな変わりのないものから、鉄のワイヤーや瓦の屋根を使用した耐久性の高いものまでさまざまです。
■【カナダ】イグルー
イグルーは、カナダのツンドラ地帯に存在する「イヌイット」と呼ばれる先住民族が主に暮らす住居です。気温が非常に低い地域で過ごすイヌイットの方たちは、アザラシ猟のために数日ごとに住居を移動させます。すべてが雪でつくられるイグルーは、日本で言う「かまくら」に似ており、厳しい寒さを耐えしのぐために最も適切な住居です。
上記のほかにも、世界中にはさまざまな特徴を持った住居が数多く存在します。子どもの好奇心や興味を引き出すためにも、世界中の住居をチェックしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
ここまで、イケア・ジャパンが制定した8月1日の記念日「やっぱり家の日」の概要から、子どもに教えられる日本の家の歴史・世界中の家の特徴を徹底的に紹介しました。
やっぱり家の日は、家の大切さや暮らし方を改めて知る機会となる、大切な記念日です。小さな子どものいる家庭や、小さな子どもの保育にかかわる保育士の方は、やっぱり家の日に備えて家・住環境にまつわる雑学や豆知識を得てみてはいかがでしょうか。
「ほいくらし」では、その他子どもの教育・保育に関するさまざまな情報をまとめています。保育士の方や、小さな子どもを持つ方は、ぜひ一度チェックしてみてください。
お得な情報や最新コラムなどをいち早くお届け!ほいくらし公式LINE 保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!ほいくらし公式X(旧Twitter)