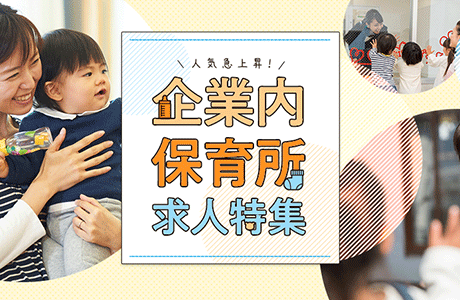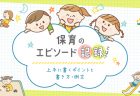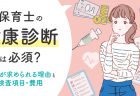保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!
X(旧Twitter)をフォローはこちら!
インクルーシブ保育は、近年多様性を認める風潮にある社会で広がってきている保育の仕組みです。しかし、インクルーシブ保育について聞いたことはあっても、どのような保育法なのか詳しく知らないという人も多いのではないでしょうか。
当記事では、インクルーシブ保育について分かりやすく解説します。インクルーシブ保育のメリット・デメリットや、インクルーシブ保育の課題についても説明するため、インクルーシブ保育に興味のある人は、当記事の内容をぜひ参考にしてください。
インクルーシブ保育とは?
インクルーシブ保育とは、子どもの年齢・国籍・障害の有無などの違いをすべて受け入れる教育法のことです。「インクルーシブ(inclusive)」とは、「包括的な、すべて含んだ」という意味があります。その意味のとおり、インクルーシブ保育はどのような背景を持った子どもも同じ環境で教育を受けさせる取り組みです。
以前は「養護学級」や「特別支援学級」といった、障害を持つ子どもを別のクラスに分ける教育が行われていました。しかし、近年では障害の有無にかかわらず、すべての子どもが必要な支援を受けながら、同じ場で教育を受ける「インクルーシブ保育」が行われるようになってきました。
1. インクルージョン教育・インテグレーション教育との違い
インテグレーション教育は統合教育とも呼ばれます。インテグレーション教育は、障害を持つ子どもを通常学級に迎え入れ、同じ環境で教育を受けさせるという考え方のもとに行われました。しかし、「同じ環境で教育する」という側面ばかりが重視され、子ども一人ひとりのサポートが不十分でした。
そこで、インテグレーション教育の延長として生まれたものが、インクルージョン教育です。インクルージョン教育は、障害のある子どもに対してだけではなく、すべての子どもに対して個々の特性を把握した上で発達支援をするという考え方です。
その後、2010年に文部科学省が「インクルーシブ教育システム構築事業」を打ち出し、インクルージョン教育の問題点をさらに改善した「インクルーシブ教育」が生まれました。
インクルーシブ保育のメリット|保育上の魅力
インクルーシブ保育は、子どもと保育士の双方にメリットがあります。幼い頃から他者の多様性に触れることで子どもの成長を促す他、保育士側にも学びがあることがインクルーシブ保育の魅力です。
ここでは、子ども側と保育士側それぞれのメリットを紹介します。
1. 子ども側:違いがあることを学べる
子どもにおけるインクルーシブ保育のメリットは、以下のとおりです。
・多種多様な人がいることを学べる
インクルーシブ保育では、年齢の違う子どもや、障害を持つ子どもが同じ教育環境で過ごします。幼い頃から多様な他者と一緒に生活することで、それぞれに違いがあることが当たり前だと認識し、成長することができます。従来の分離教育で無意識に生まれていた差別や偏見を防げることも、インクルーシブ保育のメリットです。
・違いがある人との関わり方を学べる
学年や発達に違いがある人と同じ環境に身を置くことで、年齢が同じ園児だけのクラスとは違った人間関係が生まれます。年下の子の面倒を見たり、年上の子に追いつこうとしたりと、他者に刺激を受けることで行動が変わります。
また、自分と同じことがスムーズにできない子に手を差し伸べるといったコミュニケーションも生まれます。自然と相手を思いやり、尊重するという気持ちが育つことが、インクルーシブ保育の特徴です。
2. 保育士側:幅広い知識やスキルが身に付く
保育士におけるインクルーシブ保育のメリットとしては、以下の2つが挙げられます。
・高い保育スキルが身につく
インクルーシブ保育は、多様な発達段階の子どもが同じ環境にいるため、衝突が起こりやすいと言えます。衝突が起こったときには、保育士がどう対応するのかが重要です。さまざまなケースに対応し、問題を解決していくことで、高い保育スキルを身につくでしょう。
・幅広い知識が身につく
多様な子どもたちが抱える教育的ニーズに対応するためには、専門的知識が必要になることもあります。障害のある子どもへの接し方や向き合い方、ケアの仕方など、保育士が学ぶべき事柄は多くあります。必要であれば資格を取得し、得た知識を保育に活かすことで、より多様なケースに対応できるようになるでしょう。インクルーシブ保育で得た知識は、通常の園でも役立てることができます。
インクルーシブ保育のデメリット|保育上の課題
近年インクルーシブ保育は広がりつつありますが、実践にはまだ課題も残っています。多種多様な子どもが同じ環境で保育されるというインクルーシブ保育の特徴は、いい面ばかりではなく注意が必要な面もあります。保育士だけでなく、子どもにもよくない影響が及ぶこともあるため、デメリットを把握しておくことが大切です。
ここでは、インクルーシブ保育のデメリットや課題を紹介します。
1. 子ども側:劣等感や衝突を生む可能性がある
子どもにおけるインクルーシブ保育のデメリットは、以下の3つです。
・多様な環境を受け入れるまでに時間がかかる
インクルーシブ保育は多種多様な子どもが一緒に生活できる反面、お互いの違いを受け入れるまでに時間がかかるといったデメリットがあります。子ども同士で違いを理解することが難しく、喧嘩や衝突をしてしまうことは避けられません。また、理解のスピードに個人差があることから、トラブルが生じることもあります。
・劣等感を感じる可能性がある
多様な子どもが同じ環境で過ごすインクルーシブ保育では、障害のある子どもが劣等感を抱く可能性があります。障害のない子どもと常に一緒に過ごすため、できることの量を比較してしまい、障害のある子どもにとって大きなストレスがかかる場合があります。
・満足度の違いが生じる
インクルーシブ保育は、障害のある子どもと障害のない子どもが一緒に過ごすため、発達度合いによってはカリキュラム内容を退屈に感じ、満足できない場合があります。場合によっては、子どもの成長を妨げてしまうことにもなりかねないため、支援方法に注意が必要です。
2. 保育士側:相応の時間と努力が必要になる
保育士におけるインクルーシブ保育のデメリットには、次のようなものがあります。
・時間的負担が増える
インクルーシブ保育を行うにあたり、保育士側には多種多様な子どもに対応できる力が求められます。保育士としての知識に加えて、障害のある子どもに対応できるよう専門知識を勉強したり、時には資格を取得したりといったスキルアップが必要となります。園での勤務に加えて自身で学習する時間を確保しなければならない場合、時間的負担を避けることが難しいでしょう。
・学び続ける姿勢が必要
インクルーシブ保育において、保育士は身につけた知識を実践しながら、子ども一人ひとりに気を配る必要があります。インクルーシブ保育は通常の保育よりも気をつけることが多く、神経を使うため、保育士の負担が大きいことは否めません。多様なケースに対応できるよう、常に対応を工夫し、学び続ける努力が必要です。
インクルーシブ保育を実践するためには?
インクルーシブ保育の実践にあたっては、自分自身が知識を身に付けた上で、納得できる職場を選ぶことが重要です。
園によっては、多国籍の子どもの受け入れや保護者対応のために、外国語の知識が必要な場合もあります。受け入れる子どもや現場によっては、専門知識や医療ケアが求められたりすることもあるでしょう。勤務する園の仕事内容や、どのような子どもを受け入れているかを、自身の知識と照らし合わせて確認することが大切です。
また、インクルーシブ保育を謳っていても、実際には十分な支援体制が整っていない園もあります。職員のスキルやノウハウが不足していたり、勤務する保育士に対して十分な指導が行われていなかったりする場合があります。勤務する園を選ぶ際には、事前によく話を聞いたり、見学をしたりして、適切な対応がなされている職場かどうか見極めましょう。
まとめ
インクルーシブ保育は、多種多様な子どもを障害の有無や年齢で分け隔てることなく保育する方法です。障害があるかないかという観点ではなく、一人ひとりの個性に合わせた教育を行うことで、多様性を受け入れる姿勢を幼い頃から身につけることができます。一方で、保育士の高いスキルが要求されたり、子どもが劣等感や不満を抱くこともあるなど、課題も残っています。
インクルーシブ保育を実践する際には、正しい知識を持って、さまざまなケースに対応できる環境を整えることが大切です。
「ほいくらし」には、子育てに関する知識やアイデアを豊富に掲載しています。保育に行き詰まったときには、ぜひ「ほいくらし」を参考にし、新しいアイデアを実践してみてください。
お得な情報や最新コラムなどをいち早くお届け!ほいくらし公式LINE 保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!ほいくらし公式X(旧Twitter)