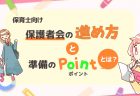探索活動(探索行動)とは?年齢別の特徴・保育士の援助方法

保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!
X(旧Twitter)をフォローはこちら!
探索活動は、子どもが目に映るものや耳に聞こえるものに対して強い好奇心を抱き、その正体を探ろうとして行う行動です。保育所に預けられる子どもたちは、ちょうど探索活動が活発となる時期に相当します。保育士が子どもたちの健やかで伸びやかな成長を助けるためには、探索活動のねらいを理解した上で、万全の準備を整えることが大切です。
今回は、子どもが探索活動を行う理由や年齢別の特徴、保育所における探索活動のねらい、保育士の援助方法を解説します。
探索活動(探索行動)とは?
探索活動とは、子どもが初めて出会うものに対して興味を抱き、どのようなものかを知ろうとする行動のことです。個人差はあるものの、生後半年を過ぎた頃から活発化します。特につかまり立ちを始めると視界や行動できる距離が一気に広がり、赤ちゃんの好奇心も旺盛になるため、探索活動を行う範囲も大きくなることが特徴です。
厚生労働省の保育所保育指針では、子どもの探索活動には「精神的発達に関する視点」から以下の効果があるとしています。
| 身近な環境に興味や好奇心をもって関わり、感じたことや考えたことを表現する力の基盤を培う。 (ア)ねらい ① 身の回りのものに親しみ、様々なものに興味や関心をもつ。 ② 見る、触れる、探索するなど、身近な環境に自分から関わろうとする。 ③ 身体の諸感覚による認識が豊かになり、表情や手足、体の動き等で表現する。 |
探索活動は、子どもが周囲の状況を理解したり、物事の善し悪しを判断できるようになったりするために重要な行動です。「指差し行動」や「確認行動」をはじめ、子どもの成長度合いに応じて複数の種類が見られます。
指差し行動
指差し行動とは、主に人差し指などを立てて興味・関心を持った対象に向ける行動です。子どもの視界に入った未知の存在に対して「触ってみたい」「どのようなものか知りたい」といった好奇心を持った際に、下記のような行動として表れます。
| ・身の回りにあるものを指差して「アーアー」や「ウー」などと声を発する ・絵本に書かれている字や絵を指差す ・何かを指差しながら、ばたばたと身体を動かす ・何かを指差しながら、大人に視線を向けて反応をうかがう |
子どもが指差し行動を行った際、保育士は「教えてほしい」「取ってほしい」といった欲求を敏感に察知し、気持ちに寄り添った言動を心がけなければなりません。指差し行動によって大人が言葉をかけてくれたり、自分の気持ちを汲んでくれたりする体験から、子どもは「指差し行動はコミュニケーションを取るための手段である」ことを学びます。大人との信頼関係が構築されると、子どもはより積極的に関心を持った物事への指差し行動を繰り返し、自らの世界を広げるようになります。
確認行動
確認行動とは、興味・関心を持った対象をじっと見つめる・手で掴む・舐める・口に含むといった行動です。確認行動では、さまざまな方向性から興味の対象物に触れ、動かすことで触感や重さ、機能、動かし方などを学習します。
子どもの確認行動が見られたら、分かりやすい言葉で対象物の名前や使い方を教えることが大切です。例えば、子どもがミニカーに興味を持ったら、「これはブーブーよ。こうしたら走るの。すごいでしょ」と語りかけながら遊び方のお手本を見せましょう。それを見た子どもは「ブーブー」と言って、ミニカーを走らせる動作をまねする可能性があります。
一度で正確に覚えることができなくとも、子どもは何度も確認行動を繰り返す中で「物の名前」や「言葉の意味」を学習します。大人の言葉や動作をまねしながら理解できる事柄が増えていくことで、子どもが興味・関心を抱く対象は自然と増えるでしょう。
0歳・1歳・2歳における探索活動
探索活動は、子どもの発達度合いによって少しずつ行動が変化します。下記は、0~2歳ごろに行われる探索活動の目安です。
| 0歳 | 生後半年を過ぎた頃から、活発な探索活動が見られるようになり、指差し・確認行動が目立ち始めます。ハイハイやつかまり立ちができるようになると、より行動範囲が広がり、自分から興味のある事柄へ向かっていくことが増えます。 |
| 1歳 | 自力での歩行が可能になり、ただ目に入ったものへ関心を向けるだけではなく、子ども自身が興味を持てる対象を探し出す段階です。蓋や扉を開けたり、棚や箱の中身を取り出したりすることも多くなります。 |
| 2歳 | 語彙が増えることで、つたないながらも疑問や質問を自ら投げかけるようになる段階です。運動能力が上がることで積極的な探索活動が可能となる反面、自力でできないことに対してかんしゃくを起しやすくなります。 |
【保育所】探索活動のねらい
保育所において子どもの探索活動を助けることには、下記のようなねらいがあります。
| ・保育所の環境や保育士の存在になじませ、安心して過ごせるようにする ・新たな発見を通して、豊かな感性と自己表現力を身に付ける ・身近なものから子どもの理解を深め、興味・関心を持つ範囲を広げる |
子どもの好奇心を育てながら心や身体の発達を助けることが、保育所における探索活動の主なねらいです。大人からは「いたずら」や「意味・必要性のないこと」にしか思えなくても、子どもにとっては「好奇心を満たすため」の重要な行動になります。そのため、行動の意図が読めなくとも、子どもの様子を見守る中で時には一緒になって楽しむことが重要です。
保育士による探索活動の援助方法
子どもの探索活動中は、できるだけ子どもの好奇心を阻害しないよう、行動過程を見守ることが基本です。しかし、ただ見守るだけでは子どもの身に危険が及びかねません。保育所で子どもに探索活動を行う際には、十分に気を配った援助が必要です。 最後に、保育士による子どもの探索活動の援助方法を解説します。
子どもの安全を重視する
探索活動をさせる際は、子どもの安全を確保しなければなりません。物事の善し悪しが判別できない子どもは、大人なら避ける行為も平然と行う可能性があります。事故を起こさないために、下記の点に注意を払いましょう。
| ・誤飲につながるものが落ちていないか ・子どもや保育士の着ている服のボタンはしっかりと付いているか ・刃物や先の尖ったものが周辺に置かれていないか ・子どもが触れるものは清潔に保てているか ・塗料は子どもが舐めても大丈夫か ・子どもが保育士の死角に入らないか ・子どもが保育士の手の届かない場所へ行っていないか ・床にマットが敷かれているか ・遊具は固定されているか |
特に、幼いうちは周りのものを手あたり次第に口に入れてしまうため、子どもから目を離さないことが重要です。
探索できる環境を整える
子どもが好奇心の赴くままに探索できる環境を整えることも大切です。保育所に通う子どもは、個人の発達度合いや性格によって興味を持つ対象や積極性が異なります。「できることがない」「したいことがない」子どもが出ないよう、下記の点に配慮しながら環境を整備しましょう。
| ・探索活動を途中で切り上げなくてよいよう、十分な時間を確保する ・子どもの月齢・年齢や発達度合い、好みに応じたおもちゃを用意する ・おもちゃの取り合いが起きないよう、十分な数を用意する ・興味の範囲を広げられるよう、さまざまな方向性のおもちゃや遊具を用意する |
探索活動では、子どもが自分から好奇心を持って行動することが大切です。子どもの興味・関心が偏らないように、できるだけ多くの選択肢を用意しましょう。
シーンに応じた言葉をかける
探索活動中は場面に応じた言葉をかけることで、子どもは物の名称やその状況に応じた言葉を使えるようになります。また、保育士が「それはダメ」「やめて」と言っても、子どもに何がダメなのか伝わらなければ意味がありません。「トゲがあるから触らないでおこうね」「落ちないように気を付けようね」など、ダメな理由をきちんと説明することがポイントです。
今すぐには無理でも何度も言い聞かせるうちに、子どもはやってはならない行為やダメな理由を次第に理解できるようになります。子どもが物の名称や言葉を正しく使えたとき、危険を自分自身で避けられたときは、保育士がきちんと褒めることで、子どもは新たな探索に自信を持って取り組めるようになるでしょう。
まとめ
個人差はあるものの、子どもの探索活動は生後半年を過ぎた頃から活発化します。脳や身体が発達して行動範囲が広がれば、さらに興味・関心を向ける対象も多くなります。保育所で探索活動を見守る際は、子どもが安心して動けるよう、安全を確保した上で探索しやすい環境を整えましょう。興味の対象物や探索シーンに応じた言葉をかけることで、子どもの健やかな成長に大いに貢献できます。
探索活動以外に子どもの保育に関する情報を知りたい人は、ぜひ「ほいくらし」をご利用ください。
お得な情報や最新コラムなどをいち早くお届け!ほいくらし公式LINE 保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!ほいくらし公式X(旧Twitter)