脳科学者・中野信子先生の子ども悩み相談 #06 ~能力を決めつけられてつらい「コンプレックス」~
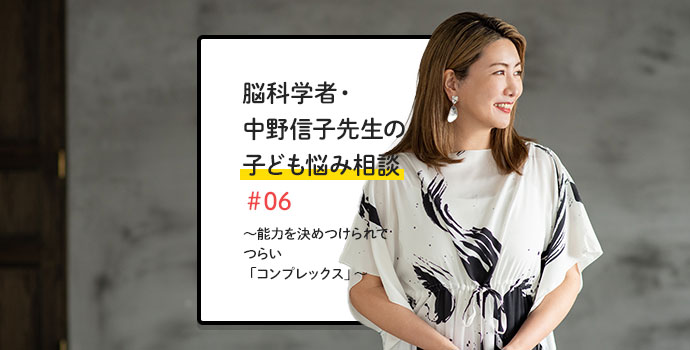
脳科学者でベストセラー著者としても知られる中野信子先生が、幼少期から思春期の子どもが抱きがちな悩みに対して、脳科学の見地からアドバイスを送ります。子どもたちの悩みやイヤな気持ちを上手に汲み取って、保育の現場でぜひ活用してください。
連載第6回目は、対人関係の悩みにつながる「コンプレックス」についてです。人にはそれぞれなにかしらの「強み」があり、それは本来、他人と比べるものではありません。しかし、自分より上手くできる友だちを目の当たりにして自信を失ってしまうことは、子どもにとってはよくあることだと思います。
そんなとき、コンプレックスを手放し、自分を認めるためにはどうしたらいいのでしょう? 集団にある特性を知ることが、自分を見つめ直すひとつの手がかりとなるようです。
Q:子どもの悩み
勉強や運動ができない……。「頭がよくない」と決めつけられて、毎日がつらくて仕方ありません

中野信子先生からのアドバイス
わたしも運動が苦手で運動オンチといわれていたので、あなたの気持ちはよくわかります。運動能力は、できる人とできない人とでまったく違うので、「体が健康ならいいや!」くらいに思うしかありませんでした。
勉強だって、記憶力などには個人差があります。それを、「頑張ればなんとかなる」と教えるほうがおかしい。しかもいまは、インターネットを使えば知識を簡単に得られるので、必死に勉強して覚えても社会に出たときにはたいした意味はないかもしれません。別に学校の勉強ができなくても、あなたは頭が悪いわけではないのだから、なにをいわれても気にしなくていいと思います。
特定の人に対してなにかを決めつけるのは、人間の集団ではよく見られる行動です。集団はバランスが取れる状態のほうが珍しく、だいたいは集団をまとめるために「弱い者」を探しはじめます。なんの落ち度もない人になにかを決めつけて、のけ者にすることで、集団の結束を高めようとするのです。人間は、そんな酷いことを行う性質を持っていることを知っておきましょう。
特に学校は、成績を中心に人の価値をはかりがちな面もあり、それは生物学的な観点から考えてもいいことではありません。なぜなら、集団内の多様性が失われると、集団の力が弱くなっていくからです。
まずあなたは、攻撃の的にならないように、勉強や運動以外のなにかであなたの価値を見せることが必要です。
もしそれが難しい場合は、万能の方法ではないけれど、「開き直る」という方法もあり。それこそ、「勉強も運動も苦手だけど、人生にはスマホを持ち込めるし、人に助けてもらうこともできるからいいんだ」と考えるのです。
「わたしは勉強や運動では期待にこたえられないから、もう誰かとタッグを組んで生きていくよ。勉強はあなたたちに任せる。頑張ってね!」みたいな言い方をして、うまく味方をつくってしまえばいいのではないでしょうか。 とにかく自分が気持ちよく生きられるように、「いまの環境のなかでできること」を、じっくり考えてみましょう。
構成/岩川悟(合同会社スリップストリーム) 協力/長野真弓
※この連載は、『中野信子のこども脳科学 「イヤな気持ち」をエネルギーに変える!』(フレーベル館)をアレンジして掲載しています。
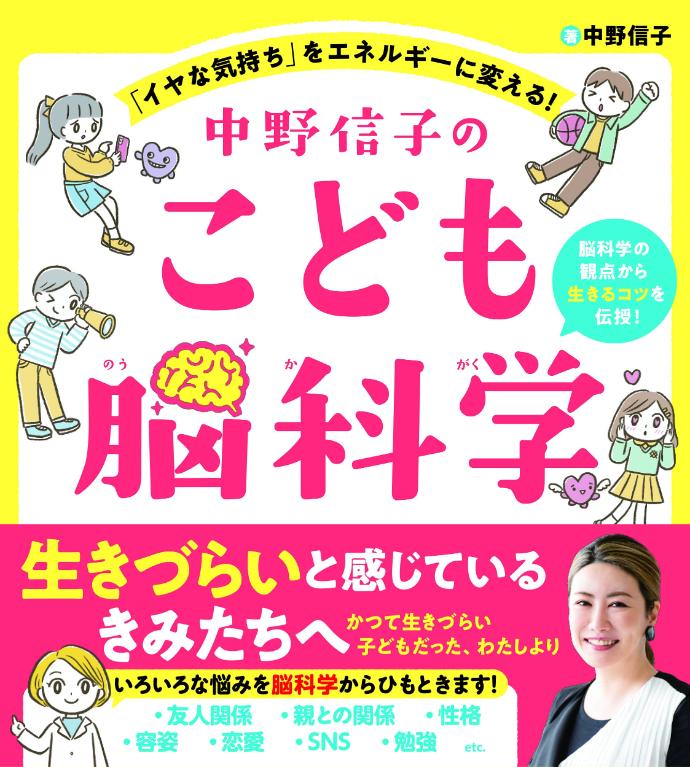
中野信子のこども脳科学「イヤな気持ち」をエネルギーに変える!
著者名:中野信子
出版社:フレーベル館
2021年8月発売





