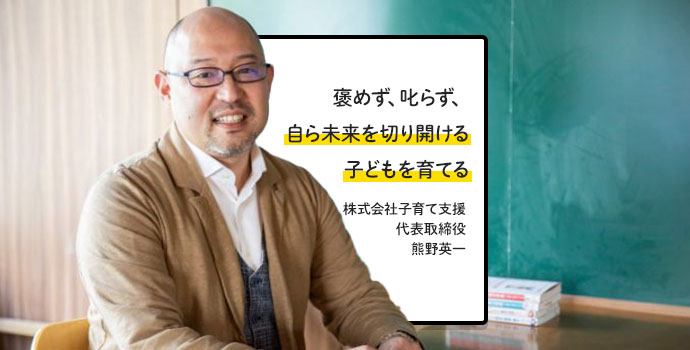保育・教育現場においては、「褒めて伸ばす」がキーワードになる場面がよくあります。一方、近年注目度が増している「アドラー心理学」に基づく子ども教育では、「褒めないこと」や「勇気づけること」が大きなテーマとなっています。これは、一体どういうことなのでしょう。日本アドラー心理学会/日本個人心理学会の正会員である株式会社子育て支援代表取締役の熊野英一さんに、子どもを「褒めずに勇気づける」ことの意義を教えてもらいました。
構成/岩川悟(合同会社スリップストリーム)
取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人
褒めたり、叱ったりする言葉の裏にある「操作の下心」

アドラー心理学における教育では、「褒めないこと」だけでなく「叱らないこと」も基本としています。そこにある狙いはまったく同じで、子どもを「操作しようとしない」ということです。
もちろん、褒めることや叱ることがすべて悪いわけではありません。褒める言葉、叱る言葉の裏側に「操作の下心」があるかどうかに着目したいのです。
ここでいう「操作」を別の言葉にするなら、親や保育者が自分の思いどおりに子どもをコントロールしようとすること。たとえば、「ゴミを拾って、いい子だね」と褒めることにも、「ゴミを拾わなかったから、あなたは悪い子」と叱ることにも、子どもにゴミを拾わせようとする下心——すなわち、操作の下心があります。
そして、「ゴミを拾って、いい子だね」「ゴミを拾わなかったから、あなたは悪い子」など、操作の下心がある言葉を使い続けると、子どもは褒めてもらうため、あるいは叱られないためにゴミを拾うようになっていきます。逆に言うと、褒められなければ、叱られなければゴミを拾おうとしなくなる可能性が高まるのです。 でも、保育者が本来望んでいるのは、そんなことではありませんよね? 自分の部屋だけでなく、お友だちと一緒に使う遊び場などでも、ゴミが落ちていたら拾う。誰かに見られていなくても、誰かに褒められたり叱られたりしなくても、率先してゴミを拾う。そんな子どもに育ってほしいはずです。
大げさに褒めることが、子どもを「指示待ち人間」にする

操作の下心がある褒め言葉を使い続けることには、さらなる危険性も潜んでいます。一つは、いわゆるアメとムチのうちの「アメ」に対する要求が、エスカレートしかねないことです。
いつもは「いい子だね」といえば、やってほしいことをやってくれていた子どもが、そのうち「そんな言葉だけじゃ、やらないよ」と、それこそ本当に甘いキャンディーを要求してくるかもしれません。そして、そのキャンディーがアイスクリームになり、アイスクリームのなかでも高級なものになり、いずれはゲームやスマホになっていく。そんなことにもなりかねないのです。
とはいえ、本当に恐ろしいのは、もう一つの危険性のほう。「子どもの自信を失わせることにもなりかねない」ということです。操作の下心がある褒め言葉の危険性を知らない親や保育者は、まさに「褒めて伸ばす」つもりで、そういう言葉を投げかけます。しかし、何かをうまくできた場面で大げさに褒めてしまうと、子どもは伸びるどころかむしろ自信を失うことにもなるのです。
たとえば、勉強の基本問題で子どもが100点を取ったとします。また、そのときに「よくできたね! すごいね!」と大げさに褒め、操作の下心を持って「あなたはよくできる子だから、応用問題もやってみようか」と促したとしましょう。
そう言われたとき、子どもは何を考えるでしょうか? 「100点を取ったときだけ褒められるのだから、この難しい問題で100点を取れなかったら叱られてしまう」ということです。そして、思うような結果が出なくなると「僕、無理」「もうやらない」と自信を失っていくのです。
そんなことを繰り返していると、子どもが「指示待ち人間」になってしまうこともあり得ます。褒められないと何もしない、自分で考えて行動できない、チャレンジする勇気を持てない。そんな人間になってしまっては困りますよね。
人間は、「勇気」によって進化し続けてきた

アドラー心理学に基づく教育では、褒めたり叱ったりすることではなく、「勇気づける」ことを重視しています。なぜなら、私たち人間は、本能的に持っている何かを「やってみたい」「できるようになりたい」といった気持ち——つまり、勇気によって進化し、未来を切り開いてきたからです。
今、人類は宇宙にロケットを飛ばせます。しかし、そこに至るまでの過程は平坦ではありませんでした。それこそ巨大な大砲で宇宙船を打ち出すような発想から始まり、何万回もの失敗を繰り返してきました。それでも、「あきらめずにやってみよう」「今はうまくいかなくても、いずれ何とかなる」と多くの人が自分を信じ、勇気を持ってチャレンジし続けた結果、ロケットを宇宙に飛ばすことにつながったのです。
もちろん、そういったチャレンジは、これからの未来を生きる子どもたちにも必要なものです。そして、そのためにいちばん大事なものが勇気です。それを考えると、保育や教育の仕事の面白さは、「未来を担う子どもたちに、ダイレクトに勇気を与えられる」という点にあるのかもしれませんね。
「子どもの話を聴く」のがいちばん大事なこと

では、この「勇気づけ」を保育現場に取り入れるには、どうすれば良いのでしょう。よく「どんな言葉がけをすれば良いですか?」と聞かれるのですが、残念ながら“魔法の言葉”のようなものは存在しません。
「どういう言葉がけをするか?」ということも確かに大事ですが、それ以上に大事なのは「子どもの話を聴く」ということです。
言い換えるなら、それは「保育現場で子どもたちの話を聴く時間を確保し、一人ひとりの気持ちに共感する」ということ。子どもが体験しているものを、子どもの目になって見、子どもの耳になって聴き、子どもの心になって感じてみてください。そうやって、相手の関心に対して寄り添うように関心を寄せていくと、子どもはその保育者を信頼するようになります。
その結果、子どもは「自分の気持ちをわかってくれる人がいるんだ」「自分は一人じゃないんだ」と思うようになり、「この人とのつながりのなかで、一人ではできなかったことをやってみよう」という勇気を得ることになるのです。 昨日までは、ただ泣きわめいて大人の側から助けてもらうことを選択していた子どもが、「なぜ泣きたかったのかを理解してくれる人がいるんだ」と認識したことで、「今日からは助けてもらわないでやってみよう」という勇気を持つかもしれない。あるいは、「まだ一人ではできないけれど、自分の言葉で『助けてほしい』といってみよう」という勇気を持つかもしれません。そういった関わりを持つことが、「勇気づけ」なのです。
子どもの話を聴く時間がないのは、話を聴かないから

私は、保育者のみなさんや親御さんには、「ぜひ、子どもたちのインタビュアーになってください」と伝えています。
もちろん、子どもたち一人ひとりの話を聴くのはとても大変ですし、「そんな時間はない」と言う人もいるかもしれません。でも、もしかしたら子どもの話をしっかり聴いていないからこそ、時間がない状況に陥っているとも考えられます。
子どもというのは、大人に「見てほしい」「話を聴いてほしい」「注目してほしい」と思っていることが多いもの。大人の側が「忙しいからあとで」と話を聴かないでいると、物を壊したり、他の子をたたいたりといった不適切な行動で注意を引こうとします。すると、大人は結果的に起こったトラブルへの対処で時間を奪われることに……。保育現場では、よくあるケースではないでしょうか。 だからこそ、まずは子どもの話を聴いてあげてください。子どもが「話を聴いて」と言ってきたときに手が離せなかったとしても、「お話を聴いてほしいんだね」と共感を示してから「あとでちゃんと聴くから、少し待ってね」と伝えたのちに、しっかり話を聴きましょう。そうすれば、無駄なトラブルも減り、子どもの話を聴く時間が確保できると思いますよ。
メルセデス・ベンツ日本人事部門に勤務後、米国Indiana University Kelley School of Businessに留学(MBA/経営学修士)。製薬企業イーライ・リリー米国本社及び日本法人を経て、保育サービスの株式会社コティに統括部長として入社。
約60の保育施設の立ち上げ・運営、ベビーシッター事業に従事。
2007年、株式会社子育て支援を設立し、代表取締役に就任。日本アドラー心理学会/日本個人心理学会正会員。主な著書に『夫婦の教科書』(アルテ)、『急に「変われ」と言われても』(小学館)、『仕事も家庭も充実させたいパパのための本』(小学館)、『家庭の教科書』(アルテ)、『育児の教科書』(アルテ)がある。