感染症のプロ岸田直哉先生に聞く! 保育園で本当に必要な新型コロナ対策ってどんなもの?
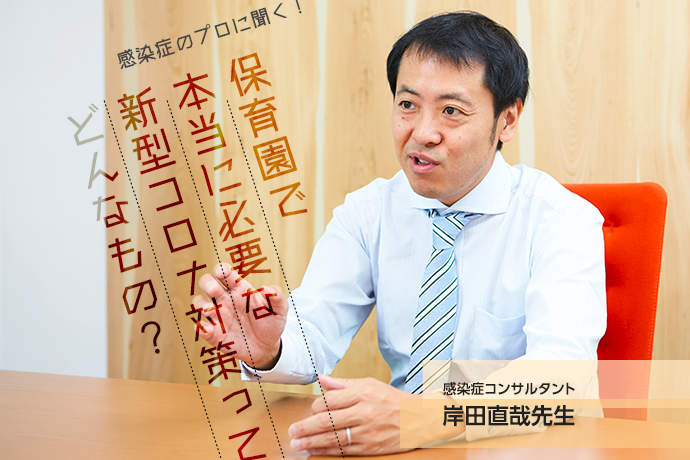
保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!
X(旧Twitter)をフォローはこちら!
新型コロナウイルス感染症の流行により、保育の現場もさまざまな影響を受けました。そして、危機対応という面ではいまだに予断を許さない状況が続いています。そうした中、「実際のところ、どんな感染対策をすればいいの?」と悩みながら働いている保育士さんも多いのではないでしょうか。そこで、感染症専門医であり、感染症コンサルタントとしても活躍する岸田直樹先生に、保育園で求められる新型コロナ対策について教えてもらいました。
目標は「やりすぎ」にならない感染対策

新型コロナウイルスの感染予防を考えるときに大切なのは、「リスクに応じてメリハリをつけること」です。重症化のリスクが極めて高い患者さんが入院している急性期病院では徹底的な感染予防策が必要ですが、同じことを各家庭に求めると? おそらく生活が成り立たなくなってしまうでしょう。
そうした意味では、一般的な保育園は家庭に近い環境、条件にあり、病院と同レベルの対策を講じようとするのは「やりすぎ」だといえます。もちろん、感染予防につとめることは大切ですが、それによって子どもたちの楽しみを過度に奪ったり、健全な発達を妨げたり、保育士さんの業務に悪影響を及ぼしたりしないように、十分な注意が必要です。
たとえば、園内全体をひんぱんに消毒しようとすると、莫大な時間、労力が必要となり、メリットよりデメリットのほうが大きくなります。そこに力を注ぐくらいなら、毎朝の子どもたちの健康チェックを確実に実施したり、大人数のクラスを分割して活動させたりすることのほうが、よほど意義があると思いませんか。
手洗いや口からの飛沫を意識して、園の環境を見直そう

では、日常的な感染予防策として保育園で実施すべき点を確認していきましょう。基本となるのはやはり「手洗い」。流水と石けんで30秒ほどかけて、ていねいに洗うことが重要です(アルコール消毒薬を使用してもOKです)。一度きれいにしても何かに触ったとたんに汚れてしまうので、「食事の前に手を洗う」「外にあるものを触ったら洗う」など、タイミングを決めておくことも大切でしょう。
また、新型コロナウイルスは口から出た飛沫による感染例が非常に多いため、つばが飛び散りやすい食事の場面では、とりわけ配慮が必要です。政府の専門家会議が発表した「新しい生活様式」にもある通り、できるだけ2mの間隔を空け、対面ではなく横並びで座ることが理想的でしょう。どうしても子どもたちが対面してしまうようなら、ついたてを用いるのも一案です。ついたては使用する人の顔の高さまであれば十分ですが、下の部分が大きく空きすぎているタイプは、そこから飛沫が流れていきやすいため注意してください。
睡眠中は、活発に動いたり、話したりしている状態に比べて、感染リスクが低いため、昼寝の際に敷く布団は、必ずしも2mおきでなくても大丈夫でしょう。ただし、子どもが突然泣き出すようなこともあると思うので、年齢や個性によっては間隔を広めにするべきかもしれません。新型コロナウイルスは、ノロウイルスなどと比較して排泄物からの感染リスクがそれほど高くありませんので、おむつ替えやトイレ介助の後は、しっかりと手洗いすれば大丈夫です。
園内の掃除は通常通りで十分だと思いますが、口からの飛沫が付着しやすい洗面所や食事用テーブル、子どもが口に入れたものなどは意識的に消毒するようにしてください。その観点からすると、うがいや歯磨きに用いるコップも、ぜひ個人持ちのものを用意したいところ。どうしても共用になってしまう場合は、使うたびに口が触れた部分を洗うようにしましょう。
加えて、こまめな換気も心がけたいところですが、冬場は室内温度が下がりすぎるおそれがあります。暖房器具を使用することはもちろん、状況に応じて上着などを着せてあげてください。
子どものマスク着用には慎重な判断を!

マスクをはじめとする個人防護具についても、正しい認識を持つことが大切です。マスクは、自分が感染していた場合に「他者にうつさないために着用するもの」なので、保育士さんが園で着用するのであれば、市販のマスクで十分でしょう。最近では、口元を透明のシートで覆ったマウスシールドも見かけるようになりましたが、顔全体(あるいは表情)が見えやすいというメリットがある一方、すき間が大きいため一部の飛沫しか捕捉できず、効果は限定的です。また、顔全体を覆うフェイスシールドは「自分を守る」ためのものであり、口や鼻はもちろん、目からの飛沫感染を防ぐ目的で使用されます。
なお、子どものマスク着用については、より慎重に考えなくてはなりません。WHO(世界保健機関)は「5歳以下の子どもは必ずしもマスク着用にこだわらなくていい」という見解を出していますが、マスクの着用が熱中症や誤嚥を招くことや、顔が隠れるために異変に気付きにくいことなどから、子どもに重大な健康被害をもたらすおそれがあるとも指摘されています。そもそも幼い子どもの場合、マスクをきちんと着用し続けること自体が難しいのではないでしょうか。もちろん、性格や環境によってはマスク着用が安全で意味をなすケースもあるでしょうが、少なくとも2歳未満の子どもでは避けたほうがいいでしょう。
新型コロナ対策は、揺れ動く「振り子」のようなもの
2020年7月にスタートしたGo Toトラベルキャンペーンでは、その是非が議論されましたが、旅行にともなう行為(食事、会話、移動など)の多くは、日常生活でも必ず行うもの。それぞれの場面ごとに適切な感染対策を講じれば大丈夫です。とはいえ、とはいえ、旅行中に気が緩んでしまって、人込みでマスクを外したり、食事中に大声で話してしまったりすることは十分にあり得ます。旅行やレジャーの際は、羽目を外しすぎないよう注意してください。
なお、多くの感染症と同様、新型コロナウイルスは冬季に流行しやすい傾向があると考えられています。今後も感染が拡大する可能性は十分にあり、感染症専門医の立場としても「この冬が本当の勝負」だと感じています。インフルエンザの同時流行も懸念されているので、手洗いやマスクの着用を徹底するほか、できるだけ予防接種を受けるようにしましょう。
最後になりますが、みなさんの頭の中で「振り子」を想像してみてください。非常事態宣言が出された当初は、厳しい対策を実施する方向にグッと振り子が動きました。しかし、現在は過剰だった感染対策をうまく「引き算」していく段階に入っており、振り子が逆サイドに振れつつあります。コロナ対策を言葉にするなら、そうやって少しずつ調整をはかりながら、次第に対策の精度が上がっていき、やがて一点に収束していくイメージ。そんな流れを踏まえつつ、自施設や地域の状況を把握し、最適な感染対策を模索していくことが、「持続可能な対策」につながるのではないでしょうか。
総合診療医、感染症専門医、感染症コンサルタント
Master of Public Health(北海道大学大学院医学院修士課程公衆衛生学コース)
一般社団法人Sapporo Medical Academy代表理事








