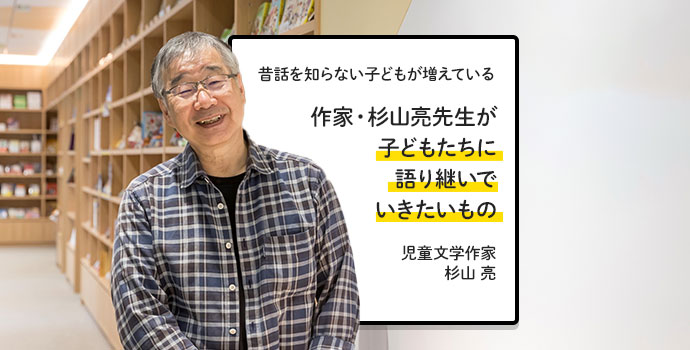「ミルキー杉山のあなたも名探偵」シリーズ(偕成社)などで知られる児童文学作家の杉山亮先生は、なんと保育士の経験もあるというユニークな経歴の持ち主。この7月には、おばけ話絵本シリーズの最新刊となる『ばけねこ』(ポプラ社)も発売されました。ほいくらしでは、そんな杉山先生にインタビュー取材を行い、絵本の制作秘話や子どもたちへの想い、そして保育士時代のエピソードをたっぷりと語っていただきました。最後には、ほいくらし読者に向けた、とっておきのメッセージもご紹介しますので、お楽しみに!
取材・文:保育ライター野口 燈 写真:高嶋一成
「おはなし迷路」がSNSで話題に! 子どもたちに支持され続ける児童文学作家

杉山亮先生といえば、「ミルキー杉山のあなたも名探偵」シリーズでおなじみの児童文学作家です。みなさんも、一度はその作品を手に取ったことがあるのではないでしょうか? また先生は、最近SNSで話題になった「おはなし迷路※」の“生みの親”としても知られており、長きにわたって子どもたちをワクワクさせる作品を作り続けてきました。
といっても、先生が手がけてきたのは、探偵ものや謎解きといった「子どもの思考力を鍛える物語」ばかりではありません。日本に古くから伝わるかっぱやのっぺらぼうなどの話をベースにした「おばけ話絵本」シリーズも、杉山先生の代表作のひとつ。幼児期の怖いもの見たさの心理を刺激する世界観が、子どもたちにとても人気です。
さて、今回はその「おばけ話絵本」シリーズの完結となる『ばけねこ』が刊行されたことを記念して、先生にインタビューを依頼。普段は山梨にお住まいの先生にお会いして、たっぷりとお話を伺ってきました。絵本のことから保育の仕事のことまで、子どもと関わるときに役立つヒントが盛りだくさんなので、ぜひ参考にしてください!
※スタートからゴールまで、文字をたどりながらおはなしを進めていく一風変わった迷路です。読み進めていくなかで、行き止まりにぶつかったり、分岐を選んだりすることになりますが、選択したストーリーによって話が変化するのが「おはなし迷路」の面白さ。よく知られている昔話がベースになっているので、子どもも大人も一緒になって楽しめます。

【杉山先生インタビュー】「怖い」と「不思議」が子どもの心を動かす

——先生はこれまでに膨大な数の児童書や謎解き話を作り続けていらっしゃいます。アイデアはどこから湧いてくるのでしょうか?
子どものころに体験したことや見聞きしたことを思い出しながら、「これは使えそうだな」「これとこれを組み合わせたらどうなるんだろう」といった作業を繰り返している感じです。みなさんの頭の中にも、子どものころから溜め込んできたものがあるはずなんですよね。普段は忘れているけれど、ずっと引っかかっていることとか、ふとしたときに思い出す不思議な体験とか。ただ、同じものを見て同じ体験をしても、それが引っかかる人と素通りしちゃう人がいて、素通りしちゃう人は、あまり物書きに向かないかもしれません(笑)。
——最近では「おはなし迷路」がSNSで話題になりました。反響の大きさを実感されることはありますか?
僕のところに直接声が届くことはありませんが、「おはなし迷路」を取り扱ってくれているお店では反響が大きいと聞いています。ただ、これを最初に書いたのは28年も前のこと。ネットで知った人にとっては、急に出てきたものかもしれませんが、知っている人の中ではずっと存在し続けていて、何年もたったいまになって注目を集めているわけです。そう考えると、何とも不思議な感覚ですね。
そして、「ネットって怖いな」とも思いますね。ネットで見つかったら「ある」ってことになって、見つからないうちは「ない」ってことになっちゃう。ネットで見つからないと評価の対象にすらならないのかな、と。まあ、それはそれとして、いまの若い人たちの間で人気が出るのはやっぱり嬉しいですね。
——「おばけ話絵本」シリーズについてお聞きします。このシリーズは、ただ怖いだけではなく、不思議な面白さを味わえる作品ばかり。子どもたちに人気があるのもうなずけます。
子どもは基本的に「怖い」とか「不思議」が好きですよね。きっと、「よくわからないものがわかる」というのが好きなんじゃないかな。だからこそ、“おばけもの”には心が動きやすい。「心が動く」という言葉には、「笑える」「泣ける」「腹が立つ」「驚く」といったあらゆる感情が含まれるわけですが、いちばん心が動くのは「ワクワクする」ということですよね。
もちろん、大人になると「しんみりしてていいね」とか「しみじみしていいね」という感覚もわかるようになりますが、小さいうちは、まだそのあたりが理解できない。それで、「怖い」とか「笑える」とか、素直にワクワクできることが求められるんだと思います。

——シリーズ完結となる最新作『ばけねこ』では、主人公の少女の緊張や不安がとてもリアルに描かれていて、いつの間にか物語の世界に入り込んだ感覚になりました。どのような経緯で「化け猫」をテーマにしようと思ったのですか?
日本には、おばけの絵本や物語がたくさんありますが、「化け猫」を扱ったものはあまりないんです。理由として考えられるのは、古くから伝わる化け猫騒動のお話がすごくおどろおどろしいから。つまり、子どもに読ませる絵本には、向かないエピソードなんですよね。
でも、僕にとっての化け猫は、ビジュアル的にとても惹かれるものでした。とくに、夜中に行燈の油を舐める姿を描いた絵はいい。首から下は着物を着た女の人なのに、障子に映る影には猫の耳が生えていて……。とても印象的なんです。それで、「あのビジュアルを生かしながら、どうにかして子どもが読みやすい物語を作りたい」と考えたのが、『ばけねこ』を描いたきっかけでした。
——とくに工夫された点はありますか?
「迷い家(まよいが)」という現象をご存じですか? これは、「山の中の怪しい家に迷い込んでそこで“何か”が起きるものの、一度離れてしまうと二度とその家にはたどり着けない」という不思議な現象のこと。日本に古くからある伝承で、遠野物語などにも登場します。この迷い家と化け猫をミックスしようと思いついたおかげで、子どもたちが好きな「怖い」と「不思議」がうまく表現できたと思います。
——アンマサコさんが描く絵も、物語の世界観にぴったりですね。
すごくいいですよね。畳の目まで細かく描き込んでくれている。ある程度リアルに描いたほうがちゃんと怖くなるので、こうして細部にまでこだわってもらえると、世界観がぐっと引き立ちます。怖いけれど、柔らかさや温かさが感じられる色使いもとてもいい。

保育士は子どもと世界をつなぐ“コーディネーター”であれ
——先生は保育士(当時は保父)としてのご経験があると伺っています。男性の保育士さんが非常に珍しかった時代に、その道に進むのは大変だったのではないですか?
40年前ですからね、まわりの反応はひどいものでしたよ。「大の男がやる仕事なのか?」と(苦笑)。その当時は、児童福祉法にも「保育所で働く“女子”を保母といい」と書いてあったんですよね。つまり国をはじめ、世の中全体が「育児や保育は女性の仕事」という認識だったわけです。
そんな時代だから、男子を入れてくれる学校もありませんでした。当然ですよね。男子を入学させたところで、資格が取れないんですから。でも都内で一校だけ、僕を入れてくれが専門学校があったんです。「授業に出て単位を取れば卒業証書はあげましょう。その後は自分で何とかしなさいね」というのが条件で、入学した男子は僕だけ。その環境で、がんばって2年間勉強しました。
——その後、どのような経緯で保育の仕事に就いたのでしょう?
とても珍しいケースですが、伊豆諸島の利島(としま)という村の村長さんが、「保育の現場には男性もいた方がいい」と言ってくださって、島にある保育園で働かせてくれたんです。人口280人、世帯にすると100もない村で、子どもはたったの11人でした。
そこでは、子どもたちがのびのびと過ごしている反面、人数が少ないからこそ見えてくる問題もありましたね。たとえば、子どもたちの間に上下関係ができてしまうと、一生そのままだったりすること。都会だと学校やクラスが変わることで、また一から人間関係をやり直すこともできるんですが、人数が少ないとずっと同じメンバーと過ごすことになるんです。もちろんそれがメリットになることもありますが、かわいそうな面もありますよね。
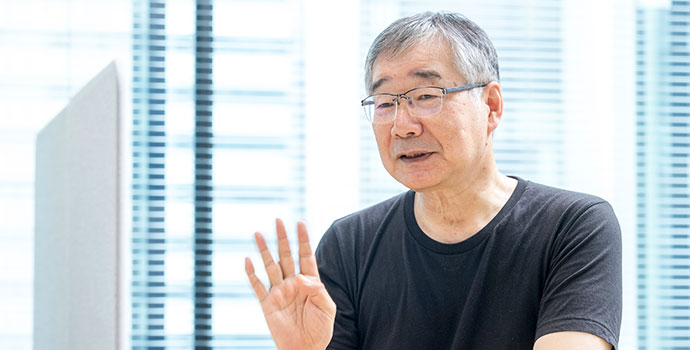
——子どもの成長には、まわりの環境が大きく影響しますよね。先生は読み聞かせや講演会などで、長年たくさんの子どもたちと接してこられました。昔といまを比べてみて、「変わったな」と感じることはありますか?
「基本的な物語」が頭に入っていない子が増えたように感じます。たとえば『桃太郎』。最近は「どんなお話か知らない」っていう子もいるんですよね。『桃太郎』と『浦島太郎』『金太郎』は、携帯電話のCMのなかの話だと思っている(笑)。
——子どもなら誰もが知っている昔話だと思っていました。
もちろん知っている子のほうが多いんですが、わからない子も一定数います。だから、「最初に犬がきて、次に猿がきました。では、最後に何がきたでしょう?」というクイズが成り立ったりするんですよね。
そして、知らないこと以上に問題なのは、知らないのに「知らない」と言ってくれないことです。いまの子どもたちって、「わからない」「知らない」と言うのが本当に恥ずかしいみたいで、恥ずかしい思いをするくらいなら、黙っていようとするんです。僕が、『桃太郎』を知らない子どもがいると気づけたのも、たまたま「それ何? わかんない」って言ってくれた子がいたから。黙ったまま見逃されている子も、結構いるのではないでしょうか。
——それだと、昔話を知らないまま大人になることもあり得ますね。
十分あります。でも、別に知識としては困らないわけですよね。テレビやネットを見れば情報が得られるから、親もあまり気にしない。そういう物語をたくさん読むことで育まれるものも、絶対にあるはずなのに……。このままでは、この国に住んでいる子どもたちが、「共通の物語」を失ってしまうのではないかと危惧しています。
また、昔から伝わる物語の中には、共通の価値観や幸福観、美意識が入っているので、昔話を読まないことでそれらを失いつつあるのかもしれない。そう考えると、悲しい気持ちになりますね。
——いまは情報が多すぎて、保護者の多くは迷いながら子育てをしているようにも感じます。子どもへの関わり方について、大人としてどのようなことを心がけるべきでしょうか?
僕は作家なので、絵本や物語への向き合い方という点でアドバイスすると、子どもたちには「雑読」や「乱読」をさせるべきだと考えています。大人って、どうしても子どもに名作を与えたがりますよね。その結果、「これを読ませておけば間違いない」みたいなものばかり選んでしまう。でも本来は、もっとたくさんの本を読ませるべきです。たくさんの本に触れて、笑ったり怖がったりするなかで、「これは面白い」「これはつまらない」ということを自分なりに感じとる。子どもにとっては、それが大事なんです。
「これは面白い」「これはつまらない」と気づくのは、子どもの成長の証。「自分はこういうのが好きだ」という基準が、その子のなかにできたということでもあります。そうなるためにも、子どもたちにはたくさんの本を読める環境や時間を作ってあげてください。
——最後に、「ほいくらし」読者である現役の保育士さんたちにメッセージをお願いします。
保育士の仕事はすごく大変ですよね。でも、その一方でとてもやりがいがある職業だとも思います。ただ、自分だけで全部を教えようとすると限界がありますから、絵本や物語、遊びやおもちゃなど、いろいろなツールを活用しながら、うまくやっていくほうがいいですよ。
保育士は、子どもたちとほかの世界とのつながりを作る「コーディネーターみたいなもの」だと考えるといいかもしれないですね。ひとりで背負い込むとあまりいいことはないので、「自分では手に負えないからこの本にやってもらおう」くらいに考えてみてください。そうすると、気持ちがずっと楽になるはずです。
手作りおもちゃ屋「なぞなぞ工房」を主宰。現在は児童文学作家として活動中。
「ミルキー杉山のあなたも名探偵」シリーズや「わんわん探偵団」シリーズ
(偕成社)をはじめ、「おばけ話絵本」シリーズ(ポプラ社)など著書多数。