保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!
X(旧Twitter)をフォローはこちら!
保育士になるため資格を取得しようとする場合、どのような方法で勉強をしようか迷っている方は多いでしょう。保育士になるためには、保育が学べる専門学校や大学に進学して学ぶ方法と、自分で勉強をして国家試験に合格する方法の2つがあります。
進学する場合は文字通り学校で学ぶわけですが、自分で勉強する場合にはどのような勉強法があるのか、どのように勉強すればいいのかわからない方も多くいるでしょう。
そこで今回は、自分で勉強をする際に通信講座を利用する方法、通信講座のメリットやデメリット、保育士試験の内容や合格率について紹介します。
保育士資格を取得したあとの就職先については、保育士資格を活かせる仕事とは?就職・転職におすすめのサイトも紹介にて紹介していますので、こちらもご覧ください!
保育士資格は通信講座でも取得できる?

これまでは、保育士資格の取得には専門知識が必要であり、自己学習では限界があったため、専門学校や大学に進学する方が大多数でした。近年では通信技術の発展や普及により、通信講座でも専門的なことが十分に学べるようになり、保育士資格を取得できるようになったため、進学を選択しない方も増えています。
ここでは、通信講座を利用するメリットやデメリット、通信講座選びのポイントを解説します。
保育士資格の取得方法は2種類
保育士資格を取得するには、通学して卒業と同時に保育士資格を得るか、自己学習で保育士国家試験に合格するといった2つの方法があります。
専門学校や大学で指定の課程を修めると、卒業と同時に保育士資格が取得できます。国家試験を受ける必要はありません。一方、通信講座などで自己学習した場合は、年に2回開催される保育士国家試験に合格する必要があります。
通信講座を受ける場合の費用やスクールを選ぶ際のポイント
進学する場合と通信講座を受講する場合の大きな違いは、やはり費用です。保育士の通信講座の受講費用は3万〜8万円ほどとなります。通信制大学では、年間で100万円ほど必要です。
費用は、通信講座か進学かを決める判断材料の一つですが、全てではなく、学習方法や学習期間が重要です。通信講座を選ぶ際も同様であり、費用以外のことを考慮しなければなりません。
以下は、通信講座を選ぶときのポイントです。
| ①学習方法と期間 | 無理のない学習プランか、すべての科目の学習がどれくらいの期間で学習できるかを確認。 |
| ②試験対策の有無 | 知識として知っておくことを勉強した後は、試験対策があるかどうかも重要なポイント。 |
| ③課題の添削回数 | 課題提出回数や添削の上限回数を確認。 |
| ④質問できるシステムの有無 | 気軽に質問できるシステムか、有料か無料かも確認。 |
| ⑤スクーリングの有無 | 実技についての学習ツールは何かを確認。 |
| ⑥不合格だったときのサポート | 試験に不合格だった場合のサポート期間、受講期間無料延長、受講料の返金などの システムがあるか確認。 |
| ⑦予算とのすり合わせ | 講座内容と自分の予算が合っているか確認する。通信講座の教材の他に、問題集などを 購入する可能性があるため、学習費用の予算を確認。 |
保育士資格を通信講座で取得するメリット・デメリット

保育士資格を通信講座で取得しようと考えている方には、進学するための学費が出せなかったり、時間がなかったりと様々な理由から、通信講座を選択した方も多いでしょう。
前述したように、費用面でみると通信講座は進学する場合よりも安く済みますが、費用以外にも、メリットとデメリットがあります。
ここでは、通信講座のメリット・デメリットを紹介します。
保育士資格を通信講座で取得するメリット
保育士資格を通信講座で取得するメリットには、以下のようなことがあります。
○学費を安く抑えられる
通信講座は試験に合格するために、効率よく学習できるオリジナル教材が準備されています。入学金もないため、進学よりも学費を安く抑えることができるでしょう。
○勉強時間を自由に確保できる
通勤途中や帰宅後、子どもが寝た後など、勉強する時間の確保が生活スタイルに合わせて自由にできます。
○挑戦しやすい環境が整っている
申込みの際に提出書類などが少ないこと、テキストなどが郵送されること、オンラインで講義動画が視聴できるなど、挑戦しやすい環境が整っています。
保育士資格を通信講座で取得するデメリット
保育士資格を通信講座で取得するデメリットには、以下のことがあります。
○実技のスキルを独学で磨く必要がある
学科試験に合格すると、「音楽に関する技術」「造形に関する技術」「言語に関する技術」の実技試験があり、3科目のうち2科目を選択して受験します。通信講座の場合、実技のスキルを独学で磨く必要があります。
○モチベーションの維持が難しくなる
また通信講座には、一緒に学ぶ学友などはいないため、モチベーションを保つことが難しくなるかもしれません。目的意識をしっかり持ち、気分転換をしながら学習できるように工夫する必要があります。
保育士資格の試験は難しい?
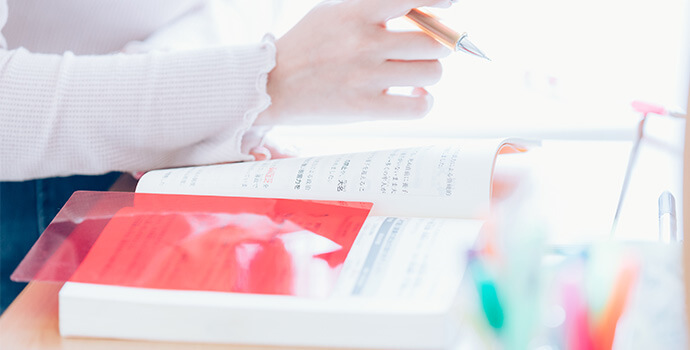
保育士国家試験は年に2回行われていますが、合格率は高いものではありません。
それでも通信講座を選択した場合は、試験に合格しなければ保育士資格を取得することはできないため、合格するために努力する必要があります。
ここでは、保育士国家試験の合格率や試験内容について解説します。
合格率は10~20%程度

保育士の国家試験合格率は、20%前後で推移しています。厚生労働省が発表したデータによると、平成26年度は19.3%、平成27年度は22.6%、平成28年度は25.8%、平成29年度は21.6%となっています。
(出典:保育士試験の概要pdf/https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000088256.pdf
また、「教育原理及び社会的養護」は一つの科目として数え、50点ずつの配点となります。
どちらの科目も60%以上の得点がなければ、「教育原理及び社会的養護」の科目は合格にはなりません。どちらか一方が満点で、合計60%の得点があったとしても、この科目は不合格となります。
筆記試験の内容
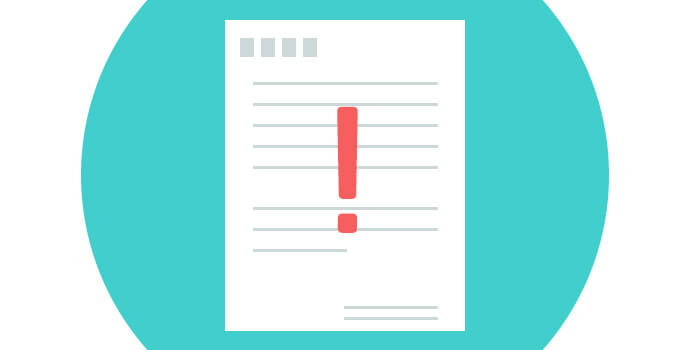
保育士国家試験の筆記試験科目は、以下の8科目です。一度合格した科目は3年間有効となるため、有効期間内の受験ではその科目は免除されます。
- ①保育原理
- ②教育原理及び社会的養護
- ③子ども家庭福祉
- ④社会福祉
- ⑤保育の心理学
- ⑥子どもの保健
- ⑦子どもの食と栄養
- ⑧保育実習理論
(※令和2年の試験より児童家庭福祉が子ども家庭福祉に名称が変わりました)
また、以下の表のように、幼稚園教諭、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の免許を持っている人に関しては、一部試験科目が免除となります。幼稚園教諭は、幼稚園や認定こども園などの特定の機関の実務経験がある場合は、特例制度により保育実習理論の科目も免除されます。
| 取得資格 | 免除科目 |
|---|---|
| 幼稚園教諭 | 保育の心理学・教育原理・実技試験 |
| 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士 | 社会的養護・子ども家庭福祉・社会福祉 |
実技試験の内容
実技試験は、筆記試験の合格者だけが受験します。令和2年の試験より、実技科目の名称が「音楽に関する技術」「造形に関する技術」「言語に関する技術」に変更になりました。3つのうち2科目を選び受験します。
音楽に関する技術では、課題曲をピアノ、ギター、アコーディオンのいずれかで演奏して歌います。造形に関する技術では、制限時間以内に課題となる保育活動について色鉛筆で絵を描きます。言語に関する技術では、課題のお話を3分程度で、園児に話すようにお話するという試験です。どの試験も表現力が試される試験です。
保育士資格の取得から働くまでの流れ

保育士資格を取得するまでの流れを説明します。2020年現在、試験は、前期・後期試験の年に2回開催されています。
| 資格取得までの流れ | 前期試験 | 後期試験 |
|---|---|---|
| ①保育士試験の申込み | 1月下旬 | 7月下旬 |
| ②筆記試験 | 4月下旬 | 10月下旬 |
| ③筆記試験の合格発表 | 6月下旬 | 11月下旬 |
| ④実技試験 | 7月上旬 | 12月中旬 |
| ⑤実技試験の合格発表 | 8月上旬 | 翌年1月中旬 |
| ⑥保育士資格取得 | ー | ー |
| 登録〜勤務の流れ | |
|---|---|
| ①登録手続き | ・登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」を取り寄せる。 ・登録手数料を振り込む。 ・登録事務処理センターへ書類を送付する。 |
| ②保育士証の交付 | ・申請先の都道府県で審査され、審査を通ると都道府県の 保育士登録簿へ登録され、保育士証が交付される。 ・申請から交付までは2ヶ月ほど。 |
| ③就職先を探す | ・自分で勤務施設を探したり、人材紹介会社に登録して、就職先を探す。 |
| ④保育士として働く | ・就職し保育士として働く。 |
以上のように試験を合格して安心するのではなく、合格後は速やかに就職先を探す必要があります。保育士は試験に合格して終わりではなく、合格してやっとスタートラインに立った状態であることを覚えておきましょう。
まとめ
保育士資格は、進学して学ぶ以外にも通信講座で自己学習し、国家試験に合格すると取得可能です。筆記試験は8科目あり、全て合格した者だけが実技試験に臨めます。実技試験は、音楽、造形、言語に関する技術から2科目を選びます。
合格率は約20%前後となっており、決して簡単ではありませんが、一度合格した科目は3年間有効です。試験は年に2回行われているため、一度で全てに合格する必要はありません。
通信講座を利用して保育士資格の取得を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
小児看護の質の向上を目指して保育士免許を取得。現在は緩和ケア認定看護師として、
子どもの苦痛緩和や療養環境の整備を中心に活動している。









