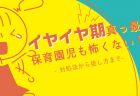【0歳児保育】園での過ごし方|保育中に気を付けるべきポイント3選

保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!
X(旧Twitter)をフォローはこちら!
働いている保護者にとって、出産後の会社復帰の時期は気になる点です。最近では「0歳児保育」が浸透してきたとはいえ、0歳から子どもを保育園に預けることにためらいを感じている人も多くいるでしょう。
そこで今回は、0歳児保育で子どもがどのように過ごしているのか、具体的な園での過ごし方・スケジュールを紹介します。また、0歳児保育にあたり気を付けるべきポイントも解説しているので、ぜひご覧ください。
0歳児は保育園に預けられる?

多くの保育園では認可園・認可外園に関わらず、子どもが生後57日(生後2ヶ月)以上から受け入れを行っています。
ただし、保育園によって受け入れ対象年齢は異なりますので、注意が必要です。
夫婦共働きの家庭が増えているものの、両親が遠方に住んでいたり、ご近所付き合いが減っていたりと、子育てのサポートを受けづらくなっています。そのため、女性の社会進出が進みつつある現在、0歳児の子どもを保育園に預ける家庭は増加傾向です。
また、0歳児から預かってくれる場所があることは、保護者に安心感を与えます。育児ノイローゼから子どもへと辛くあたってしまうケースが報告されていることもあり、0歳児保育への周囲の理解は進んでいる状況です。
「0歳児保育」と「乳児保育」の違い
「乳児保育」は、0歳~2歳の子どもを対象とする保育です。そのなかでも、0歳児に限定したクラスで保育を行うことを「0歳児保育」と呼びます。
0歳児保育とその他の乳児保育で大きく異なる点は、「保育士の配置基準」です。下記の表のように、0歳児保育は子ども3人に保育士1人を配置するよう決められています。
| 子どもの年齢 | 保育士の配置基準 |
|---|---|
| 0歳児 | 子ども3人ごとに保育士1人 |
| 1~2歳児 | 子ども6人ごとに保育士1人 |
| 3歳児 | 子ども20人ごとに保育士1人 |
| 4~5歳児 | 子ども30人ごとに保育士1人 |
(出典:電子政府の総合窓口e-Gov「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」/https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323M40000100063)
このように、保育士の人数を手厚く配置することにより、まだ繊細なケアが必要な0歳児を、安全に保育できるよう配慮されています。
【0歳児保育】1日のスケジュール|基本の遊び方

0歳児を保育園に預けた場合、子どもはどのような1日を園で過ごすのでしょうか。0歳児保育の1日のスケジュールの一例を見てみましょう。
| 時間帯 | 活動項目 | 活動内容 |
|---|---|---|
| 9:00 | 登園 | 保育園へ登園。登園したらオムツ換えをして、教室で自由に過ごす。 朝の会を実施し、朝のおやつを食べる。 |
| 10:00~12:00 | 主活動 | お散歩などの戸外活動やお絵描きなどの室内遊びを実施し、 子どもの興味や発達に合わせた活動を行う。 |
| 12:00 | 昼食 | 主活動で身体を動かした後に、昼食を食べる。月齢や離乳食の進み具合に合わせて離乳食やミルクが準備されている。 3回食に慣れていない子は時間を調整する。 |
| 13:00 | 昼寝 | 昼食後は、昼寝をして身体を休ませる。子どもがぐっすり眠れるよう、 保育士が読み聞かせを行うこともある。 |
| 15:00 | おやつ | 昼寝から起床した後、おやつを食べる。 |
| 16:00 | 自由遊び | 手遊びや積み木など、保育士と一緒に自由遊びをしながらお迎えを待つ。 |
| 17:00~ | 降園 | ママ・パパのお迎えが来て、降園する。 |
0歳児保育では、特に子どもの月齢や発育に配慮したスケジュールがとられています。保育園によっては、早朝保育・延長保育が行われているため、仕事の都合がつかない場合は園へ予め相談するようにしましょう。
0歳児保育では、さまざまな活動を通じて、同年代の子どもと触れ合うことができたり、家庭ではできないような体験をしていくことで、情緒などの発達面でも良い刺激をたくさん受けることができます。
自宅で過ごしていると経験できない外の世界を知れることは、0歳児保育の大きなメリットといえるでしょう。
0歳児保育で気を付けておくべき3つのポイント

前述したように、0歳児保育は大きな配慮がなされており、さまざまなメリットがあります。
しかし0歳児保育には、気を付けておくべき点もあります。
ここでは、0歳児保育で気を付けておくべき3つのポイントを解説します。
保護者と保育士がコミュニケーションをしっかりとる必要がある
0歳児はあっという間に成長するため、保護者・保育士がより密にコミュニケーションをしっかりととることが重要です。
0歳児保育では、保護者と保育士が分担して育児をするため、負担が軽くなるというメリットがあります。しかし、お互い1日中一緒に子どもと過ごせるわけではないため、子どもの早い成長に戸惑いを感じることもあるでしょう。
0歳児は、泣く・笑う以外の方法で感情を出すことは、なかなかできません。子どもの変化を見逃さないよう、子どもの顔をしっかりと見て、積極的にコミュニケーションをとっていく必要があります。
感染症がうつる可能性がある
0歳児は、生後6ヵ月頃までは、母体から受けた免疫力を持っていますが、徐々にその効果は薄れていきます。
保育園は、多くの人が集まるという性質上、風邪やインフルエンザ、ノロウイルスといった感染症がうつる可能性があります。
大人にとっては「ただの風邪」で済むことも、生後6ヵ月を過ぎた0歳児にとっては体への負担が大きいです。そのため、0歳児保育をする上では、いつも以上にウイルス感染に気を付けておかなくてはなりません。
ちょっとした風邪だと思っても、他の子どもにうつしてしまわないよう送り迎えを控えるなど、充分に対策しましょう。
保育園と保護者が一体となって、子どもたちを守っていく体制作りが必要です。
完全母乳育児ができなくなる
0歳児保育での授乳は哺乳瓶によるミルクが基本ですので、保育園に預けると完全母乳育児ができなくなってしまいます。
近年の粉ミルクや液体ミルクは、法律により成分規格が定められており、赤ちゃんが必要とする栄養素は十分です。母乳の少ないママには、粉・液体ミルクとの混合育児が医師から勧められています。
それでも、ママのなかには、できるだけ母乳で育てたいと思う人もいるでしょう。
保育園によっては、園内での授乳に柔軟に対応している園も存在します。搾乳してストックした母乳を保育中に与えてもらえるかなど、保育園側の担当者と事前に相談しておくとよいでしょう。
0歳児保育は保護者と担任保育士の信頼関係が大切!

働きながら子育てをしている保護者のなかには、自分の子どもを0歳児から保育園に預けていることに引け目を感じている人も少なくありません。
一方、預かっている保育士側も、0歳児を預かることは、大きな責任を感じてしまうものです。
そのため、0歳児保育では、保護者と担任保育士の信頼関係がとても大切です。
お互いがこまめに情報を伝え合うことで、相互に自分が接していない時間の子どもの様子を把握できます。そうした会話を通じて信頼関係を築いていくことで、子どもにとって良い影響を与えるだけでなく、保護者は育児に関する悩みを解消でき、担当保育士も子どもの変化を伝えやすくなるでしょう。
何よりも大切なことは、子どもが楽しく、安心して過ごす環境を作ることです。何気ない会話から積み重ね、相互に信頼を感じられる関係を築いていきましょう。
まとめ
共働き世帯が増えているなか、0歳児保育は注目されています。周囲に頼れる親族のいない世帯が増加していることもその一因です。保育園側でも、社会状況に応じて、0歳児からの保育を始めている園が増加しています。
0歳児保育では、子ども3人に保育士が1人付くという手厚い人員配置が特徴的です。また、食事や活動、休息などをうまく組み合わせ、子どもの成長に合わせたスケジュールが組まれています。
早い段階から外の世界に触れられることが、0歳児保育のメリットです。保護者と担任保育士で協力して信頼関係を築き、0歳児が楽しみ安心できる環境を作りましょう。
7年間保育士として保育園に勤務。
その後、ベビーシッターとして活動をしつつ
「保育百華」就職アドバイザーとしてYouTubeでの発信やコミュニティ運営にも携わる。