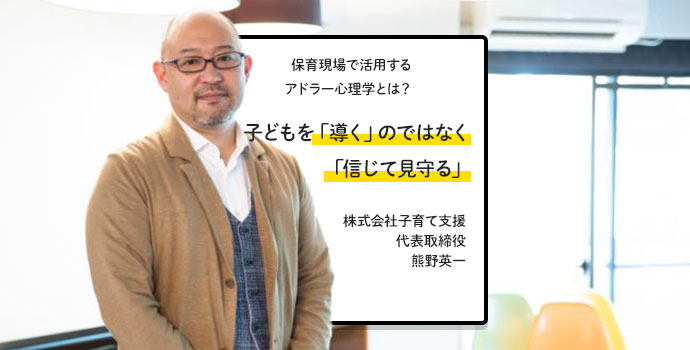子育ての場や保育・教育現場において、注目度がどんどん増している「アドラー心理学」。保育者のみなさんであれば、名前くらいは聞いたことがあるかと思います。しかし、アルフレッド・アドラーといえば、1800年代末期から1900年代初頭にかけて活躍した心理学者。なぜ、今になって注目を集めているのでしょうか。また、実際に保育の現場に役立てるにはどうしたらよいのでしょうか。日本アドラー心理学会/日本個人心理学会の正会員である、株式会社子育て支援代表取締役の熊野英一さんが、アドラー心理学の基礎知識と保育現場に取り入れるためのコツを解説してくれました。
構成/岩川悟(合同会社スリップストリーム)
取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人
アドラー心理学の注目度が増している理由

アルフレッド・アドラーといえば、フロイトやユングと並ぶ三大心理学者の一人です。しかし、日本での知名度はさほど高くなく、日本語に訳された著書も、不登校の子どもを持つ親や民主的に学級を運営したいと考える教員など、ごく一部の人たちに広まっていた程度。一般的に知られる存在ではありませんでした。
そうした状況が大きく変わったのは、2013年のこと。アドラーの教えを伝えた書籍『嫌われる勇気』(ダイヤモンド社/岸見一郎・古賀史健 著)が大ヒットしたことで、アドラー心理学の名が広く知れ渡ったのです。
では、なぜ今になって、アドラー心理学が注目を浴びるようになったのでしょうか? 理由の一つとして、アドラー心理学が100年以上も前に体系化された「古典」だということがあげられます。現代はとても変化の激しい時代です。インターネットが普及したことで、社会がグローバル化し、時間の自由度やコミュニケーションの量も大きく変化しました。さらには、新型コロナウイルス感染症によるパンデミックが起こったり、ロシアのウクライナ侵攻が起こったりと、まさに“先のことが見えない状況”になっています。
そんな時代だからこそ、私たちは「答え」が欲しくなる。そして、答えを導くための指針として注目を集めたのが、アドラー心理学や中国の『論語』、ギリシャ哲学といった古典だったのです。長い歴史の変化のなかを生き延びてきた古典だからこそ、答えそのものが書かれていなくても、何かしらのヒントは与えてくれるはず。そんな考えに基づいた流行だったといえば、わかりやすいでしょうか。
アドラー心理学が注目されているもう一つの理由は、「今のわたしたちが、勇気をくじかれているから」だと考えています。日本ではバブル崩壊以降、ずっと不景気で右肩下がりの状態です。“イケイケドンドン”で突っ走れるような状況にはなく、なかなか前向きになることができません。 そのように社会全体がどんよりした状況だからこそ、アドラー心理学がぴったりとはまったのでしょう。なぜかというと、アドラー心理学が重視することの一つに「勇気づけ」があるからです。ここでいう勇気づけとは、単純に励ましたり、後押しをしたりということではなく、相手に困難を克服する活力を与えること。人間は常に変化したり成長したりするものですが、そのための活力が「勇気」というわけです。嫌われるかもしれないし、失敗するかもしれないけれど、自分が思っていることを素直に表現したり、自分が進みたいと思う道を自分らしく進んだりする勇気を与える。それがアドラー心理学のあり方なのです。
専門的に学んでいなくても使い勝手がいい

ただし、「自分が思っていることを素直に表現したり、自分が進みたいと思う道を自分らしく進んだりする」からといって、アドラーは「自分さえよければいい」と言っているわけではありません。そもそも、そんな姿勢では誰もハッピーになれませんよね。
自分と同じように他者を大事にする。アドラーは、そういう「勇気」を身につけたうえで、前に進んでいこうと言っています。
ここで、「自分と同じように他者を大事にする」という言葉を子育ての場や保育・教育現場に当てはめてみましょう。子育ての場や保育・教育現場というのは、子どもたちに対して、「自分のことを大事にしつつ、他者を思いやる気持ちを持つことが大事」だと伝えていく場でもあります。つまり、アドラーがいう「勇気」をとても大事にする場でもある。そう考えると、家庭における子育てや保育・教育現場においてアドラー心理学が広く認知されるようになった理由がおわかりいただけるのではないでしょうか。
付け加えると、アドラー心理学は子育ての場や保育・教育現場において、とても「使い勝手がいい」思考法でもあります。なぜなら、内容がとてもシンプルなのです。たとえばアドラーと同時代に活躍した心理学の巨頭・フロイトは、基本的に心の問題を抱えている人の精神を分析したり、心の闇を探ったりすることで、問題の原因を解明していくスタンスでした。しかし、それでは問題の分析はできても問題解決には時間がかかりますし、専門的に学んだ人でなければうまく扱えません。
対するアドラー心理学は、「どうすれば私とあなたが仲良くできるのか」といったことにフォーカスを当てて、わかりやすく解説したもの。心理学を学んでいない人にとっても、実践的で使い勝手がいい。それもまた、アドラー心理学の注目度を上げている理由だと考えられます。
アドラー心理学により身につけられる「共同体感覚」

では、アドラー心理学を保育現場に取り入れると、子どもたちにどんな好影響があるのでしょう。いちばんのメリットは「共同体感覚」が身につくことです。
共同体感覚とは、簡単に言うと「思いやり」です。私たちは、人生を歩むなかで多くの選択を迫られます。そのとき自分よがりな選択をするのか、自分も他者もハッピーになれる選択をするのかによって結果は大きく変わりますが、私たちが理想とするのはもちろん後者。自分を思いやり他者をも思いやって、みんながハッピーになることですよね。
そして、「自分も他者も、ハッピーになれる選択ができる子どもに育てること」は、アドラー心理学が子育てや教育において目指しているゴールでもあります。 このゴールは、「子どもが自立すること」と言い換えてもいいと思います。集団で社会生活を営む人間は、決して一人では生きていけない生き物です。また、社会のなかで充実した人生を歩むためには、自分よがりではなく、自分も他者もハッピーになる選択ができる人間になることが欠かせません。そう考えると、たとえアドラー心理学に基づく保育方針を掲げていなくても、多くの園の理念、あるいは保育者が目指す理想形はアドラーの考え方とほぼ一致しているのではないでしょうか。「自分よがりな子どもを育てる」などという理念を掲げている園なんて、どこにもありませんからね。
子どもの自立のためには、「操作」は絶対にNG

では、アドラー心理学の考えを保育現場に取り入れるときは、何に配慮するべきでしょう。まず意識してほしいのは、自分の心のなかにある「操作」を手放すことです。
先に、アドラー心理学における子育てや教育のゴールは、「子どもが自立すること」だと述べましたが、ここで注意してほしいのは、「自立すること」であって「自立させること」ではないという点です。アドラー心理学においては、「子どもが自分で自立するようにサポートすること」が親や保育者など大人の役割。しかし、保育者や教育者のなかには、「私が子どもを自立させなくては」と考えている人も多く、そうした人たちは子どもに対して「この子を自立させるために、私が何かをしてあげよう」という視点で関わってしまいます。
よかれと思ってやっていることだとしても、それはサポートではなく操作です。そして、そういう関わり方をした瞬間に、子どもは自立のチャンスを奪い取られることになります。もちろん、子どもたちに何かを教えることは必要です。しかし、教え過ぎはよくありません。なぜなら、「こうしたほうがいい」「こっちのほうがいい」「答えはこれ」といった言葉が、子どもの選択の幅をどんどん狭めてしまうからです。
また、そういう関わり方をされた子どもは、保育者や教育者に甘えるようになります。何かを「自分でやるより、泣いてわめけば先生がなんでもやってくれる」と考えるようになった子どもが、果たして自立などできるでしょうか? 答えは言うまでもありませんね。 「子どもが自分で自立するようにサポートする」という役割を見失い、「わたしが子どもを自立させる」という気持ちを前面に出した瞬間、望んでいるはずの子どもの自立が、逆に遠のいていく……。そんな結果を招きかねないのです。
遠過ぎず近過ぎない「距離感」を意識する

そうならないためにも、まずは「子どもを操作していい方向に導こう」という思いを手放してはどうでしょうか。とはいえ、それは保育者にとって簡単なことではないでしょう。なぜなら、「いい子になるように、子どもを導きたい」という思いを持って保育者になった人が少なくないからです。けれど、子どもの自立をいちばんに考えるなら、子どもを操作して導くのではなく、「信じて見守る」ことを考えてほしいと思います。
子どもは、子どもなりに自分で自立に向かう力を秘めています。「お友だちとけんかをしても、この子たちなら自分たちで仲直りできるだろう」「失敗しても、そこから何かを学ぶはず」「私が手を出さなくても、この子は自分で工夫してできるようになる」と考え、信じて見守ってください。
もちろん、そのときの子どもとの距離感も大切です。放置して距離感が遠くなり過ぎたり、無視したりするようなことがあれば、保育者の存在意義はまったくなくなります。もちろん、「こうしなさい」というような近過ぎる距離感もよくありません。
みなさんにおすすめしたいのは、保育者同士、あるいは保育者と親御さんとでたくさん対話をして試行錯誤をすることです。そうやって「あの子はもう少し距離を置いて見守ってみよう」とか、「ご家庭でも、もうちょっと子どもを信じて口出しをやめてみませんか」というふうに、大人の側で適切な距離感を探ってみてください。子どもというのは、大人が思う以上に、自分で何かを成し遂げる力を持っているものですよ。
メルセデス・ベンツ日本人事部門に勤務後、米国Indiana University Kelley School of Businessに留学(MBA/経営学修士)。製薬企業イーライ・リリー米国本社及び日本法人を経て、保育サービスの株式会社コティに統括部長として入社。
約60の保育施設の立ち上げ・運営、ベビーシッター事業に従事。
2007年、株式会社子育て支援を設立し、代表取締役に就任。日本アドラー心理学会/日本個人心理学会正会員。主な著書に『夫婦の教科書』(アルテ)、『急に「変われ」と言われても』(小学館)、『仕事も家庭も充実させたいパパのための本』(小学館)、『家庭の教科書』(アルテ)、『育児の教科書』(アルテ)がある。