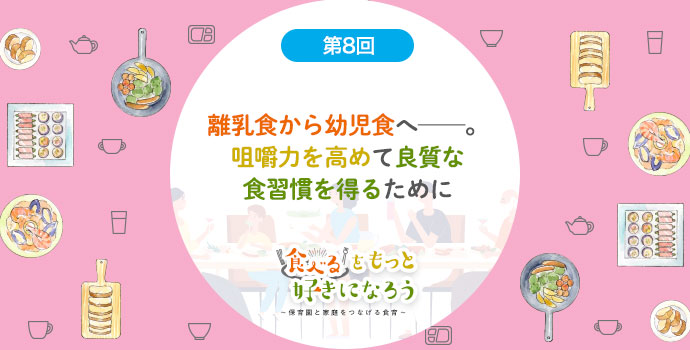
食べ物の栄養を効率よく摂取するうえで欠かせない咀嚼力(噛むちから)。
月齢が上がれば、「好き嫌いなく食べているか」「残さずに食べているか」「お昼ご飯の時間内に食べきれているか」といったことに気を取られがちですが、離乳食から幼児食になっても咀嚼機能の発達はまだまだ続くのです。
子どもたちの将来にも大きな影響を与える「咀嚼力」についてあらためて考えてみます。
文/栄養士 笠井奈津子 写真/櫻井健司
咀嚼は栄養摂取における基本能力
子どもの栄養摂取の形態は、生後半年くらいになると母乳やミルクを飲む哺乳から離乳食へと変化していきます。それから1歳半くらいで離乳期が完了すると幼児食に移り、3歳にもなれば5歳の子と同じようなものを食べることができるというのが一般的な認知かもしれません。
しかし、3歳の子が5歳の子とまったく同じように食べることができるかといえば、答えは「NO」です。
幼児食後期に入る3歳くらいだと、噛む力は大人の半分程度とされます。「上の子(もしくは大人と)と同じものを食べたがるので、早い時期から同じような物を食べさせていた(食べていた)」という話は兄弟がいる家庭でよく聞かれる話ですが、お兄さん、お姉さん、大人と比べたら、口の大きさもあきらかにちがい、あごの大きさや骨の強度も発達過程にあるので、咀嚼力は弱いものです。
口に入れて飲み込んでいれば「ちゃんと食べている」と思いがちですが、「ただ飲み込んでいる」のと「よく噛んでいる(咀嚼できている)」とでは、まるで話はちがってきます。
咀嚼は、きちんと食べるうえで必要な能力であるとともに、栄養摂取における基本能力ともいえます。なぜなら、咀嚼には消化吸収がスムーズになって効率的に栄養を摂ることができるという、子どもの心身の健やかな発達に欠かせない役割があるからです。
咀嚼力を身につけていくためには、離乳食や幼児食がとても重要だということがおわかりになるでしょう。
平成29年の「保育所保育指針」にある食育の推進には、『保育所における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標とすること』と書かれていますが、咀嚼はまさに、基礎中の基礎なのです。
参考:保育所保育指針(平成29年03月31日厚生労働省告示第117号)
よく噛む習慣は将来に役立つ

咀嚼力は年齢や月齢できれいに区切れるものではなく、個人差があるものです。多くの子どもが同時に食事をする幼稚園や保育園のような環境下においては、個別の対応は難しいでしょう。それでも、咀嚼力が不足している子が、まわりに合わせて無理にステップアップしてしまっては、その学習の機会を失ってしまうことになりかねません。
小さな子どもたちの食事には注意すべきポイントがたくさんあります。たとえば、授乳期にはちゃんと体重が増えているかをチェックするでしょうし、離乳食の時期にはアレルギーの問題がないかも気になるはずです。
そして、幼児食の段階になると、ついつい「好き嫌いなく」「上手に」「きれいに」食べることができているかという部分に目がいくようになると思います。
しかし、本来気にすべき点は、乳幼児期にいい食習慣を身につけることです。よく噛む習慣は将来の肥満防止にも役立ちますし、ここではそのメカニズムこそ省略しますが、虫歯予防、歯ならびがよくなる、胃腸の働きを助ける、脳の活性化といったものにもつながっていきます。
咀嚼力を上げるためには、やはり経験からもたらされる学習が必要不可欠。乳歯の生え具合や手指の発達といった食べるための機能面、それから食材の大きさや形態、加熱時間などに工夫をしてステップアップしていくことを意識しましょう。
咀嚼がしっかりできているかを確認する方法

保育の場で子どもの咀嚼力をサポートするには、「個人差がある」ということを前提に、食べている姿をよく観察してほしいと思います。
観察のポイントは大きく分けて次の3点。それぞれを詳しく解説していきましょう。
①口と頬の動きを見て、噛んでいるかをチェックする
②口の中を見て、食べ物が小さくなっているか確認する
③噛むことが好きか、食べる意欲を調べる
ちゃんと咀嚼できているかを確認するには、まずは口と頬の動きを見ることが挙げられます。口と顎があまり動かずにすぐ飲み込んでいるようであれば、「よく噛んでね」の声かけ以前に、食材が大き過ぎるのかもしれません。どんな料理だとよく噛めていて、どんな料理だと飲み込むように食べているのかをチェックすることも、その子個人の咀嚼力を知るひとつの手がかりになります。
また、あまりにも早く飲み込んでいるように感じるときには、「ちょっとお口のなかを見せてね」ということがあってもいいでしょう。口に食べものが入っている状態で口を開けるのは無作法ではありますが、食べものがちゃんと奥歯に乗って小さくなっているようであれば問題ないですし、舌の上に乗って大きさがあまり変わらないようであれば、調理に一工夫が必要かもしれません。そして、「噛む」という行為の意味を、その子にあった言葉で説明してあげるのもいいと思います。
最近は、家庭の食卓に柔らかい食事が出ることが多く、そもそも噛むことがあまり好きでないという子も少なくありません。その場合、「咀嚼への意欲」を高めるために「食べる意欲」の底上げも必要になってきます。
とくに意識したいのは、特定の料理の好き嫌いではなく、食事の時間そのものにあまり意欲を感じない子どもへの対応です。「食べたくない」理由は様々なことが考えられますが、給食の場合であれば調理場のスタッフと保育の現場で対応できることがそれぞれあるはずなので、栄養士や調理師と連携した個別対応も一考の余地があるでしょう。
たとえば、調理に従事するスタッフのみなさんが実際に子どもたちの食べている様子を観察することで、いろいろなことが見えてくると推測します。
「食べる力」には個人差がある

咀嚼は食事環境とも深い関係があります。物理的なことなら、上手にスプーンを口まで運べない子どもであればテーブルの高さも食事のしやすさに影響するでしょう。家庭の環境では、起床時間が遅く、登園時間ギリギリに朝食を食べている子どもは昼食をあまり食べないかもしれません。
それ以前に、「○分以内に食べ終える」という目標時間がなかなか理解できない子どももいます。しかし、完食できることで自信をつける時期があるのも事実。
「歩く」「話す」の発達に個人差があるように、「食べる力」の発達にも個人差があるものです。ですから、時間で完全に区切ることなく、しっかり噛んで食べ終えるということもポイントになってくると思います。
咀嚼力は子どもにとって栄養を摂取する大事な食習慣の基礎です。そういったことにも目を配れる大人がまわりにいることで、親御さんはもちろんのこと、子どもたちの安心感も増し、心の栄養も高まっていくのではないでしょうか。
産後、働き方を見直すなかでパラレルキャリアの道を開拓。








