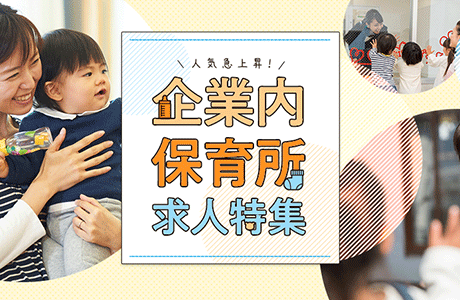取材・文/原 あいみ 伊藤 律子(京田クリエーション)
撮影/筒井 聖子
イヤイヤ期真っ最中の“にこちゃん”が主人公の人気絵本『おにのこ にこちゃん』(発行:ポプラ社)と、マイナビ保育士によるコラボ企画がスタート! 有識者のインタビューや保育士のみなさんからのアンケートをもとに「理想の園」を考え、にこちゃんが入園予定の「はらっぱえん」として絵本に登場させる夢のプロジェクトです。第2回は、『ほいくらし』のサイトでも人気の教育学者・汐見稔幸先生に、お話をうかがいました(全6回予定)。
『おにのこ にこちゃん』についてはこちらをチェック


【プロフィール】
汐見稔幸先生
東京大学名誉教授・白梅学園大学名誉学長・全国保育士養成協議会会長・日本保育学会理事(前会長)。専門は教育人間学、保育学、育児学。子どもの教育に幅広くかかわる教育者であり、NHK教育テレビをはじめとする子育て番組などのコメンテーターとしても人気です。

【プロフィール】
原 あいみさん
イラストレーター。『おにのこ にこちゃん』の絵を担当しているほか、企業や商品のイメージキャラクターも数多く手がけています。難しいことをわかりやすくマンガで伝えることが得意で、2歳だったころのわが子をモデルに、リアルで愛くるしい“にこちゃん像”を作りあげました。Twitterにて、にこちゃんのマンガ「きょうもにこまるけ。」も配信中(毎週水曜朝8時)。
広すぎない「放牧場」で、自由に&安心して遊べるのが理想

原あいみ(以下、原):汐見先生には、にこちゃんが通う園の園長先生になったつもりで理想の園を語っていただきたいと思います。また、今の日本の保育に足りていない部分についても、辛口のご意見をうかがいたいです。
汐見先生(以下、汐見):よろしくお願いします。まずは僕が保育を考える際、念頭においていることからお話しましょう。それは「保育の本質は放牧である」「子どもをきちんと放牧してあげるべきだ」ということです。つまり、子どもたちが自由に「今日はこれをして遊ぼう!」と選べる環境が、園としての理想なんです。そして、それを実現するには「園が無意味に広すぎないこと」が大切になります。
原:園庭は広いほうがのびのび遊べるように感じるのですが、そうではないのですね。
汐見:広すぎてなにもない運動場や園庭というのは、子どもにとってあまりありがたくない存在なんです。広いだけじゃ、走り回ることしかできませんからね。それよりも、山のような起伏があったり、登れる高さの木があったり、隠れられる穴や寝転がれる芝生があったり、ビオトープがあったり——。適度な広さのなかに、いろいろな要素が配置されていて、遊びの想像が膨らむような園庭がいい。「小さな里山のような場所」と言えばイメージしやすいでしょうか。そういう場所があってこそ、子どもたちをきちんと、そして自由に放牧できると思います。
原:そのなかで、保育者はどう関わるのが理想でしょうか?
汐見:子どもを上手に放牧している園の特徴として、「先生が大きい声を出してしない」ということが挙げられます。子どもたちは、先生を気にしないで一生懸命に遊び、園庭から聞こえてくるのは遊んでいるみんなの声だけ。保育者は子どもたちを信頼して、「好きなように遊びなさいね」と伝えて、丁寧に見守っていればそれでいいんです。
汐見:子どもは自分だけでは生きていけない存在なので、老若男女のなかで実はいちばん空気を読むのが上手です。怖い先生の言動なんて、本当によく見ていますよ(笑)。でも、親や保育者の立場からすれば、「小さいときから空気なんて読まずに、好きなことやっていいよ」と言って育てたいと思いませんか? 一見秩序がないけれど、一生懸命に遊ぶ子どもたちの後ろには、笑顔で見守る先生がいる。そういう独特の秩序のある園こそが、子どもたちにとって安心して遊べる理想の場所なんです。

原:先ほどの広さについてですが、保育室も広すぎないほうが良いのですか?
汐見:子どもは空間の大きさを自分の身の丈、歩幅、手の長さを基準にして感じています。保育園に通う0〜1歳の子は、私たちの1/3くらいの身長しかない。ということは、大人と同じものを見たときに、3倍大きく感じる可能性があるわけです。それを踏まえると、大人にとってはそんなに広くない保育室が、子どもには体育館くらいに感じられるかもしれません。もし、毎日体育館で生活してくださいと言われたら、どうですか?
原:きっと、広すぎて落ち着かないですね。
汐見:狭い子宮から出てきて、それほど年月が経っていない子どもにとって、広すぎる空間は心理的にすごく不安定になる場所なんです。だから、子どものための空間は全体としては広くても、パーテーションなどで区切って、安心感を与える必要があります。
子どもだって「自分だけの居場所」が欲しいんです!
汐見:子どもが自由に遊ぶためには、保育室に一人ひとりの居場所があることも大事です。2歳くらいになったら、ごはんを食べるときにも、粘土で遊ぶときにも使える「あなたの机」という居場所を与えるのがいいでしょう。たとえば、月齢が低い子どもたち用の机を4つくらい置き、そこに椅子を2個ずつ用意したら、名前を書いて場所を決めます。そして、机の側にはその年齢の子どもたち向けのおもちゃを上手に配置して、「自由に遊んでいいよ」と伝えるんです。
原:そこが安心して遊べる居場所になるわけですね。
汐見:その場合、隣のテーブルは中月齢、さらに隣は高月齢の子のスペースという具合に設置して、何も置かれていない空間がほぼないようにし、テーブルごとに作業が決まっているアトリエのような配置にするかですね。
原:空きスペースをなくすのは、どうしてですか?
汐見:なにも置いていない空間があると、活発な子どもが走り出してしまいます。でも、家のリビングでは「走ったらだめ!」と怒られるのに、保育室だと走っていいというのはおかしいですよね。保育室は走り回る場所じゃないと理解してもらうためにも、何もない空間をたくさん作ってはだめなんです。

保育室にはソファを置いて、色や雰囲気にも気を配りたい
汐見:保育室には、ソファも欲しいですね。
原:えっ、ソファですか!?
汐見:家にたとえると、保育室はアトリエでありリビングルームに近いと空間だと思います。疲れたときに休める場所にもしたいので、保育室には小さな子どもが休めるようなソファを置きたいですね。
原:リビングだと考えるなら、ほかのインテリアにも気を遣いたくなりますね。
汐見:カーテンや床を何色にするかは、子どもの行動心理に影響します。だから、冬は寒いから暖色のカーテンに変えようとか、夏は涼しい色にしようといった配慮はとても大事です。実は以前、何色の床なら子どもが熱中して遊ぶかという検証をした人がいるんですよ。
原:それは面白いですね! 結果が気になります。
汐見:ある日はピンク、ある日は白という具合に変えていったところ、子どもたちがいちばん集中して遊んだのは水色の床でした。床を真っ赤にした日もあるのですが、刺激が強すぎたのか集中して遊ばなかったですね。ひとつの園でしか検証していないので、参考程度の話ではありますが、「どんな空間なら落ち着いて過ごせるか?」を考えるのも先生の大事な役目だと思います。空間を勝手にアレンジできる園は少ないでしょうが、大人も子どもも床の色やインテリアから受ける印象は変わらないので、できるだけみんなが素敵だと思う空間にしてあげたいですよね。

保育者は「保護者サービス」に一生懸命になってはいけない
原:私は娘を3ヵ所の保育園に預けましたが、親が見やすいところに子どもの作品が飾ってあるなど、どの保育園も雰囲気が似ていました。正直、個性はあまり感じられなかったですね。
汐見:特に公立の場合だと、どこも同じような雰囲気ですよね。そして、子どもが作った作品を安易に飾っている園には「ちょっと!」と言いたいです。
原:作品は飾らないほうがいいというお考えなのですか?
汐見:自分ではうまくできなかったと思っている絵を、勝手に貼り出されたらどう思います? 大人なら「やめてください!」と言いますよね。もちろん、子どもに「この作品、とても素敵だからここに貼ってもいい?」と許可を得て飾るなら構いません。でも、多くの園は保護者へのサービスとしてやっているだけです。
原:言われてみれば、絵や工作を飾るのは保護者向けのサービスかもしれません。
汐見:そうではなくて、園は常に「子どもファースト」であってほしい。作品を飾ったりすることも含めて、いろいろなことを子どもに相談しながら進めていくのが理想です。

地域の人が当たり前に出入りする、風通しの良い園がおもしろい

原:話は変わりますが、地域と園はどのように関わるのが理想なのでしょう?
汐見:理想的な関わり方という点では、横浜におもしろい園があります。そこでは地域の八百屋さん、肉屋さん、電機業者など、園に出入りしている人たちが、園の運営協議会メンバーになっていて、園長が「みなさんは園の子どもたちにどんなことをさせたらいいと思いますか?」「こういうことやりたいけれど、お手伝いお願いできますか?」と積極的にコミュニケーションを取っているんです。
原:まさに地域との連携ですね。
汐見:「子どもたちが魚に興味を持つようにするにはどうすればいいか?」という話になったときは、みんなで魚拓を作って魚の名前を教えたり、おすすめの魚レシピを紹介したり、移動水族館の人に来てもらったりしたそうですよ。そして、それを提案したのは地域の魚屋さんだったとか。これからどんどん少子化が進んでいきますが、そうやって地域の人が運営に協力してくれる園は確実に残っていくはずです。
原:にこちゃんが通う予定のはらっぱえんも、地域や街の人が自由に出入りできる園にできたら楽しそうです!