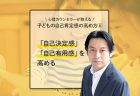脳科学者でベストセラー著者としても知られる中野信子先生が、幼少期から思春期の子どもが抱きがちな悩みに対して、脳科学の見地からアドバイスを送ります。子どもたちの悩みやイヤな気持ちを上手に汲み取って、保育の現場でぜひ活用してください。
連載第4回目は、人前で「あがらない方法」についてです。大人でも、たくさんの人の前で話をするのは、多少なりとも緊張するものです。そんなとき子どもの場合は、立ちすくんだり、泣いてしまったり…と大人以上の緊張を味わっています。不安や恥ずかしさからくる感情に、それこそ押しつぶされてしまいそうになる子もいるでしょう。
その不安とは、どこからくるものなのでしょうか? 「あがり症」のメカニズムを知り対策を知れば、子どもたちも少しずつあがらずにふるまえるはずです。
Q:子どもの悩み
人前に出ると緊張して、うまくふるまえません。どうすれば緊張しなくなるのでしょうか?

中野信子先生からのアドバイス
いわゆる「あがり症」でしょうか。この現象には、「ノルアドレナリン」という物質が関係しています。「ヤバい」状況に立たされると、あなたの体が必死になって戦おうとして、この物質が脳などから分泌されます。そして、血液をたくさん体に送り出そうと、心臓が心拍を速くしたり、筋肉がよく動くように血糖値を上げたりするので、心臓がばくばくしたり顔や体が熱くなって冷や汗が出たりするわけです。
でも実際には、あなたは戦うわけではなく、人前で話すだけですよね? 目の前にいる人は敵ではなくて、これからあなたの話を聞こうとしてくれている、味方になる可能性の高い人たちです。
それなのに、勝手に危険を感じて体や筋肉が緊張しはじめ、自動的に戦闘態勢に入ってしまうわけですから、体の状態とまわりの状況が、少しちくはぐになっています。あがり症は、そんな現代の人間ならではの興味深い状態です。
では、どうすれば人前に出てもこのような状態にならずに済むでしょうか?
その答えはとてもシンプル。はじめての状況であるほど、それを危険だと感じて体はより緊張してしまうので、それを「はじめて」でない状態にすればいいのです。家族と話すときにあがる人は、滅多にいないと思います。同じように、人前で話すことが家で話すのと同じくらいの行動になれば、あがることはなくなるでしょう。たとえ、家と同じとまではいかなくても、「敵ではない」ということが実感として湧くようになるだけで、体が自動的に反応してしまう状況は起こりにくくなります。
そのために、最初は少人数や自分の親しい人たちの前でいいので、なるべく、人前で話すことを何度も体験するようにしてみましょう。そのなかで、「こうすればうまく話せる」という成功体験が積み重なっていきます。そうやっていいイメージを重ねながら、トレーニングやリハーサルを繰り返し繰り返しやっておくのです。
準備をしっかりしていくことが、あがらない自分をつくりあげていくための、地味だけれども確実な一歩です。
構成/岩川悟(合同会社スリップストリーム) 協力/長野真弓
※この連載は、『中野信子のこども脳科学 「イヤな気持ち」をエネルギーに変える!』(フレーベル館)をアレンジして掲載しています。
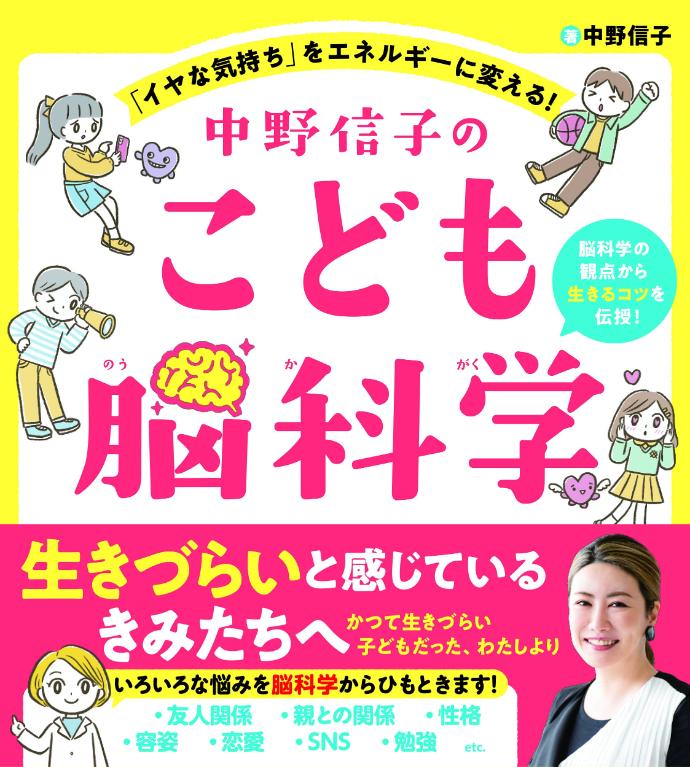
中野信子のこども脳科学「イヤな気持ち」をエネルギーに変える!
著者名:中野信子
出版社:フレーベル館
2021年8月発売